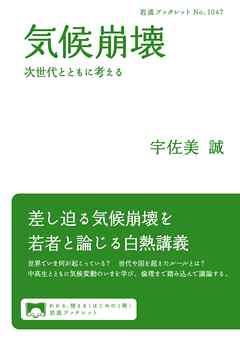あらすじ
「気候崩壊」は防げるか? 世界でいま何が起こっている? 今後は何が起こる? 本当の原因は? 世代や国を越えたルールとは? 若者とともに気候変動のいまを学び,私たちの倫理まで踏み込んで議論する.渋谷教育学園渋谷中学高等学校での特別講義をもとに,中高生の意見も多数収録.大人世代にも手にとってほしい一冊.
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
作品紹介文で冒頭から「『気候崩壊』は防げるか?」と書かれているところから、誤解が生じないかと心配になった。
なぜなら、現代の人類の知見では、気候崩壊に関する抜本的な防止策または解決策を残念ながら導き出せないところに、この問題の難しさがあるからだ。ストレートに言えば現時点では誰もが“お手上げ”なのだ。
だから現状において防止策または解決策を探すことを優先順位の筆頭にしてしまうと、迷路におちいって時間だけが無駄に過ぎてしまうし、楽観論、気候変動否定論や無関心層に対して自分たちに都合のいい安心材料を与えてしまう。
著者はそれがわかっているので、「次世代とともに考える」とサブタイトルを付けている。
つまり本書のテーマは気候崩壊を回避するための技術的ノウハウの紹介ではない。もっと別の側面からの話であり、今出来ないとか理解できないからと言って、さじを投げたり見て見ぬふりをするという安直で自己中心的なスタンスを未来世代の者には身につけてほしくないといった、人間の生き方に迫った哲学的な内容の講義だ。
だから私は、宇佐美先生の講義内容が気候や環境といったカテゴリーにおさまらないもっと広い内容であり、教科ごとのタテ割りの勉強しかしていない中高生にとって、自分で理論を組み立て、ゆえに何が正しいのかを自分で判断しなければならないため、少し難しいかなともと感じた。
具体的に言えば、若い世代に対して、現状と将来起こり得ることについて、根拠のない議論に惑わされずに正確に状況把握するという姿勢を、駅伝のたすきのように現世代から未来世代へ確実に渡すことを目的としたテキストが本書だ。
それにしても、本書の舞台である東京都内の私立中学校高等学校の生徒による気候崩壊に関する質問が、それぞれ簡にして要を得ており、自分自身を振り返ってみたときに当時の自分がそこまでできたのかと思うと恥ずかしくなる。
例えば冒頭の質問-「気候変動の原因や影響について、いろいろな事実や予想を紹介されました。でも気候変動の原因については、さまざまな研究があるわけですし、予想についても、幅があると思うのです。先生は、情報をどのように取捨選択しているのでしょうか。」(P29)
それに対する宇佐美先生の返しもいい-「最初からすばらしい質問が出ましたね。-」
先生はほかの生徒に対しても、目の付け所の良さなど、まず生徒の質問をほめる言葉から回答を始めている。次世代とともに考えることを標榜する宇佐美先生の面目躍如だ。
一方で、聴講を終えた生徒たちによる“フィードバックミーティング”も後半に採録されているが、宇佐美先生との建設的な質疑応答の後に読むと、違和感が生じたのが正直なところ。
なぜというと、環境問題の議論が活発化しない原因に、政治家やメディアなど自分の周囲から離れた抽象的なものを悪役にかつぎ上げたり、気候正義の“正義”という字面だけを見て絵空事のようにとらえたり…
やっぱりこのあたりが今の日本の中高生の限界かな、とも思った。つまり、生徒だけの議論になると、思春期にありがちの露悪趣味が出てしまい、本音と正反対の斜に構えた主張を他人に対してしてしまうもの。これは何十年も前の私たちの時代と同じだ。
聡明な若い世代ならば、くどい言い方をしなくてもわかると思うが、今の若い世代は自分たちで思うほど過去の世代よりも進歩はしていない。納得できないかもしれないけれど。
だから「論破」という言葉で自分の主張をごり押しし、結局は相手の意見を切り捨てて勝ったつもりでいるだけの、三歩進んで二歩下がるどころか、三歩以上下がっているように見える危うい立ち位置の現代の中高生が、この本をどう読むのだろうか。この本の主題は確かに環境問題だが、いまの若い世代の生き方全般にかかるような、つまり「君たちはどう生きるか」という問いかけも含んだ、試金石のような内容だと私は受け止めている。