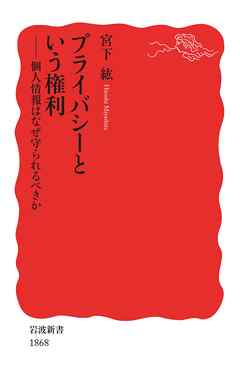あらすじ
デジタル環境の変化に伴い,私たちの個人情報は自分の知らないうちにビッグデータとして利用され,ときに安全や効率をもたらし,ときにリスクをも生み出す.個人が尊重される社会を実現するため必要となるのは,人格形成や民主主義にも関わる重要な問題として,権利としてのプライバシーを問いなおすことだ.
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
なかなか難しいけど勉強になる本。プライバシーが憲法の論点であること、公私での位置付けの違い、各国での哲学の違いなど、ふむふむという感じ。この分野はまだまだ整理が必要そうですね。次回はコロナも踏まえ、アジアの観点も加味したものを期待。
Posted by ブクログ
プライバシーについて非常にわかりやすくまとめられた本だと思いました。
この本では少し触れられていた、「防犯カメラ」についていえば、個人的には、よくテレビなどの犯罪に関する報道で、「防犯カメラに映っていた犯人の映像」などと言っているけど、よく考えるとそのカメラは、その犯罪の防止そのものには役に立っていないわけで・・・。「防犯カメラ」というなら、カメラがその犯罪を行っている人に対して「ちょっとちょっと、そんな悪いことするんじゃないよ」という声がけぐらいして欲しいと思う(笑)。「防犯カメラ」になってないんだから、メディアもいさぎよく「監視カメラ」と言えばいいのにと思ってしまったのでした。
Posted by ブクログ
2021年頃時点での、プライバシーに関する法的・社会的論点について国内外の動向を整理しており、読みやすい。2022年4月に施行される改正個人情報保護法についても、主要な論点をカバーしているように思われた。
1〜3章では、「害悪に基づくアプローチ」を採用する米国と、「権利基底アプローチ」を採用する欧州(特にドイツ)でプライバシー保護に関する捉え方が異なること、また、日本においては、法律上「プライバシー」の保護は明文化されていないものの、他の様々な権利と関連するかたちでの保護が考えられていることに言及している。
4章以降はより具体的に、GDPRと日本の個人情報保護法の内容を中心に、プライバシー保護に関する国内外動向を紹介している。
特に日本の個情法の課題として、公的機関における個人情報の取扱いについての独立監視機関が存在していないことが挙げられている。
また、104ページに記載されている、日本の個情法において権利関係が十分に整理されていないことが、事業者の義務内容の非限定性に影響してしまっているという指摘も興味深い。
最終章で触れられているAIの「説明可能性」については、アルゴリズムに関する専門性を有する者が、アルゴリズムの論理回路を同様の知識をもつ他者に対して説明可能であることを指すとしている。たしかに、人間による介入自体はこのような監査プロセスによって一応成立するように思われる。同時に指摘しているように、他の重要用語である「透明性」や「説明責任」
との区別についてもたしかに大事だと感じた。
これら3つが総合的に達成されたような状態として人間介入の権利を達成していくことが重要であるという点についても理解できた。
Posted by ブクログ
プライバシーと言っても、ドイツを中心としたEU圏とアメリカでは守るべき規範が大きく異なっている、ということを本書で初めて知りました。
日本には、「個人情報保護法」はあるけれど、その法律により守られることが期待されている「プライバシーの権利」については規定されていない、ということも。
ドイツは個人情報にうるさいらしい、と漫然と思っていたことについて、その思想の背景も理解することができましたし、何故海外でフェイスブックがこんなに厳しく批判されているのか、とか、ビッグデータの保存サーバをどの国に置くかが問われる理由等、漠然と抱いていた疑問が、プライバシーの権利やその国際動向を知ることにより、理解できたように思います。
Posted by ブクログ
なぜ、プライバシーは保護されなければならないのか?情報法に通じた専門家が、人格形成や民主主義にも関わる問題である、権利としてのプライバシーを論じる書籍。
プライバシーの保護は、各人の私秘性を保ち、公共性を維持する上で重要である。
それを示す象徴的な出来事が、ケンブリッジ・アナリティカ事件だ。フェイスブック上の膨大な個人データが米大統領選などに利用されたこの事件は「個人データの搾取による民主主義への挑戦」として捉えられた。
プライバシーとは「恥」を隠し、品位を保つための営為である。他方、電話などを無断で聞かれると、羞恥感情はなくともプライバシーを侵害されたと感じる。それは、各人に関する情報は、その人の「人格」の一部をなしているからだ。
従って、プライバシー保護の対象は、恥にとどまらず、各人のあらゆる属性としての自我、つまり人格であると考えられる。
日本の司法の場でプライバシー権が肯認されたのは、1964年「宴のあと」事件と呼ばれる裁判である。その判決において初めて、「私生活をみだりに公開されないという法的保
障ないし権利」としてのプライバシー権が認められた。
欧州評議会「個人データの自動処理に係る個人の保護に関する条約」は、プライバシー保護に関する拘束力をもつ唯一の国際条約だ。
この条約が表す「人間の尊厳」というヨーロッパ的価値をより端的に反映したのが、個人情報に関する様々な規定等を定めたEUのGDPR(一般データ保護規則)である。
データ保護を巡っては、アメリカとヨーロッパの間で衝突が起きている。その原因は、アメリカは「自由の恵沢」、ヨーロッパは「人間の尊厳」と、それぞれ異なる思想に基づいてプライバシー権を発展させてきたことにある。
Posted by ブクログ
大学准教授である著者が最近起きたプライバシーに関する事件やアメリカ、ヨーロッパでの考え方など自身の知見などを元に解説した一冊。
プライバシーという曖昧な概念を日本での歴史と捉え方、アメリカとヨーロッパでのプライバシーの考え方の違いなどをプライバシーをめぐる事件などから知ることができ勉強になりました。
また、ベネッセの名簿売買やリクナビの個人データ販売の問題、新型コロナウイルスにおける接触確認アプリなど最近の事例から法律としてある個人情報保護法とプライバシーの権利の関係や違いやインターネットにおける忘れられる権利など読んでいて考えさせられることも多くありました。
そんな本書の中でも義務の章典と権利の章典で企業か個人のどちらにフォーカスを当てるかで解釈がかなり変わってくることやGDPRが今の日本の法制度では対応が難しいことなどは勉強になり、印象に残りました。
本書を読んで今の世の中においてネットのなどの普及によりプライバシーに関する問題は新しい局面を迎えているとともにアメリカやヨーロッパの動向を踏まえて日本のプライバシーについての本質的な理解をもっと深めないといけないと感じた一冊でした。
Posted by ブクログ
個人情報保護の問題については、この数年、日本では個人情報保護法の改正、EUのGDPRの施行等、大きな変化が生じている。
本書は、全体を通して、プライバシーの保護、個人情報の保護はなぜ求められるのか、その核心は何なのかについて、主に法学的観点からの考察がされている。興味深いのは、第四章「プライバシー保護法制の国際動向」で、EUと米国の取組姿勢の違いや具体的な規制の在り方に関して、政府からの「個人の自由」を確保することに主眼を置くアメリカに対し、「個人の尊厳」を重視するEU、両者の対象が論じられている。
個人情報の保護と、データの有効な利活用、両者のバランスをどう図るのか。個人個人でも考え方は違うだろうが、制度的にどのように構築するか難しい問題だと思う。そうした難しい問題を考える上で、本書のような原理的なところからの考察は、極めて有意義だと思われる。