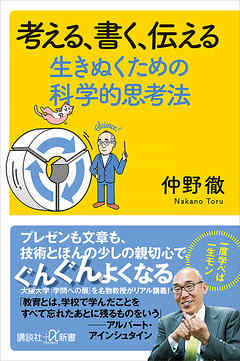あらすじ
お笑い芸人で小説家の又吉直樹が世の中の不思議を探る教養バラエティ「ヘウレーカ」で、たびたび招かれるのが、大阪大学医学部病理学教授・仲野徹先生。専門は「いろんな細胞はどうやってできてくるのだろうか」学。ベストセラー『こわいもの知らずの病理学講義 』の著者でもあります。
ご当人は「めざすはお笑い系研究者」と述べていますが、ノーベル賞を受賞した本庶先生の愛弟子としても有名です。
その仲野先生が、自ら実践してきた「学び方を身につける」ための方法論を初めて披露します。
大阪大学「学問への扉」仲野ゼミを舞台に、大学1年生14人に行った講義は、わかりやすくかつ実践的。仲野先生は、論文、プレゼンなどの指導とともに、学びの頂点である「発想」や「考える」技術を教えていきます。それは、生きるために欠かせない一生使える力です。
コロナ禍で始まった15回のゼミ。オンラインでつながった学生14人が、仲野先生の講義でどう成長していくかも実感でき、何が成長の要因かも見えてくるでしょう。
さらに、論文やプレゼンは医学と健康をテーマにしています。ゼミ生とともに正しい情報のとり方や選択の仕方も楽しく学べます。
仲野先生が、「教育とは、学校で学んだことをすべて忘れたあとに残るものである」というアルバート・アインシュタインの名言を現実のものとするゼミを開講。
「ようこそ、『学問への扉 仲野ゼミ』へ! あなたも受講するつもりで、いっしょに楽しんでください」
感情タグBEST3
Posted by ブクログ
科学的な考え方を持って、適切なデータを集めて論文という形まで書き上げたゼミを紹介した書籍。擬似体験的に学ぶくとができる。科学的思考を学ぶために選ばれたテーマも興味深いもので、読みもとしても楽しめる一冊でした。
Posted by ブクログ
一度だけ近くでお話を伺う機会がありFacebookでもお友達になって頂いている高名な先生の作品。こういう間違って本人の目に入る可能性があるものについては感想書くのやめようかとも思ったのだが内容が素晴らしかったので…。先生が勤務されている大学で実際に行われた講義を元にまとめられたものでその講義の目的はタイトルにある通り。ある事柄を科学的に捉えて理解し、それを他者に伝える方法を指導するというもの。自分は文学部を出ていて科学的とは程遠いバックグラウンドなのだけど非常に興味深く読んだ。まず何よりも感じたのは大学に入って最初にこういうことを教えてもらえる生徒は幸せだな、ということ。論文の書き方とか思えばちゃんと教えてもらえてない、もしくは学べていない気がした。だいたい講義のレポートにやっつけで対応して卒論もなんだか…という感じだったので...正直いうと卒論に関してはもっとちゃんと書きたかったな、と今でもかなり後悔している。自分は文学部で卒論も古典作品に関するものだったわけだがこの作品で説明されているような手法を知っていればもう少しマシなものが書けたのでは、と思う。もちろん思索が一番重要だけど本作で示されているような一つの雛形というかテンプレートのようなものがあって、いわばコツのようななものがあった方がはるかにやり易いことは言うまでもないだろう。そしてここで書かれているようなことは社会に出て報告や説明を行う際にも大いに役に立つに違いない。学生さんたちの実例も載っていてやはり良い大学の学生さんは優秀だなと感心した。願わくば半ばリタイアしたような今ではなくもっと若い頃に読みたかった。理系文系問わず大いに参考になる内容。おすすめです。
Posted by ブクログ
大阪大学の仲野徹教授のゼミを書籍化したもの。興味の湧くテーマを決めて、調べて、問いを立てて、論文としてまとめあげる一連の流れを学生が実践している。実験や研究はしない。誰でもできる「調べて、書くこと」を噛み砕いて説明し、学生にやらせてみて、添削し、推敲を重ねて完成品をつくっている。この「調べて、書いてみること」がなかなかに大変であることが読んでいてもわかるし、実際にやってみると大変だ。でも仲野教授はこの一連の流れがなによりも大切で、生きるための基礎力になることを力説している。誰でもできる。習慣化すれば早く質の良いものが出せる。考えも深まっていく。
メモとして特に印象に残った部分を個人的に引用する。
>結局のところ、いろいろと書いても、読んだ人が覚えていることはごくわずかです。「Take home message」は少ししかない、ということです。なので、タイトルで引きつけておいて、それに対する結論をパチンと書くのが望ましい。覚えてもらえるとしても、タイトルと結論だけぐらいですから。
Posted by ブクログ
従来の詰込み型学習から、自由である反面、態度によって圧倒的に差がつく主体的学習への移行期たる大学入学時。受講生の感想にもあるように、この内容の講義を受けられるのは僥倖かも。プレゼンにしろ論文にしろ、離れたら離れたでどんどんコツを忘れていくもので、そういう意味では、結構復習になりました。自分の今後において、はたしてどれだけ使う機会があるか、そこがまた微妙だけど。
Posted by ブクログ
「学ぶ」と言う事の大切さは、年齢に関わらずその人の人生にとって有益となる。それには「考える力」を養い、それを「形にする」(書く・プレゼンする・教える・伝える)事で自分の知識として蓄積されて行くと思う。 「なぜ」がその初歩的アプローチになるのだ。好奇心を持って「なぜ」の質問をし、自分の知識を積み重ねていきたい。
Posted by ブクログ
<目次>
序章 仲野ゼミのテーマ
第1章 本番開始!
第2章 最低限のノウハウ1
第3章 最低限のノウハウ2
第4章 実践編 初めての個人論文
第5章 実践編 改善した個人論文
第6章 実践編 グループで作る論文
第7章 授業終了
<内容>
おなじみ大阪大学仲野教授が大学で実践した、大学入門ゼミを文字化したもの。大阪大学の1回生が受けている「学問の扉」という入門ゼミを担当した仲野先生が、2020年度、コロナ禍でZoomを使っておこなったこのゼミの模様を、実況中継した様子が綴られる。先生は医学部の教授ですが、入門ゼミなので他学部の学生ばかり。2回の実践をおこなっているが、第1回は故人で論文&発表。2回目は4人組(一部5人)で集団で論文&発表。むろんその間にテーマを発表して、討論してもらい、改善していく。全員のものはないが、2人と1組の実践内容が示されている。みるみるよくなっていく様子が見て取れる。本校(高校)の「総合学習」で似た取り組みをしているが、さすが大学生と大学教授。学生に示す示唆も素晴らしいし、学生もしっかりと取り組んでいる。今の学生は真面目なので、ちゃんと道筋を示せば、しっかりと取り組むんだよね。うちの先生たちに読ませたい。