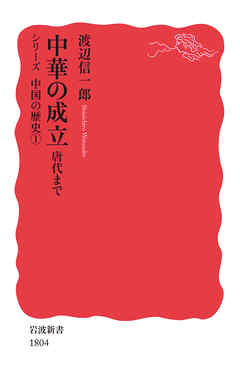あらすじ
「中国」はどこから来てどこへ行くのか.群雄割拠を繰り返してきた雄大な歴史を,世界史的な視座から全五巻で描きだす画期的な試み.第1巻では黄河文明が展開した華北を中心に,先史時代から秦漢の統一や三国時代などを経て,中華帝国が形成される八世紀半ばの唐代中期までを扱い,伝統中国の原型を明らかにする.
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
中国の歴史に関する基礎知識が足りなさすぎて、半分も理解できなかったけれど、知識をつけてから読んだら相当おもしろいだろうと思う。
「二里頭文化を形成した人びとは、みずからを夏あるいは夏人とよんだとみられる。(中略)二里頭文化は夏王朝と密接な関係をもっている。最近では、中国はもとより、日本の研究者も、二里頭文化とのかかわりから夏王朝の実在を説く人が多くなった。」p.21
「殷は、卜辞の中では終始自らを商と称し、その中心聚落を大邑商・天邑商・中商などと記述している。王朝名である商は中核聚落の土地名であり、殷という名は周が美称としてよんだもので、盛んであること、殷賑を意味する。」p.23
「周は、殷を討伐し、王権を掌握する正統性の根拠として天、天命の観念を創造した。(中略)やがてそれは王の称号のほかに、天使の称号を生みだした。」p.28
「前770年、内部対立と周辺諸族の侵入により、周王は、宗周を放棄して成周に遷った。これ以後、前221年の始皇帝による全国統一までの約550年間を東周とよぶ。
東周期は、さらに二つに分けられる。前期(春秋時代)は、通説では西周東遷の前770年から、大国であった晋国が韓・魏・趙三国に分裂する前453年までをいう。(中略)
それ以後、前231年までを、主要12か国の政治過程や遊説家の言動を記した『戦国策』にちなんで、戦国時代とよんで区別する。
(中略)それは、中国における「英雄時代」、すなわち国家形成の時代であった。」p.40
「春秋時代には、周王に対する諸侯の自立性が高まるとともに周王の権威が衰退し、封建制が動揺した。春秋時代にはいると、各国間の戦争が常態化するようになる。戦争による競合の中で、諸侯は天子に対する貢献を経常的におこなわなくなり、封建制の基盤である貢納性が不安定になった。斉国の恒公(在位前685~前643)・晋国の文公(在位前636~前628)など覇者とよばれる国君がつぎつぎに現れ、諸侯を一堂に集めて会盟をおこない、王権に対する貢献性を再構築して封建制の維持をはかった。」p.41
「秦国は、秦王嬴政(えいせい 前259~前210、在位前246~前210)の統治時代にひると、さきにみたようにつぎつぎと六国を滅ぼし、県の上に群を設置していき、前221年、天下を統一した。秦王政は、王・天子の称号を棄て、それらをこえる王権の称号として皇帝号を採用し、始皇帝と称した。皇帝号は、天上の絶対神である皇天上帝に由来し、宇宙を主宰する偉大な上帝そのものを意味した。」p.74
「前210年、巡行の途中で始皇帝が病死した。それがおおやけになると、前209年、陳勝(?~前208)、呉広(?~前209)などの農民軍や旧六国の王族たちが各地で蜂起した。」p.82
「文帝劉恒(在位前180~前157)は、在位の23年間、倹約に努めて百姓の生活安定を図り、「もっぱら徳によって民衆を教化したため、天下は殷富となった」(『漢書』文帝紀賛)。しかし文帝が即位したころ、北方ではすでに匈奴が強大な遊牧国家を形成していた。
匈奴は、前4世紀末ごろに起こり、前3世紀末の冒頓単于は、当方の東胡、西方の月氏等の諸種族を統合してモンゴル高原を支配した。前200年、高祖は、匈奴を討つために親征したが、白登山(山西省大同市東北)で大敗し、屈辱的な和議を結んだ。文帝の時代に至るまで、漢は、毎年黄金や高級織物を匈奴の貢納して臣従を示していた。」p.84
「文帝とつづく景帝劉啓(在位前157~前141)は、二代にわたって王国・侯国の領土と権力の削減につとめた。これに反抗して、前154年、呉楚七国が反乱を起こしたが、わずか三か月で漢朝に制圧された。これを転機として王国・侯国の権力削減がいっそう進んだ。」p.85
Posted by ブクログ
中国は、強権的な政治体制で国民の権利を制限しつつ、国家主導で経済力や軍事力を発展させ、国際的に様々な影響を与えている。海洋進出、環境汚染、経済力にものを言わせた途上国への影響力行使・・・。その覇権主義的な動向は、民主的な国々との対立を深めている。果たして、この国はどのような歴史的な過程を経て現在に至るのか。今後、世界情勢はどのような経緯をだどるのか。そのヒントを探したく、手に取ってみる。第1巻は先史時代から中唐時代まで。黄河・長江流域の地域での多様で多くの文明の中から王朝国家が生まれ、紆余曲折を経て中央集権的な体制が採られていく過程を描く。
Posted by ブクログ
中国はいかにして中国になったのか――歴史を紐解きながら中国に迫っていくシリーズの第1巻。扱われるのは中国の「古典国制」の成立とその変容。政治と社会の仕組みからその実態を追っていく。王莽の再評価、従来説による均田制や租調庸制についての批判など、新しい成果を反映した記述になっていて興味深い。とはいえ、注意を要する記述もある。斉の国都から出土した人骨から抽出したDNAがヨーロッパ人類集団に近いとの説などは、これを否定する論文もでている。
Posted by ブクログ
岩波新書には「中国近現代史シリーズ」もあるので、本シリーズは清までを扱う。第1分冊でいきなり唐代までという切り方もすごいなと思う。国家の成り立ちを行政それも収税システムをメインにして展開するところが新鮮だった。これは最新の研究成果に負うところが大きいらしい。納税にまつわる資料の発見が進んでいるということなんだそうだ。僕らが思う中国のカタチは王莽が考え、後漢の時代に形成されたものってのは、初めて認識できたように思う。うん面白かった。次が楽しみだ。
Posted by ブクログ
紀元前5000年から始まる仰韶(ぎょうしょう)文化、前3000年の龍山文化をスタートとして隋の時代までを新書にまとめるのは、凄い労力のいる仕事だと感じた.前221年に始皇帝が曲がりなりにも中国の統一を果たすが、北からの侵略や内乱で揺れ動く.郡県制を成立させ、封禅祭祀を挙行することで皇帝としての権威を誇示した由.国の形の根本に生民論と承天論があり、王莽(おうもう)が様々な制度を作り上げた.安禄山が出てきて、第1巻は終わったが、次巻にも取り組もう.
Posted by ブクログ
入り組んだ中国の歴史を読み解くシリーズの第一弾。
初期の中国は戦国時代の印象が強く、武力による統一という点に焦点があたりがちだ。
本書はフラットな目線で国家の成立や衰退が描かれており、官僚制度や律令の重要性を感じとることができる。
この分野の門外漢としては用語の意味を追うだけでもなかなかに大変だったが、大国の成り立ちを知るよいきっかけになった。
Posted by ブクログ
難しかった。これまで読んできた中国史の本とは視点が違っていて、社会のシステムの話がメインだった。中国を、草原世界の東端と、海洋世界の北端が出会う場所だという話は印象的だった。
Posted by ブクログ
「シリーズ中国の歴史」の第一巻目、古代から隋唐時代までを一冊にまとめられています。古代については、資料などからどのような集団を作っていたのかを具体的に浮かぶように説明されていて、その中からどのように支配層が誕生してきたのかが想像でき、当時の様子を思い浮かべながら興味深く読むことができました。そのためか、(発掘資料などからの)古代の人々の生活状態の解明から、中国各地の国家群の形成まで進めていくことで、後半部分は、必然的に内政を中心に書かれたものとなっています。政府の形態や、そこで働く官僚の手当、それぞれの地域を守る兵士の徴用など。これはこれで面白かったのですが、これでは中国の歴史の一部になってしまっており、個人的には後漢あたりで2冊に分けても良かったのではと感じました。著者もそのあたりは了解されているようで、2巻にてそのあたりを補完されるとのことです。
Posted by ブクログ
〈シリーズ中国の歴史〉の第一巻。
全5巻各冊の冒頭に、「今、中国史をみつめなおすために」と題した、本シリーズ全体の狙いが述べられている。「中国」という枠組自体を自明視することなく、多元性、多様性の中国をいかに捉まえ、現代中国につながる歴史を論ずることができるか。野心的で、非常に楽しみな試みである。
第一巻においては、中国はどのような社会と政治のしくみを創りあげながら、隋唐時代にいたる中国・中華世界を原型を形成したのかが主題とされる。
まずは素朴な感想。文字史料の絶対的に少ない古代社会を知るには考古学的資料が重要であるが、中国の経済開発に伴い発掘が進み、農耕聚落の構造や大規模城郭の様相等、多数の新たな発見が相次いでいることを改めて知ることができた。
社会統合の制度として、殷代の貢献制、西周の封建制、春秋戦国期の県制、秦王朝の郡県制、漢の郡国制と、その変遷が叙述されるが、この辺りの記述は正直良く分からない。また、非常に重要な税制、財政に関する叙述も、基礎知識に乏しい読者には理解に厳しいものがある。
ということで、歯応えのある内容であることは間違いないと思うのだが、読者には相当の歴史的素養が求められているようだ。