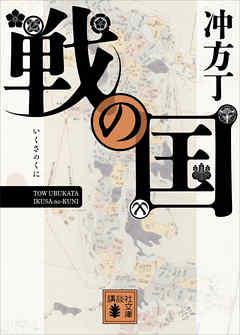あらすじ
織田信長、上杉謙信、明智光秀、大谷吉継、小早川秀秋、豊臣秀頼。
戦国時代を駆け抜けた6人の真の姿を描き切る。
『天地明察』『光圀伝』と傑作を残してきた著者の、新たな代表作。
感情タグBEST3
Posted by ブクログ
この本を読んでから、大谷吉継が推しになりました。会社の同僚や、周りの人を見ても、
この人、戦国時代なら出世しただろうなぁ、
とか、
この人、足軽で真っ先に死ぬタイプやな、
とか、
全てを武将に置き換えてニヤニヤしてしまう。
たのしい。おすすめ。
Posted by ブクログ
信長と義元、景虎と晴信、光秀と信長、秀頼と家康など、直接会話をするわけではない相手との関係性を意識した作品群。元は雑誌企画のようだが、一冊の本としてよくまとまっている。話が出尽くされてる戦国ものをこれだけしっかり書けるのはすごい。
Posted by ブクログ
時系列順に様々な武将の生き様がオムニバス形式で執筆されていたので、戦国時代をそれぞれの人物の視点から体験。
特に晩年の家康と豊臣秀頼の水面下での知略の攻防が面白かった。互いに牽制し会うなかで二人が知将ゆえに共感しあう部分があるのは興味深かったです。
Posted by ブクログ
戦国時代を駆け抜けた有名無名六名の武将を、それぞれの視点で描く短編連作ながら、全てが繋がっている完成度と緻密さ、何より全作品の説得力に圧倒されました。
以前、別の本で「白き鬼札」を読んだ時には、光秀が本能寺の変に至るまでの心境の変化にかつてなく納得し、その光秀像が自分の中で最も腑に落ちると思っていたのですが……この本に収録されている他の五編についても、同様の衝撃を感動を覚えました。
信長や光秀と言った智将で知れた人物は言わずもがな、一般的なイメージでは暗愚や凡庸な小者として描かれがちな武将たちも、この本では皆、類まれな頭脳と高い理想の持ち主として登場し、それぞれの信念を曲げることなく、智謀を巡らせ、家康らと互角に渡り合う。その深い思想に違和感を覚えることなく、どの主人公にも一切嫌悪感を持つことなく物語に没入できます。いやはや、特に大谷吉継の格好良いことよ……!
この方が秀吉や家康を描いたらどうなるのかな、などと妄想を膨らませつつ。血腥い戦場が舞台でありながら、からりと気持ちの良い将たちの生き様が快い、短編ながら骨太な一作でした。
Posted by ブクログ
「決戦!」シリーズに書き下ろした作品に加筆し、「道」というテーマで統一した連作集。
織田信長、上杉謙信、明智光秀、大谷吉継、小早川秀秋、豊臣秀頼という戦国末期の六人の武将を、著者独自の視点で描いている。
各編とも、著者の想像力を駆使して、今までの歴史観を覆すような人物像が現れる。
特に、『真紅の米』の小早川秀秋。
凡愚の代名詞のように言われているが、けっして凡愚などではなく、彼は生い立ちの立場から利発さを秘して行動していたとしている。
『燃ゆる病葉』の大谷吉継。
関ヶ原での活躍ばかりが語られるが、家康とも厚誼があり、最後まで関ヶ原の戦いを忌避せんと光秀を説得しており、家臣からも絶対の信頼を寄せられていたことが綴られる。
『黄金児』の豊臣秀頼。
家康とも対等に渡り合う、英明で戦略的な傑物として描かれている。大阪の冬の陣では、秀頼自ら出陣したとも。
歴史は勝者によって造られるとの言葉がある。取り上げられているのはいずれも非業に倒れた人物たちであり、こういう見方もあるのかと、新発見をする作品といえる。
Posted by ブクログ
6編から成る戦国時代の短編集。
織田信長の桶狭間・上杉謙信の川中島・明智光秀の本能寺・大谷吉継の西軍関ヶ原・小早川秀秋の東軍関ヶ原・豊臣秀頼の大坂冬、夏の陣をそれぞれの一人称の視点で描写し、戦国時代を表現しています。
それぞれいろいろな戦を集めた短編集から集めた作品ですが、戦の相手の想いも加え巧く戦国時代を表現している一冊となっていると感じました。
Posted by ブクログ
目次
・覇舞謡(はぶよう)―織田信長
・五宝の矛(ほこ)―上杉謙信
・純白(しろ)き鬼札―明智光秀
・燃ゆる病葉(わくらば)―大谷吉継
・真紅(しんく)の米―小早川秀秋
・黄金児(おうごんじ)―豊臣秀頼
すっきりと短い文章がリズミカルに続き、とても読みやすいのだが、逆に文章がつるつると滑り、血は沸かず、肉踊ることがない。
どの主人公も同じ論理を内包し、一人それを抱えて戦に向かう姿には顔がない。
よくできた講釈を聞かされたようで面白くはあったが、心が震えるまではいかなかった。
冲方丁ってこういう文章を書く人だったかなあ。
隠しテーマである『道』にとらわれ過ぎたのではないか。
戦の要は道である。
軍団を素早く安全に運ぶための道は、物資を運ぶ道となり、その道を通って人が集まり、集落ができる。
戦の先を見据えた武将たちの物語。
元々は講談社の歴史アンソロジー企画「決戦!」シリーズとして書かれたものを、一冊にまとめたのが本作。
ばらばらの短編をつなぐのが、『道』ということなのだが…。
この中では、本能寺の変を扱った「純白き鬼札」が面白かった、
そう、本能寺の変の時、光秀は当時でいうともう老将なのだった。
見たいものだけを見、見たくないものを避けて信長に付き従った10年。
齋藤道三亡き後頼った朝倉氏を見捨て、将軍家をも切り捨てて従った信長に自身の老いを突きつけられた時、光秀は何を考えたのか。
これがしみじみ理解できる年齢に私もなったということか。
Posted by ブクログ
久しぶりの歴史小説。『天地明察』&『光圀伝』で完全にノックアウトされて、冲方歴史作品への信頼が固まったんだけど、『はなとゆめ』がイマイチで、ひょっとして戦国ものに限って優れているのかも、と思い直して今に至る。それだけに、本作に対する期待もひとしお。で、結論としてはまずまず。件の二作品には到底届かず。短編集ってこともあるし、個人的には並べ方もまずかったと思う。最初の2章が全然ダメで、それだけだと☆2.5くらい。信長と謙信については、目下連載継続中の漫画作品をまさに読んでいるせいもあってか、事実の羅列にしか感じられんかった。3章以降はそれなりに楽しめたから評価は持ち直したけど、せめて発表順に並んでいたら、もうちょっと印象も変わったのかも。必然的に長くなりがちな歴史小説だけに、短編集で読んだ経験はあまりない気がするけど、やっぱりジャンル的に合わないのでは、と思えた次第。
Posted by ブクログ
盛り上げが上手で、テンポよく話が進み分かりやすかったが、精神論がややしつこく飽きそうにもなった。今まで知っていた武将のイメージに、膨らみができて良かった。
Posted by ブクログ
歴史に取材した小説だが、現代的な視点で描いてある、モダーンな感じ。光秀のビジョナリーな様子は、こういう捉え方もあるのかと感心した。また、小早川秀秋が実は才人で、というのは新鮮だ。確かに正史にきちんと残らなかった人々とはいっても、官僚制が整っていない時代に、いっときは国を統べ、大勢の家臣を束ねるトップであったのだから、全くの暗愚ではなかっただろう。
Posted by ブクログ
正直なところ、今までの冲方丁作品よりは面白くなかったが、それでも最後の秀頼の話は新しい観点で面白かった。教科書で知ってる戦国武将とはだいぶ違うので、フィクションということはあるけれど新鮮でワクワクしながら読めた。
Posted by ブクログ
日本史は正直全然わからない自分でも知っているような合戦に臨む武将の短編集。いやぁ、面白かった!
歴史上人物だって一人の人間だし、こういう風に考えたのかもしれない、こんなことを感じながら戦場に臨んだのかもしれない、と思うとさらに面白かったです。
私はあまり時代小説を読まないのですが、筆者に思い入れがありすぎる作品だと、歴史上の人物が超人すぎたり、感情表現が奇天烈すぎたり、それにまた入れ込み過ぎる家臣などが出たりすると随分ウェットだなぁと思っていたことがありました。ま、お涙頂戴ものは昔から好まれる王道パターンではあると思うのですが。
この本では人間関係がそこまでドロドロしてないというか、自分がそうしたいからそうした、というような非常にわかりやすくカラッとした動機で動くので明快でわかりやすかったです。もしかしたらこういう一面もあったのかもしれない。なかったのかもしれない。その辺りを考えるのもロマンですしねぇ。
というわけで武士の世が終わる辺りではこういう痛快な時代が終わってしまうのか…という一抹の寂しさのようなものを感じました。戦はイヤなんですけどねぇ。
Posted by ブクログ
織田信長、上杉謙信、明智光秀、大谷吉継、小早川秀秋、豊臣秀頼の物語。上杉謙信の「五宝の矛」がダントツで面白かった。次点で、実は色々考えていた小早川秀秋の「真紅の米
」と、同じく能ある鷹が爪を隠していた豊臣秀頼の「黄金児」。
Posted by ブクログ
苦手だ~。冲方丁の筆を持ってしても、僕には戦国時代小説は面白いと思えない。
読みやすくて分かりやすいけど、単純に面白味を感じない。
興味が持てない。江戸時代の庶民や武士の話は、とても面白く好きなのに、何故かダメなんだよな。
今回は、面白く読めると期待したけど、やっぱりな~。
伝奇小説のようには、いかないな。
Posted by ブクログ
戦国時代に活躍して6人の武将(織田信長・上杉謙信・明智光秀・大谷吉継・小早川秀秋・豊臣秀頼)を取り上げた短編集。
何となく知られている武将のエピソードを掘り下げ、著者独自の解釈で焼き直しているイメージ。
全体的に読みやすいが、個人的には何か物足りない気も。
Posted by ブクログ
表紙のデザインが良い!
解説で書いてあるとおり「道」をキーワードとして書かれたもので、戦国時代の小説を読む中で初めて、道というものを意識した。新鮮だった。
明智光秀、大谷吉継、小早川秀秋の話が特に好き。
それぞれ短編は星5こでは足りないくらい。
上杉謙信はあまり詳しくないし、今回読んでも興味を引かれなかった。
さいごの豊臣秀頼の話は、その前の短編から優れた男の話が続いて食傷気味になっていたこともあってハマらなかった。
Posted by ブクログ
明智光秀の話がお気に入りです。お話の構成が巧みで、ミステリーを読んでいるかのような爽快感がありました。
本能寺の変を前にして、明智光秀が過去を振り返ります。
一切ハゲてないのに日常的にハゲ呼ばわりされたこと、過酷な環境で超大変な任務を任され苦労したこと、仏教施設でジェノサイドを命じられたこと、近頃信長の子供たちばかりひいきされるようになってきたこと、重要な戦から外されて手柄をあげにくくなってきたこと。
果たして、一体どの要素が謀反への決定的なトリガーとなったのか。何が光秀をここまで駆り立てたのか…。
ラストで明らかになる光秀の激情と、炎上する本能寺がとても美しいと思いました。
教科書で習った「三日天下」だと、秀吉に美味しいとこどりされた哀れな光秀という印象でしたが、本書を読むと大分かわりますね。
信長に「もうお前とは同じチームで遊んでやらねぇよ」と言われた。だから遊び仲間から対戦相手にシフトチェンジした。そんな風に読めました。