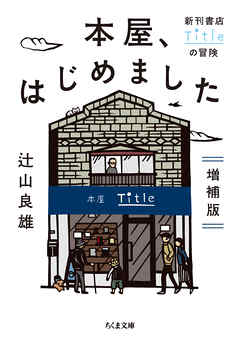あらすじ
独自性のある新刊書店として注目され続けるTitle。物件探し、店舗デザイン、カフェのメニュー、イベント、ウェブ、そして「棚づくり」の実際。事業計画書から、開店後の結果まですべて掲載。個人経営の書店が存続していくための工夫とは。リブロ池袋本店マネージャー時代から、現在まで。文庫化にあたり、開業から現在までを書き下ろした新章「その後のTitle」を増補。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
本屋開業までのプロセス、オーナーの心理状態、背景などが余すことなく語られる。おまけに事業計画書まで・・・個人の新刊書店を立ち上げたい方におすすめです。そして、最後の若松英輔さんの解説「書物が生まれる場所」が読後感をさらに満足高いものにしてくれました。
Posted by ブクログ
本屋を始めたいと考えているならまずはこれを読んで!と多くの独立書店主さんが太鼓判を押す1冊。
本屋開店までのいきさつ、流れなどを丁寧に詳しく書いてくださっているのでとてもわかりやすい。ご自身のお店に対して「こうありたい」という希望と、お客様に対する書店主としての責任感が強く感じられる。まだ訪ねたことはないけれど絶対に素敵な本屋さんだと確信できる。
Posted by ブクログ
筆者が新刊書店を開くまでと開いたあとについて記載されている。
特筆すべきはP/Lが詳細に載っており、事業計画書から内装や什器の設置など開業に必要なことが細かに書いてある。
また、筆者の店舗経営についての考えも競争戦略がきちんと立っており、学びが深い。一冊。
Posted by ブクログ
荻窪の本屋Titleの開業1年目までと、5年後に書かれた増補章。
前半のリブロパートもめちゃくちゃおもしろいし(憧れの時代のリブロ!)、開業準備・開業してからのパートはグイグイと集中して読ませてもらった。
細やかな気配りと目配り、町への愛着、選書へのこだわり。あーTitleに行ってみたい!行ったら、ますます本屋を開くことに挑戦したくなってしまうのだろうな…。
Posted by ブクログ
行ってみたかった本屋さんがあった。
本屋さんなんてどこも同じ、では決してない。
意思がある本屋さんにあこがれる。
だけど、こじゃれたブックcafeとか、
本をおしゃれな小道具的に扱うような本屋さんは範疇外で。
荻窪駅から徒歩10分以上、あれ? この道で合ってるよね?
と思い始めたときにさりげなく現れる書店。
それがこの本の著者が経営するTitleだ。
最初は2階のギャラリーで行われる展示に興味があって出かけた。
展示自体にもワクワクして本をにぎりしめ(ちなみに牟田都子氏の『文にあたる』)
階段を駆け下りて購入し、今度は書棚をじっくり見る。
欲しい本がたくさんある。1階でもワクワクして止まらない。
書棚の奥にはカフェがあるが、そこに購入前の本は持ち込めないところも好き。
「きれいな状態で本を売りたいので」とのポリシーに(勝手に)激しく賛同する。
子どもの頃から本屋さんはあこがれだった。
だけど小学生の頭の中では、本屋さんてヒマそう。としか思えなかった。
そこに戦略があるとか、販売努力があるとか想像だにしなかった。
だけど、どんな店でもあたりまえにそういうものはある。
そんなことに今さらながら気づかせてもらった。
p231
以前の会社でも本を売る仕事はしていたが、Titleをはじめてから、自分は本に関して何も知らなかったと気づかされることが多かった。この本読んだとか、この作家はどういうひとなのかと、店頭で尋ねられるのはいつものこと。そのようなときに名前を知っているだけでは、お客さんからの信頼は得られない。
↑
ここ、本当にそうなのだけれど、そういうことを店員さんに聞く人がいることが驚いたというか、聞いていいんだ、そりゃそうか本屋さんなんだもの。と思った。そしてこう続く。
p231
本について知りたければ、自分でも数多く読んでみること以外ほかにはない。店に並べているなかに、読んだことのある本が増えてくると、そこにある本が自らの延長のように思えてくる。
↑
そして
その見当がつくようになると、自分の実感がこもったことばで本を紹介できる。
と言う。
本を人に紹介するとき、ただ「よかった」を連呼して、やみくもに冗長に語りがちな私だが、「自分の実感がこもったことば」を持ちたい。
p233
(本も同じであり、)差一緒は読めないなと思った本でも、毎日少しずつでも読むことで、その本に出合ったと思う瞬間が訪れる。突如目のまえにあらわれた、自分の実感と深く結びつくようなことばが、一瞬にしてその本全体のことを、読むものに伝えるのだ。
p235
(だから、)必要な手間がかけられていない本は、どこか薄っぺらく見えてしまう。いま本が出せればそれでよいというその場しのぎで作られた本には、長く人の心をとらえる力が宿らない。細部に手をかければかけるほど、出来上がったものの網の目が細かくなり、時間に耐えうるものになるのは、本も本屋も同じことである。
↑
本に携わる人間として実感と自戒をこめて
p242
本はどこで買っても同じとはよく言われることだが、実はどこで買っても同じではない。価格やポイントでお客さんを釣るのではなく、本の勝井を〈場〉の力で引き立てることにより、その本は買った店と共に、記憶に残る一冊となる。
個人の想いが詰まった本
私自身も個人経営したみたい願望があり、この本を手にとりました。しっかりとしたビジョンを確立しており、本人がやりたいようにお店を作っていっている模様が随所にかいまみえました。大変、参考になりました。
Posted by ブクログ
大手書店員時代のエピソードも興味深かったが、特に印象に残ったのは、退職後に実際に新刊書店をオープンするまでの具体的なノウハウや苦労が綴られていた点である。理想だけでは成り立たない現実的な問題や準備の大変さが描かれており、巻末の事業計画も含め、その過程がとても面白かった。
かつては家の近所に、小さな個人経営の本屋があるのが当たり前だった。
しかし、本が売れにくい今の時代、ただ「街の本屋」というだけでは生き残るのは難しい。これから個人で新刊書店を経営していくには、何かしらの強い特色や工夫が必要なのだろうと感じた。
Posted by ブクログ
本屋をやる、楽しくやる、工夫してやる気力が湧いてくる、感化される。開業についてかなり詳しく書いてくれているので実践的な役にも立つ本。店舗に行きたくなる。
Posted by ブクログ
元リブロで、個人書店Titleの経営者の辻山良雄氏による「創業体験記」といった本。
最大の特徴は、巻末に、事業計画書と実際の1年目の損益計算書が掲載されていること。
そして、最大の驚きは、予算の精度が非常に高いこと。
「今から店を出す」という時点で、どうやったらここまで精度の高い予算が組めるのか、想像もできない。
Posted by ブクログ
本に対する豊富な知識と、本に向き合う姿勢がまっすぐで感動的。
さりげない部分にこだわりが詰まっている本屋さん。
いつか行ってみたい場所になりました。
Posted by ブクログ
新卒で入社した全国チェーンの書店で15年働き、マネージャーを務めた巨大店舗閉店とともに退社、新刊書店開業。
会社員としての下地がこの挑戦を底上げしている上に、自分のやりたいこと、やるべきことをしっかり持っている印象。Titleは必ず行くと決めている書店のひとつ。
Posted by ブクログ
著書の本屋の独立開業の経緯を丁寧に書いた本。
実際に店舗に何度か足を運んだことがある身としては、著者の考え方がうまく店舗に反映されているのがよくわかる。
一方でイベントの仕掛け方やプロモーションなど、ビジネスのリアルな部分も見える内容となっている。銀行から融資を受けるところから丁寧に描かれており、単なるサクセスストーリーではない個人事業の空気感も伝わってきた。
Posted by ブクログ
さっくり読めます。
最近個人本屋さんが増えており、旅先でもよく行きます。どのように開業しているのか、どんな思いでやっているのかの一端が垣間見えます。
本屋さんに行く前に読むと、より本屋が楽しめる良書です。
Posted by ブクログ
事業計画など、数字の面を赤裸々に綴っていて、書店経営の実情を知ることができたのが面白かった。
それでも、書店をやってみたいと思わされる内容だった。
Posted by ブクログ
大手書店で勤務していた著者による本屋開業までの道のりと、どのように開業したのかを詳細に記した本。ちょっとした小物の金額まで書かれていて、もし自分が本屋を開業しようと思ったら真っ先に読み返すことになるだろう。
今でこそ界隈では有名になった『title』という本屋。淡々と、それでいて想いを込めた書棚作り、イベントと、併設するカフェメニュー開発。好きを仕事にすることって本当に楽しい。
Posted by ブクログ
書店に勤めていた著者が、自らの店を持つまでのお話。店を出すと決断するまでの経緯や、決めてからの準備、開いてからの活動など、リアルに感じられる内容で面白かった。起業、開業など考えている人には参考になるのでは。衰退傾向にある書店を新たに始める著者ご自身の意義、目的、目指したい姿など。つまるところそこが大事なんだと感じさせてくれる。売ることだけに執着すれば他のアプローチもあるだろう。ただしそこはご自身の本に対する、あるいは書店に対する想いからがあるからこそ、踏み外さない理想の姿を追い求めて前に進んでいるように感じられる。店を通してセルフプロデュースがなされているのかもしれない。どんなところなのか興味が湧いて、行ってみたいなと思わせる。
Posted by ブクログ
本屋をやってみたいと読書が好きなら一度は考えるかと思うが、本屋をやるうえでの苦労ややりがいなど、とても具体的に伝わってきた
ぜひ行ってみたいと思えた一冊
Posted by ブクログ
個人の本屋さん、好きです。
東京には、たくさんの個性的な本屋さんがあって、ほんとうにうらやましい限りです…
こんなことまで教えてくださるの?と驚くくらいに赤裸々な実体験で、なかなかに面白かったです。
経験値からの選書や、臨機応変に変えるところと頑なに変えないところの加減など、なるほどなぁと。
近所にTitleさんみたいな本屋さんがあれば、入り浸るだろうなぁ♡
Posted by ブクログ
福岡にリブロができて、書店の本を店内の椅子に座って読める事に驚き、嬉しくて、天神に行くたびに必ず通った日々を思い出した。
試し読めることをいい事に、あれこれ背伸びして名作を試し読みしたり、手持ちの予算でどちらを買うか悩んだり、自分自身で本を選ぶ経験をたくさん重ねて、自分の読書の土台のようなものができた時期だった。
その裏にはこんな方がいたんだなぁ。
巻末の企画書、事業計画と収支の項は目にする機会のない内容で、(企画書は作ってる人も少ないのだろうけど)後進のために詳らかにしてあげよう、という著者の気持ちと、『これくらいの実行力と実力が本屋には必要なのだ!』という気概のようなものを感じた。
住む街に本屋が無くなってしまった、地方の本屋難民にとっては、こんな新刊本屋が身近に欲しいなと思った。
Posted by ブクログ
この本に巡り会えたきっかけは、尹雄大さんの新刊本のトークイベント会場を調べたら、titleという本屋さんだった。その本屋さんの経営者がこの本の作者だった。とても面白かった。titleという本屋さんもとても居心地の良い本屋さんでした。近くにこんな本屋さんがあるなら幸せだろうなあ。
解説書いてる若松英輔さんの著書、『読書のちから』も大好きな本の一つ。
Posted by ブクログ
本屋ってどうやって開くんだろな?という単純な疑問と、いつか本屋やってみたいかもな〜という少しの憧れで購入。
結果、私では無理だ…という結論に落ち着く。辻山さんの誰にも換えが効かない豊かな経験と情熱、将来を見据えた確かな眼差しがあってこそこの本屋は(行ったことないけど)オープンできて、そして今に至るまで続いているのだろうし、辻山さんの働きぶりにただただ敬意を表したい。そしていつか行ってみたい。
辻山さんの著作、他にもあるそうなのでまた機会があったら読んでみたいと思う。自分で本屋を開くのはちょっと無理そうです。
Posted by ブクログ
本屋「Title」店主辻山さんの本屋「Title」さんができるまでのお話。大好きな本屋さんです。
営業成績まで明らかにしていて、とてもオープンな貴重な
話を聞けた気がしました。
感想としては、辻山さんは「町」ここでいうと荻窪に根差したというか、フィットした本屋さんを作られたのかなと思いました。「町」を非常に大事にされておられると感じました。
Posted by ブクログ
本屋titleの店主が書いた本
本屋を始めるまで、始めてからのことなどが書いてある
準備段階のことや費用がいくらかかり損益はどうだったかなど
ただベストセラーを置いたり新刊を並べるだけではダメで、わざわざtitleに来てもらう、titleで買ってもらうようにするために努力されていると感じた
Posted by ブクログ
「自分で本屋をやってみたい」
そう夢想したことのある読書好きは少なくないでしょう。
本書はリブロの書店員を経て、荻窪に個人で新刊書店Titleを開いた辻山さんの書いた本。「本屋をつくること」についてこれだけ詳らかに書かれている本があったのか。今度東京行くときには訪れてみたい。「いつか本屋ができたら楽しいだろうなぁ」という漠然とした妄想と自分が本気でやりたいのかということの距離感が現実的によくわかって、もちろんだいぶ距離はあったのだけど、なんだかすっきりとした気持ちになった。とりあえず自分の本棚をもっと楽しく並べ直してみよう。
Posted by ブクログ
本屋じゃなくてもお店を始めたいと思っている人が読むと非常に勉強になると思います。
ビジョンというか、どういうお店を目指すか、はっきり明確にしているお店の方が続くんですね。
1度このお店に伺ってみたいです。
Posted by ブクログ
著者は、荻窪にあるという本屋さん。元々リブロで働いていたが、自分の店を構えたという。本の内容を立体的に伝えるためのギャラリーやトークイベントの開催、奥さんによるカフェの併設など、本を売るだけではない工夫がたくさん。選書はもちろん、ディテールまで著者の想いが詰まった個人商店。素敵だなと思うとともに、運営上派生する様々な細かい作業の多さに驚く。大変な面もあるけれど、充実した生き方なのだろうな。いつか行ってみよう。
Posted by ブクログ
ちくま文庫フェアにつき。前から気になっていた本屋、はじめました。を。これはタイトルがよい。荻窪で書店をされている辻山さんの書店をはじめる話。エッセイ風の備忘録と、書店にまつわるよもやま話。本のセレクトショップや独立系書店も増えてはきたが、どこか尖りすぎていて、一見さんにはハードルが高い気がする。Titleは町の書店の延長線上にある気がする。本が好きで、書店が好きな辻山さんの思いが詰まっているし、商売人・経営者の視点もある。そのバランスが心地よい。
Posted by ブクログ
本好きな人は夢見たことがある本屋の開業を地でいった人の話。ただし筆者は大型書店の統括マネージャーまでやってた人なので本屋のプロ。
事業計画などもきちんと立てられていてさすがだなあと思う。
Posted by ブクログ
本屋にまつわる本は単純に大好き。
これは、本当にある個人経営の本屋さんのお話。かなり踏み込んで本屋を個人が経営することについて赤裸々に書かれているように思う。
経営努力もそうだが、当たり前かもしれないけど本当に本が好きじゃないと出来ないなと。
私は個人経営の本屋さんには入ったことがない。楽しそうと思いつつ一見さんには敷居が高いような気もするので御近所さんにでもないと私には縁がなさそうです。量販店でも物凄く本屋さんは楽しいので、個人経営の本屋さんならもっときっと楽しいでしょう。