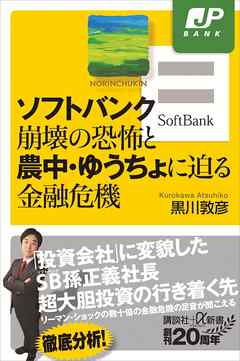あらすじ
YouTubeで16万人のチャンネル登録者を持つカリスマが、ついに書籍を刊行!
2019年11月のソフトバンク巨額赤字決算の意味することは何か。
100兆円もの資金を動かす「日本最大のヘッジファンド」農林中央金庫の抱える爆弾とは!?
ゆうちょ銀行がいつの間にか、投資先を外債に大変更していた!?
「リーマン・ショックの数十倍」と言われる次なる金融危機の足音は、すぐそこにまで迫っている!!
感情タグBEST3
日本がババを引いてしまっている
リーマンショックをはるかに超える金融危機が起こるという危機感が著者を政治活動に駆り立てたとのことで、本書では金融危機がくる根拠がタイトルにある日本企業を中心にビジネス形態や金融商品の運用から数字を多用して説明されている。行き過ぎたグローバル資本主義が進んだことで実体経済を伴わない数字だけのマネーゲームがすでにバブルの様相を呈しており、あとは誰がババを引くかの状態にあることがこれでもかとばかり説明されている。悲しいことに国民にも大きな影響をもつ日本企業や金融機関がすでにババを引いているようだ。今後来るであろう金融危機の規模感の大小はあるにせよ、本書で指摘されている現在の金融システムが不健全であることは確かで(例えば世界のGDPの数倍の金融資産があるのはおかしい)、金融危機によって生じる悲惨な状況を政治で食い止めたいという著者の思いは伝わった。個別の組織や個人名が若干センショーナルに表現されているため陰謀論のように見えるところもあるが、公になっている財務諸表や人や政治の動きの事実に基づいており、著者の自称する「炭鉱のカナリア」としての注意喚起は真摯に受け止めたい。本書は新型コロナウィルスの影響がまだ認識されていない時点で執筆されていることからその影響については言及されていないが、金融危機のタイミングを早め規模は大きくなることだろう。国と金融システムへの問題提起だけでなく、個人がどう資産を守るかについても若干だが言及されているので参考にしたい。
Posted by ブクログ
これから起ころうとしているコロナショック、金融危機、ドイツ銀行の破綻等とても示唆のある話が多くて勉強になった。仕組債CLO、金融商品には歯止めが利かないので監視する必要性あり、不動産OYO、WeWork、CLO(Collateralized Loan Obligation)、金融資本のやり方を学ぶ必要性があると感じた。
Posted by ブクログ
世界的投資ファンドになっているとソフトバンクと農林中金、ゆうちょについて分析した一冊。
これらの企業が世界の金融市場においてカモられていることは知っていたが、それが日本の金融危機にまでつながることは初めて知った。
Posted by ブクログ
ソフトバンクも投資会社化しているという新聞記事も見かけるようになって、それがどうしたの感であったのが、本書を読んで少し心配になってきた。
「早ければ2020年中にリーマン/ショックの数十倍の金融危機が訪れる」
とあったが、もう少し(自分が持っているソフトバンク社債の満期日までは)持ちこたえて欲しい!
Posted by ブクログ
ソフトバンク社債 65万口座 3兆7300億円 1~3%利率
有利子負債18兆円obligation
ソフトバンクグループは投資会社
WeWork、OYO、Uber、ネマスカリチウム、失敗続き
ソフトバンク 営業利益8000億円
ヤフー+LINE ?
CLO Collateralized Loan Obligation
信用が低い企業向けローンをもとにした高金利債権
例:WeWork
農林中金 JAバンクの預金を運用する金融機関
資産総額108兆4000万円 (2019年9月)
リーマンショックでトップの1兆5000万円の損失
CLO保有額7兆9000万円 世界トップ 銀行法外
ゼロ金利で利益の出ない地銀
純資産以上の「その他証券」=ジャンク債で利益
ドイツ銀行
5500兆円のデリバティブ(金融派生商品)
ドイツGDPの12倍
ゴールドマンサックス証券
大株主不明、リーマンショック時も利益
日本法人副会長 佐藤氏⇒ゆうちょ銀行副社長
⇒ソフトバンクグループ副社長
著者:オリーブの木 党首
Posted by ブクログ
私が今の会社に転職したのが2006年ですが、それから数年後にリーマンショックが起きまして、そのお陰で大変良い勉強をしたのを覚えています。サブプライムローンが拡大して取り返しがつかなくなったという結末だったと理解していますが、この本によればその教訓を活かせていないという以上に、より巧妙に金融商品が作られて、リーマン以上のスケールで売りさばかれているようです。
弾けないバブルは無いというのが歴史が証明するところですが、いま正にバブルの真っ最中とのことです。さらに今は全世界コロナショックです、これに乗じてとてつもない大恐慌が起きるのではないかとこの本では警鐘を鳴らしています。
コロナショックにより今年の各業種の売上は減ることは必至であり何が起きても全てコロナのせいで多くの人が諦めることになるのかもしれませんが、早ければ今年にも起きるとこの本では言っていますが、それまでに何か対策すべきことは無いのか、自分なりに考えてみようと思いました。お金や見える資産で残すよりも、今あるお金を使って、コロナ後にも使える資産(経験、知識等)をどうもつかが考えところかもしれませんね。
以下は気になったポイントです。
・ソフトバンクは現在、有利子負債が18兆円を超えている、ソフトバンクにもしものことがあればメインバンクとなっている、みずほ銀行も壊滅的な打撃を受けるだろう(p8)
・逆イールド(アメリカの長期10年債の利回りが2年利回りを下回った)の背景にあるのは、世界的なカネ余りである(p9)
・ソフトバンクの負債は2014年のスプリント、17年のアーム買収によって急増している。18年にはビジョン・ファンド(10兆円非公開市場)を運用開始している。サウジ・ムハンマド皇太子は4.8兆円出資しているが、この部分は7%もの利回りを保証されている(p26、28)
・みずほ銀行のソフトバンクへの野放図な融資に疑問をもった社外取締役は2019年に突如退任した(p39)
・ウーバーがやったことは、世界中のドライバーの生活を困窮させ、タクシー業界を危機に陥れただけ(p52)
・孫氏は蓄電池市場の拡大を予想して、その根幹となるリチウムを押さえようとして18年4月にネマスカリチウム(カナダ)に82億円出資したが、2019年夏に中国での電気自動車生産が急減して、リチウム価格が急落した(p57)
・カリスマ投資家、ピーター・ティール氏は、人工知能も自動運転も新聞紙面を飾っているような夢の技術は、株価を吊り上げるための実態の無い「流行語」に過ぎないと言っている(p59)
・いま金融の世界で最もリスクの高い金融商品はCLO=信用力の無い企業に対して貸し出している債権を証券化したもの、いま起きているのは、コベナンツ・ライト・ローンの増加、貸し付け時の条件が緩く借り手が追加で債務を増やすことのみを制限しているものでこれが急増している(p78、80)
・農林中金のCLO保有額は7.9兆円で世界でも圧倒的トップ、これは銀行法適用外で、ゴールドマンサックス等によって作られた商品である(p87)
・農林中金は純資産が7.7兆円、有価証券は55.4兆円、CLOに代表されるその他証券は43.1兆円、価値が半額になると大変なことになる(p89)
・現在のドイツ銀行は保有する5500兆円にも及ぶデリバティブがある、ドイツ国家のGDPの12倍(p112)
・地球では少なくとも過去5回、最大で生物の96%の種が短期間に絶滅する大きな生態系の変化があったとされている、このままいくと人類の活動が6回目の大量絶滅の引き金を引くだろうと強い危惧を感じる(p176)
・この資本主義の大きな問題点は、利子と通貨の発行の仕組みにある。それを変えるのが行きすぎたグローバリズムを是正すること(p177)
2020年4月18日作成
Posted by ブクログ
ソフトバンクという企業を安心して見ているとリスクが大きいという事を知らされた。
確かに孫氏の仕事のやり方はギャンブルとも呼べる。後ろ盾が亡くなれば終わり。株も集中投資はしないようにしよう。
・リーマンブラザーズ破綻時 格付けトリプルA デリバテイブが破綻したため。64兆円の負債総額 貸借対照表に記載されないしくみ。現在のドイツ銀行も550兆円デリバテイブ取引が有る。ゴミ同然の金融商品。
・世界のデリバテイブ総額は6京円!
・トルコはNATO加盟国にも関わらずロシアから兵器を購入している。アメリカとの関係悪化でリラ急落中
・ゴールドマンサックスはブラック企業
会社の利益しか考えていない。顧客に損をさせた人間が出世。デリバデイブ商品のオンパレード。
ゆうちょ銀行、GPIF,ソフトバンクが代表的な顧客
Posted by ブクログ
2022年3月刊行、この感想は2022年10月に記載。
まず、著者の政治的信念とか在り方にはふれません。
その上で、今のところ、ソフトバンクもゆうちょ銀行も農林中金もさほど問題にはなっていません。しかし、最近、クレデイスイス銀行の安全性がとりざたされるなど、きな臭い感じは確実にあります。「いつかは」みたいなこういう本は、「もしそういう状況になれば」危険にさらされる企業のリストとしては納得感あります。しかし、その「いつ」が知りたいんです。
Posted by ブクログ
投資事業会社へ変貌し将来の雲行きが怪しいソフトバンク、CLOを所有する農中及びCDSを所有するゆうちょ銀行に訪れるであろう金融崩壊を予測している。ソフトバンクについては、巷で騒がられていたがやっと腑におちた。OYOやWe workといったベンチャー企業に従来から目をつけて投資をしていたが業績は思うように上がっていない。寧ろ下がり目にも関わらず再度多額の金額を投資することで再建させようとしていることに、疑問の声が上がっている。ソフトバンクへの融資にはメガバンクも渋り、社債の発行も思うように進んでいないことから周りの評価は厳しい。アリペイへの早くからの投資により、今の地位を確立しているが果たして乗り切れるか、勝負どころである。
また、農林中央金庫とゆうちょ銀行が危うい状況にあるのは全くもって知らなかった。リスクの高い商品にも関わらず高リターンにつられ、買い増しを続けていることが原因。
コロナウイルスの影響により、金融崩壊は刻一刻と迫っている。ソフトバンク・農中・ゆうちょが今後どのような業績を辿るか楽しみである。