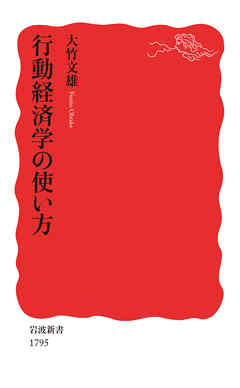あらすじ
学ぶだけではもう足りない。研究と応用が進み、行動経済学は「使う」段階に来ているのだ。本書では「ナッジ」の作り方を解説する。人間の行動の特性をふまえ、自由な選択を確保しつつ、より良い意思決定、より良い行動を引き出す。その知恵と工夫が「ナッジ」だ。この本を通して、行動経済学の応用力を身につけよう。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
行動経済学の基礎から学べる本だった。心理学と経済学が掛け合わさっていてマーケティングに応用したいと思いこの本を読んだ。基礎から学べるとはいえ基本的な用語は知らないと読みづらい。
Posted by ブクログ
経済学の知見を実社会に応用しようとしたら、かなりの場面で生活者の慣習と衝突したり、利害に影響を与えるので政治的決着を求められ玉虫色的になることが多い。
行動経済学は政府や生産者側が消費者側(必ずしも一方的では無いだろうが政府、生産者側からのアプローチが多いだろうと思う)にこちらの意図に沿った行動を促すための知恵を与え、上記の問題の有効な解決方法を与えてくれる。
それは厚生の向上へのコストを削減して社会全体の効用をあげることが出来るのだろうが、パレート改善に至るまでの調整過程に、人間行動の面白さを感じることができるとしたら、そこも法則が発見され理論化されていくと何か味気ないような気がする。
また権力にとっては非常に有効な武器になり得るので、表面上は自由民主主義を標榜している国家が、実は巧妙な世論誘導により市民を恣意的に特定の層に有利になるように操作している、いわば操作された民主主義へと移行するのではという一抹の不安を感じる。
ただネガティブなことを言っても仕方がない。行動経済学は制約がある資源を有効に利用、配分方法を思考すると言う経済学の理念に沿っていると思う。
消費者側からもこの理論を熟知する必要があるだろう。社会が我々にどう行動させようと動機付しているのかを理解することは政府や生産者側にとって必ずしも都合が悪い訳では無い。誠実なコミュニケーションを発生するきっかけを与え、市民社会の熟成が期待できるからだ。
Posted by ブクログ
話題になって久しい行動経済学。何冊かこのジャンルの本は読ませていただいていますが、今回は新書にて。
新書ならではの分かりやすさが、私にとってはとてもありがたかったです。
第2章のナッジに関する記述と、第7章の医療・健康活動への応用が私にとっては特に有用な内容でした。
一連のコロナ騒動においても、おそらく随所で行動経済学の知見が取り入れられているのでしょうね。
巻末の「文献解題」が充実しており、さすが学者の方だなぁと。
付箋は24枚付きました。
Posted by ブクログ
題名から、個人レベルの「使い方」を期待したが、課税など個人レベルの使い方ではない部分も多かった。但し、行動経済学の内容を説明してから本題に入ってくれるので、理解が追い付かないことはなかった。
ナッジを仕事やプライベートでどう活かすか考えたい。キーは、本にも多く登場した「現在バイアス」を意識して意思決定することかと思う。
Posted by ブクログ
誰しも自分が思っているより合理的でない行動することがわかる。それにもかかわらず、適切な対応をしないことが多い。それは我々の行動が合理的に行われていると心のどこかで信じているのではないかと思った。
はじめにの部分で
つまり、人間の意思決定は合理的なものから予測可能な形でずれる。逆に言えば、行動経済学的な特性を使って、私たちの意思決定をより合理的なものに近づけることができるかもしれない。ⅳ
とある。
確実なものと不確実なものでは、確実なものを強く好む傾向がある特性。利得よりも損失を大きく嫌う特性。これら二つの特性から同じ内容でも表現方法が異なるだけで、意思決定が異なってくる。このような特性を知ることは社会において恣意的な情報に踊らされないと共に、ビジネスなどの人の意思決定を操作したい場面でも有効である。
計画はできるのに、それを実行する時になると、現在の楽しみを優先し、計画を先延ばしにしてしまう「現在バイアス」というものがある。これは生活の中で誰しも経験があることだと思う。ダイエットが成功しない、三日坊主になってしまう。
このような意思決定の歪みを、行動経済学特性を用いることで、より良いものに変えていこうという考え方があり、それを「ナッジ」と呼ぶ。利得と損失はデフォルトからの差であると認識している。デフォルトの設定が習慣化や夢の実現のためには重要であるのだ。実際の例が本書ではずらずらとあり、非常にわかりやすい。
このようなバイアスがあるからこそ他人とは違うのが当たり前である。私たちは他人とよく比べたがる。比べたその差もバイアスであるかもしれない。
Posted by ブクログ
行動経済学で自身の習慣をよい方向へ変えられないかと思い、この本を見つけて読んでみた。
行動経済学とは、人間の性質を知る学問だなと読んで思った。
取りあえず、ナッジと現在バイアスの先延ばし行動が役に立ちそうだ。
Posted by ブクログ
行動経済学の簡単な説明と、仕事や健康や日々の生活でナッジをどのように作るかを教えてくれている本。様々な実験や研究の例を示しながら説明してくれている。言い回しが少し難しく感じる箇所もあったが全体的に面白く、実際に生活の中で使ってみようと思った。
Posted by ブクログ
大学の講義のために購入。
最初は課題として読んでいたが、読んでいくうちに行動経済学の面白さに気づくことができて楽しく読むことができた。
何気ない行動も意思と密接に関わっていることがわかった
Posted by ブクログ
自主ゼミで勧められたので購入。行動経済学って何ぞやを知るにはいい本の一つだと思います。他にも何冊かあるのでもう少し勉強して比較できたらなあと思います。
Posted by ブクログ
人間は自分達が思うほど合理的に判断を下せるわけではない。文脈や、基準点や、状況をナッジ(軽く肘でつつくという意味らしい)すれば、喫煙、がん検診、災害避難、スポーツetc...数%人々の行動をずらし、変えることが可能である。
相撲の勝ち越しとか、最近の政府広報の言い回しとか、なんとなくそんな気はしていたけど、改めて調査され、データで示されると面白いし、ほんの少し怖さもある。これを知っていると違和感に気づいて立ち止まって考えるし、自分で「参照点」を作らず最善を尽くして行こうと思える気がするので、読んで良かったです。
Posted by ブクログ
私は行動経済学に基づくナッジ理論を用いて人々の行動変容によって健康状態を改善させるスタートアップ企業で働いているので、もとより行動経済学には触れているものの、一通りの書籍には目を通すようにしている。そうした日本語で書かれた書籍の中で、もっとも分かりやすさ・実践性に富む示唆を与えてくれるのがこの著者、大竹氏であると感じている。
本作は新書という極めてコンパクトな中に、行動経済学を実務で応用するためのエッセンスが詰まっている良書である。良い点として、
・行動経済学はなかなか理論的な全体像/ユニバースを把握するのが難しい中で、そのベースにある人間心理のバグを4つに整理して示している(1.プロスペクト理論、2.現在バイアス、3.互恵性と利他性、4.ヒューリスティクス)
・実際に行動経済学を実務に応用する際には、望ましい行動が取られていない原因が何かによって、その打ち手を変える必要が当然ながらある。そうした典型的な原因のパターンと代表的な打ち手が整理されている
が挙げられる。
コンパクトなので、手元に置いておくと便利な本でもあり、私自身も常に手に届くところに置いておくようにしている。
Posted by ブクログ
人間の様々な意志決定には、伝統的な経済学からずれるというバイアスがあり、それを前提とした行動経済学が1980年代から発展してきた。
本書では、行動経済学的な特性を使い、人の意志決定をより合理的なものに近づけるため、主にナッジと呼ばれる知恵と工夫、その具体的な活用について解説する。
損失回避、現在バイアス、サンク(埋没)コスト、ヒューリスティックス(直感)、アンカリング(係留)効果、ピア(同僚)効果、デフォルト(初期値設定)そしてナッジといった専門用語がこれでもかと出てくるが、いずれも具体例が示され、分かりやすく説明されている。
公私両面で時々の判断や相手との折衝の場面で応用できればと思いながら読み進めたが、初心者ゆえ、そこまでいくにはもっと勉強する必要があると感じた。
しかし、より一層の興味が深まったのは確か、以下に記憶しておきたい知識をメモとして残しておく。
・株式の保有について、購入価格より株価が上昇すれば利益確定はできるが、株価下落の際は損切りできないという行動は損失回避効果で説明できる。
・「術後1カ月の生存率は90%です。」「術後1カ月の死亡率は10%です」という表現方法の違いで手術に踏み切る人の割合が異なるのは「フレーミング効果」
・現状を変更する方が望ましい場合でも、変更を損失と理解し現状維持を好むのが「現状維持バイアス」
・なかなかダイエットを実行できなかったり、夏休みの宿題を夏休み後半までしないといった現在の楽しみを優先し、計画を先延ばしするのが「現在バイアス」
・現在バイアスに対して、自分の将来の行動にあらかじめ目標を掲げたり制約をかけるのが、コミットメントー手段
・他人が自分に親切な行動をしてくれた場合にそれを返すという選好を互恵性という。
・思考費用がかかったり、計算能力に限界があったりすることで、ヒューリスティックスという直感的意志決定を取り入れがち
・取り戻せないサンクコスト(埋没費用)を回収しようと不合理な意志決定をすることがある
・最初に与えられた数字を参照点として無意識に用いてしまい、その数字に意志決定が左右されるアンカリング(係留)効果
・デフォルト(初期値設定)が大事という事例としては臓器移植に関して日本のように「提供しない」がデフォルトになっている国は「提供する」がデフォルトになっているフランスのような国に比べ提供の意思表示割合は低いということがあげられる。また、千葉市では育休を取得する際にその理由を申請させていた制度を育休取得をデフォルトにして育休を取得しない場合にその理由を申請させる制度に変更することで、育休取得率が大幅に向上した。
・健康活動は、行動経済学的なバイアスが発生しやすい分野。たとえば、デフォルトで接種日が決められていた場合の方がワクチンの接種率が高い。ただし、接種希望者が日時を選んで予約する場合は、コミットメントがより強いため、予約変更の通知をしないで接種日に来ないというようなことは少ない。
・ナッジとして公共政策に効果があるのは、多数派の行動を社会規範として示し、それから乖離している人を少数派として意識させるメッセージ
医療の現場における患者の意志決定や防災の知識や避難場所についての教育を生かした防災行動に関し、いざという時、なかなか冷静な判断ができないのが人間。その人間の特性を踏まえた上で世の中の仕組みを
考えるべきだというのが、本書の肝。
Posted by ブクログ
実用例が豊富でわかりやすかったが政治経済に関する知識を持っていないと難しい内容もあった。読んだ後、ものの見方が変わった。今後情報提供者になったときにはこのナッジと呼ばれるテクニックを活用していきたい。
Posted by ブクログ
行動経済学、ナッジの実用場面が簡潔にまとめてある。
他の参考書籍を読んでからだととても繋がりやすいし、コンパクトなので参照しやすいと思う。
ここから入ってもいいけれど、どちらかというとまとめの本かなぁ、という感じ。
Posted by ブクログ
とても学術的。理解するのに頭を使う。以前、行動経済学の本である「ヘンテコノミクス」を読んでいたので、何とか理解できた。文字数が多いので当たり前だが、ヘンテコノミクスより例が多い。
初めて知ったものとしては、締め切りを細かく設定することで、現在バイアスから発生する先延ばしを防ぐ効果。
例えば、学生にタイプミスを訂正する課題を与え、
①3週間後に3枚すべてを提出
②1週間ごとに1枚ずつ提出
③締め切りを自分で設定
という3グループに分けた。
最もミスが少なく、締め切りからの遅れもなかったのは、②のグループ。次に良かったのは③。成績が最も悪かったのは①。
Posted by ブクログ
プロスペクト理論=確実性効果と損失回避。
フレーミング効果。保有効果。現在バイアス=先延ばし行動=コミットメントの利用。
互恵性と利他性=社会的選好
ヒューリスティック=近道による意思決定、サンクコスト、意志力の枯渇、選択過剰負荷と情報過剰負荷、平均への回帰。
メンタルアカウンティング、利用可能性ヒューリスティックと代表性ヒューリスティック、アンカリング効果、極端回避性、社会規範と同調効果、プロジェクションバイアス。
ナッジ=軽く肘でつつく。ナッジは簡単で魅力的で社会規範を利用しタイムリーなものがよい。
稼げる日のほうが、労働時間は短い。バーディーパットはショートしやすい。ピア効果=同僚効果。
年功賃金の説明は、現在バイアスのために無駄遣いするから。
参照点=最初に提示された条件に引きずられる。
金銭より、モノで感謝を表されたほうが満足度が高い。
昇給は最初は満足するが、長続きしない=少しずつ昇給するほうがいい。
多数派の行動を強調すると、避けてほしい行動を減らせる。
現在パイアス=現在の決定は、易きに流れやすい。
実行計画を紙に書きだすと、コミットメントしやすい。
習慣化できるルールを作る。
デフォルトの利用。
所得税20%と消費税25%は同じ負担。消費税のほうが重く感じる。消費税のほうが課税時期が遅いので抵抗が少ない。
軽減税率は、補助金と同じ。高額所得者のほうが多く受け取る補助金。
保険が民間だけだと機能しない理由。
伝統的経済学では、情報の非対称性やモラルハザードが問題になる。
行動経済学的には、現在バイアスや損失回避が問題となる。
渡されたお金の名称の違い。払い戻しとボーナス所得では、払い戻し、のほうが貯蓄が増えた。
O型の人が献血が多いのは、同じ負担でもより貢献できる度合いが高いから。貢献度合いが多いという理由で、寄付が増える可能性がある。
Posted by ブクログ
行動経済学の考え方、「ナッジ」肘で小突いて行動させる方法が具体的に書いてある。
診察カードの裏に自分で日時を記載させるとキャンセルが出にくいなど、行動を相手に自然に誘導する例がもっと知りたい。
Posted by ブクログ
平均への回帰。女性よりも男性の方が競争好きという統計データがあるが、文化的環境的背景によるという説もある。シーシュボスの岩実験→人は意義のある仕事やその実績を実感できる仕事に対してやりがいを感じる→仕事の記録・見える化重要。オプトイン・オプトアウトに見るデフォルトの効果。軽減税率は低所得者に不利。色んなナッジの話。
Posted by ブクログ
従来の経済学では、計算能力が高く、情報を最大限に利用して、自分の利益を最大にするように合理的な行動計画を立てて、それを実行できるような人間像を考えてきた。行動経済学は、従来の経済学で考えられていた人間像をいくつかの点で現実的なものに変えている。
第一に、不確実性のもとでの意思決定の仕方に違いがある。従来の経済学では、人間は将来起こりうる事態が発生した際の満足度をその発生確率で加重平均した値をもとに意思決定していると考えてきた。行動経済学では、プロスペクト理論と呼ばれる考え方で、人々は意思決定すると考えられている。その際、利得と損失を非対称に感じたり、ある事象が発生する確率をそのまま使わないという特徴がある。
第二に、現在と将来で、いつ行動するか、という意思決定において伝統的経済学と行動経済学で異なっている。従来の経済学では、将来のことを今決めると、時間が経ってもそれ以外の状況に変化がなければ、決めたことをそのまま実行できると想定されている。しかし、私たちは、嫌なことを先延ばししてしまい、後悔することも多い。行動経済学は、現在バイアスという特性を用いて、このような先延ばし行動を説明する。
第三に、従来の伝統的経済学では、利己的な人間を前提にしても競争的市場があれば、社会が豊かになることを考えてきた。行動経済学では、利他性や互恵性を人間がもっていることを前提にして人間社会を考える。
第四に、従来の経済学では、計算能力が高い人間を前提にしていたが、行動経済学では計算能力が不十分なことを前提に直感的な意思決定をすることを考えている。そうした一定のパターンをもった直感的意思決定をヒューリスティックスと呼んでいる。
◾️保有効果
現状を変更する方がより望ましい場合でも、現状の維持を好む傾向のことを現状維持バイアスという。現状維持バイアスが発生するのは、現状を参照点とみなして、そこから変更することを損失と感じる損失回避が発生しているためと考えることもできる。
電力会社の契約先や携帯電話の契約先を変更した方が得なのに、現状の契約を維持し続けるのも、切り替えの費用に加えて、現状維持バイアスが影響しているかもしれない。会議や授業でたまたま最初に座った席に次の時も座り続けるのも、最初に座った席が参照点になってしまうことによる現状維持バイアスと解釈できる。
現状維持バイアスを保有効果で説明することも可能だ。つまり、現在の状態を自分がそれを保有していると感じてしまうのだ。保有効果とは、既に所有しているものの価値を高く見積もり、ものを所有する前と所有した後で、そのものに対する価値の見積もりを変えてしまう特性のことを指す。例えば、企業が無料で試供品を配布するのは、この保有効果を狙った販売戦略である。
◾️意思決定のボトルネックと対策
対策←ボトルネック
・自制心を活性化するようなコミットメントメカニズムの提供、社会規範ナッジ
←本人が自分がしなければならないことを知っているのに達成できないのか?
・情報提供、デフォルト設定、社会規範メッセージ
←望ましい行動を知らないのでできないのか?
・コミットメントメカニズムの提供、デフォルトコミットメント
←自分自身でナッジを課するだけの意欲があるのか?
・損失回避・社会規範の利用
←情報を正しく提供すればよいのか?
・シンプルに、何をすればよいのかがわかるように、必要な情報だけに
←情報の負荷が多すぎるのか?
・競合的な行動を抑制するようなナッジ(社会規範、ルール化)
←引き起こしたい行動と競合的な行動が存在するのか?
◾️行動経済学による年功賃金の説明
行動経済学での年功賃金の説明はつぎのようになる。現在の賃金水準を参照点とすれば、私たちは賃金上昇を利得、賃金下落を損失と感じるので、賃金上昇が続く賃金制度の方が、賃金の下落の可能性がある賃金制度よりも従業員の満足度が高くなるというものだ。
◾️減量のナッジ
対策・具体例・ナッジ
▶︎減量という将来 の目標だけでは なく、今日の行動 を目標に
目標を即座に報酬が得られるものにする
・毎日体重計に乗って計測する
・毎日7000歩以上歩く
目標達成の報酬→金銭的報酬、スマホゲームのポイントな ど非金銭的報酬
損失回避を用いる→最初に一定額の金額やポイントをも らっておいて、体重計測をしないか、7000歩を歩かな かった場合に一定額の金額やポイントが差し引かれる
▶︎コミットメント 手段を利用
目標を決めて、目標が達成できない場 合の罰則を決めておく
減量中であることを意識しやすくする
一定額を預けておき、預けた金額が没収される
きっちきちーダイエット→利き手の親指の爪に「キ」と書く
▶︎贈与交換を利用
減量仲間での情報交換や励まし 医療者やトレーナーが、対象者に特別 にケアをサービスしていると思わせる
お互いに励まし合う トレーナーからの個別メールやアドバイス
▶︎デフォルトを利用
運動や食事をルール化する
通勤に歩くルートを採用 夜9時以降は食べない・ご飯はお茶碗1杯まで
▶︎社会規範を利用
周囲の人の運動量を参照点にする
減量仲間の平均的運動量を知らせる
Posted by ブクログ
ナッジの活用方法を知るために読んでみた。前半は類書で見聞きした内容で、後半は仕事や医療、防災での活用事例等は参考になったが、事例の紹介に留まっており少し物足りない。アンカリング、参照点を変えることで行動を変化させる手法が印象的だった。
Posted by ブクログ
著者は経済学者でコロナ禍の時に「分科会」にも所属していた人。行動経済学の基礎を初学者向けに書いた本で、読んでいて大学一年生向けの基礎講座を受講したような気分になった。巻末に詳細な参考文献一覧があるのも嬉しい。行動経済学について学ぶ時のとっかかりとして、最適となる一冊であるように思う。
Posted by ブクログ
大学の勉強内容に行動経済学があったので、興味本位で読んだ。まず、第一に感じたことは、人間の何気ない行動1つ1つ全てに、なんらかの因果関係があり、その多くは言語化が可能なことに驚いた。様々なバイアスやナッジによって人間がその行動を取るということを知った。
まだ行動経済学の基本を知っただけだが、行動経済学は様々な場面で役に立つと感じた。本の中で挙げられていた実例のように、社会の中や自分の行動を制御することに大きな可能性を感じた。
行動経済学について、少し興味が湧いた。
Posted by ブクログ
とても社会心理学的な性格を持った内容なので
人の行動原理を臨床的に検証するのに有効なのではないかと感じる
大きなポイントは
☆☆メッセージにより選択は変わる☆☆
という点だ
例えば 「消費税を上げる必要がある」と書かれた本を読んでそれだけを信じてしまうような人はいる。多様な価値観の中で、どう行動すれば より良い選択行動なのかは自分の頭で考える訓練をしてからでないと盲目的で危険なヒューリスティックの渦に巻き込まれてしまいます とでも怖いです
キーワードは ナッジ
医療への活用もあって実用性が注目されているので読んでおきたいと思って お勉強
人間の行動パターンを理解するのに、心理学と併せて理解を深めたいと考えさせられる
リチャード・セイラー の提示した
Posted by ブクログ
行動経済学におけるナッジの作り方が分かった。
ただ、文と文の繋がりが分かりづらかったり、おかしなところで改行されていたりにて、文章としては読みにくかった。
Posted by ブクログ
行動経済学2冊目。1冊目と同様、著者は大竹文雄氏。
感想。行動経済学は偉大だ。ナッジの研究はとても大事だ。私は研究結果を知り、活用をする側で十分だと思った。以前読んだ本を思い出した。
備忘録。
・従来の経済学では合理的経済人。行動経済学ではプロスペクト理論と呼ばれる考え方で、従来型の確率論がそのまま適用できない特徴あり。
・確実性効果。例えば100%もらえる3万円と、確率80%で貰える4万円は、所謂期待値で言うと後者の方が大きくなるが、確実な貰える前者を選ぶケースが多い。
・その他、損失回避、保有効果、現在バイアス(先延ばし)とかとか。
・ナッジ。行動経済学的手段を用いて、選択の自由を確保しながら、金銭的なインセンティブを用いないで、行動変容を引き起こすこと。人々の行動特性を考えてナッジを設計する。