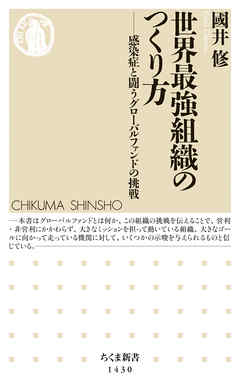あらすじ
1990年代に猛威を振るったHIV、結核、マラリア。それら三大感染症と戦うために生まれ、コフィ・アナン、ビル・ゲイツ、ボノ等から絶大な支援を受けてきた国際基金グローバルファンド。その官民共同の新たなビジネスモデルは「21世紀のグローバルヘルスの大いなる革新」と呼ばれ、「世界最強の国際機関」とも称される。戦略局長としてジュネーブを拠点に日々グローバルに活動する著者が、世界最強の組織の条件を、自らの体験をもとに解き明かす。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
世界最強組織のつくり方
感染症と闘うグローバルファンドの挑戦
著:國井 修
ちくま新書 1430
世界エイズ・結核・マラリア対策基金、通称「グローバルファンド」
ビル・ゲイツ、コフィ・アナン、U2ボノが支援する、三大感染症と闘う国際ファンド
WHOに凌駕する規模の医療援助を展開しているこのファンドの内容を紹介するのが本書です
エイズ、結核、マラリア、三大感染症。毎日ジャンボが2,3機墜落するほどの死者を出している
過去16年で、500憶ドルを調達、年間50億ドルの予算を組んでいる
WHOの年間予算の2倍であり国際機関の保健医療援助額としては最大である
気になったのは、以下です
・吉田松陰 夢なき者に理想なし、理想なき者に計画なし、計画なき者に実行なし、実行なき者に成功なし
故に、夢なき者に成功ない
・成功のプロセスとして重要なもの、VMOSA
V:ビジジョン
M:ミッション
O:目的
S:戦略
A:アクションプラン
・ピーター・ドラッカー 未来の社会における多国籍企業の最大の課題は、その社会的正当性を示すことだ
そして、そのために、ビジョン、ミッション、バリューが必要だ
・目標の設定
むちゃな目標:前年比、他社データ、管理者できめる
ストレッチ目標:市場サイズ、シェア、顧客の意識、行動の趨勢などのデータを用いて決める
⇒野心的だが現実的な目標
・3%のコストダウンは難しいが、3割のコストダウンはすぐにできる ⇒ストレッチ目標を考えよ
・バックキャスティング ⇒ 達成したい目標を起点に、現実を振り返り、途中で何かすべきかを考え、
マイルストーンを設定する方法をいう
・課題が大きく、それに関与するステークホルダーが多くなればなるほど、責任と役割が不明瞭になりやすい
・大きな課題を扱うときは、森をみながら、木をみる、ことが重要である
・リザルトチェーン
インプット⇒活動⇒アウトプット⇒アウトカム⇒インパクト を課題ごとに図示する全体把握のためのツール
・2つのモニタリングツール
KPI:重要業績評価指標
KGI:重要目的達成指標
・実行計画策定の際の重要事項 整合性、連携性、最適化、優先順位、順序づけ
・悪魔は細部に宿る、多くの落とし穴は細部に隠れている
・トレンド思考:過去の経験や延長線上から未来を予測する
・ゼロベース思考:過去の知識をゼロにして、現在や将来のニーズが可能性を加味して、ロジックを使って考える
・どんな状況でも異なった組織・団体は簡単に一致団結し、足並みをそろえるわけではない
・我々は責任を分かち合い、共通の目的に向かって一緒に働いているんだ
・その資金によってどれほどのリターンが生まれるのか、という投資の観点から厳しく吟味することも重要になっている
・売り手によし、買い手によし、世間によし、の三方よし
・4つのリスク:ドラッカー
①負うべきリスク
②負えるリスク
③負えないリスク
④追わないことによるリスク
・ESG投資:環境、社会、企業投資
・責任は2つある 説明責任と、実行責任だ
・孫子:名君賢将の動きて人に勝ち、衆に出づる所以のものは、先知なり
・DIKWモデル
①D:データ:体系化されていない情報
②I:情報:データを分析分類統合したもの
③K:知識:情報から導き出される規則性、傾向を活用した知見
④W:知恵:知識を活用して意思決定や判断をする力としてつかえるもの
・Vfm:バリュー・フォー・マネジメント
自国の税金がどれだけ価値あるサービスに使われているかを評価する概念・指標
・インベンション(発明)しなくても、イノベーション(革新)によって効率・効果を高める
目次
はじめに
第一章 世界最強の組織を創る
第二章 ビジョンを描く
第三章 パートナーシップを築く
第四章 資金を集め、投資する
第五章 インパクトを示す
第六章 人材を活用する
第七章 未来を創る
おわりに
謝辞
巻末資料
参考文献
写真出典一覧
ISBN:9784480072443
出版社:筑摩書房
判型:新書
ページ数:304ページ
定価:900円(本体)
2019年08月10日第1刷
Posted by ブクログ
國井修氏(1962年~)は、自治医大卒、公衆衛生学修士(ハーバード大学)、医学博士(東京大学)。これまでに医療活動を行ってきた国は110ヶ国以上。栃木県の山間僻地での診療に始まり、NGO、国立国際医療センター、東京大学、外務省、長崎大学熱帯医学研究所(教授)、ユニセフ(ニューヨーク本部、ミャンマー、ソマリアでの保健・栄養・水衛生事業を統括)を経て、2013年、本書で語られている「世界エイズ・結核・マラリア対策基金(通称・グローバルファンド)」に移り、現在は、約10人の幹部の一人として、戦略情報部、技術支援・連携促進部、コミュニティ・人権・ジェンダー促進部などを統括している。尚、國井氏のユニセフ時代までの半生は、自著『国家救援医-私は破綻国家の医師になった』に詳しい。
本書は、グローバルファンドがなぜ「世界最強の組織」と呼ばれるのかについて、組織論的なアプローチで書かれているため、グローバルファンドが活動の対象領域とする世界の開発問題や地球規模の課題に関心を持つ人びとだけでなく、営利・非営利に限らず、組織のマネジメントに携わる多くの人びとに様々な示唆を与えてくれる内容となっている。國井氏も、「組織の利益と社会の利益、そして未来のニーズや可能性との結びつきを考えて、組織のリーダーシップやマネジメントをもう一度見直す機会を与えることができれば幸甚・・・グローバルファンドの学びや進化が、グローバルな経験が、日本の課題解決のため、さらに日本の素晴らしい未来のために、活用できれば幸い」と語っている。
私は、本書から様々な気付きを得られたが、強く印象に残ったものとしては、ジェームズ・C・コリンズの『ビジョナリー・カンパニー2』からの引用で、先見性のある組織のリーダーの特性とは、「カリスマ性でも、特殊な能力でもなく、「謙虚さ」、それも「驚くほどの謙虚さ」、そして「不屈の精神」」である、といい、本書に紹介されたグローバルファンドのリーダーは正にそうした人びとだということである。國井氏も当然例外ではなく、(私は國井氏の宇都宮高校時代の後輩なのだが)学生時代から最近お会いしたときまで、そのリーダーシップは不変であった。
また、「Value for Money(VfM)」の概念の構成要素の一つである「公正」の考え方にははっとさせられた。そこでは、「公正(Equality)」と「平等(Equity)」の違いを「3秒で教えてくれる」絵で示されているのだが、大人と10歳ほどの子どもと5歳ほどの子どもの3人が、大人の肩の高さの塀の向こうの野球を見ようとしているとき、同じ高さの3つの踏み台の配分の仕方を描いている。「平等」と書かれた絵では、踏み台はそれぞれに1つずつ配分されているため、5歳の子どもは相変わらず塀の向こう側を見ることはできない。一方、「公正」と書かれた絵では、大人にはゼロ、10歳の子どもに1つ、5歳の子どもに2つ配分されているため、全員が野球をみることができるのである。目から鱗であった。。。
國井氏は「不屈の精神」をもって、今後活躍の場をどこまで広げていくのか、とても楽しみであるが、一読者としては、國井氏の魅力が一層輝くような「現場」を描いたものを読みたいと思ってしまうのは欲張りだろうか。。。
(2019年11月了)