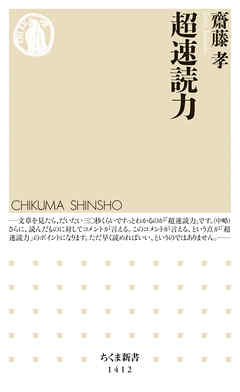あらすじ
「超速読力」とは、本や書類を見た瞬間に内容を理解し、コメントを言えるという新しい力。現代が、スピードが求められる時代ということもあるが、実は本や文章の本質をつかむには一番求められる力なのだ。実用書や資料、ネットの情報を読むときに有益だが、必ずおさえておきたい古典や名著などを読むためにも使える。この本では、「超速読力」を長年鍛えてきた著者が、その意義とトレーニング法をわかりやすく公開する。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
ぬぁぁ
楽し!!
読書本は定期的に読むと【もっと読みたい欲】が増進されますね
小説などじっくり読みたいですが
専門書、書類、実用書など時間制限つけて読むのが自分は好きで、要点を文面から採取して内容を思い込みの無いように【考察したり】【理解したり】色々な楽しみ方をします
日常生活で一瞬で見なくてはいけないのは
道路の標識など…
意識するだけで
秒で理解できるようにもなります
自分の勤務先は、本を読まないゲームか、ギャンブルしかしない奴らのあつまり
書類の見落とし当たり前
スケジュール書かれたホワイトボードも見落とし
毎日仕事が終わる1時間ほど前に【あれ?この無いようさっきまで書いてなかったですよね?】と毎回ほざく…
読む習慣は
絶対に必要ですよね
Posted by ブクログ
(速読について)
・日本語には漢字がある→漢字には多くの意味が含まれている
・速読を身に付けると膨大な情報に接することができる
(読み方)
・獲物をとらえるように読む(一ページ15秒ほど)
・ 3分で新書を要約→答え合わせをする
・難しい古典でも有名な箇所を探すように(もっと活用する)
・古典はおみくじを引くように→ランダムに見て与えられた言葉を大切にする
・沼津の干物→手に入れた本はすぐに処理をする
・付箋、赤丸、線を引く
・本屋で選別力を養え
(アウトプット)
・誰かに伝える
・アウトプットする目的をもつと早く読める
★行動プラン
・読むときは漢字に着目
・新書を要約してYouTubeのまとめチャンネル答え合わせ
・本を買った、借りたら即目を通す
・月に一回は本屋に行く
Posted by ブクログ
斎藤先生が論文の細かいミスを指摘されて頭を抱えたというエピソードに勇気づけられた。あら捜しばかりしていると議論の筋を見失う。どこに力を入れているかを共感的に読み解くべき。あったことないけど、とても優しい人なんだろうな。
Posted by ブクログ
「超速読力」とはいとことで言うと、「目次」
だけでも、「はじめに」と「おわりに」だけを
読むだけでもいいので、そこから内容を理解し
コメントできるレベルに引き上げること、です。
「なあんだ」と思わないで下さい。それもまた
読書の一つです。
もし「この本を1分だけ目を通して、内容を
説明せよ」と言われたら、とにかく何か
キーワードやあらすじを掴もうとするはずです。
そんな風に、とにかく読んで何かの”獲物”を
持ち帰る感覚、それが超速読力です。
「なるほど、そういう読み方もあるのか」と
読書に対して、新たな発見を得られる一冊です。
Posted by ブクログ
速読術、ではなく速読力。少ない時間でいかにその本からモノにするか? が端的に語られていて、いわゆる速読本マニュアルが飽和している中で出色の出来。それには著者が「速読専門家」のような人ではなく、著述家研究者として一流であるところかが要因だろう。
Posted by ブクログ
本を読むきっかけになればと思い購入した本。
今までは本はじっくり読まねばとの考えで、大事に読んでたら時間がかかり、結局一冊読みきれずリタイアするという結果になっていた。
農作業の様に時間をかけて、最後まで読むと大きな成果が得られる、そんなやり方。
この本は、そんな発想を変えてくれた本でした。
本は全部読まなくても良い。
とりあえず、大事そうなところを読むんだ。
はじめは、大した事書いてないから、途中からでも良い。ただ、読んだ後には何かアウトプットできる様にする事が大事。じっくり読んで、何も得られないのでは意味がない。早くても、少しでも得られたらそっちの方がよい。
邪道だが、本を読む習慣のきっかけには良いかなと思いました。
Posted by ブクログ
超速読力とは、「速く読む+コメントを言う」のセットである。
読む(インプット)だけではダメであり、コメント(アウトプット)を言うことも必須。
情報化社会において、大量の情報に触れる日々において、必要不可欠な能力。
すべてを読む必要はなく、フォークアイ(鷹の目)のように、キーワードから必要箇所だけを読むことが大切。
本を読むときは、本に線を引いたりして、ときめく言葉を拾っていくべし。
たった15分の読書でも、得るものがある。
Posted by ブクログ
読むだけではなくそれをコメント(アウトプット)することが重要というのは共感。自分自身でもアウトプットした本の内容は今でも覚えているが、何もしなかった本のことはほとんど忘れてしまっている。
手法としては全部読むのではなく重要なところを読むという内容が中心で、それをコメントして自分のものに少しでもするというのは納得だが、それが他人から一目置かれるためにという目的に見受けられた部分は少し違うなぁと思った。あくまで自分のために速読して、少しでも自分のためになることが重要ということかと感じた。
Posted by ブクログ
超速読は、1文字1文字を辿って読む尺取り虫のような、又農耕型読書ではなく、著書の大事なところ、本質を掴んで読む読み方だと理解した。
教養書や新書などの自分の知識を増やしたいと思って読む本については、重要箇所のみ読めるという方法で適していると感じた。
ただ、小説についてはこの読み方は勿体無いと思った。作品を味わうという点で、一部分のみ読むのは文章の表現方法を楽しんだり、登場人物の気持ちに寄り添うことが難しくてなってしまう。小説は時間をかけても何度も同じ文を読み直して楽しみたい。
読書初心者として、とても勉強になる本だった。
「出会いのときを祝祭に!」
多くの本に出会えるように、超速読力を高めていこうと思う。
Posted by ブクログ
数字に注目する。
最後から読んでみる。
読んだものの内容についてアウトプットをする
前提で読む。
似たテーマの本をまとめて読む。
1枚15秒で読む。
資料に目を通す時はもちろん、普通に読もうとすると難しい古典とかはこういった読み方は有益だと感じた。
ネットサーフィン、Twitterのチェックなども、時間をかけることなくさっさと読み内容を理解できるようになりたい。
Posted by ブクログ
1冊の本を読んだ直後にどれくらい言語化できるか?読書するときはアウトプットを強く意識しておきたい。常日頃感じていることだが、適当に読んだ本は全くサマリーを書けないし、どんな本だったか一瞬で忘れるし、何より読書の時間が無駄になってしまう。
Posted by ブクログ
本を沢山読むには、速読が必要という事で。
超が付く書籍は、数多くあるため、期待せずに読みました。
超速読力とは、本を速く読み、要約し、誰かに説明出来る力。
速く読むだけでは無いのですね。
普通の人は、1ページ目から順番に読んでしまいますが、この本は必要な箇所だけ読むことや、必要なワード付近を読むなど、テクニックが書かれています。
それをやるのが難しい…。また、アウトプットも難しい。
Posted by ブクログ
資料や本の要点をすばやく捉えて、コメントできるようになるためのハウツー本。
資料を読んで適切なコメントをすることで評価が上がる学生や新社会人の方に特にオススメ。
「講演を聞いた後なにも要約して話せないとすると、ただ2時間幻聴を聞き幻覚を見ていたのと大差ない。聞き終わった直後に何も言えないようなら3日後、1週間後にも何も出てこない」
という箇所は、乱読ばかりでアウトプットをサボりがちな自分の心に痛烈に響いた。
具体的なテクニックでは下記が印象に残った。ぜひ活用していきたい。
・世界史レベルで有名な言葉をおさえ、その前後に注目する(小説や古典)
・素敵な言葉が出てくる文脈をしっかりつかんで実生活に活用する(小説や古典)
・その人がいちばんエネルギーをかけたところがどこか探す「精力善用」で読むと理想的なコメントが言える(資料)
Posted by ブクログ
超速読力とは、本の表紙や裏表紙、帯、袖、目次、後書き、見出しなどをまず読む。
つまり、要約されているところや重要な所からそん本の全体を把握する。
場合によっては、ネットで要約を見て予備知識を得てから本に挑むなど、一字一句を速く読むというより重要な所をいかに速く拾えるかといった内容だと理解した。
Posted by ブクログ
「読書という名のハンティングゲームに課金せよ!」
読書する時は、その本の「急所」を掴むことが大事とある。これを読んで、本を1ページ目から「一字一句丁寧に読む」のは、愚の骨頂だなと思うようになった。
Posted by ブクログ
本を読むことを情報処理と考えると良書。今まで時間をかけてきた「 農耕型読書」を改める考えさせられる内容であった。
新書や実用書では参考となる部分が大いにあると感じたが、自分の場合小説の読み方としてはなじまないと思った。
「 超速読力」は 読む力(インプット)とコメントする力(アウトプット)が基本。
「 超速読力」は 学校で教えられない能力。 ただし練習すれば誰でも 身に付けられる能力。
「農耕型読書」: 最初から順番に読んでいく。
↓
「 狩猟型読書」: 読んだ内容を理解して コメントを言う* コメントが『獲物』。
いらない文章を飛ばす 勇気が必要。 不要な部分は割り切って捨てる(断捨離読み)
迷ったら「ときめくかときめかないか」で判断する。
資料や本を読むときはテレビに出て自分の意見を言う という思い込みを持つ。 コメントをいう緊張感が生まれる。
「最後から読め!逆走せよ!」
先に結論を知ってると理解が早い。
映画や小説でやるのは邪道と思うが、情報処理の資の場合は理解が深まる。 概要や予備知識 がある分、 内容に親しみあり読みやすいと思う。
「 知らないから面白いのではなく知ってるから読める」
「はじめに」「目次」「小見出し」などで全体像を把握。 全体像から類推される重要箇所に線を引きながら読む。
またネットなどで 文章のあらすじを把握して読むのも効果的であると思った。
文章には必ず何かしらの目的・テーマがある。
作者がエネルギーをかけたところ(目的)に注目して読む。
作者の思いを心情的に理解する「共感読み」を行う。
作者の 好き嫌いや立場に共感するのがコツ。読んでる間だけは共感する。
関連するキーワードを五つくらい設定して 全体像を頭に入れる。
目線は今読んでる所プラス少し先まで見る。
「アイスパン」が広がって全体の見通しが良くなる。
自分で線を引いたり、書き込んだりして自分が世話をしたと言う 「特別の本」を作る。
読んだら必ずアウトプットする。
Posted by ブクログ
難しい本は読んでいるうちに最初のほうからどんどん忘れていく、というフレーズにとても共感した。
要点をかいつまんで読むなんて背徳感があって楽しそう。
日頃からパラパラと読んで大体頭に入らないかな、なんて思っていたので是非試してみたい。
本の感想を言い合う友達と小学校から東大まで一緒だったというのが素敵。そんな友達どこにいるんだろう。
Posted by ブクログ
本を早く読む+コメントが言えるようになる方法を解説した本。数字の変化に着目すること、キーワード読み、人格読み等様々な読み方を紹介している。新しい読み方を知りたい、本に対して意見を言えるようになりたい人にオススメ
#事実 何がどうした
#日本語 たいてい結論は最後
#肝 目的、オリジナリティ
#精力善用 粗探ししても誰にも良いことはない エネルギーを傾けてるところを探して話す
#人格読み 好き嫌い
#ストップウォッチ読み
#ホークアイ セレクト能力
#アイスパン
#デュアルタスク
#前頭前野 不安や攻撃性を抑える
#駅弁方式 全体を要約する力 深い本質に触れる力
#一期一会読書 文書のスタイルに注目
#引きつけ読み
自分のエピソードと絡めてアウトプットする
#エビングハウスの忘却曲線
20min 42% 1h 56% 忘れる
#観 俯瞰する目
#見 細部を見る目
#子供時代の忘れかけた思い出の一瞬こそリアルで本質的
#時間と集中力
#カフェは時間と空間を購入
Posted by ブクログ
全てを読む速読とは違い、本の要点や必要な部分をピックアップする速読法でしょうか。時間がなかなか取れない自分には非常に良い知識を与えてくれました。本を全て読まなくてもいいというのは、バカ真面目に読んでなかなか進まなかった時間をもっと有意義に使えると感じましたね。
合う合わないはあるでしょうが、考え方は非常に参考になります。
Posted by ブクログ
さすが齋藤孝氏の「読書」に関する本にはハズレなしだ。本書も面白く読めた。
そもそも、「本はじっくり味わって読もう」と言いそうな齋藤氏だけに、「超速読力」なんて本を出されたことに少々驚きがあり、どんなことが書かれているのだろうと興味深々で読んだ。
どちらかというと、本書は「速読をせまられたとき」「速読しなければならない状況に追い込まれたとき」などにどう速読をこなすのかというのがメインの趣旨のようではあるが、著者の本音としては、多くの本との出会いをつくるのに、この「超速読力」が役に立つのだと言いたいのだと思う。
本書の途中で宮本武蔵の言葉が紹介されている。「千日の稽古を鍛とし、万日の稽古を錬とする」とするという剣の修行の言葉だ。それをもじって著者は「千冊を鍛とし、万冊を錬とする」と言っていた。
世の中の読書家の人はだいたい1000冊の単位で本を読んでいき、10000冊までいくと、本を見る目ができてくると感じるのだそうだ。
齋藤氏自身、まぁ学者であるのでそれは常識なのかもしれないが、1日に新書1冊は読まれていると書かれていた。その齋藤氏が驚いていたのは、「打ちのめされるようなすごい本」の著者で、ロシア語通訳をされていた米原万里さんの1日に7冊読むことを習慣とされていたという事実。人生で4桁を読める人は超人としか私には思えない(笑)。
本書に書かれていたが目次は大事だ。本書の目次は、大目次だけピックアップするとこんな感じだ。
第1章 「超速読力」を身につける基礎準備 心構え
第2章 「超速読」のやり方 資料を読む
第3章 「超速読」のやり方 新書、実用書を読む
第4章 「超速読」のトレーニング
第5章 高度な「超速読」 小説・古典を味わう
第6章 実際に小説や古典を「超速読」してみよう
心構えから実践、そして実践も高度なものへと展開あれている。この目次は、本書自体を「超速読」するのに非常に役立つ構成となってる。
第6章の実践で登場するのは、こんな著名な方々の名著。
デカルト「方法序説」
宮本武蔵「五輪書」
サン・テグジュペリ「星の王子さま」
プラトン「ソクラテスの弁明」
ニーチェ「ツァラトゥストラ」
マルクス/エンゲルス「共産党宣言」
齋藤氏は、読書のモチベーションを刺激してくる。
自分が、本書の中でもっとまっとうな意見として感じたのは、第4章の中の「知識量を増やせ!知っていれば読むスピードが速くなる」。知識が増えれば読むスピードが増す。読むスピードが増せば知識が増える。これは相乗効果だ。テクニックを度外視した基本中の基本だと思う。
Posted by ブクログ
速読の本は初めて読んだ。重要な箇所を素早く抽出することで全体を理解し、自分のものにするためのテクニックについて述べた本。
文学作品も有名な箇所だけ押さえてその前後だけ読むというのは個人的には好きになれないが、会議で資料を把握するような場合に大変役立ちそう。アウトプットするまでが超速読というのはなるほどと思った。
Posted by ブクログ
そう、日本人は最初から読むよねぇ。
で、最後にどんでん返しがあって結論がある。
速読も意識で鍛えられる。
これから速読を意識して読書をするようにします。
Posted by ブクログ
知るとより速く読め、さらに読みたくなる。
どんどん読書に挑戦していこう。
岩波新書を全部読んでいる人がいるらしいという話にはびっくりした。ちなみに3200冊以上あるそうだ。
Posted by ブクログ
わたしには、せっかく読むのだからこそ、最初から最後まで、しっかり読まないといけない、という思い込みがある。アルバム曲も、作り手が練りに練った順番があるんだから、それをシャッフル機能で聞くだなんて失礼だろ!?という思い込みもある。
でも、斉藤氏の「一期一会読書法」が、これらの罪悪感に近い思い込みを払拭してくれそうな気がした。一期一会読書法とは、本を「超速読」で「人格読み」すること。「ソクラテス先生とお話しできるのは五分です。」と言われれば、「ほぅ!そりゃ5分でもえぇ!」となるわけだ。この心持ちで積読を捌いていきたいと思う。
Posted by ブクログ
古典とかいつかは読まないとなあと思っていながらいつまでも積んだままにしてる自分としては、この本の有名な部分だけを読んでみる方法や、概要を把握した上で読む方法は良いかも。
とにかく読まないよりは少しでも読んだ方がいいから、読むハードルを下げましょうって考え方も合理的。
Posted by ブクログ
これは社会に受け入れられているので 呉服の人たちに読まれているので 分かると思われているので 知らない人へのメッセージ 知っているリピーターをたくさん増やした方が 良いのではないかと 覚え方
Posted by ブクログ
速読の本は多いが、
自分なりのコメントをする、というところを
ゴールにしているのが卓見。
古典を読む際に、有名な言葉にポイントを絞って
読む方法など、具体的で応用しやすい。