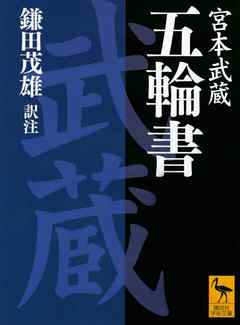あらすじ
一切の甘えを切り捨て、ひたすら剣の道に生きた絶対不敗の武芸者宮本武蔵。彼は「千日の稽古を鍛とし、万日の稽古を錬とす」る何10年にも亙る烈しい朝鍛夕錬の稽古と自らの命懸けの体験を通して「万理一空」の兵法の極意を究め、その真髄を『五輪書』に遺した。本書は、二天一流の達人宮本武蔵の兵法の奥儀や人生観を知りたいと思う人々のために、『五輪書』の原文に現代語訳と解説、さらに「兵法35箇条」「独行道」を付した。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
五輪書は、不敗の書である。
二十八まで、六十余回勝負したが、一度も負けなかった。
武蔵はそれを、たまたま理にかなっていたか、相手が弱かったに過ぎないと言い切っている。
そして、後半生をかけて、武道と向き合い、その奥義を、「五輪書」としてまとめ上げて、肥後細川家に奉じた。
五輪とは、仏教で、地、水、火、風、空。仏教が万物を構成する要素(元素)を表しています。仏塔になどにも五輪の塔といい、仏教の世界観を表しています。
つまり、武蔵は、武道のあまねく世界の神髄として、五輪書を世に残しています。
ちなみに、儒教の言う、五行とは、木・火・土・金・水です。
その本質は、次のとおりです。
①徹底した実利主義と合理主義 敵を切ること以外の不要なものを一切排除する姿勢
②朝鍛夕錬 一歩一歩、稽古を積むことにより道の深奥を体得する姿勢 千日の稽古を鍛といい、万日の稽古を錬という。
③自らの力のみをたのみとする独行の姿勢
④仏法儒道の古道をもからず 自らが認識した事実のみを用いる姿勢
気になったのは以下です。
■地之巻
・神仏を頼まず
・朝鍛夕錬
・万事のおいて、我に師匠なし
・道を行う法則
①実直な正しい道を思う
②鍛錬すること
③広く多芸に触れる
④広く多くの職能の道を知る
⑤物事の利害損失を知る
⑥あらゆることについて、直実を見分ける
⑦目にみえないところを悟る
⑧わずかなことにも気を配る
⑨役に立たないことはしない
■水之巻
・不動な心、平常な心を保つ
・千里の道も一歩づつ運ぶ。
・ゆっくりと気長に取り組み、修業を続ける。
■火之巻
・太陽を後ろにして構える。できなければ、右の脇に太陽を置くようにする。
・「敵になる」ということは、わが身を敵の身になりかわって考えるということをいう。
・同じことを二度繰り返すのは仕方ないが、三度してはならない。
■風之巻
・他流の道を知ることがなければ、道を究めることはできない。
・芸によっては、極意秘伝といって奥義に通じる入口はあるが、いざ敵と打ち合うときになれば、表で戦い、裏で切るなどというものでない。
・人に教える場合は、その人の技量に応じて、早くできそうなところからまず習わせ、早く理解できるような道理を先に教え、理解しがたい道理については、その人の理解力の進んできたころあいにしたがって次第に深い道理を教えていく。
・我が兵法にあたっては、何をかくし、何をおおやけにすることなどあるであろうか。したがって、我が流儀を伝えるには、誓紙や罰文といったものは用いない。
■空之巻
・空とは兵法の極意である。
・空とは、きまった形がないということ、形を知ることができないものを空とみるのである。もちろん空とは何もないことである。
・一切の迷いがなくなった空こそが兵法の究極であり、兵法の道を朝鍛夕錬することよって、空の境地に到達できるのである。
・空というものには、善のみがあって、悪はない
目次
はじがき
「五輪書」を読むにあたって
地之巻
水之巻
火之巻
風之巻
空之巻
兵法三十五箇条
独行道
ISBN:9784061587359
出版社:講談社
判型:文庫
ページ数:264ページ
定価:1050円(本体)
発行年月日:2009年04月15日第55刷
Posted by ブクログ
何度も読み返すべき本の類か。けふはきのうの我にかち、明日は下手にかち、あとは上手にかつこれは座右の銘にしよう日々鍛錬することがいかに重要かを説いている。千日の修行を鍛といい、万日の修行を錬という。このような心がけ。重要だ。最後の独行道もよい
Posted by ブクログ
恥を思い、死することにかけては、武士ばかりに限らず、女も子供も百姓以下に至るまで、日本人の国民性なのだから、ただ死ぬことのみに価値を見いだすのが武士道というのは間違っている。
と、宮本武蔵が熱く語ります。
Posted by ブクログ
人を斬る事をひたすら追求した指南書というべきか。朝鍛夕練、幾度となく命のやりとりをした武蔵の武士道の精華。
現代の我々には想像もつかない人生を歩んだ武蔵の兵法書であるが、それでも時を超えて我々にいろいろな示唆を与えてくれる。
「兵法の道において、心の持ちやうは、常の心に替る事なかれ。」
「鼠頭午首といふは、敵と戦のうちに、互いにこまかなる所を思ひ合はせて、もつるる心になる時、兵法の道をつねに鼠頭午首そとうごしゆとおもひて、いかにもこまかなるうちに、俄に大きなる心にして、大小にはかる事、兵法一つの心だて也。平生人の心も、そとうごしゆと思ふべき所、武士の肝心也。」
「道理を得ては道理をはなれ、兵法の道に、おのれと自由ありて、おのれと奇特を得、時にあひてはひやうしを知り、おのづから打ち、おのづからあたる、是れみな空の道也。」
Posted by ブクログ
年末年始の休みで少しボケ気味の自分に喝を入れようと思って、手にした一冊。
宮本武蔵が、自身が剣(=敵を斬る剣)の道を極めたと感じたのは50歳のとき。そして、その奥義を60歳の時からしたため始め、二年の歳月を経て出来上がったのがこの『五輪書』。
「朝鍛夕錬(ちょうたんせきれん)」という言葉が何度も出てくる通り、奥義を極めるには近道などなく、朝に夕に鍛錬を重ねることがまず中心。そして、それを効果的に行うために何をすべきかを、五つの巻(地、水、火、風、空)に分けて説く。
徹底した合理主義で、とてもここまでの真似は凡人にはできないなと思いつつも、現代でもそのまま通じる指摘があちこちに出てくるから、読むのを止められない。例えば、無心と平常心のくだり。無心とは心があっても動揺しないことであり、それすなわち平常心。真の技を発揮できるのは平常心を持っているからこそ。また、相手の動作は「見る」が、相手の気の動きは「観る」という指摘は、目先だけにとらわれていては先が見えなくなることに通じる。
剣の奥義が様々なことに応用が効くというよりは、奥義を極めた人は物事の本質を見抜くことができている、ということなのだろう。読んでいると自然に背筋がシャンとしてきて、期待通りの喝が入った。
Posted by ブクログ
"現在の仕事道にも活かせる思考、兵法。目的は何かを常に考えて行動すること=剣の奥義は何か?人を殺すこと、太刀を交えるからには真剣勝負である。
生き方にもつながる大事なこと。太刀振る舞いに無駄があってはいけないのである。常に全体を俯瞰して眺めておきながら、心は常に止まることなくなめらかに、と水之巻がとても印象に残っている。"
Posted by ブクログ
宮本武蔵の勝負に対するひたむきな姿が伝わってきた。別れや恋慕にも心を動かされてはならないというまさに勝負のために生きている。勝負は美学ではなく勝つことが目的であり、そのために剣術だけでなく、考えられるあらゆる方向から検討を加えるようにしている。他の書物を読まずともこの書物だけで理解できるよう、後継への心遣いもしているところが素晴らしい。
以下メモ
・心を一か所にとめず自由にすることで柔軟性や力量が発揮できる。
・物事には拍子があり、流れに乗るためには良い拍子を心がけ、相手に勝つためには相手の拍子を外すことが肝心
・広く多芸に触れ、実直を見分ける力をつけ、わずかにも気を配り、無駄なことはしない。
・無心でなければならない。無心とは平常心を保つこと。鏡のようにどんな姿を映そうとも鏡自体は変化しないように。
・見の目、観の目で見ることが必要。目や耳は自分のとらえたいようにしか感じない。心の目で相手の気配を捉えることが大事。
・身を太刀よりも先に行くつもりでないと斬れない
⇒リスクをとらねば勝てない。
・先手を取ること。相手が攻めてくるとき、自分から攻める時、両者が攻める時、いずれも先手で勝負が左右される。
・小手先だけで踏み込まない。太刀、足、身、心全てで踏み込む
⇒中途半端な対応をしない
・敵の身になって考える。敵の立場から自分は今どのように感じられるか
・鼠の頭、午の首。細かいところから大局まで考える、視点を変えてみる。
・不動の心とは動かない事でなく、前後左右に自在に動きながら対象にとらわれず、少しもとどまらない心をいう。相手の動作に心をとめてはいけない。
Posted by ブクログ
本職が物書きではない人が、自分が学んだ全てを1冊で表現しようとした書。
故に抽象的な表現が多く、すんなりと入ってこないが、反芻すると旨味が出る、奥の深い書。
Posted by ブクログ
一切の甘えを切り捨て、ひたすら剣の道に生きた絶対不敗の武芸者宮本武蔵。武蔵は、「千日の稽古を鍛とし、万日の稽古を錬とす」る何十年にも亙る烈しい朝鍛夕錬の稽古と自らの生命懸けの体験を通して「万里一空」の兵法の極意を究め、その真髄を『五輪書』に遺した。本書は、二天一流の達人宮本武蔵の兵法の奥儀や人生観を知りたいと思う人々のために、『五輪書』の原文に現代語訳と解説、さらに「兵法35箇条」「独行道」を付した。
Posted by ブクログ
目の付けやうは、
大きに広く付くる眼也。
観見(かんけん)二つの事、観の眼つよく、見の眼よはく、
遠き所を近く見、ちかき所を遠く見る事、兵法の専也。
敵の太刀をしり、聊かも敵の太刀を見ずといふ事、兵法の大事也。
心眼という言葉があるように、
視ることとは、その対峙するもの、対象に対して、
眼をとおして身体全体で、<心-身>を総動員してあることが前提とされていよう。
いわば、<身―構え>と云うべきものが。
通常、視るとは、自分の居場所、その固定点からのパースペクティブ―遠近法
的な座標なのだが、
大きく広く、<観>と<見>、強く・弱く働かせよ、遠き所を近く、近き所を遠く
ひとつの舞台を創っていく作業でも、或は作品を鑑賞する場合でも、
同じようなことが言える。
能では、<離見の見>と云う言葉があるが、
この語もまた、<観―見>と相似た地平にあるだろう。
俯瞰あるいは鳥瞰することにも通じるものを感じさせる。
Posted by ブクログ
武士道の本というより、剣術の本だと思う。そういう視点で見れば、とても具体的で、なるほどと思う点も多い。例えば、形を追求しても、形にとらわれるべきではない、というくだりはコラムのネタに使わせていただいた。全体に表面だけで剣術を捉える他流派に対する非難が書かれているところがなんとも新鮮。この時代から剣術は形骸化していたのだろうか。
Posted by ブクログ
宮本武蔵が書いた本を
著者がわかりやすく伝えてくれています。
アメリカのビジネス書として読まれているらしいですが
日本でも同様に何の世界でも通用する考えだと思います。
「刀は相手の太刀をよけるためでも、受けながすためでもなく
あくまでも相手に一太刀をあびせるために振る。
相手の太刀をかわすことを考えている時点で負ける。遅い。」
こんなちょっとしたことが人生の一瞬一瞬で考えれるように
自分を奮い立たせてくれる一冊です。
Posted by ブクログ
かの宮本武蔵が書いた武芸書です。しかし戦いは最小単位が個人であり、個人の集合体が部隊である以上、個人のマインドが戦いに及ぼす影響はかなり大きなものになります。その点本書は実に示唆に富んだ内容といえるでしょう。
Posted by ブクログ
【読む目的】
五輪書を通して宮本武蔵の人生観について知りたい。
【読んだ感想】
『恋慕の道思いよるこころなし』など賛成出来ない箇所もあったが(^^;
『千日の稽古を鍛とし、万日の稽古を錬とす』『千里の道もひと足づつはこぶなり』この二つの言葉を見つけただけでも、この本を読んだ甲斐があったと思う。
Posted by ブクログ
宮本武蔵の兵法と人生観がわかる本。
「能く能く吟味すべし」「能く能く工夫有るべきなり」「能く能く鍛錬すべし」みたいな言葉多い印象。
この本で道標はしてあげられるけど、結局は自分で考えて日々努力重ねるしかないんだよ、と言われている気がした。確かにその通りだ。
兵法は「相手を斬る」ためのものであり、目的に対してとことん合理的に考え、本質を見失わない武蔵の姿勢は見習うべきだと思う。
仕事などにいかせそうな内容も少しあった。
スポーツなどの勝負ごとをやる人にとっては役立つことが多いと思う。
Posted by ブクログ
宮本武蔵が武術の心得を説いた『五輪書』のテクストと現代語訳に加えて、編者による解説が付されている本です。
編者の鎌田茂雄は仏教学者ですが、仏教的な世界観にもとづいて『五輪書』を解釈することは手控えられており、もっぱら武蔵の実利主義と合理主義の精神に注目しています。とはいえ、彼の説く実利主義が、一つのところに居つくことを排するという精神につらぬかれている点に、「応無所住而生其心」という仏教の教えと呼応する内容を見いだしたくなるのも自然なことであるような気がします。
谷沢永一のように、現代のビジネス・マインドに通じるような教えを『五輪書』に読み込もうとするスタンスの解説書はちょっといただけないという読者には、入門書として有益なのではないかと思います。
Posted by ブクログ
剣豪宮本武蔵の本。
活躍したのは安土桃山時代。
剣術だけの本ではなく、人生をどう生きるかに繋がる本。実際に剣以外にもマルチに活躍している。
変化の早い現代においても、自分を高める考え方について学べる。
五輪は仏教用語で万物を表す地水火風空を示す。
地、ひとつを極めれば万物を知ることが出来る。物事の本質は、横展開可能ということ。
水、地道な鍛錬が必要で、勝つべきは昨日の自分。いざというときに心を体を使いこなすために経験を積み重ねよ、ということ。
火、先手を取るという駆け引きの話。そのために有利な環境を父の手、そして相手を知る。その先に相手を崩して、それを捉えて勝利につなげる。
風、偏り・型に囚われずに目的を忘れてはない。瑣末な事に囚われずに勝つための基本を磨く事。これは8:2の法則にある、2割の有効な事が全体の8割を生んでおり、選択と集中を見失わない考え方に繋がるように思った。
空、心を磨き一点の曇りもない状態となる。
2025年の大阪万博にも「空」がテーマにある。
あるけど、ない空っぽの状態。
難しいけど万博のテーマの持続可能な社会は消費社会で見失った価値観から、生きるための目的を日本的に捉えていて面白い。
空、迷い、朝鍛夕練。
とらわれるな、深い。
Posted by ブクログ
【能々鍛錬すべし。能々吟味すべし】
思ってた内容と違って本当に剣術の実用書です。
1.この本を一言で表すと?
・剣の実用的ノウハウ本
2.よかった点を3〜5つ
・あらゆることにおいて直実を見分ける力を養うこと。目に見えないところを悟ること、(p87)
→身体だけでなく心も鍛錬しなければならないということ。心の鍛錬は自分に足りていないと感じている。
・観の目をつよくし、見の目は弱くする(p101)
→心を落ち着かせてじっくり向き合うことがないなぁと実感。
・枕をおさえる(p167)
→自分の人生、いろんなことが後手後手になっている。先を読む力が足りていないと感じているのでこの文が目に留まりました。
・能々鍛錬すべし。能々吟味すべし。
→何度も出てくるフレーズ。やはり読んだだけ、聞いただけでは身につかず、実際に繰り返し練習実践が必要ということ。武蔵の思想がよく出ている個所ではないか。
2.参考にならなかった所(つっこみ所)
・万里一空の感覚がいまいちつかみにくかった
・恋愛を邪魔という考え方は、何か我慢した生き方ではないだろうか?
3.実践してみようとおもうこと
・道を行う9つの法則(p87)を手帳に書き写して行動指針とする
4.聞いてみたいこと
・武蔵が極めた「万里一空」とは?私たちが目指すべきものか?
・この本がみなさんの生き方にどう影響すると思いますか?
Posted by ブクログ
ま、あたり前の話なんだが、こういうセンスとか勘とか、何か「言葉ならざるもの」で体得している技術を、「こういうことなんだよ」と言葉で説明するのって難しいなあ。
現代なら、優秀なライターがなんとかものにしてくれる場合はあるのだろうけど。
にしても五輪書、「詳しくは口伝で」って、ええー!そこを読みたいのにー!
Posted by ブクログ
宮本武蔵の生き様が窺える。きっと合理主義者で勝利に飢え、一切の甘えを捨てて剣に生きるような人物だったはずだ。そして合理主義者・武蔵が最も雄弁に語っているのは勝つためには「心の充実」が必要不可欠であるということ。これは興味深いなあ。
Posted by ブクログ
宮本武蔵著の五輪の書の原文と、著者が現代語訳したもの、補足事項などが記載された作品。武の道を極めるのみでなく、様々なことに取り組むことの必要性、戦いにおける心構え(これについてはどの分野でも応用可能)、剣の使い方など、武の道を極めた武蔵だからこそ至った境地について書かれている。
特に敵の心を乱し、その隙を逃さず徹底的に攻撃するという考えについて多く述べられていた。
Posted by ブクログ
昔から読みたかったんだけど、読んでみて「一度も敗れていない」っつうところにちょっと冷める。
まぁ負けてないから生きているという事なのだろうが・・・。
日々の生活にも参考になる言葉が結構ある点では、興味深かった。
Posted by ブクログ
ご存知! 剣豪・宮本武蔵による兵法の指南書。自身の兵法観、二天一流の戦い方なんかを記しています。
あくまでも兵法の指南書なので、「太刀でもっていかに戦うか」「戦いの際の心構え」等が記述の主だったことになります。しかし、至る箇所の記述で日常生活に役立てられるものを見つけられるのですよ、これが。
たとえば戦いを議論やプレゼンテーションに置き換えてみてはいかがでせうか? 置き換えながら、読みながらしていたら意外と「ほうほう」なのです☆ 早速今度つかってみよ☆ さすがに「太刀筋について」をそのまま日常生活に応用するのは難しいかもしれましぇんが・・・。(´ω`)
本の作りとしては、原文・訳文はもちろん、鎌田さんによる補説・解説が「付記」として掲載されています。また、『五輪書』の条文にあたる「兵法三十五箇条」の記述が「参考」として載せているので、横にも縦にも読める感じです。
・・・うん、まあ慣れるまでは鎌田さんがちょっとうるさいかな。
【目次】
はしがき
「五輪書」を読むにあたって
地之巻
水之巻
火之巻
風之巻
空之巻
兵法三十五箇条
独行道