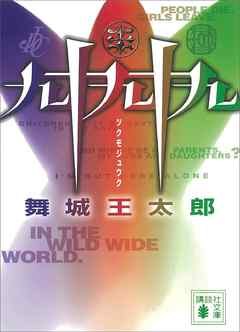あらすじ
あまりの美しさに、素顔を見せるだけで相手を失神させてしまう僕は加藤家の養子となり、九十九十九(ツクモジュウク)と名づけられた。九十九十九は日本探偵倶楽部(JDC)に所属する探偵神でもある。聖書、創世記、ヨハネの黙示録の見立て連続殺人事件に探偵神の僕は挑む。清涼院流水作品の人気キャラクターが舞城ワールドで大活躍!
...続きを読む感情タグBEST3
このページにはネタバレを含むレビューが表示されています
Posted by ブクログ
ツライ。今回は辛さが勝(まさ)ってしまった。
この場合の「ツライ」はしんどいとか悲しいとかの意味です。
しばらく立ち直れないかもしれない。
清涼院流水のJDCシリーズの二次創作なのかと思って読み始める。
九十九十九が主人公で、美しすぎるって設定はそのままで、九十九十九が誕生するシーンから始まるんだけど、美しすぎて生まれた途端周りが失神して、美しすぎるので誘拐されて、美しすぎて顔を傷つけられたり折檻されたりして…って展開に、清涼院流水の世界ではまるっと無視されていた美しすぎることの現実(いやフィクションなんだけど)を突き付けられて、のっけから雲行きの怪しさを感じ取る。
誘拐犯で虐待者である鈴木君の暴力から逃れるため、夫の加藤君が、鈴木君と加藤君のコドモであるツトムとともに九十九十九を連れて実家の福井に帰る(福井かぁ舞城王太郎だなぁ)と、九十九十九は加藤家のコドモであるセシルとセリカにペット扱いされる。
この時点で、これいわゆる二次創作じゃなくね?と気づく(←遅い)。
清涼院流水が自作で繰り広げる言葉遊びを舞城も見せるんだけど、舞城の方が巧みで(あくまで個人の感想です)、清涼院流水の立場無いなぁとか思ってしまう。
でも清涼院流水は先駆者という点において絶対的な存在なのは揺るがない。
で、舞城は流水を凌駕しつつ、流水をすごく良く理解しているとも感じる。「JDCシリーズの本質は執拗なアナグラムと駄洒落にあるからね」なんて台詞は、鋭い指摘だなと思う。
清涼院流水の創作世界は現実とは切り離された「優しい世界」なのに対して、舞城王太郎のそれはとことん現実が介入してくる。しかも楽しくないほうの現実。
私は多少なりとも現実逃避したくてフィクション読んでるところがあるので、全然逃避させてもらえない舞城王太郎の世界はツライ。
第二話で清涼院流水の書いた第一話が届くのは、清涼院流水作品を踏まえてるが、その内容は、第二話の九十九十九が経験したこととそうでないことの両方が取り込まれてて、つまり事実に反している。第一話というフィクションと第二話という現実の二重世界が進行するくだりは、清涼院流水以上に『匣の中の失楽』ぽい。
でも第三話で届く清涼院流水の書いた第二話は(それを読む九十九十九が言うには)やはり事実に反していて、ここでも世界は分岐する。『匣の中の失楽』では奇数章と偶数章のパラレルワールドだったけど、舞城の世界はマトリョーシカを仕舞っていく感じでどんどん外殻が出来る。
そのうち、舞城の過去作品で起こったエピソードが挿入されたり、エキストラが舞城作品のどこかで出てきた人の名前だったりして、自らの作品をも取り込んでゆく。
作品中にはあらゆる見立てが散りばめられている。
でも見立てって見立てられるモノが万人に共有されていることで成立する手法なので、名物編集者やら話題の作家やら、よほどミステリ業界と講談社ノベルス界隈に詳しくないと通じない楽屋落ち的な一面は、ぼんやりとしか分からない(やけに佐藤友哉推しなのが気になる)。
一方、作品の核でもある創世記の見立ては、自分が創世記をちゃんと知らないものだから、こちらもぼんやりとしか分からなくて残念(これは教養の問題なので私の落ち度である)。
でもぼんやりとしか分からなくても、九十九十九の美しさとは何なのかという核心に物語が迫ってくると、ツラサMAXになる。
これ、JDCでも何でもないやん。
奇形児を中心に繰り広げられるネグレクトや虐待と、家族愛という、作品世界の正体は、最高にツライ。
ここに閉じ込もるべきか現実を受け入れるべきか、と当事者が葛藤する。
神(=創造主=作者)の設定は清涼院流水に重なるけど、物語を破壊しようとする行為は、舞城王太郎による「優しい世界」の否定でもあるのかも。(ちょっとこの辺りは確信がない)
虐待と家族愛は舞城王太郎の不変のテーマだけど、今回辛さが勝ってしまったのは、いや舞城は決して虐待を肯定してるんじゃないのは分かってるんだけど、ほんのちょっとそんな兆しをどこかに見てしまったからな気がする。
タイムワープして行ったり戻ったりするあたり、戻って読み直した方がより判るだろうとは思いつつ、舞城王太郎はやっぱり二度は読めないのである。
(追伸:ネット上に落ちている本作品の批評に良質なものがありました)
Posted by ブクログ
元の探偵ものシリーズのトリビュートとのことですが、未読のままこちらを読んだ自分も問題なく楽しめました。
(wikiの該当キャラの項目を先に読んでおいたほうが面白かったかも?)
それを踏まえても、元小説のファンはこの内容で怒らなかったんだろうか?と心配になる^^;
●以下ネタバレ
章の順番がめちゃくちゃなところからも、この小説がどういうものかがわかる訳ですが、色々時系列を気にして頭を回転させながら読んでも、ああ、そういうことなの・・・みたいなオチだから脱力すると同時にその疲労が全部悲しみに変わるストーリー構築なので再読する自信がまだ無い。
つくもかわいそうすぎるやろ・・・
●以下ラストネタバレ
ラストの「アキレスと亀」の引用は、時間をどんどん分割していくことによってはたからみたら永遠に静止しているように見える、ということを言っていると思う。
つまりカーズ様よろしく「考えるのをやめた」のだから結局目覚めないんじゃ・・・という結論になってしまって悲しい。
ていうか元々加藤さんちの地下室から出てないんじゃないかと思うんだけど・・セシルとセリカも本当はいないんじゃないかな。
って考えると本当に悲しいのでちゃんと目覚めて現実と向き合う展開で終わってほしい訳ですがそうなるともう別の小説なので続かないんだろうなあ
Posted by ブクログ
前話が次の話の中で作中作として消化されていく入れ子構造をとったとんでもなくメタメタな作品。
一見すると意味の見えない行動、現象もその後の話の中で見立てとして回収され、意味のないものを全て消し去る勢いであらゆるものに意味付けがなされていく。
作品内で自分が登場する小説を読まされる九十九十九は読者の視点を共有しながらも自身が虚構内の存在にすぎないためどっちつかずの宙ぶらりんな状態に放っておかれる。
その不安定さをだんだんと九十九十九自身自覚していき、最終的にはその不安定な状態を積極的に肯定する形で作品は終わる。
東浩紀の『ゲーム的リアリズムの誕生』で取り上げられていた通りの解釈だけに留まる作品とは思えないが、繰り返される物語と増殖するプレイヤー=九十九十九の部分は確かに一部分言い当てているように思える。
最後の一文「その一瞬の永遠の中で、僕というアキレスは先を行く亀に追いつけない」がたまらなくかっこいい。