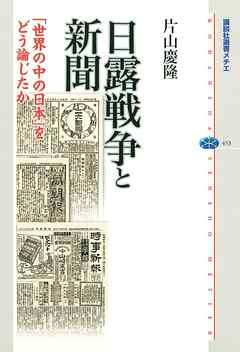あらすじ
日英同盟の是非、開戦論vs.非戦論、「露探」問題、日比谷焼打……新聞がいちばん面白かった時代。日露戦争の時代、新聞界は黄金期を迎えていた。福澤諭吉創刊の『時事新報』、陸羯南主筆『日本』といった高級紙から伊東巳代治による『東京日日新聞』、徳富蘇峰『国民新聞』や『東京朝日新聞』など時の政府に近いもの、政治家の女性問題のようなゴシップから政府・大企業批判、リベラルな主張までを載せる『萬朝報』『二六新報』。知識人から下層階級、政府支持から社会主義者まで、多様な読者に向けた無数で雑多な新聞が、大国との戦争へと向かう日本と世界をいかに語り、論争をしたか。膨大な史料を掘り起こし、新聞が大企業化する以前の、粗野で豊かだった時代を活写する、メディア史研究の試み! (講談社選書メチエ)
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
本書は、日露戦争期におけるメディア-特に、新聞報道を考察したものである。この時期の新聞報道と言えば、大多数の新聞は日英同盟を背景に対ロシア強硬論(開戦論)を煽る一方で、ごく少数の「非戦論」者たちが開戦に反対した・・・というイメージが一般的に持たれている。筆者は、そうしたイメージは「神話」に過ぎないとして、複数の新聞を比較検討することで、当時の新聞報道の実態に迫っている。
本書が明らかにしたのは「当時の新聞の外国認識は、きわめて多様性に満ちており、それは一様でも、また政府の言いなりでもなかった」(p.201)という事実である。例えば、国を挙げて歓迎されたと言われている日英同盟でさえ、実は反対論を唱えていた新聞があった-また、その影響力は決して低くなかった-ことを指摘している。
確かに、これらの新聞も最終的には同盟を支持しており、“結果”だけを見れば「神話」を覆すほどの目新しさがあるわけではない。しかし、そうした「賛-否」という二項対立の評価軸を取っ払い、同じ「賛成派」でも、その結論に至るまでの関心や根拠は一様ではなかったという“プロセス”に注目した所に、本書の面白さがある。また、そうした“プロセス”に注目することで、その後の新聞の動向に影響を与える“伏線”を浮かび上がらせることができる。例えば、新聞各紙の中には、ロシア「国家」には強硬論を唱えながらも、ロシア「国民」(民衆)には同情を示す論調が少なくなかった。本書は、ここに「戦後の日露「和解」につながるような議論が準備されていた」(p.189)として、一九〇七年の日露協約成立の“伏線”があったと指摘している。これは、単に「開戦」か「非戦」かという二項対立の評価軸からでは浮かび上がらない考察であろう。
ともすれば、我々は「賛-否」という評価軸でメディアを分析しがちである。しかし、同じ「賛成派(反対派)」でも、その論理が全く同じであるということはあり得ない。むしろ、そうした“細部”にこそ、メディアの独創性が色濃く反映されているのだと言えよう。
Posted by ブクログ
[ 内容 ]
日露戦争の時代、新聞界は黄金期を迎えていた。
福澤諭吉創刊の『時事新報』、陸羯南主筆『日本』といった高級紙から伊東巳代治による『東京日日新聞』、徳富蘇峰『国民新聞』や『東京朝日新聞』など時の政府に近いもの、政治家の女性問題のようなゴシップから政府・大企業批判、リベラルな主張までを載せる『萬朝報』『二六新報』。
知識人から下層階級、政府支持から社会主義者まで、多様な読者に向けた無数で雑多な新聞が、大国との戦争へと向かう日本と世界をいかに語り、論争をしたか。
膨大な史料を掘り起こし、新聞が大企業化する以前の、粗野で豊かだった時代を活写する、メディア史研究の試み。
[ 目次 ]
第1章 日英同盟への期待と危惧
第2章 開戦論への道
第3章 日露戦争勃発
第4章 韓国の保護国化
第5章 戦争の終わり
終章 日露戦後の新聞界
[ POP ]
[ おすすめ度 ]
☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度
☆☆☆☆☆☆☆ 文章
☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー
☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性
☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性
☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度
共感度(空振り三振・一部・参った!)
読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ)
[ 関連図書 ]
[ 参考となる書評 ]