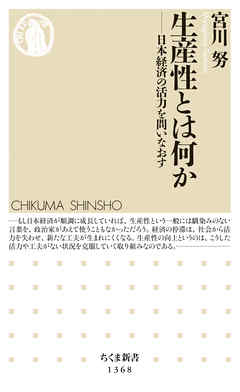あらすじ
バブル崩壊後、日本経済が停滞を脱することができないのは、生産性向上をなおざりにしたからである。アベノミクスでも成長戦略は後回しにされ、日本は世界から取り残された。誤解されがちな「生産性」概念を経済学の観点から捉えなおし、その上で、市場の新陳代謝、既存企業による開発や多角化、経営能力の向上など、生産性向上策について最新のデータをもとに論じる。日本経済が活力を取り戻すための新たな方策を提言する一冊。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
2023年6月に閣議決定された「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2023改訂版(以下、実行計画)」は、長期に渡る日本経済の低迷の主要な原因を、日本の雇用システムに求めている。
これまで我が国では、「企業は人に十分な投資を行わず、個人は十分な自己啓発を行わない状況が継続してきた」とし、そういったことが理由で「我が国の賃金水準は、長期にわたり低迷してきた」としている。そして、「問題の背景には、年功賃金などの戦後に形成された雇用システムがある」とし、いわゆる「日本型雇用システム」の改革を、訴えている。具体的には、①リスキリングによる能力向上支援②個々の企業の実態に応じた職務給の導入③成長分野への労働移動の円滑化、といういわゆる「三位一体の労働市場改革」の実行を政策の柱とすることを提言している。これは、「成長と分配の好循環を目指す政府の複数年度に渡る計画」と位置付けられている。
これに対しては多くの議論がある。例えば以下のようなもの。
■日本では少子高齢化が進み、生産年齢人口が減りつつあるが、つい最近まで実は就業者人口は増えていた。これは、女性と高齢者が新たに就業者に数多く参入してきたためである。ただ、女性と高齢者は短時間勤務などの非正規雇用者の割合が大きく、賃金が低い。このことによって、雇用者全体の平均的な賃金は低迷してきた。
■また、賃上げの理想的な展開は「人的資本投資→人的資本ストックの増加→生産性向上→付加価値向上→賃上げ」である。まずは、生産性の向上が必要であり、そのためには人的資本への投資(教育訓練など)が必要となる。人的資本への投資は、全ての働く人を対象にすべきであり、非正規労働者等もその対象に含まれるべきである
■これまで日本では、人的資本への投資は諸外国に比べてかなり低かった(OJTを費用にカウントしないケース。OJTを含めると諸外国並みという試算もある)と言われており、生産性を向上させるために、人的資本投資を増やすことから始める必要がある
すなわち、政府の実行計画には「生産性」という概念が抜け落ちている。「日本的雇用システム」が問題の根源であると言うならば、「日本的雇用システム」が生産性を上げる作用を持たなかった、付加価値をあげる作用を持たなかったということを、メカニズムを含めて説明しないと納得性が低い。
「生産性」というのは、経済学の概念であるが、本書は、「生産性」の概念を丁寧に説明すると同時に、日本の生産性は特に国際比較においてどのような状況にあるのか、それに対してどのように対処すべきか、等をこれまでの研究や、関連データ等を用いて論じたものである。
分かりやすく、話も面白かった。
Posted by ブクログ
なかなかわかりにくい概念、「生産性」を真正面から論じた新書にしては硬派な本。正直難解な部分もあるが、アベノミクスの実態を論じた最終章はわかりやすかった。安倍首相に読んでほしい。
Posted by ブクログ
この本のタイトルそのものである「生産性とは何か」を知りたいと思って読んでみた。というのも、生産性って経済分野とかで使われるのはまあわかるんだけど、最近では医療や介護分野でも生産性の向上ということがよくいわれていて、こうした分野での生産性向上とは「患者/利用者満足の向上」なのだといったことがいわれるんだけど、どうもそれが腑に落ちにくい、胡散くさいようなうまく言いくるめられているような気がしてならず、生産性向上の本来的な定義でそうした解釈は妥当なのかが知りたいと思ったからだ。
結果的に、定義や解釈の幅を広くみるようなことはこの本からはつかめず、むしろ副題の「日本経済の~」のほうに主眼がおかれた内容だった。
というわけで、当初期待にかなう内容ではなかったわけだけど、なかなか面白かった。日本の現状の社会の仕組みや政治のあり方ってお粗末なんだなあとあらためて思った。また、生産性向上という視点のみで見ると、なかなかの極論も出てくるようで、たとえば40歳定年とかについて、人生が長いのだから後半生に向けて1回定年を迎えてみたいなことが書いてあるけど、それって新卒一括採用みたいな慣行を打破していく流れと併存できるのだろうか。それとも新卒一括採用ってある意味、生産性高い方法な気もするからそれは温存するってことなのかな。それに40歳定年になったら著者ご自身のような研究職のキャリアはどう構築されるのだろう。大学や研究機関を次から次へと移っていくし、高度専門系の人間だから別って考えになるのかしらん。
とはいえ、生産性向上って単純に考えれば労働者をたくさん働かせればいいところを、そうではないあり方で日本経済を変えていかなければという提言がいろいろされているのは、生活のいろんな場面でのヒントにもなりそうだった。スポーツ界が変わってきて成果を上げられるようになったエピソードはすごくわかりやすかった。生産性向上ありきというのはちょっと抵抗があるんだけど、少なくともわりと上位づけて考えないといけなそうだし、経済分野でなくても本来の目的を果たすために効率や成果を重視すべきというのは、まあうなずける話だな、と。
Posted by ブクログ
国民生活を豊かにするための1つの見方として、1人あたりの実質GDPの成長があるが、そのためには生産性の向上が必要であると言われている。その生産性について正確な定義を確認した上で、生産性向上のメカニズムをわかりやすく説明している。ただ、少子高齢化、人口減少に直面している日本にとって、困難な課題であることも浮き彫りにしている。
Posted by ブクログ
経済学の見地から生産性について書かれた一冊。
生産性の公式を定義し、その考え方を順序立てて説明してくれています。
私は、本書を読んで始めてTFP(TOTAL FACTOR PRODUCTIVITY)なるものを知りました。
公式にはざっとこんなものがありました。
生産性=産出物
労働生産性=生産量(付加価値量)/労働投入量
全要素生産性(TFP)=生産量/各投入要素の集計量
TFP変化率=付加価値量の変化率-労働分配率×労働投入量の変化率-資本分配率×資本投入量の変化率
生産性向上の要因を探る
TFP変化率=知識資産の収益率×研究開発投資集約度(=研究開発投資額/付加価値額)
残念ながら実務における生産性向上のヒントはあまり見当たらなかったです。