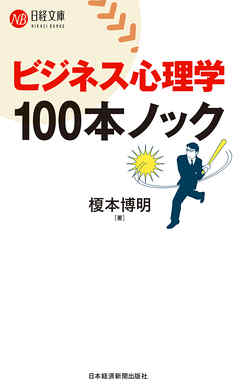あらすじ
●感情的な部分は無視できない
ロジカルに考え、プレゼン資料にも気を遣い、誠意を持って仕事に向き合う――。しかし、これだけでビジネスで成功できるほど、世の中は甘くない。人間はえてして感情的に物事をとらえる向きがあり、そこの部分を無視してはうまくいかない。本書は、『「上から目線」の構造』などでヒットを飛ばした著者が、ビジネスシーンに絞って必要な要素を100項目に凝縮し、見開き2ページで解説するもの。
感情タグBEST3
Posted by ブクログ
端的にビジネスでの応用事例が載っているため、大変勉強になりました。
上司とのコミュニティ、交渉、顧客対応、マーケティングなど多岐にわたる分野の知識が得られます。
Posted by ブクログ
心理学博士である著者がビジネスや人付き合いにおける行動の数々を心理学の観点から解説した一冊。
組織運営やマーケティングの施策や会議時の発言などを心理学の観点から改善策が書かれており勉強になりました。
そして、本書を読んで自分をコントロールすることや組織と上手く立ち回る方法を学ぶことが出来ました。
また、慮ることからくる甘えの心理や言語構造からくる初対面の人との社交性や間人主義と個人主義の違いなど日本人の特性からくるものもあることも知ることが出来ました。
そんな本書の中でも説得の方法に一面的と両面的の手法を相手によって使い分けることや日本人は人間関係も大いに仕事に影響を与えることなどは印象に残りました。
また、流動性知能と結晶性知能は年齢を経るにあっての仕事のやり方を考えるきっかけになりました。
本書を読んで自発的に目標を定め行動することの大切さや他の人の言葉を真摯に受け止めて聴くことなど実践できるポイントとともに日本型組織として属人思考に潜む問題など心理学の知識をもとに日常生活での適応力を磨くことのできた一冊でした。
Posted by ブクログ
「ビジネス心理学大全」からの流れ読み。同じ著者により「大全」は2020年に、本著は2018年に出版された。
なるほど、100本ノックで鍛えてから、さらにそのなかからエッセンスをわかりやすく解説するという位置づけだろう。
本著100本ノックは各項目が見開き2ページにコンパクトにまとめられ大変読みやすくなっており、もっと深掘りしたい人は各項目ごとに他書で勉強すればいいだろう。
「こまった人の心理学」項では専門家の実験や研究が挙げられていないので(まぁそうだろうなと思いつつ)、参考文献でもあればなぁと感じた。
Posted by ブクログ
初対面は大事、紹介文を読んだだけでも好印象を与える。
心のモニターカメラの性能を上げる。他人のカメラの性能に文句は言わない=人のふり見て我がふり直せ
接触回数が多いほど親近感がわく=営業がこまめに顔を出す理由。
日本人がはっきり言わないのは、気持ちが通じ合う間柄だから。
場面にふさわしい自分を演じている。日本人は間柄、を生きている。相手との関係を測る=相手との関係性がはっきりしないとどう対応していいかわからない。
欧米は、自己中心の文化、日本は間柄の文化。
人は自分には甘い。
不安が強い人は、用意周到になれるから成功する。不安に対抗できる人が強い。
最善を尽くす、より具体的で困難な目標がパフォーマンスを高める。
やりたいこと探し、より目の前のことに没頭する。
キャリアデザインより、計画された偶発性理論。
好奇心=後で何に役立つかわからない
粘り強さ=つまづいてもすぐにあきらめない
柔軟性=状況に応じて行動を変更する
楽観性=新たな状況も委縮せず前向きに考える
冒険心=リスクを過度に恐れず、とりあえず全力を尽くす
単純な暗記は30歳から下がる。理解はいつまでも上がる。
乳幼児には、非認知的能力=自己コントロール力、感情を抑制する力、を身に着けさせたほうが、成人後成功する確率が高い。
内発的動機付けを悪用する経営者がいる。=やりがい搾取
内的統制と外的統制=結果の要因が自分のうちにあるか外にある、と考えるか。能力があるからではなく、努力したから成功したと考えるべき。
日本人特有のモチベーションは人間関係=他者指向性。
現代ではますます強くなっている。
快適な環境にすると、交渉や商談がうまくいきやすい
人は期待されると伸びる=ピグマリオン効果。
全会一致は異論が許されない雰囲気があった証拠=反対意見をわざと出させて空気を変える。
不祥事の元凶は属人思考。事柄ではなく人で判断しがち。まとまりの強さは、不祥事につながりやすい。
みんなで決めるとリスキーシフト(リスクを選好しやすい)を起こしやすい。
権威と好感度による信用性の付与=学者とタレントをCMに使う。
心理的負債感があると、お返しの心理が働き、承諾しやすくなる=まずプレゼントをする
みんな、を基準にすると選択を誤る。明確な基準がないときは他人の行動を参照しやすい。
飲食中は相手の言い分を受け入れやすい=ランチミーティングなど。
選択の自由を奪われることには抵抗したがる=売り切れ間近、本日限り、などに弱い。
ツァイガルニク効果=中断されたものは引っかかる。少し手を付けておく。
断るより受け入れるほうが心理的負担が軽く感じられる=フットインザドア技法。最初に受け入れると次も受け入れやすい。
おまけや値引きに弱い。好条件は後出しで。お返しの法則。
旅先だと無駄遣いしやすい=心の財布が違う。
現在志向のバイアス=目の前のことを優先しがち。ダイエットが成功しない理由。
ほめて育てる、という育て方で、レジリエンス=状況に合わせてやりぬく力、が弱くなる。傷つきやすい。
Posted by ブクログ
学生の頃に習った心理学用語がたくさん出て来て懐かしい。その時々の自分の感情がどういった要因によって引き起こされているのか、心理学を理解することは自分自身を理解することなのだと改めて感じることができた。
自己効力感が下がる原因について教えてくれる項目が面白かった。自分の生活を見直してみるきっかけにもなるかもしれない。
Posted by ブクログ
・コミュニケーションにおいてスレ違いが起こる背景には、人間の自己中心的な性格が絡んでいる。人は自分に都合よく物事を知覚し(選択的知覚)、都合よく物事を記憶している(選択的記憶)。
・仕事ができるのに不安が強いタイプ(防衛的悲観主義)の人は、最悪の事態を想定して用意周到に準備を行うがゆえに、成果を出せる。このタイプの人に「自信を持て」と声をかけると不安が消え、かえってパフォーマンスは下がる。
・説得する際は、最初に好条件を示すのではなく、後から追加する「ザッツ・ノット・オール技法」が有効である。追加の条件に相手は得をした気持ちになり、納得しやすくなる。
・商品や企画を売り込む際、相手がはじめから関心を持っている場合は、セールスポイントを最後に強調し(クライマックス法)、相手の関心が薄い場合は、最初に強調する(反クライマックス法)と効果的。
・会議で異論を唱えにくい雰囲気がある時、そこには無言の「同調圧力」が働いている。同調圧力に屈すると、疑問に思える提案を全会一致で可決する、といったことが起こり得る。
・物事を決める時、集団で話し合うと、リスクのある判断を下してしまう「リスキーシフト」に陥ることがある。皆で決めると気が大きくなり、各自の責任感が薄れるからだ。
・他人の不幸を喜ぶ心理のことを「シャーデンフロイデ」と呼ぶ。政治家や芸能人など、社会的地位の高い人の不祥事を興奮気味に語る人は、この心理傾向が強い可能性がある。