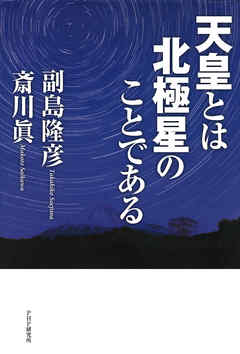あらすじ
今上天皇の譲位問題について議論が高まっている。この問題を考えるにつけても、日本人が知識として知っておかねばならないことは、「天皇」という言葉の意味についてである。「天皇」とは、「天の輝き」のことであり、天の中心に位置する「北極星」のことをさす、ということを、斎川眞氏が、その著書『天皇がわかれば日本がわかる』(ちくま新書)で解明した。本書は、この本を土台として、副島隆彦氏との再度の共同研究によって、さらに意味を掘り下げ、わかりやすく解説する。すべては、「天皇」という言葉の下に、なぜ日本人は歴史を紡いできたのかを理解するところから、現代日本人にとっての自覚ある国家観が生ずる。「日本人とは何か」という根本問題を、法制史の側面から浮き彫りにした、好著である。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
「天皇」とは、「天の輝き」という意味で、晴れた日の夜の北の空で、この星(恒星)だけは動くことなく、小さく輝く星である。その周りを他の衆星(恒星たち)すべてが回っている。即ちこれが北極星(The Polar Star:ザ・ポーラー・スター)である。
古代の日本、皇室の方々のこと、古代中国、朝鮮半島等と日本の関係、668年の日本国の成立・建国以来の日本国の国王様の「天皇」というコトバは、中国史上唯一の女性皇帝である「則天武后(武則天)」が660年に正式に使い始めた、と「旧唐書」に書いてあるのを、移入(採用・借用)して日本国の称号として使った。
”中国史で唯一の女性皇帝の則天武后の方は、後世に伝えられているのとは全く逆で、実は大変、民衆や周囲の人たちに救世主、女神のように慕われていた、偉大な女帝だったらしい。
それは、女性が六十年もの長い支配(統治)を続けたこと、洛陽の龍門石窟に製作された、ひときわ大きく優美な大仏の像の柔和な女性の顔の大仏像「奉先寺大仏」や、武則天の命令によって幽閉されていた息子二人が、母親の死後、それぞれ最大限褒め称えた尊敬の諡号(おくり名)を与えたことなどから、周りや民衆たちからとても崇拝されていたとしか説明がつかない。”
と本に書かれています。
いろいろな意味で、”六六三年の白村江の戦い”が、古代日本にとってとても大きな影響があったことは明らかなことです。
森嶋通夫さんや本書からも、それまでは北九州の「倭国」と近畿の「大和」の2つの大きな勢力が古代日本にあり、「倭国」の貴族・有力者たちが唐と新羅の連合軍に”白村江の戦い”で大敗し、「全滅」もしくは「滅亡」「衰退」していき、そして近畿地方の「大和」が日本を統一し、今に続く日本国が誕生し、日本国王、天皇号、ご皇室の方々として現代までに継続してきている。
という説がいちばん説得力があります。
ちなみに森嶋通夫さんの本では、”白村江の戦い”の結果、古代朝鮮半島から日本に、大勢の「百済」出身の王族や貴族などの高貴な一族で家柄と育ちの良い男女の方々が逃れてくることになり、当時の日本の皇室関係の男女の方々たちは優先的にそうした人達と婚姻関係を結んでいったと書かれています。
また、わたしが”白村江の戦い”にとても興味があるのは、どうしても、いまの日本、台湾、中国、韓国、北朝鮮などの東アジアの状況が、古代の東アジアの状況ととてもよく似ていると思うからでもあります。
古代と異なるのは「台湾」の存在です。古代には今の「台湾」の地には、大きな勢力は存在がしていませんでした。
最近はとても台湾と中国との危機が報道されています。
もしも中国が軍事侵攻をしたとすれば、実際に戦って、中国人と殺し合いをしていくことになるのは、アメリカ人達ではなくて、地理的に中国と近い、「いまの日本人達」になってしまうと思います。
つまり今の日本人達がたくさん、殺されたり、身障者になってしまう可能性が高いのです。
そういう方向にならざるを得ないように、アメリカに唆されてしまうことになる可能性が高いと思います。
邪馬台国が男女の奴隷と貢物をもって中国に朝貢していた。
古代日本が日本国内に立て籠もり、国内を整備していく話、立派な政治を行われた日本史上初の女性天皇の推古天皇様のことや、古代日本の大秀才たちが遣隋使、遣唐使として命懸けで海を渡っていったことの話を読めたことは、とてもよかったです。
大和朝廷はもともとは部族の長であった、白村江の戦いの結果、倭部族が衰退していき、大和部族が日本国家の長になった。そして中華帝国みたいな国を作るぞ、と決意し天皇を長とする律令体制の国家体制を作り上げた。
天皇様が今も続いている理由のうちには、日本には天皇を打ち倒して、自分自身の権力を唯一無二のものにするという政治思想を持っていなかったことや、結果として天皇様は直属の軍をずっと持っていなかったので、自分の軍隊を率いて、みずから合戦に行くということもなく、軍事抗争からも超然としているような存在が続いてきた。
斎川眞さんが、”日本は、本質的に、千年間何にも変わっていないのである。日本が、今日、ぶつかっているような問題はすべて、八世紀の律令の時代に現れている。”と書かれています。
「大和」というのは「大きな平和」という意味、「大きな平和、秩序即ち大和を喜ぶ」という東アジアの歴代の支配者(皇帝)たちの支配感を、日本に持ってきて、奈良の「やまと」という地名にかぶせた「大和」を無理矢理「大和」と読むことにした。
わたしは古代日本の皇室の方々たちはとても立派な方々たちが多かったと思います。