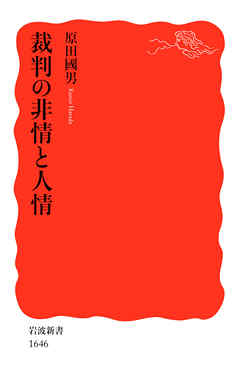あらすじ
裁かれるのも「人」なら、裁くのも「人」のはず。しかし、私たちにとって裁判と裁判官はいまだ遠い存在だ。有罪率99%といわれる日本の刑事裁判で、20件以上の無罪判決を言い渡した元東京高裁判事が、思わず笑いを誘う法廷での一コマもまじえながら、裁判員制度、冤罪、死刑などをめぐり、裁判官の知られざる仕事と胸のうちを綴る。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
親しみある語り口で裁判官の矜持が伝わる筆致は、司法の立場を熟知した表れだと感じる。審判はどこに焦点を合わせるのか、被告人の生い立ちや原告側の悲しみ、各々の生活の崩壊や感情の不穏に身を寄せながら法の尊重や良心からの判断を肝に銘じる。決して己の立身出世や保身であってはならない。そこに司法の腐敗は宿る。終盤、冤罪は不正義だという意見にも賛同する。ほんの少しずつだが社会は変わっていく。その些少な希望に期待したい。
Posted by ブクログ
素晴らしい一冊だった。裁判官というのは厳粛さに満ちていて異世界のようにさえ思っていた。本書の内容からもそうであるが、ユーモアを交えた原田さんの淡々として親切な文章、読んでいてワクワクするような文章力そのものにも裁判官へのイメージがアップデートされ世界が広がった感覚を抱くことができた。
Posted by ブクログ
エピソードトークがおもろい
あと、先輩たちへのリスペクトがすてき
尊敬できる人がまわりにいてくれるのまじでありがたいしラッキーと思う
薬物犯罪は病院にぶち込む一択
証人が長々と話しているのに、通訳人があまりに短い言葉で通訳すると、不信感をもつ。
これめっちゃわかるー!!
主文の言い回し、無罪だけが「被告人〝は〟」で、死刑とか懲役なら「被告人〝を〟処する」だから、この〝は〟か〝を〟かが、運命の分かれ道
「被告人を無罪とする」とは言わない
Posted by ブクログ
感動した。特に働き方について学ぶことが多かった。また司法と裁判官のあるべき姿・ありたい姿について自由な捉え方を可能にしてくれる。そして、人としての謙虚な考え方を一つ学んだ。
なお内容は法律モノのエッセイであり、判決文の書き方にまつわる小咄や、裁判官の趣味・生き方、司法制度改革に関わる意見など、いろいろな話が載っている。それぞれの話の特徴は、簡潔で知的に面白い内容であること。
判決文を簡潔にする石田裁判官と、文学的な長文とする四ツ谷裁判官の対比が面白く、石田裁判官が四ツ谷裁判官の補佐をした際には長文としていたという話も、石田氏の謙虚さが窺えて面白い。また若いうちは長い証拠文書を効率よく読もうとするが諦めて最後の一行まで読まなくては意味がないのでちゃんと読め、という話は反省させられた。また趣意書は初めに読んでおけ、というのも、仮説を早めに持って考えを深められるからなんだろうと考えさせられる。仕事に直接役に立つ励ましの言葉と受け止めた。
また、司法と裁判官は杓子定規ではなく、違法行為であっても人情を大切にすべきだというのか原田の立場である。法律や規則とは不自由の代名詞のようであり裁判官はその象徴のようかもしれないが、原田はプロフェッショナルな職業倫理の軸足の一つを人情において、あるいみやりたいように裁判やっていたようだ。こういう温かい裁判もアリだ、と思わせてくれる。
「最高裁判所長官になりたいです!」という若者が増えたことを嘆く原田は、もう単なるおじいさんである。しかしこの嘆きは、人の人生を左右する裁きを下す裁判官という役割を担うのに、出世しようという考えを持つことは責任の重大性をわかっていないということだという考えからきている(と思う)。良くも悪くも裁判官の仕事の恐ろしさや重みを深く知った原田だからこその説得力あるご意見であり、僕は感動した。こんな裁判官たりたい、と思った。
また、彼やその知人の好きないろんな本や映画などが紹介されていて、裁判官の世界をもっと深くまで知ることができるような面白みのある本だった。
Posted by ブクログ
よく知らない裁判官の世界。裁判官が書いたものを読むのは初めてかも?
堅苦しい話はほとんどなくて、裁判官が世間からどうみられているか、それなりによく認識されていることに多少の驚きあり。。。彼らは、どのようにその世間の見方を知るのだろうかとか。
紹介されてた本が軒並み面白そう。
『法服の王国』『汽車ポッポ判事の鉄道と戦争 』『青春の柩―生と死の航跡』『裁判官の書架』『落日の宴』
法服の王国だけ、意外にも黒木亮さん作だったので、買ってみた。
厳密さは違うけど、内部監査の独立性や「保証」の難しさが、裁判所、裁判での事実認定と重なってみえて、妙な親近感がわいてきました。
・訓戒は無意味なのか
→仕事での注意も無意味だろうか。信念に近い行動か。
・自由な議論とは、何を言っても、人事上の不利益を加えないということである。
・正解を得られない問題を考え抜くことは大切。これにより一種の謙虚さが生まれる。
Posted by ブクログ
裁かれるのも「人」なら、裁くのも「人」のはず。しかし、私たちにとって裁判と裁判官は、いまだ遠い存在だ。有罪率99%といわれる日本の刑事裁判で、20件以上の無罪判決を言い渡した元東京高裁判事が、思わず笑いを誘う法廷での一コマから、裁判員制度、冤罪、死刑にいたるまで、その知られざる仕事と胸のうちを綴る。(2016年刊)
・第一章 裁判は小説よりも奇なりー忘れがたい法廷での出会い
・第二章 判事の仕事ーその常識、非常識
・第三章 無罪判決雑感
・第四章 法廷から離れてー裁判所の舞台裏
・第五章 裁判員と裁判官ー公平な判断のために求められるもの
・おわりに
本書は、岩波書店の「世界」に連載したコラム「裁判官の余白録」をまとめたものであるという。
読み始めて、文章の平易さ、内容の面白さ、著者の率直な心情の吐露など、魅力が満載で、一気に読みあげた。交流のある裁判官とのエピソードもあり、興味深いものとなっている。本書は、お勧めの1冊である。
以下、備忘録として、
p3判決書の起案の話では、内容を、まったく直さない裁判長の話が出てくる。この裁判長は、合議でも自分の意見は、最後まで言わないのだという。自分の意見は殺して、合議体として最高の合議結果と判決を練り上げようとしたということであるが、なかなか出来ることで無い。
p8では、偽証の問題を取り上げている。日本では、検察がよっぽどの事が無い限り起訴しないという。p10「それに、検察は、警察官の偽証をまず起訴しない」のだという。「警察官の偽証は闇から闇へ葬られる」とは恐ろしい話であるが、日本の風土の問題かも知れない。
p46では「法服の王国」(岩波現代文庫 黒木亮著)が取り上げられている。「かなりのフィクションも含まれているが、最高裁判所を中心とした戦後の司法の大きな流れ(それも暗部)はほぼ正確に摑んでいると思う」という感想は貴重である。著者が直接聞いたという、矢口浩一の言葉のことばなど、本書には、貴重な証言がちりばめられている。
p58高度に専門的な問題をどの様に判断するのかということも面白い。法律判断と技術理解は別ということに納得する。
p81無罪判決に勇気はいるのかという議論を取り上げている。著者は、この議論を「ためにするものである」としているが、そうであって欲しいものである。
p108では、最高裁判所調査官について語られている。著者の「内示を受けたときは、本当に、かけねなしに、嬉しかった」、「裁判官であれば、正直、一度はあこがれるポストなのである。」という言葉は、ほほえましい。職業人として、己の能力を買われ、力を振るうことが出来るのは、身の出世とは別に、幸せなことであろう。著者は、東京地裁の部総括判事についても、裁判官の檜舞台としているが、どんな仕事であっても、「気力、体力、実力、能力が一番充実した時期」に打ち込むことが出来れば、「その期間が人生で最も充実した時間なのである」という言葉には含蓄がある。
Posted by ブクログ
裁判官が書く「判決文」が「悪文」である、という指摘は多いが、その悔しさもあるのだろうか。やや滑りがちな感もなきにしもあらずだが、軽妙で味わい深いエッセー。
刑事の裁判官のビジネスキャリアが、その生活、信条の面からよくわかる。
Posted by ブクログ
判決文をじっくりと読んだことはないが、しっかりした論理構成になっていることが予測され、それを書く裁判官は文章作成能力に秀でていると期待できる.したがって本書も簡潔な文章で楽しめるエッセイ集になっている.随所に引用されている本、例えばp12の『裁判の書』.様々な本に目を通しておられることが、素晴らしい判決に結びついていると感じた.
Posted by ブクログ
原田元判事の経験から見た裁判所。
裁判所に絶望するわけではなく、しかし全肯定するわけでもない。
朗らかな文体と相俟って、大きく槍玉に挙げられるようには思えないのは、さすがのバランス感覚というべきなのか。
Posted by ブクログ
普段関わることのない裁判所の中で起こることを知ることができ、有益だった。有罪か無罪かというラインは白か黒かの判断は、「白か黒かの判断ではなく、黒と断定できるかどうかの判断である」と述べられており、この判断基準は私たち一般人には浸透していない部分だと感じた。
現在は裁判員制度があるので、いつ裁判に関わることになるか分からない。そういう意味でも読んでおいてよかったと感じた。
Posted by ブクログ
法律を扱う仕事をしているのに、法律や裁判にどこか苦手意識を抱いている。
試しに「裁判」の2文字を頭に浮かべると、イメージとして広がるのは、冷たいコンクリート色したグレーの世界。
もちろん、公平さを期するために感情を排した慎重なシステムであるべきなのはその通りだし、よくわかるのだけど。
でも、私が好きなのは、例えば新聞だったら家庭面に「ひととき」などの名前がつけられ掲載されている、誰かが綴った生活の小さなひとコマや喜怒哀楽の話なのだ。
本書は、長年の間、刑事事件の裁判官を務めていた著者による、裁判や裁判所、裁判官の仕事についてのエッセイ集。
エッセイといったって、そこは裁判官。
難しい、厳しいお話が多いのかな? と覚悟しつつページをめくると、予想はくつがえされる。
なんせ、本書の中の本人の言葉を借りれば、著者は「いらいらするほど、緩いキャラ」。
裁判官が自分のことを「緩いキャラ」ってふつう言わないでしょ! と突っ込みたくなるが、他にも随所に答えのない悩みに右往左往したり、ユーモラスな仕掛けをしてことの成り行きを見守る著者がいて、とにかく全体的にとても人間くさいのである。
例えば「裁判の記録」という言葉の意味をインターネットでひくと、「民事訴訟法上、一定の訴訟事件に関する一切の書類を綴り込んだ帳簿」などと表示される。
これだけだと、正直なんのこっちゃ、である。
でも、本書の中に登場するのは、持ち帰った記録を無くさないように寝るときは枕元に風呂敷に包んで置いておいたり、列車の網棚に置いていたものを間違って持ち去られそうになりハラハラしたりする著書の姿である。
このくだりを読んで以来、「記録」という言葉は、私の中でコンクリート色ではなくなった。
苦手なのではなく、ただ単に、知らないことに気が重くなっていただけだったのである。
裁判官も、被告人も、私と同じ困ったり怒ったり喜んだりする人間である。
裁判という、非情な世界を舞台にしているからこそ、そのことが際立つ1冊である。
Posted by ブクログ
テレビや新聞のニュースでしか知り得ない事件の
裁判をする人たちのことは、そうなのかと知らないことばかり
未知の世界と言っていいのか
ちょっとドラマで見た感じともリンクしているのか
とにかく、興味深く、驚いたり安心したり
読んで楽しかった?というか良かったなと思った
Posted by ブクログ
裁判官を退官された著者がその仕事人生をエッセイで振り返られています。裁判官としての自分はこんな人なんですよということが紹介されていて面白く読ませていただきました。また他の裁判官のことについても少し話されていて、この仕事に就く人の日常といったものを知ることができます。仕事とプライベート、新人時代のことなど、今まで特殊な世界だと思っていたところが色々と分かって「へえー」と気楽に楽しめる内容になっています。
裁判官の主とした仕事である判決を出すということについては、現状の問題点含めて考えさせられます。こんなこと考えながら苦労されていたのだなということが分かって、裁判に対する気持ち的な理解を持つことができたとも思います。
Posted by ブクログ
どうせ裁かれるなら、こういう裁判官に裁かれたい。そんな気持ちにさせてくれるエッセイです。
裁判官は世間知らずというけれど、逆に人間味があり過ぎるような気もします。裁判官の懊悩も垣間見れて、裁判官の魅力が分かる一冊です。
#読書 #読書記録 #読書倶楽部
#裁判の非情と人情
#原田國男
#2017年28冊目
#裁判官 #弁護士
Posted by ブクログ
藤沢周平「海鳴り」「玄鳥」「蝉しぐれ」
学者は締め切りになってから書き始める
人間は他人の良いところを学べず、悪いところばかり真似をすることになる。
司法権の独立は自浄作用を前提とする
まず余暇を入れてその残りで仕事をする。そうでないと仕事に追いまくられる。
無期懲役では自由に手紙を出せない、死刑なら出せる。
「若き志願囚」「偽囚記」
国民は少年であることを刑を重くする要素と考えている。
少年の大半は更生している。少年法の理念。
被告人から距離があるほど嘘を言っていると思いやすい。世間は罪人と判定しやすい。弁護人は無罪を信じやすい。
人質司法。
無実と身柄についての感覚がない。
裁判員裁判事件と検察独自事件だけが可視化の対象。
録・録=録音録画
人着=人相着衣
見せしめへの過度な期待は常に重罰を招く。しかし目的を達せられない。刑事裁判の限界。
冤罪
無罪となったのだから冤罪はない、という冤罪不存在論。
制度リスク論=不可避の現象である=冤罪不可避論。
刑事学者はこの2つが主流。
Posted by ブクログ
山田洋二監督の帯文「こんな裁判官がいる限りこの国の法曹界を信じたい」に惹かれ、手に取った。
元高裁判事の、雑誌連載をまとめたエッセイ。
法廷内での出来事とか、法曹界の課題問題を軽妙に綴っている。
その中で著者は、誤審判決に絡み、人を裁くことの意味を問い、人を裁くということは、人に許された仕事なのか、本質的に許されない業なのではないか、と逡巡する。
再審無罪までの時間の長さにも、裁判所の責任は、と問う。
監督の推薦文にも納得。
裁判官の判決文にふれ、「名文とは、文章の形ではなく、その中身であり、その訴えかける力の強さだと知る。そういう意味での名文を裁判官は目指すべきである。」と、述べている。裁判官ばかりでなく、一般の人が文章を書く時にも参考になる心構えだと思う。
Posted by ブクログ
軽い語り口で、一人の刑事裁判官としての物の考え方を示しておられる。
弁護士としては、一般の方々には無論、若い刑事裁判官に読んで欲しい。先生の授業そのまま、人柄のよくわかる本である。
Posted by ブクログ
元刑事裁判官による、裁判官人生記。
刑事裁判の妙味と難しさ、裁判員裁判への思い、裁判所等での執務風景などが、著者自身の具体的経験を基に語られており、法曹関係者や法学部生のみならず、一般国民にとっても興味深い内容ばかりである。
裁判官に対して抱かれがちな「堅苦しい」イメージとは裏腹に、とても軽妙な語り口で、すいすい読めてしまう。
Posted by ブクログ
著者は元裁判官。裁判官の多くは清廉潔白であり、冤罪を防ぐため、また、正しい判断をするために、日々膨大な資料を読み込み、事件と向き合っているという。雑誌の連載を元にした書籍のためか、全体的にさらりとした印象。未知の世界に触れた楽しさはあるが、よりリアルな実情にも興味がわいた。支部でのエピソードはとてもほほえましかった。
Posted by ブクログ
元・判事、現在、客員教授の方の雑誌定期掲載記事のまとめ本。執筆時点で72歳(2017年明け前後)なので、戦中生まれだが戦中派ではない、という世代。
中身は、"堅苦しい"ものではないが、"砕けたもの"でもなく。裁判傍聴記の類の書籍とは、筆者の立場も責任も違うので比較するまでも無く、その点では全般に"堅い"。
筆者自身も"ガチガチの堅物"ではなさそうだが、はやり堅実なお人柄が全体に色濃く出ている。
筆者的には"柔らかく"を意識されているようだが。
さすがに旧仮名遣いなどは無いが、やはり年齢層等の文章で、良く言えば落ち着いている。悪く言えば、まあ当たり前なのだけれど堅くて眠くなる面も少なくない。
"判事"と言われて、その人物像のステレオイメージが沸くか?、と聞かれれば"さあ??"というのが本音だった(正直、余り関心が無かった)ので、筆者を含めてその知人・関係者達の記載には面白い部分もあったか。
Posted by ブクログ
元東京高裁判事が雑誌に連載した法廷エッセーを集めたもの。裁判官や検事は普通、一般人との交流も制限されているのでなかなかナマの声を聞く機会もないが、裁判官にも迷いや悩みがあることがよく分かる。
・裁判の事実認定が難しいのは、真実は神のみぞではなく、目の前の被告人が一番よく知っているというところにある
・人を裁くというのはどういうことなのか、間違った判断を下したらどうすべきなのか。こういった難問をいくら考えても正解は得られないが、正解を得られない問題を考え抜くこと自体が重要である。一種の謙虚さが生まれるからだ。自分は人を裁く資格などないのかもしれないと自覚することで自分の判断が専横になることを防ぐことができる
・死刑の場合は主文を最後に読む。最初に読んで被告人が失神でもしてしまうと言い渡し手続きが未完になってしまうからだ。他にも判決文は「被告人を」で始まると有罪だが、「被告人は無罪。」というように「は」になると無罪。判決文では「被告人を無罪にする」という言い方はしない