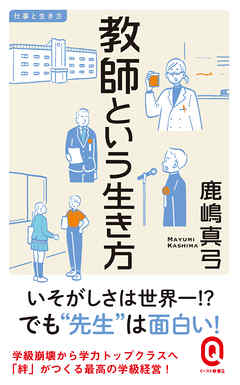あらすじ
学級崩壊から学力トップクラスへ
「絆」がつくる最高の学級運営とは?
日本の中学校教師は世界一多忙!? 生徒との関わり方、授業の工夫、同僚とのつき合い、保護者対応、様々な校内トラブルなど。教育現場が複雑・多様化するなかで、変わらない教師の資質、醍醐味とは何か。30年間、公立中学校の教員として勤務し、いじめや学級崩壊を起こさせない取り組みのひとつである「構成的グループ・エンカウンター」実践者として注目される著書が仕事への想いを語り尽くす。
感情タグBEST3
Posted by ブクログ
鹿嶋さんすごいなひたすらに思った。
出産してすぐに出社って。
それに育児もワンオペみたいな感じやったし。
私には無理だなーと思った。
教師になれても夫のことでやること増えたら死ぬと思う。
困った子は困っている子っていう言葉が何ヶ月たっても心に残っています。
現在学生で塾での講師をしており、いわゆる困った子を新人である私が担当することになりましたがこの言葉を知っていたおかげで焦ることもありませんでした。
仲良くなれたことで寝ることへの注意や、ゲーム感覚でタイマーを用意し10分寝る時間あげるから自分で減らしていく制度など導入したことで寝ないようになり他の講師から一目置かれました。ありがとうございました。
小学校の先生は中学とはまた違うと思うから、さらに教育系の本をたくさん読んでいきたいなと思う。
Posted by ブクログ
<目次>
第1章 学校という現場
第2章 生徒と向き合う
第3章 教師としてのスキル
第4章 変わる教室
<内容>
大筋は著者の体験談。ただ教師は、きちんとしたマニュアルがないので(あっちゃいけないのかもしれない)、自分の自慢話のように体験談が語られる。本書もそうだ。「若いころ、大変な現場でこんなことしてきた」という話が続く。しかし、第3章あたりから、体験的エンカウンターなどの話が入ってくる。著者も若さや直感だけでは「ダメだ」と感じたのだろう。その辺の話は非常に使える部分が多い。
最終的には、この著者の「教師」力に惹きこまれてしまった。自分の体験から言っても、この著者の言う話は妥当性が高い。
Posted by ブクログ
教師をしているが、今までHOWTO的な内容の本ばかり読んできた。これまでと趣向が異なる本だが、やはりHOWTOを求めてしまう自分に気づかされた。
①小テストでは10点満点中8点以上で合格。7点以下の人は教えてほしい人を選んでいい。再テストは何度でもチャレンジでき、その最高得点が記録として残る。これで焦るのは8点9点の子たち。それで満足しているとどんどん抜かされていくため、合格しても満点を取りに行く。そして学力向上につながる。
②生徒指導で「この場合どうしますか?」と正解を聞いてくる新人が多い。しかしケースバイケースがほとんど。学級経営に問題がある102の学級で、教師の学級経営が柔軟性を欠いているというケースが70以上あった。自分で考えて行動し解決していく力が必要。
③学級開きのエンカウンターでバースデーラインがある。言葉を使わないで誕生日順に並ぶ活動。目的は2つあり、最初の席の固定化を防ぐこと。もう一つは明るい子だけがお喋りして盛り上がることを防ぐこと。人間のコミュニケーションの70%はノンバーバルであるから問題なし。
④先生を知る○×クイズ。自分を語るためのきっかけ問題を10問設定。それについて班で話し合ってもらう。一問読み上げて一斉にジェスチャーで答えてもらう。これが目的。みんなが喜んでいるときに同じリアクションをすることは大切なソーシャルスキル。同じリアクションをすることで感情交流が図ることができ一体感が生まれる。