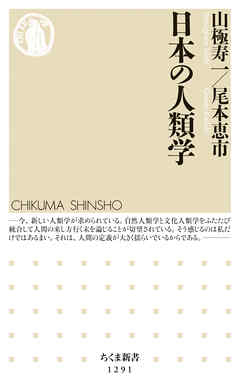あらすじ
遺伝子研究を導入して人類の進化をたどってきた東大の人類学と、独自の霊長類研究を展開してきた京大の霊長類学。日本の人類学は、彼らの切磋琢磨によって世界をリードしてきた。東大分子人類学の泰斗である尾本恵市と、京大霊長類学を代表する研究者である山極寿一が、人類学のこれまでの歩みと未来を語り尽くす。人類はどこからやってきたのか。ヒトはなぜユニークなのか。ユニークさゆえに生じる人間社会の問題とはなにか。新しい人類学を求める視点から鋭く論じる。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
人類学は京大と東大が両輪のごとく、それぞれの特徴を生かしつつ発展してきたとのことで、京大の山極(現総長)、東大の尾本両氏の対談が実に楽しい。尾本氏からすると人類学の学者が総長になるのは、いかにも京大らしく羨ましいとのこと。東大は分子人類学、遺伝子研究に、そして一方では京大は霊長類学に特色。霊長類学は本来は人類学と動物学の狭間の領域。今西錦司氏以来の伝統で、それが日本の人類学の権威になっていることに誇りを覚える。ルワンダの山奥で26年ぶりに出会った34歳のゴリラのタイタスが、山極氏を憶えていた!近づいてきてまじまじと見つめ、子供っぽい表情になったという!34歳は老年の域になるらしい。この実話は本当に感動的だった。ゴリラとチンパンジーの性格の違いで、チンパンジーは相手を理解しても助けてやらない。ゴリラは相手を助けようとするいかに平和な動物かということが印象的。いずれもヒト科の動物で、サルよりも人間に近いらしい。確かに「彼ら」を研究することが人類の理解に役立つことは間違いない!
Posted by ブクログ
大学の先生の話は
立派かもしれないけれども
ちっとも面白くない
そんな定説(?)をすっかり
覆してくださる
いやあ 人類学って
こんなに 面白いんだ
こんな 歴史を背負っていたんだ
こんな 人たちが居たんだ
「人類学」って
私たちの過去と
私たちの未来と
何より
私たちの現在と
ちゃんと つながっているんだ
そんな 気持ちを
持たせて もらいました
この お二人の碩学の対談を
企画された編集者さんに感謝です
Posted by ブクログ
人類学にも自然人類学と文化人類学等の種類に分けられているみたいなのですが、本書は自然人類学についての対談がメインでした。確かに人類学というものは馴染みが薄く、あまり意識したこともなかったのでしたが、 人間の本質を知るのに人類学という分野は非常に大事だと思いました。勢いが弱まりつつある人類学ですが、本書を読んだのを機にもっと知っていこうという思いが芽生えました。
Posted by ブクログ
2000万年前、類人猿は何十種類もいたが、サルは少なかった。サルは、サバンナに出て多産になると、森に戻ってきてから栄え、類人猿を追い詰めた。人類もサバンナに進出して多産になった。
デニソワ人は、64万年前にネアンデルタール人から分岐した。現在のメラネシア人やオーストラリア原住民、フィリピンのネグリト人のゲノムには、デニソワ人のDNAが数%含まれている。インドや東南アジアの人たちのDNAには、デニソワ人の痕跡は全くない。
単独生活やペア社会の動物は、雌雄の体格差がない。規模の大きな群れ生活をする動物では、オスがメスより大きくなる。複数のオスが共存する群れ社会では、厳格な優劣の順位ができる。母系社会では、ニホンザルのような階層性を持つが、父系社会の類人猿は、平等な関係を保とうとする。
チンパンジーは個体の利益を最大化するために連合して戦うが、人間の集団間の戦いでは、集団の利益を最大化するために個人が奉仕する。
夜行性の原猿類は、単独で縄張りを持った生活をする。昼行性になって群れが大きくなると、食料を求めて広い範囲を探さなければならないため、縄張りを維持できない。ヒトも狩猟採集生活までは縄張りを持っていなかったが、農耕や牧畜を始めて、広い範囲を動き回らずに済むようになると、縄張りを持てるようになった。
人間の子どもは、脳を成長させるために体脂肪率が高い。赤ちゃんは重いので、母親は抱き続けることができず、置いてしまう。母親が赤ちゃんに働きかけるために声をかける。それが大人の間に広がり、心を同一化させる機能を持って普及した。音楽の起源と考えられる。
アフリカの野生動物は、人の活動に適応していたため、気性が荒く、一種たりとも家畜化されていない。
religionの語源であるラテン語のreligioは、集まるという意味。
頭髪のアタマジラミと陰毛のケジラミは種が異なり、DNAの変異から120万年前に分かれた。人間が体毛を失ったのは、その頃と考えられる。コロモジラミは、7万年前にアタマジラミから進化しており、衣服の起源がその頃と推定される。
Posted by ブクログ
2014年より京大総長に就任した霊長類学(特にゴリラの研究で著名)を専門とする山極氏と、東大で長らく遺伝人類学の権威として活躍した尾本氏という2人の人類学者が、現代における人類学の意義について語った対談集。
期待の割には東大と京大を代表する人類学者のポジショントーク的な部分が非常に多く、スリリングな知的興奮が得られる場所が少ないという印象。
ただ、最終章の「これからの人類学」のパートだけは、純粋に面白く、ここに本書の面白さは凝集されているという印象。
特に、
・インターネットの大きな特徴の一つは「何度でもやり直しが利く」という点にあり、徐々にそうした世界観が普通のものだと子供たちは考えるようになってきている。一方、自然は「二度とやり直しが利かない」という特徴を持っており、世界い対する見方が180度違う。自然との触れ合いがもっと必要ではないのか
・かつてのコミュニティが存在していた社会と異なり、現代では個人が孤立した存在として置かれやすくなっている。そうした社会では、独裁国家によるコントロールが容易になってしまう点に危機感を感じる
というあたりの議論は非常に面白い。
後者はまさにハンナ・アレントが「全体主義の起源」において述べている内容と同一のコンテクストに置かれ得るものであり、政治学と人類学という全く異なった学問的バックグラウンドを持つ両者が同じような結論を持つに至ったという点に興味を持った。