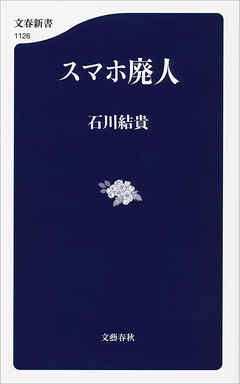あらすじ
スマホが手放せない! その先に待っているのは……
10代のスマホ普及率は9割を超え、シニアでも約半数が活用するスマートフォン。
圧倒的な便利さから「手放せない」人が多いのではないでしょうか。しかし、その裏には、「手放せない」のにはたくさんの理由があることが、綿密な取材から明らかになりました。
■スマホに管理される子育て
・母子手帳がアプリ化。子育ての相談はAIが24時間体制で応じてくれる
・アプリが授乳のタイミングをお知らせしてくれる。子育ての悩みは掲示板へ
・母親の目線を集めたい子供を描いた絵本『ママのスマホになりたい』がヒット
■がんじがらめの学生生活
・風呂の間も、寝るときも……すぐに返事をしなければならない「LINE」の恐怖
・グループから外されたらいじめがスタート
・「直接殴るのは怖いけど、LINEなら『死ね』って言えちゃう」手軽さ
■たこつぼ化するコミュニティ
・ソーシャルゲームの中だけでは「勇者」でいられるという孤独
・ゲームコミュニティーの居場所を維持するために課金を続ける人々
■いじらせ続ける、その秘訣
・動くモノを追いかけてしまう人間の心理
・トイレまでスマホを持っていく人の数とは?
廃人にならず、賢くスマホと付き合う方法とは何か? スマホの論点が分かる一冊!
目次
◆第1章 子育ての異変
◆第2章 スクールカーストとつながり地獄
◆第3章 すきま時間を埋めたくなる心理
◆第4章 エンドレスに飲み込まれる人々
◆第5章 「廃」への道
感情タグBEST3
このページにはネタバレを含むレビューが表示されています
Posted by ブクログ
「ママのスマホになりたい」
シンガポールの小学生が作文に書いたこの言葉…みなさんは、この言葉の意味が分かりますか?
彼のママは日々スマホに夢中。スマホに自分がなればママに見てもらえる、だからスマホになりたいと彼は作文に書いたのです。これは、シンガポールの子どものみならず、今の日本の子どもたちにも重なる部分があるのかもしれません。
スマホネグレクトという言葉を提唱している人がいるように、親自身もスマホとの付き合い方を考えなければいけない時にきているのだと考えさせられました。
Posted by ブクログ
〈全体の感想〉
スマホが人に与える影響について、あらゆる人を想定しているところがこの本の持ち味だ。赤ちゃんと母親の話から始まり、若い男の子や女の子、おじいちゃん、おばあちゃん、主婦、サラリーマン、就活生と非常に幅広い人を対象としている。
その一方でスマホ依存になってしまう原因についても科学的かつ論理的に述べられており、説得力がある。
〈面白かったところ〉
日本での普及率の高いチャット・通話サービスのLINEの開発時の話がはじめに書かれている。そこではLINEの有名な機能の一つである「既読」についての逸話が記されており、個人的に印象に残った。これは東日本大震災を受けて、すぐに返信ができない状態でも生存はしているということを伝えることができるいわば安否確認のための機能だった。
このように、コロナ禍によってリモートワークが見直されたように、災害や社会問題が生じ、人間が追い込まれて初めて、テクノロジーは進化するのだなと感じた。そのあとは、そのテクノロジーとうまく付き合っていく方法を模索していく必要があるだろう。
〈反論・疑問点〉
ソシャゲ廃人になってしまった青年の例が出されていたが、心療内科の先生はソシャゲ廃人についての理解が足りず、相手にしてもらえなかったという。どうすれば正しい治療を受けられるのか、また、誰に相談するのが正しいのかを知りたかった。