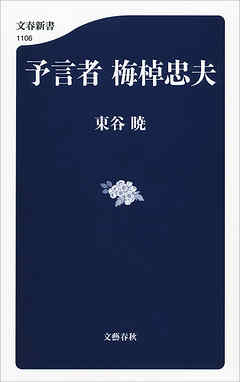あらすじ
戦後の論壇に颯爽と登場し、大胆な変化を次々と予言した梅棹忠夫。
その謦咳に接した著者が、彼の発言を多面的に読みなおし、その予言がいかにして実現していったのか振り返る。
<目次>
【プロローグ 実現した予言と失われた時代】
【第一章 「文明の生態史観」の衝撃】
異例ずくめの「出生作」/日本文化を機能論的に見直す/進歩的知識人からの批判・・・など
【第二章 モンゴルの生態学者】
京都町衆の生まれ/山登りで危うく放校に/京都学派と梅棹をつなぐ線・・・など
【第三章 奇説を語る少壮学者】
『モゴール族探検記』/激しい論争を呼んだ「妻無用論」・・・など
【第四章 豊かな日本という未来】
「ぼくはマルクスの徒です」/数十年後の日本文明を予測する・・・など
【第五章 情報社会論の先駆者】
情報の時代を生物学的に論じる/お布施の原理による経済学・・・など
【第六章 イスラーム圏の動乱を予告する】
「生態史観」は中東から/イスラーム原理主義の「伝染」/近代化とイスラーム・・・など
【第七章 万博と民博のオーガナイザー】
「万国博を考える会」の結成/グローバル時代論の先駆者・・・など
【第八章 文化行政の主導者へ】
文化を「開発」する/田園都市国家構想とその評価・・・など
【第九章 ポスト「戦後」への視線】
梅棹忠夫と司馬遼太郎/核武装の可能性による抑止/日本文明は終わりか・・・など
【第十章 行為と妄想】
見えないなりの知的生産/「あそび」と「学問」/文明史曲線の先にあるもの・・・など
【エピローグ 梅棹忠夫を「裏切る」ために】
思想家としての梅棹/あかるい虚無家/精神のキバ・・・など
感情タグBEST3
Posted by ブクログ
デザイン思考のルーツはKJ法であったということを知り、川喜田二郎氏に興味を持った。川喜田二郎氏といえばフィールドワークの先駆者的存在。氏と同じ時代にフィールドワークに魅了された方には、とにかくすごい方が多い。そのひとりが梅棹忠男氏。
『予言者 梅棹忠男』というこの本のタイトルは、けっして大げさではない。梅棹氏は、ぶっ飛んでる。戦後に日本の高度成長、情報化社会、グローバル化、ソ連崩壊、専業主婦の減少などを言いあてたそうだ。
どうして、これほどのことを言い当てることができたのか? このヒントがこの本にある。
この本は、梅棹忠男氏の伝記としてもおもしろいが、マーケティングや顧客心理を掴むということにおいて、とても参考になる。
梅棹氏は、『モンゴルの遊牧は、人間が家畜を連れて歩くのではのうて、家畜に人間がついて歩くのですわ』という放牧論を打ち立てた。放牧は、動物の群れに人がついて歩いたのが起源とのことだ。
自らも同じようにフィールドワークをして、このような結論が導けるだろうか?
戦後、焼野原と化した日本で多くの国民が希望を失うなか、
「もはや『心の平安』へのねがいは、『よりよいくらし』へのねがいの、競争相手ではなくなっている 、戦前・戦中の非合理性から解放された日本は高度成長を迎える」
といった未来を見通せるだろうか?
いずれも、主体と環境の関係性をあるがままに見定めることに集中されたからだそうだ。
マーケティングや顧客心理を掴むのも同じことだと思う。
主体と環境の関係性をあるがままに見定められているだろうか?
私は、『モンゴルの遊牧は、人間が家畜を連れて歩くのではのうて、家畜に人間がついて歩くのですわ』といったレベルには、まだまだほど遠い気がする。
Posted by ブクログ
ジャーナリストの著者が、大学在学中から国立民族博物館監修『季刊民族学』編集部に従事し、梅棹忠夫の知遇を得たという経歴で、梅棹忠夫の評伝を、書いたのがこの本である。
多くの弟子筋が書いたものは、文化人類学者や知的生産の技術者、あるいは探検家思考の作家によるものであり、フィーウドワークのすばらしさや、私的探求心の旺盛さを描き出すものが多い。
この本は、預言者 梅棹忠夫という視点で、まとめられたものである。
プロローグ ――実現した予言と失われた時代
第1章 「文明の生態史観」の衝撃
第2章 モンゴルの生態学者
第3章 奇説を語る少壮学者
第4章 豊かな日本という未来
第5章 情報社会論の先駆者
第6章 イスラーム圏の動乱を予告する
第7章 万博と民博のオーガナイザー
第8章 文化行政の主導者へ
第9章 ポスト「戦後」への視線
第10章 行為と妄想
エピローグ 梅棹忠夫を「裏切る」ために
あとがき
でした。
Posted by ブクログ
梅棹忠夫と交流のあったジャーナリストの著者が、梅棹の仕事について解説している本です。
梅棹の生涯と思想の全貌をえがいているわけではないので、評伝というにはすこしもの足りなく感じられますが、たんに著者自身の目を通して見られた梅棹にかんするエピソードが紹介されている本ではなく、文明論者としての梅棹の「予言」に着目し、現代の視点からその先駆性を評価するという試みがなされています。
わたくし自身は、歴史や社会についての歴史法則主義的な議論には意味があるとは思えず、梅棹の文明史的な立場からなされた「予言」についても、著者のように高い評価ができるかいささか疑問をいだいているのですが、梅棹のユニークな思索についてわかりやすく説明がなされているという点では、興味深く読むことができたように思います。また、国立民族学博物館の設立や、田園都市国家の構想など、梅棹の文化行政へのかかわりについても改めていろいろな事実を知ることができたのも有益でした。