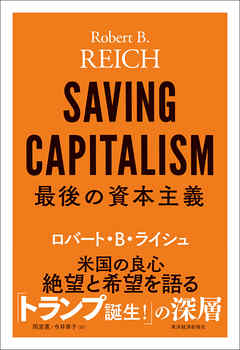あらすじ
ライシュの提案する、新しい資本主義の形。政府か市場か、の二者択一ではなく、市場メカニズムの根幹となる市場のルールを見直すことで、資本主義を壊すことなく、サステナブルな資本主義を構築できる。
市場メカニズムのルール自体が、勝者だけが勝ち続け、富が一方的に上方に移動するような仕組みになっている。ここにメスを入れずして、ゲーム終了時の所得再分配の率だけを議論しても意味がない。ルールそのものを、そして資本主義そのものを、一部の勝者のためだけに利するものではなく、大勢の人が生き残っていけるようなものにしていこう。
このままでは、人間の働くことの価値はますます小さくなり、稼ぐことのできるものは資本のみとなってしまう。技術が発達し、ロボットがどんなにすばらしい財・サービスを提供できても、それを買うことのできる層は消滅する。そしてロボットが代替するのは単純労働だけではないのだ。頭脳労働でさえも、ロボットにとって代わられる時代が来ている。
今こそ、新しいルールの下で資本主義を立て直さなければならない。そうでないと、資本主義はその土台部分から壊れてしまう。
感情タグBEST3
Posted by ブクログ
政治献金や天下りをエサに自分たちに有利なように市場のルールを変更する各業界の強欲さに呆れ返る
法律の成立を妨害し、法律を骨抜きにし、あるいは執行させないよう予算を削らせる
身勝手の極地だろう
歪んだ資本主義ではなく、資本主義を歪めたのだ
こんな市場を誰が信じるというのか
ビジネスマンとしても大統領としてもトランプがでてきたのは当然だと思えた
市場万能という神話は誰がルールを決め、ルールを執行しているかを見過ごさせるというのはもっともな指摘だ
富裕層は嫌がらせのためにこんなことをしているのではない。
ただただ自分のことしか考えていないだけなのだ
昔のように下位層で連帯し、歪められたルールを元に戻すことが必要だというのは賛成する
訳者あとがきで日本はむしろ超富裕層の程度が弱まっているとあったが、これは日本人が逸脱を許さないことと金に対してマイナスイメージがあるせいかもしれない。
Posted by ブクログ
ライシュ氏の本はすでに日本語版で何冊か出ていますが、2017年時点では本書が最新になります。原題はSaving Capitalism、つまり資本主義を救え、ということです。ライシュ氏の主張を一言で言えば、今の資本主義は大多数の人間のための仕組みではなく、少数の富める人間のためのシステムになってしまっているから、そのルールを修正することで資本主義を健全な形に戻そう、ということです。その意味では、訳者解説の中にもありましたが、本人は共産主義者でもアナーキストでもなく、資本主義礼賛者であって、今の「ゆがんだ」資本主義を「健全な」資本主義に戻す必要がある、というのが主眼になっています。
また彼の主張の中心にあるのが、特に米国を中心に起こっている「自由主義」(右)vs.「政府の介入」(左)という政府の介入度合いをベースにした対立はまやかしであって、資本主義のルールが「誰を利するようになっているか」という視点で対立軸を考えるべきという主張でしょう。「自由主義」(右)vs.「政府の介入」(左)という視点は、特に知識人の間では根強く、おそらくその根底には、ハイエクvs.ケインズの論争があります。それに対してライシュの視点は、むしろ資本家と労働者の対立にフォーカスをあてたマルクス色が強いと言えるのかもしれません。ただ厳密に言えば、ライシュ氏自身も本書で述べているように、現代の資本主義では「資本家になった経営者」と労働者の対立と言った方がよいとは思います(つまりストップオプションを大量に付与された経営者と従業員の対立)。
本書で説得力があると感じたのは、米国が過去にも同様の境地に陥った際に、民主主義が最後は機能して、多数のための資本主義、つまり資本主義が民主主義と折り合いをつけた事例をいくつか紹介していることです(19世紀のジャクソニアンの登場など)。それらを事例に挙げながら、ライシュ氏は米国の資本主義はまだ終わっていない、今は修正の時である、と力説されていてそこは希望が持てる点でした。その意味では邦題の「最後の資本主義」というのは少し誤ったニュアンスを読者に与える気がしました。このタイトルだけを見てしまうと、あたかもライシュ氏はアンチ資本主義者であって、資本主義の終焉は近いぞ!と歓喜の声を上げている論者かのような印象を与えてしまいます。ですから邦題は素直に「資本主義を救え」のようなものにした方が著者のメッセージが伝わるのではないでしょうか。
Posted by ブクログ
資本主義の根幹である自由主義は、所有権、独占、契約、破産、執行の5つで構成されているが、それらは富裕層、大手企業に利するようにルールが歪められており、中間層が没落しているというのが、本書の一貫した主張。
市場の失敗を抑制する手段として、公共事業の実施、財政政策、などの政府による介入があるが、政府自体も富裕層や大手企業など、自由市場から利益を享受しているグループと結託している。それ故に、政府も過度な自由主義を推進することになり、中間層・貧困層と富裕層との格差は拡大してしまう。
能力主義と自由主義が合わさることで、中間層・貧困層と富裕層の分断は一層進んでいる。多くの富を持つことが、価値であると考えられていることで、富を持たない人は、自身の能力不足・努力不足ゆえに、年収が低いのだと屈辱感を覚えてしまう。
マイケル・サンデルの「実力も運のうち」の主張と似ているが、本書は経済的な側面から過度な能力主義を批判している。
Posted by ブクログ
拮抗勢力の衰退、労働組合、中小企業
※健全で信頼されるカウンターパワーが必要
グローバル化と技術革新は遠心力を持つ、繁栄を分かち合うための抜本的手段が必要
ステークホルダー資本主義対株主資本主義、ステークホルダー資本主義を勝利させなければならない。
新たなルールの構築が必要
Posted by ブクログ
「暴走する資本主義」から10年。その後も富の格差は広がり続けている。本書のテーマは一貫して自由経済と政府の対立軸がなくなっていること。資本主義は自由経済によって健全な競争が保たれる前提だが、資本主義の勝者がゲームに勝つことよりルール(法律)を変えることを優先した場合、富は適切に配分されずに一部に集中し続けてしまう。
問題定義からその真因分析、そして目指すべき方針まで示された優良図書。
Posted by ブクログ
この世のどこかに「自由市場」という概念が存在しており、そこに政府が「介入する」のだ、という考え方ほど人々の判断力を鈍らせるものはない。政府なくして自由市場は存在しない。文明とはルールによって成るもの。
法律のどこを見ても、「株主が企業の唯一の所有者であり、したがって企業の唯一の目的は彼らの投資価値の最大化にある」とは書かれていない。
これは、1980年代に企業の株主利益を最大化したい乗っ取り屋が経営者達に対し、採算性の悪い資産を売却し、工場を閉鎖し、借金をもっと引き受けて社員を解雇するよう要求し始めた頃に出てきたもの。
1978年から2011年にかけて、新しい大企業が支配力を強めていくのに伴い、新規企業の参入割合は半減した。
モンサントの市場独占により、大豆畑1エーカー当たりの平均作付け費用は、1994年から2011年の間に325%増、とうもろこしの作付けコストは259%増となった。そして、種子の遺伝子的な多様性は劇的に減少した。
個人の収入を決定づけているのは、相続、コネの有無、先入観等その人の能力以外のもの。能力主義では全くない。
納税者が社会的意義のある職業をもっと強く支援する方法として、社会福祉や幼児保育、高齢者介護、看護、法律相談、教育などの職業を選択した卒業生についてはその学費ローンを免除するのがよい。
CEO報酬は1978年から2013年の間に937%増加し、同時期の労働者の賃金上昇はわずか10.2%。
最も報酬の高い役員上位5名に対する報酬額がその企業の法人所得に占める割合は、1993年には平均5%であったが、2013年には15%を上回る。さらにこれらの報酬のほとんどは法人所得税から控除されていた為、残る普通の人々が所得の割に高い税金を払い、税収の穴埋めをしてきた。
2001年から2013年にかけて、S&P500インデックス企業による自社株買い額は3.6兆ドル。CF総額の3分の1。
2003年から2012年にかけて、自社株買いが最も多かった上位10位のCEOは、報酬の70%をストックオプションもしくはストックアワードで受け取っていた。
高額のCEO報酬を出している上位150社のPERは、同業他社よりも10%低い。業績も平均15%低い。さらに、高額報酬のCEOの在任期間が長ければ長いほど業績が悪化している。
2013年銀行上位5行に出された640億ドルの補助金は、この5行の年間利益総額とほぼ同額。この補助金がなければ、267億ドルもの賞与の原資はおろか、利益の全てが失われていた。彼らが賞与をもらう事ができたのは、彼らの能力ではなく、米国の政財界において特権的な立場にいるから。
1950年代初頭、GEは全てのステークホルダーにとってバランスのとれた最善の利益を追求する事で有名であった。
企業経営は全ての人々の利益になるような経済を期待して国民から託される職務。
米国の富裕上位1%層に向かう国内総所得の割合は1960年代の10%から2013年には20%を超えるまでに上昇したが、ドイツのそれは40年間11%のまま。
ドイツのガバナンスは、取締役会の上に監査役会があり、監査役会の半数は社員の代表者で構成されている。この為、労働者の権利が受容的。
労働者の所得の低下は、彼らが経済力や政治力を持っていない事に起因する。
最低賃金が高いほど、従業員の離職率が低い。
低賃金で働く労働者の給与が引き上げられても、競争にさらされているので商品価格が上昇する事はない。
貧しい人は向上心がないから貧困から抜け出せないのではなく、機会とそれを獲得する政治力がないから。
最も裕福な米国人上位10人のうち、6人が遺産相続によるもの。
システムが不公平で独断に満ちており、勤勉が報いられないと人々が感じると、私たち全員が損をする結果になる。マイナスサムゲーム。
この30年間、企業を動かす誘因の全てが一般労働者の賃金を引き下げ、取締役の報酬を引き上げる結果につながった。
カリフォルニアでは、CEOの報酬がその企業の平均労働者の賃金の100倍であれば、法人税率が8.8%から8%に下がり、25倍なら7%に下がる。200倍であれば9.5%、400倍であれば13%に引き上げられる。
平均的労働者の賃金に対するCEO報酬の比率開示義務はドッドフランク法。
年間生産性上昇率に合わせて労働者の賃金を引き上げる経営者には低い税率を課し、引き上げない経営者には高い税率を課す方法もある。国全体の経済的利益と労働者の収入を連動させる。
カリフォルニアでは、低賃金の仕事を多く下請けに出すほど高い税率を課し、企業が雇用者を個人請負業者として不正に分類する事や、かつて社内で働いていた低賃金労働者を他者に転属させる事を禁じている。
従業員持株制度や利益分配制度、または従業員が会社を所有する形式に協同組合を組織する事に優遇税制を適用して、従業員により直接的なオーナーシップを与える方法もある。
企業とは契約と知的財産の集合に過ぎず、株主に所有されているわけではない。
企業の取締役には自社の株式価値を最大化する信任義務があるという考え方は法的根拠のないフィクションにすぎない。株主は企業の役員を選ぶが、役員には株主利益を最優先しなければならないという法的義務はない。
2014年スーパーチェーンのマーケットバスケットの取締役会は、CEOのアーサーT.デモーラスを解任した。それは彼がステークホルダー全員が利益を享受できる合同会社とみなしていた為だが、これに対し社員と顧客がデモやボイコットを起こし、最終的には取締役会は同社をアーサーに売却した。
パタゴニアは、ベネフィットコーポレーションという形態で組織されている。株主と共に社員や地域社会、環境の利害を考慮する事を定款に定めている。
60年前の米国では当たり前だったステークホルダー資本主義
1980年代に定着した株主資本主義は、労働者の賃金を下げ、地域社会が荒廃した。
1990年から2008年の間に、高校を卒業していない米国白人女性の平均寿命は5歳短くなった。
ベーシックインカムがあれば、人々はあらゆる種類の芸術や趣味の追求に意義を見出せ、社会は芸術活動やボランティア活動による成果を享受できる。大多数の人が肉体的、精神的な活動よりも怠惰を貪る事を選ぶとは考えにくい。むしろ、多くの仕事が「天職」、すなわち働くことが単なる金稼ぎの手段ではなく、個人としての深い関与であるとみなされた時代に回帰するだろう。→hanahanaそのもの!
次は民主主義に対する挑戦。将来を決定づける議論は政府の「規模」に関する議論ではなく、政府が誰の為にあるのかという議論。
人々が幅広く繁栄を分かち合うように設計された市場か、ほぼ全ての利益が頂点にいる限られた人々に集中するように設計された市場かという選択をする事。
事後に再分配を行わなくとも、公平な分配がなされていると大多数の人々が受け止められるような経済を生み出す市場のルールを設計する事。
Posted by ブクログ
25年ほど前に著者の本「ワークオブネイション」を大学時代に読み21世紀はグローバル化が進み、国家の最大の役割は人材をつくることになる、そしてもっとも付加価値の高い人材はシンボリックアナリストと呼ばれるものをつくるのではなく概念的思考をする人になる、という内容に衝撃をうけて自分のその後の職業観、就職におおきく影響をされたとおもう。
あれから26年、著者の予言どおり、世界はグローバル化し、そしてシンボリック穴リストの職業としてインターネット関連、グローバルな金融、バイオなどまさに予言どおりとなっている。
しかしながらそれによって、あらたにシンボリックアナリストがあまりに力をもちすぎて、市場のルールを自らの都合の良いように策定していると主張。その結果、経済格差が進み中産階級が崩壊しつつあると。
自由主義か政府による管理かという二元論にいみはなく、自由主義とはいっても、だれかがだれかのためにルールを策定する、それは誰がだれのためにつくってるのか?ということをみるべきだと主張。たとえば金融業界が強くなれば金融に関する規制緩和が進むし、インターネット業界が強くなればねっとん関する規制緩和が進む。
いくら金融系の社長の能力がたかくても一般社員の1000倍の給料をとる理由はないと。
著者はあまりの巨大格差は資本主義の自壊をうむ、だからそれをふせがないといけない。とくにルールの策定に誰がどのようなロビー活動で影響をおよぼしてるかを情報開示して、チェックしなければと。最終的にはベーシックインカムのような所得を配る政策を実施。とくにAIによって労働力がおきかわるリスクがあるのでBIをすることで、人はついに労働から解放され、ボランティアや芸術に取り組む時代がくると主張。
グローバル化の実相を世界でもっとも早く予見した人が、そのあとの格差を予見できなかった悔恨の書ともいえるが、こういう知的巨人がクリントン政権で労働長官をつとめていたという人材の分厚さにアメリカ政治のすごさを感じる。