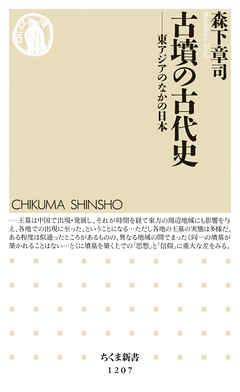あらすじ
紀元前一~四世紀の中国・朝鮮・日本。この時代の東アジアでは、中国の影響を受け、朝鮮・倭など周辺地域において、大小の「渦巻」が発生するごとく社会が階層化し、やがて「王」と呼ばれる支配者が登場する。その状況を最も雄弁に語る考古資料が「墳墓」だ。領域の明確な境界も形成されていなかった時代、ひととものが往来し、漢文化が大量に流入する一方で、東アジア諸地域の「ちがい」はむしろ拡大の方向へと向かった。明白に存在するそのちがいとは? それは何から生まれたのか? 最新考古学の成果に基づき、古代アジアのグローバリゼーションとローカリゼーションに迫る。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
森下章司「古墳の日本史」(ちくま新書)
倭の墳墓は弥生時代後期から古墳時代にかけて大きくなるが、そこには連続的な面と、前方後円墳の成立とその急激な拡散、さらに畿内が中心性を帯びるという非連続的な面がある。著者はその非連続性が東アジア全体の動向とからんでいると考える。中国・漢の時代に発展した墳墓の文化が朝鮮半島や倭に伝播しそれぞれに発展していく。後漢がほろび三国・南北朝と時代が進むにしたがって中国では墳墓は小さくなるが、逆に朝鮮半島や倭の墳墓は大きくなる。特に倭は仁徳陵古墳をはじめ極端に大きなものが作られる。これは漢の時代には皇帝、貴族、外藩の王といった序列意識があり、分をわきまえた墳墓を作っていたが、中国の統制が効かなくなることで周辺国、特に中国との直接交渉が薄い倭では制約なく大きなものが作られるようになったためだろう。一方で倭の中でみれば大王クラスの巨大な前方後円墳と、豪族や官人の小型の墳墓の大きさが隔絶しており、国内の序列がシンボライズされている。
中国の墳墓は地下に玄室があり、埋葬を終えた後で墳丘を作り、さらにその上に儀式用の建物を建てる。朝鮮半島北部の高句麗もそれに近い。半島南部の百済や新羅、倭ではまず墳丘を立ててその中に玄室を作る。中国や朝鮮半島では墳墓での祖先崇拝の儀礼が継続して行われたが、倭では葬儀が終わればほぼ放置された。かなり宗教感覚が違いそうだ。
副葬品も中国や朝鮮半島では死後の生活用の食器類などが多く見られるが、倭の場合は鏡が多い。鏡の呪術性が倭の人の心を捉えたのだろう。ただし大王とそれ以外を比べた時、大王クラス固有の副葬品はない。勢力が大きいほど鏡の数量が増える程度であった。
墳墓の形態も中国や朝鮮半島では円墳や方墳が多く、前方後円墳は日本で独自に発展。ただし朝鮮半島西南部の栄山江流域では5-6世紀に倭式の前方後円墳がみられ、倭人の移住などの説もあるとのこと。
Posted by ブクログ
古墳をはじめとする「墳墓」に着目して、紀元前1世紀~4世紀の中国、朝鮮、日本という古代東アジアのダイナミックな歴史像を描く。当時の東アジアでは、漢王朝など中国の動きを軸に、大小さまざまな「渦巻」が発生するような大きな社会変動のときを迎えており、それぞれの地域で大きな墳墓を造営するといった「つながり」がみられるとともに、社会の仕組みや信仰といった人の営みの根本的なところでの身体感覚な「ちがい」もみられるということを、考古資料とそれに基づく考古学の研究成果をもとに明らかにしている。
大きな意味で同じ文化圏に属する中国、朝鮮半島、日本だが、古代から「つながり」とともにさまざまな「ちがい」があったということが、古墳などの墳墓を題材として取り上げられており、とても興味深い内容だった。特に、中国や朝鮮半島の墳墓とは異なり、倭の古墳には、墳丘に対する独特の「こだわり」がある一方継続性が弱いことや、副葬品から日常生活と切り離れた存在として機能していたことが窺われることなどの特徴があるということが面白かった。
Posted by ブクログ
古代の人々が古墳に込めた意味、彼らの生き方や国にとって古墳の存在にフォーカスしながら、中国や朝鮮半島の東アジアの歴史や墳墓との共通項や違いを比較しながら話が進み、とてもわかりやすくて面白かった。地方の古墳の埋葬品を調べることで輸入の独自ルートが築かれている事がわかったり、副葬品も装飾品から銅鏡や武具にうつっていくという過程も面白い。古墳を知るために、最初に手に取るべきガイドブックという感じ。
Posted by ブクログ
紀元前一世紀から紀元四世紀の期間を中心とした古墳時代において、東アジア(日本、中国、朝鮮半島)で人や文化の交流状況が解説されている。日本の古墳だけではなく、中国や朝鮮半島の墳墓の形状や埋葬方法などの違いから、共通性や日本独自のものを説明する。正直、難しい本だった。古代史は歴史的資料が少ないため、仮説(想像)で補う部分が多く、読者にとって古代を妄想する幅が広くなる。そこが古代史にロマンを感じる部分であり、古墳は古代の思いに耽る良い材料となる。研究者にとっては迷惑な読み方だろうが、一般人の楽しみかたの一つととらえてほしい。類書にも挑戦したい。
Posted by ブクログ
古墳時代がいつから始まったのかの学説の数々。それが邪馬台国の存在場所と大きな影響があるなどの説明が説得力に富んでいた。前方後円墳の出現は最近では3世紀中ごろから後半との説が有力で早まってきたという。最近の研究により大きく通説が変動しつつあるという背景が非常に良く分った。東アジアの漢・三国・晋時代、また3韓などの陵墓との比較など、日本の古代史を探る考古学が国際的な学問であることを改めて再認識した。日本において【平城天皇陵墓】が円墳だと思われていたのが、実は平城京を造営する際に前方部分が削られてしまったことが分った!楽しい話だが、それだけ300年前の天皇がこの時期に粗末に扱われていたとは興味深いところ。そして日本から逆に中韓に影響を与えた可能性があるとは全く考えもつかなかった。著者が繰り返し書いているように真実を探っていく幸せを痛感している方であることが良く分った。発想段階のレベルでこれから実証していきたいと謙虚な言葉だが、いつの日か真実が明らかになっていくことを期待したい。