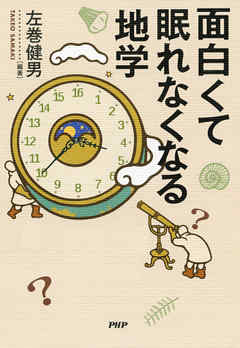あらすじ
思わず徹夜してしまう、ダイナミックな地学のはなし。地学は、とても幅広い内容をもつ自然科学です。足下の地球の内部、地球の表面、地表を覆う大気、はるかな宇宙。そこには地震、台風などの自然災害、毎日の天気など身近な内容のほか、科学者たちの大発見にともなう栄光と挫折の歴史も含まれています。わたしたちが暮らす地球のひみつに迫る、感動的でふしぎな地学の世界へようこそ。○本書の目次より 世界はもともと一つだった?/ヒマラヤ山脈はまだ高くなる?/化石になるのも楽じゃない/スノーボールアース仮説の衝撃/ジェット気流が運んだ秘密兵器/ガリレオが望遠鏡で見た宇宙/地球と金星の運命を分けたもの/地球に住めなくなったら、どこに移住する?……
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
編者は左巻健男となっているが、実際に執筆しているのは高校の先生の小林則彦さん。ブルーバックスのような専門性のない一般向けの分かりやすい本だ。知ってたことも結構あったけど、新しい知見もあって面白かった。例えばー
・北磁極の移動を示す堆積残留磁気を年代ごとにだどっていくと、アメリカ大陸とヨーロッパ大陸の動き方が違っているが、二つの大陸が大昔一つだったと想定すると、動きの軌跡が一致する。
・現在、N極が指す北と実際の北には7度のずれがある。測量でコンパスを使うときは、そのずれを考慮に入れなければならない。伊能忠敬の日本地図作成のときは、そんなことは知らずにコンパスを使っていた。実は、地球の地磁気は移動していて、伊能忠敬の時はちょうどずれがなかった時代であったのだ。何という幸運!
・地球内部の磁石は短くて、深いところに極がある。だから、コンパスの針はどちらかが下の方に傾くので、傾かない極の方を重くしてある。
・地球全球が凍りつくスノーボールアースは過去3回あった。生物の大量絶滅が起こったが、辛うじて生き残った生物が新たな遺伝情報のもとに増殖するきっかけとなった。
・夕方の太陽光線は地球に斜めに降り注ぐので、通過する空気層が長くなり、赤色だけが最後まで通り抜けてくる。西の遠くの空が晴れていれば、光がちゃんと通り抜けてくるので夕焼になる。
・地表で暖められた空気は上昇するので上空は温かくなると一見思えるが実はそうではない。上昇した空気は膨張するが、暖められて膨張したのではなく空気の薄さのために膨張するので、逆に冷たくなってしまう(断熱膨張)。
・コペルニクスの地動説が正しかったと証明されたのは、200年後に年周光行差と年周視差が発見されたからである。
・流れ星が光るのは、宇宙から飛び込んできた塵に気体が蹴散らされたり、圧縮されて光るからである。
Posted by ブクログ
非常に読んで楽しめる本だ.かなり高度な内容に触れている部分も多いが,分かりやすく説明する見本のような記述は非常に参考になる.難しいことを分かりやすく説明するのは非常に大変なことだが,それをさらりと実践しているところが素晴らしい.
Posted by ブクログ
「面白くて眠れなくなる」シリーズ。自然科学分野への入門書というか、「入り口」になる本のシリーズ、地学編。
とか書きつつ、他の分野の本を読んでいないんですが(^_^;
本書にも書かれているけれど、地学は本来、身近で日常に触れることも多い分野のはずなのだけれど、高校では授業を行っているところが少なくて非常に悲しい。
そんな地学について、ちょっとだけ本格的な話に足を踏み入れてみました、踏み入れてみませんか?な内容。
もっとも、自分はどっぷり地学人間なので、まったく縁のない方からみたら、私の知らない世界…!かも…
Posted by ブクログ
知ってしまうと絶対に人にしゃべりたくなる面白い地学話満載。「事実がそんなに面白いわけないだろう!」と絶対に疑う話ばかり。「理科」の話ってのは、たくさんの「逸話」があるけれど、「これでもか」と、量でも質でも類書を上回る圧倒的パワー。
風船爆弾放流地跡に碑文があるなんて話、知らなかったなあ。大変楽しくお勉強させていただきました。
Posted by ブクログ
高校で地学を選択していないので、地質学のイメージしかなく、地学の範疇が理解できてなかったが、地球、気象、宇宙と対象領域の幅広さを理解することができた。
coten radioで天動説と地動説の話を聞いたばかりだったので、知識が繋がり学びとなった。