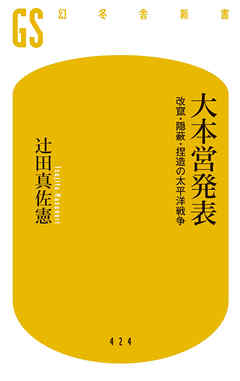あらすじ
信用できない情報の代名詞とされる「大本営発表」。その由来は、日本軍の最高司令部「大本営」にある。その公式発表によれば、日本軍は、太平洋戦争で連合軍の戦艦を四十三隻、空母を八十四隻沈めた。だが実際は、戦艦四隻、空母十一隻にすぎなかった。誤魔化しは、数字だけに留まらない。守備隊の撤退は、「転進」と言い換えられ、全滅は、「玉砕」と美化された。戦局の悪化とともに軍官僚の作文と化した大本営発表は、組織間の不和と政治と報道の一体化にその破綻の原因があった。今なお続く日本の病理。悲劇の歴史を繙く。
...続きを読む感情タグBEST3
このページにはネタバレを含むレビューが表示されています
Posted by ブクログ
いかに大本営発表が嘘だったのか。第3者の視点での検証がないからエスカレートしてしまう。日本海軍と連合国海軍の艦艇喪失数にも歴然とした差が。日本海軍は実際の数よりマイナス20隻、連合国軍はプラス112隻となっている。もう本当にめちゃくちゃである。陸軍と海軍のメンツのぶつかり合いで正しい戦果報告はできないし、嘘の大本営発表により作戦にまで影響がでてしまう。本書のおわにり「政治とメディアの一体化が日本に史上空前の災厄をもたらした現象」と書かれているがまったくその通りである。
Posted by ブクログ
この本は以下のようにして筆を擱いている。
「大本営発表はメディア史の反面教師として、今なお色あせていないのである。」
これは報道をするマスコミ側の問題だけでは無く、報道を受ける我々一般市民が注意しておかなければいけない内容である。必読。
「大本営発表」という響きには「大上段からの大嘘」というイメージが付いて回るのだが、そのイメージは誤っていないことが分かる。ただし当初(日中戦争時、及び太平洋戦争開戦後しばらく)はまだ正確な報道であったとのこと。
そして、なぜ「大本営発表」が捏造だらけの発表になったのか、なのだが、現在の日本国政府と同じく「情報の軽視」が大きいようだ。相手の損害状況は攻撃隊からの報告に依存するわけだが、その報告の正確度よりも「命を賭して闘ってきた兵士の報告は絶対」との感情論が先行していたため、必然的に成果が大きくなった。そして損害は小さく表現される。
また、作戦部と情報部との間の不仲など縦割りの影響を受けるため、大本営発表の内容は妥協的な内容に落ち着くことになることが多かった。
さらには、ラジオというメディアを利用するために、発表に修飾語がたくさん付くようになったことも、状況悪化を誤魔化す要因となった。
「大本営発表」が官僚の作文になっていき、撤退が「転進」、全滅が「玉砕」と美化されていく。本土空襲では、焼け野原になっても「相当の被害」が最大限の表現であり、「被害に関しては目下尚調査中」としたまま結果が公表されないことも増えた。
終戦直前、すでにポツダム宣言の受諾が決定された後の1945年8月12日、陸軍の戦争継続派がニセの大本営発表で徹底抗戦を訴えようとした。のだが、記者たちが「いつもの大本営発表と違う」ことに気付いて、政府筋に確認した。捏造であると判明したため、この大本営発表は全国には発表されずに済んだ。
この最後だけは報道機関のチェックが働いたわけだが、通常は発表がそのまま報道される、つまり軍部と報道とが一体となっていたため、軍部は思い通りに報道させることが出来ていた。
翻って現代の政府発表と報道機関との関係はどうか。情報が制限されていた福島第一原発に関する報道、放送法の公正中立規定を努力義務から法規として解釈し停波がありうると発言した総務大臣、安倍政権の言うことに反することは出来ないという現NHK会長(ただし来年1月には退任決定)。
政府と報道が癒着して、健全な報道が出来るわけがない。報道そのままを鵜呑みにするのでは無く、その背景を考えつつ報道を聞く必要がある、そのことに改めて気付かされる本であった。
Posted by ブクログ
○大本営発表を4期に分けて意味付けをして、それぞれの期においてどういう役割を果たしたのかが分かる。
○報道内容は独立した担当者の判断によるものではなく、現場(現地で戦闘をしている部隊等)、統帥系の高級将校、陸海軍の対立等によって事実上は制限を受けていた。
○広義の大本営発表、狭義の大本営発表、軍部の下請けと化したマスコミの報道と捉えて、一部の軍人が恣意的に大本営発表という構造を作り出したのではなく、軍部とマスコミの一体化があったこと。
Posted by ブクログ
最終章の〆が、何故か電力会社批判、安倍政権批判なので星一つ減とする。
政治と報道の癒着という意味では、マスコミ関係者を多数候補者として取り込んでいる民主党(民進党)の方がよほど危険だろと。2009年総選挙前後の報道の異様さについて読者が何も覚えていないとでも思っているのだろうか?あのような『一切の批判無しの報道』の恐ろしさが、『大本営発表』の危険さだと、この本を読んで思い至ったのだが。
あと、直近の事例だと、共産党の発表を垂れ流す豊洲新市場関連報道だね。
本題に戻ると、そもそも、『大本営発表』の起こりが、日中戦争時に過熱した報道の『暴走』に対処するために始まったとは知らなかった。そういえば、『百人切り競争報道』(捏造)とかあったしね<毎日
そして、現地の不確実な戦果がそのまま中央に報告され、報告をまとめただけの結果が、膨大な『架空の戦果』に繋がったとは、いくら情報を軽視していたと言われる日本軍にしても酷すぎる…よくもそんな体制で4年以上も対米戦できたもんだよなと。
むしろ、損害を大本営が意図的に削って発表していた方がまだましという酷さ。
しかし、大本営発表で軍部と癒着しきっていた報道陣が、癒着しきっていたが故に偽の大本営発表を見破ったという終戦直前のエピソードについては、もう顔が引きつったままどんな表情をしたら良いのかわからなくなる。(闇が闇を破った)