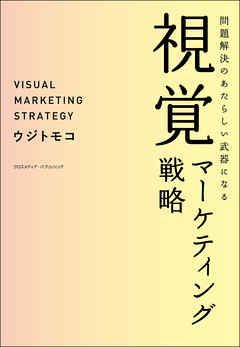あらすじ
「売り上げが上がらない」「商品力がない」「差別化できない」など、多くの企業が簡単には解決できない悩みを抱え、苦しんでいます。
しかし、伸びている企業はこういった問題をロジカルに考えるだけではなく、ビジュアルやデザインといった視覚に訴える戦略を経営に取り込み、飛躍しています。
なぜ、視覚なのか?
ヒトが得る情報量の90.9%は視覚によるものという研究結果があります。
感情は視覚から得る情報によって錯覚を引き起こし、錯覚は期待を抱かせます。
そして感情を帯びた期待によって、人は行動を起こすのです。
つまり、視覚を制するものは、ビジネスを制すると言えるのです。この本では、問題解決の新しい視点「視覚マーケティング」について述べています。
【もくじ】
第1部 デザインの力で問題を解決する
1 視覚を制するものはビジネスを制する
2 商品力・サービス力をあげる
3 ブランドを育てる
4 売り上げをあげる
5 顧客満足度をあげる
6 魅力的に見せる
7 人を動かす
第2部 プロっぽく見せるデザイン
8 デザインをはじめる前に
9 つい開きたくなる表紙デザイン
10 伝わりやすい資料のレイアウト
11 カラーの配色センスを身につける
12 写真をキレイに見せるテクニック
13 デザインセンスを磨く生活習慣
巻末付録 デザインのこれだけはやってはいけない
感情タグBEST3
Posted by ブクログ
ビジュアルやデザインの考え方を取り入れたマーケティング手法
というのは、今の時代に 必要なんですね。それで、読んでみた。
『デザインとは問題解決のことである』と定義する。
「売上をもっと伸ばしたい」
「ライバル企業との競争に勝ちたい」
「顧客のリピート率を上げたい」
「社員のやる気を引き出したい」
という問題を デザインで解決するというのだ。
『デザイナーの頭の中を覗く―ビジネスで使える「デザイン思考」』
の著者 榎本雄二は
デザイン思考の本質とは、『誰かをハッピーにすることである』と言う。
ウジトモコの唱える デザインで問題解決という定義から言えば
榎本雄二の方が 一歩進んだ考え方をしている。
デザインがなぜできるのか ということに対して ウジトモコは
「クリエイティブジャンプ」や「ブレイクスルー」があると言う。
クリエイティブジャンプ という言葉が
ある意味では デザインの力なのだろう。
論理的な思考では なかなか ジャンプができない。
論理的な思考力で 問題解決しようとしても 神がおりてこない。
デザインは 解決を降臨させるチカラがあるのかもしれない。
見ると言う行為は 「錯覚」と「期待」があると言う。
デザインをつくることで
「いい仕事ができそう」と錯覚させることができる。
感覚を通してはいってくる情報量は、目から1000万ビット(90.9%)。
皮膚からは100万ビット。耳からは10万ビット。
臭覚器官からは10万ビット。味蕾からは1000ビット。
「ユーザーイリュージョン」
味蕾からそんなに少ないのか と驚くが、やはり 視覚判断が基本なのだろう。
「見せる」ことを最適化して、「すごい」「ステキ」「おもしろい」
という感情と結びつけさせて、人を行動に駆り立てる。
LINE,Facebookは、ビジュアルコミュニケーションであるが故に 流行っている。
多くの言葉のメッセージでなく 画像を共有することで つながろうとする。
人間の成長や心の変化が 画像にも表現できる。結婚式のシーンはそれをあらわす。
人は モノを見ているのではなく そこにある「世界観」を受けとっている。
そこには 発信者の 印象から ライフスタイルが 見える。
「高そうVS安っぽい」「好きVS嫌い」という
2つのベクトルの価値観の中での判断。
なぜ 生ジュースより スムージーがはやるのかが
トレンド的な傾向を示している。
たしかに デザインは 言葉で論理的な判断よりも、感覚的な判断が可能だ。
「筋道を立てて思考することは、将来性がない」とウジトモコは言い切る。
「直感」「空想」は、混沌と混乱から光を生み出せる。
未来に好まれるデザインが どう現れて来るのか?
ブランド価値が高いものほど 情報が整理されている。
情報が混乱しているものほど 沢山詰め込もうとする。
トマトジュースが リコピン○○グラムと機能説明するが、
必要でない情報のいれすぎである。
グラフィックエレメンツ分析をして 主観的にしか見れなくなったことから
冷静さや客観性をとりもどして 対象を見る。
あぁ。実に明快な 指摘。いままで やはり 情報を整理しきれていなかった
企画を 反省させる 提言である。
デザインは 問題解決する という定義は 問題のあり方を提示する
という意味で 重要なのかもしれない。
デザインで クリエイティブジャンプする 必要があるんでしょうね。
Posted by ブクログ
デザインにはほとんど興味関心はなかったが、「問題解決の新しい武器になる」というタイトルに惹かれて読んでみた。
ヒトが得る情報の90%は視覚情報だとか。となると、タイトルもうなずける。
☆ブランディング7つの基本
・ブランドの本質や根原を知る
・企画、コンセプト
・独自性
・クオリティとトレンドを最適化
・ガイドラインの設定
・事業拡大のイメージをあらかじめ持つ
・続けられる仕組み
今迄とは違う観点から考えるきっかけになるかもしれない。
Posted by ブクログ
著者が過去に手がけた事例も交えつつ、デザインをビジネスに活かす方法が幅広く紹介されていた。
資料作りの際にオススメなフォントなど、具体的な事例を挙げている章もあったが基本的には広く浅く解説している一冊。個人的には少し物足りなさを感じた。
Posted by ブクログ
視覚から見る情報の大切さと、どうやって視覚情報を
活用してビジネスに生かすか、という本。
視覚が人の心理に与える影響の大きさについてや
「コンセプト、ターゲット、人の心理を考えたうえで
デザインや設計を考えよう」という内容に
結構ページが割かれているが、
この本を手に取る読者の多くはすでに前提の話では?
いまさら細かく説明する必要はない気がする。
それよりもこの本を手にとった人が知りたいのは、
「それではどうしたらいいの?」という話だろう。
そういう意味で、デザインガイドライン、
ブランドサイクル、レスポンスデザインの話は結構興味深い。
あとは、ビジネスのための資料資料作りでの、
見せ方や色、書体選びなども
簡単かつ実践的なので良いと思う。