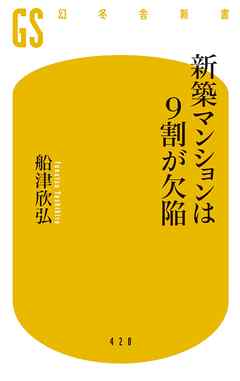あらすじ
社会を震撼させている欠陥マンション問題。国内有数の大手デベロッパーやゼネコンが手がけているにもかかわらず、なぜ欠陥はなくならないのか。ずさんすぎる現場の実態に業を煮やした建築検査のプロである著者が、事件の裏に潜む不動産業界の病理をついに告発。昨今の事例を元に、複雑に絡み合った欠陥の要因を明らかにしていく。また、資産価値が高く品質の良いマンションを購入する心得や、欠陥が見つかった場合の対処法など、住まいの安全を死守する方法を紹介。欠陥マンションという負債を人生に持ち込まないための警告と救済の一冊。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
下請多重構造、複雑な分業体制、青田売りによる工期厳守、日給月給制に代表される過酷な労働環境、それに伴う人材不足といった問題から、マンション建築には構造的に欠陥が付き物だという。2000年代の姉歯事件や2010年代のマンション傾斜問題等を例にとり、検査会社の代表取締役である著者が解説。
2022年問題―1991年に改正された生産緑地法により多くの農地が生産緑地(営農以外の用途が制限される代わりに、固定資産税が農地並みに安い)に指定された。30年の期限を迎える2022年、多数の生産緑地が(自治体による買取を受けられずに)宅地として売りに出され、地価が下落すると読まれている。地価が下がってから買うのも手かなと思ったが、ちょっと調べた限り我が家周辺には生産緑地がない模様(東京と、一部の大都市圏のみ)。マンションにしても、管理や高齢化、建て替えの意思決定の難しさからゴーストタウン(空き家)化の懸念があり、著者は分譲マンション購入を経験しているが、新築に限らずマンションの持つリスクを考えた結果、今は家族と賃貸マンション暮らしだという。それでも欲しい場合は、中古マンションで管理状況を確認し、大規模修繕の計画と実績・滞納状況を調べ(国土交通省のガイドラインによれば小規模マンションの修繕積立金は専有部分の床面積あたり218円/m2・月であり、これ未満であれば修繕時に別途徴収の可能性あり)、仲介業者経由で管理組合の総会資料や議事録を確認して(活発に議論している形跡があれば良い―管理費や修繕積立金の見直し、管理会社の変更検討を行っている等)、失敗しない購入を目指すことは可能だが、ハードルは高い。中古マンションを勧めるのは、1回目の大規模修繕を実施した中古マンションであれば、当初の施工不良も是正・補修されている可能性が高いという目論見。建て替えを考えた場合、実際の建ぺい率や容積率が法定のそれよりも小さければ(建て替え時に戸数を増やしてその利益を建て替え費用に充てることが可能なので)有利ではあるが、そもそもデベロッパーは利益最大化の為目一杯大きく建てるし、既存不適格により戸数を減らさざるを得ない場合もあるし、人口減少時代に戸数を増やしても埋まらないリスクもあるので、現実的ではないとも言える。
後半では構造欠陥といった品質の面で失敗しないために、品質管理に対する姿勢等をデベロッパーとゼネコン、それぞれ実名を挙げて調査結果を公表しているが、東京都心の話なので地方都市では参考にならず、それぞれ読者の方で調べる必要がある。
ポイント
・契約書に瑕疵担保責任の明記があるか(中古マンションでは民法の瑕疵担保責任期間1年(売主が個人の場合はもっと短い場合もあるので注意)、買取再販業者等の法人では2年)
・最近の建築裁判では瑕疵担保責任の10年ではなく不法行為の20年の時効を適用する事例が多くある
・危険負担の項目に「天災等により建物が滅失した場合は契約解除として手付金は全額返却」の文言がなければ追加してもらう。ダメなら見送る。これがないと、滅失した際に引き渡しされていないのに代金を払う必要がある、という最悪の事態もあり得る。
・重要事項説明は事前に入手し隅々まで読み込む。承諾事項と契約解除の項目に注意。
・検査頻度をデベロッパーに確認(全工程で検査していれば◎)。問い合わせはメールで残す。三菱地所レジデンスはチェックアイズレポートと呼ばれる施工状況や検査の報告書を購入者に配布しており、信頼できる。
・管理組合は面倒くさがらず、理事に立候補する覚悟をもつ。
戸建て検討中に地場の工務店を探す際に品質重視で考えていたが、マンションとなると(欠陥はなくて当たり前というか、大手だから心配ないだろうという固定観念があり)品質を疑うという頭がなかった。本書では欠陥があって当たり前と言っており(タイトルは若干煽り気味ではあるが)大手でも安心してはいられないということを知るだけでも読む価値はあると思う。地元の建設会社、デベロッパーについて横並びで調べてみるか。
Posted by ブクログ
月刊新築マンションは、欠陥住宅がほとんど。
なかなか衝撃的な文面だが、読むとなぜなのかがわかる。
欠陥住宅が起こる原因は
1建築業界の構造的問題(低賃金重労働、孫ひ孫受け構造など)
2.ベテランばかりが減っていく人材不足
3工期厳守が、ミスを招く
4.チェック体制の不備等がある。
著者の結論としては、新築ではなく賃貸を勧めている。
なかなか素人では見つけにくいマンションをチェックするポイントもいくつも挙げられている。
デベロッパーやゼネコンに直接メールをして問い合わせたり、
理事会委員になり直接交渉したりすることも勧めている。
マンションを購入するときに最寄駅からの距離や周辺環境、広さ間取りを大事に考える人が多いが品質を第一とする人はあまり多くない。しかし著者は品質を最優先に選ぶことを提言している。
Posted by ブクログ
マンション建築は、孫請け、ひ孫受けの業者が連なる重層構造により構成されている。大工の多くは日給月給の個人事業主。重層構造の最下層でピンハネ後に大工に渡る報酬は仕事の内容に見合っていない。それでも、仕事がこなくなるかもしれないという不安の中で仕事は請け負い続けざるを得ない。劣悪な環境はモラルの低下を招き、見えない部分は手抜きとなってしまう。加えて施工管理をしているはずの大手ゼネコンにも手抜きを見破る力はない。新築マンションはまず欠陥があることを前提に考えていかなければならない。これが今の日本。
Posted by ブクログ
家を買う。
大きな買い物です。持ち家か賃貸か、マンションか戸建か、新築か中古か。
日本の建築業界の実態を踏まえ、これから新たに家の購入を検討する方々へ示唆に富む一冊。
賃貸よりも資産になる方が良いじゃない、賃貸なんて金を捨ててるだけだよなんて声がチラリホラリ。勿論、価値観はそれぞれ。
晴れて新築マンションを購入しても、思い出されるのが姉歯建築の偽装建築。
ガッツリ、住宅ローン組んでいたにも不正発覚により...
瑕疵担保責任の10年超えてから、大規模修繕が必要な程の瑕疵が見つかった場合、法律上はゼネコンの負担にはならず、最悪な場合はマンションに住む住人へ総戸数にもよるが、数千万の負担を強いられることも。
2007年住宅瑕疵担保履行法が制定されてるけども、こいつも保険適用になるか否かは保険会社の匙加減一つだもんな。
法も知らない者が痛い目を見るわけですね。
91年改正の生産緑地法。適用期限の30年。
2022年には地価が大暴落か。
2016年5月第一刷発行なので、割合新しいが、法改正でまた諸々変わるんだろね。
日本の建築業界も、それぞれ専門性にすれば良いのに。
Posted by ブクログ
なかなか過激で挑戦的なタイトル。建築業界に身を置きながら、そんなタイトルで問題提起するのはそれだけマンションには違法性や見えない瑕疵が多いということなんだろう。最近のニュースではマンション基礎の杭の長さが不足し、ゼネコン負担で全棟建て直しということもあった。
著者はマンション購入で一番重視すべきは品質だという。建築業者に品質管理部門があるか、マンション管理組合は機能しているのかといったことに興味を持ち、建築基準法の知識も必要。こうしたハードルを乗り越えて、慎重にマンションを買うべきだ。
と、マンションを買うことにためらってしまいそうな本。そのトドメにマンションは買わずに賃貸すべきと、著者は言う。実際、著者は購入したマンションを手放して、賃貸マンションに移り住んでいるらしい。
早い話が、欠陥マンションを持ちたくなければ、買うなという結論だ。
Posted by ブクログ
タイトルに衝撃を受けて思わず手に取って読んでしまいました。最近は都内にタワーマンションを始め、多くの新築マンションが建設されて、完成前に完売しているケースも多くある様です。完成したものを見る前から、購入をする人達はどのような人なのかと思っていたら、中国人のお金持ちを始めた人が投資に購入しているケースも多いようですね。
私がマンションを購入したのは、もう20年くらい前になりますが、とても新築に手が出せずに、通勤時間も考えて中古マンションにしました。当時は中古にあんなに大金を出して、とも言われましたが、緑も多く駅まで近いので気に入っています。
この本では、建築検査のプロである、船津氏が自分の経験をもとに、良いマンションとはどのようなものか、様々な観点からアドバイスされています。新築マンションには、中古マンションと比較してリスクが大きいことがよくわかりました。
以下は気になったポイントです。
・マンションの価値は立地で決まるといいますが、建物としての品質、つまり、耐久性や耐震性能といった構造の品質で価値をはかるべきと考える(p4)
・ゼネコンのおもな仕事は「管理」、この能力が優れていているとされる、5大スーパーゼネコンは、鹿島・清水・大成建設・竹中工務店・大林組、である(p37)
・マンション業界が抱える問題点として、下請け多重のピラミッド構造・職方と建築技術者の不足・複数工種の存在・青田売りによる工期厳守・ずさんな管理、がある(p48)
・日本人は、目に見える「モノ」にはお金を出すが、考えを図面化する「設計」、現場での納まり等を考える「工事監理」には、なかなかお金を払いたがらない傾向がある(p52)
・新築分譲マンションは引き渡しを受けた瞬間から価値が2割下がる=新築プレミアム、と言われる。住み続けることで、購入価格の50%程度になると言われる(p67)
・1991年に改正された「生産緑地法」により指定された、生産緑地(営農以外の行為が制限される代わりに固定資産税は農地並み軽減)の指定を解除されると、宅地として売りに出される可能性がある。この法律の期限が30年でありため(p71)
・マンション全体の空室率は2.4%だが、築30年以上(昭和54築)では、10-15%、築40年では20%を超えている(p72)
・最近のマンション市場はバブル期の再来というほど高騰している、2016年1月の平均価格は前年同月比25%増の、5570万円で、過去最高だった、バブル期の6100万円に近づいている、今は新築マンションは買うべきでない。その代り、中古マンションがお薦め(p78)
・ねらい目の中古物件とは、2003-2005年竣工(築11-13年)で、かつ、大規模修繕を実施済のもの(p81)
・マンション修繕積立金のガイドラインによれば、階数15階未満50戸程度の小規模マンションでは、218円/平米・月である。75平米では、月額1.6万円程度(p89)
・2015年5月、中古住宅の流通を促進するために、インスペクションの実施の有無、を重要事項説明書に記載するように法改正を行う方針を発表した(p182)
2016年6月12日作成