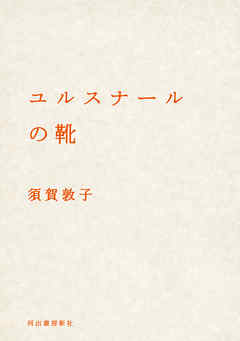あらすじ
デビュー後十年を待たずに惜しまれつつ逝った筆者の最後の著作。二十世紀フランスを代表する文学者ユルスナールの軌跡に、自らを重ねて、文学と人生の光と影を鮮やかに綴る長篇作品。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
「作家は作品を書き終えたら死ぬ、ということばをどこかで読んだことがあるが、たぶん彼女の場合にもあてはまるのだろう。」(文庫p.251)
この「彼女」はユルスナールだが、また著者にもあてはまるのが、何とも悲しい。
Posted by ブクログ
イタリア文学者でエッセイストの須賀敦子さんの『ユルスナールの靴』を読む。
マルグリット・ユルスナールはフランスの女流作家で、出口治明さんが激賞された『ハドリアヌス帝の回想』の作者。
生まれてすぐ母を亡くし、父が亡くなった20代半ば以降、パリ、ローマ、ヴェネツィア、アテネと旅に過ごした人です。第二次大戦の難を避けて恋人の女性と渡米した後は、生涯ヨーロッパに戻ることなく、アメリカ東北部メイン州のデザートアイランド島の小さな白い家で人生を終えました。
このユルスナールという、私たちにはあまり馴染みのない作家の人生を須賀さんは追っていきます。
「きっちり足にあった靴さえあれば、じぶんはどこまでも歩いていけるはずだ」という言葉を胸に、須賀さんもまた20代のころパリに渡り、ミラノで結婚され、夫の死後に帰国、と生涯を旅に過ごしました。
本作は一章ごとに、ユルスナールの足跡に自らの人生を重ねていきます。二千年前に生きたハドリアヌスの行跡を通奏低音として響かせ、三つの異なる旋律を重ねて一つの音楽に昇華させていく作業。
『ミラノ霧の風景』や『ヴェネツィアの宿』でも発揮された須賀さんの、しっとりと洗練された文章にのって、私たちは、ユルスナールの霊魂の闇や、ハドリアヌスの情熱、須賀さんの思索のそれぞれがうねり、互いに絡んでいく瞬間を追体験することができます。
作品の中で何か劇的な事件が起きるわけではありません。
あたかも、日曜の午後、親戚のおばさんのお家にお邪魔して、紅茶を飲みながら、おばさんの「どこまで話したっけ」という言葉で始まる昔語りに耳を傾けるような、ごくありふれた日常の風景。でも、後から振り返ると自分の人生にとって、すごく大切な時間だったと認識するような体験。
須賀さんの思索に自らを投影して読み進める喜びを感じつつ、しかし、物語が終わりに近づくのが惜しい。そんな貴重な本に出会うことができました。
Posted by ブクログ
修学旅行の感想を高校時代の恩師に読んでもらった時に、「須賀敦子を彷彿とさせられました」という言葉を渡されてから、ずっと心のどこかにひっかかっていた名前を、ようやく手に取る。
わたしの須賀敦子処女をこの本に、このタイミングで捧げられたことをほんとうに幸運におもう。
ユルスナールという数奇な人生を辿った女流作家と、須賀敦子という稀有な言語感覚を持った翻訳家の生が、時に伝記的に、時に紀行文的に、あるいは随筆的に語られる。
何より書き出しがいい。こんな風に書きたい、というお手本のような文章。(引用参照)
ふとじぶんの足を見る。扁平でいびつで小さく、大地を踏みしめるにはあまりに頼りなく、恥ずかしくなってしまう。
それでもこの足で歩いてきたし、歩いてゆくのだから、愛してやらないわけにはいかないだろう。
いとしさをこめて、いつか出会えるその靴を探しながら、いや、探すため、歩いてゆく。生きてゆく。
Posted by ブクログ
マルグリット・ユルスナールという作家の生涯と作品、現代の自分、二つの世界を行きつ戻りつしながらゆっくりと溶け合う。小説のような随筆のような、須賀敦子の作品の中でも一番におすすめしたい一冊。
Posted by ブクログ
秀逸なエッセイ集。
須賀敦子にしかなしえない、緻密で完璧な構成。
彼女のエッセイには、小説のような深さと重みがある。
とにかく手放しで褒めたい一冊。
Posted by ブクログ
本屋でオススメされた本。須賀敦子作品は「ミラノ 霧の風景」以来
須賀さんはとにかく文体が美しい。育ちの良さを表現するピカピカの靴と、経験を表現するグシャグシャの靴
今はもう会えなくなった、友人たちへ
Posted by ブクログ
(2024/06/21 3h)
ひとに勧められて読んだ。
すきな文章だった。
ユルスナールを知らなかったので、読む前にWikipediaで浚った。三島由紀夫の著作を好意的に
評しているということで嬉しい気持ちになる。
須賀敦子のエッセイの体を取る本。
とりあえず、須賀敦子とユルスナールを知らない更の状態でも味わうのできる本。
テイストで喩えると、セピアっぽい郷愁の滲む温かさ。癒される文章。
ピラネージ良かった!思わず得ることのできた知識もうれしい。
ユルスナールも読もう。
Posted by ブクログ
著者最期の作品。須賀敦子のや特徴である柔らかなふくらみのある文章をこれ以上に無く味わうことができる。
ユルスナールという女性作家の作品と人生を辿りつつ、同時に自らの人生を絶妙に織り込んで自然と語りきってしまうその手腕は円熟というに他無いと思う。
筆者が作中最後にユルスナールが最晩年まで過ごした部屋を訪ねるシーンがあるが、私たち読者もこの作品を通して、筆者の人生の節目節目を、一つずつ部屋を訪ねるようにそっと垣間見ることができる。
私の中の白眉は、幼少期の親友・ようちゃんとの別れを語った、「一九二九年」の章である。相変わらず涙腺に来るのである。
Posted by ブクログ
マルグリット・ユルスナールとその著作、そして著者須賀敦子自身のエピソードを交錯させながら、見事に独自の世界を気づきあげています。改めて、須賀敦子の力量に感嘆します。
Posted by ブクログ
須賀敦子 「 ユルスナールの靴 」 作家ユルスナールの軌跡を綴った本。ユルスナールの描く世界と 著者の世界を重ね合わせる構成。
作家自身が忘我し、小説の中の主人公と一体化する姿を 「自分の足にぴったり合った靴で旅をする」と表現したのだと思う
「自分の足にぴったり合った靴で旅をする」ことの意味
*旅をする=書くこと→作家として生きること
*靴=小説の主人公→作家としてのスタイル
*ぴったり合った=一体化→愛の日々→忘我の恍惚
*孤独性、放浪性(ノマッド)が 忘我の恍惚を手に入れる作家の生き方 と捉えた
神に到達しようとする魂の道 の3段階
1.神の愛に酔いしれ、身も心も弾むにまかせる
2.神の求める魂が手さぐり状態でしか歩けない
3.まばゆい神との結合に至って忘我の恍惚へ
Posted by ブクログ
須賀敦子さんの著作の中では、もっとも敷居が高かった本。ユルスナールを読んでいないことが躊躇する原因だったのだが、須賀さん自身も、ユルスナールと出会ったのはむしろ遅かったとわかりほっとした。プロローグが圧巻。
Posted by ブクログ
マルグリッド・ユルスナールというフランスの作家の生涯や作品に焦点を当てつつ、須賀敦子自身のエピソードも混ぜ込んだ素敵なエッセイ。
著者がフランスに留学していた時のエピソードは、「あるある!」って共感するところがいっぱいでした。時代が変わっても、感覚は一緒だな。
Posted by ブクログ
大学の講義中に「清潔な文章を書く」作家だと評して、先生が紹介してくれた本。
ひとつの事象について、彼我の感じるそのスピードを丁寧に表現しているところが好き。「私はこう思った」→「彼はこう思った」→「それで私はこう思う」というプロセス。
日常のスピードに押される中で、この感じるプロセスを几帳面に残していて新鮮だった。
作者の描く世界のスピード感に驚きつつ、自分がそのスピードに少し翻弄されて不思議な時空に飛ぶ。通勤電車で読んで乗りすぎた一冊。
Posted by ブクログ
なぜこの本を読もうと思ったのか、よく分からない。新聞の書評に載っていて、記憶に残っていたのかもしれない。ユルスナールというのがフランス人作家の名前だとも知らず読み始めた。ユルスナールの作品や人生と重ねるようにして、著者が自分の人生を回想する。読点の打ち方など、文体がちょっと独特。この本で紹介されているユルスナールの作品の中では、代表作という「ハドリアヌス帝の回想」よりも、再洗礼派の信仰が描かれた「黒の過程」を読んでみたいと思った。
Posted by ブクログ
桜庭一樹読書日記から。
もっと難しい評論かと思ったら、ものすごく読みやすかった。そのぶんするする進みすぎて気をつけないと色々読み飛ばす。多分いろいろ見落としてるまま読み終わってしまったので、文章が大好きなこともあって他の作品も読みたい。
ひらひら混じってくる回想が優雅でわかりやすいのになんとなく不穏なような感じで、好きというにはよくわかってない。
色々おぼつかないので再読したほうがいいと思いつつ。
「東洋綺譚」「恭しい追憶」も気になる。