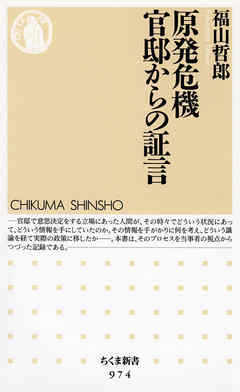あらすじ
「菅首相の現地視察が東京電力の事故対応を遅らせた」「官邸が現場の注水作業を止めた」「政府はアメリカからの冷却剤提供を断った」――これらの批判は事実無根である。首相官邸で首相、官房長官に次ぐ3番目の危機管理担当であった事故当時の官房副長官が、自ら残したノートをもとに、官邸から見た原発危機の緊迫した状況を再現。知られざる危機の真相を明らかにするとともに、緊急時の国家体制が抱える問題の構図を浮き彫りにし、事故を教訓とした日本の進むべき道筋を提言する。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
[「中枢」の言い分]突如日本を襲った福島第一原子力発電所の事故に対し、官邸はどのように動き、対処したのかを、その内部から振り返った一冊。混乱と緊迫の極みの中にあって、危機管理はどのように行われたのか、そしてそこに問題はなかったのかを考えるとともに、今後の原発政策についても所見を提示しています。著者は、東日本大震災の発生当時、内閣官房副長官としてその対応にあたった福山哲郎。
官邸サイドの知られざる内幕が外に出てくるというのは、一国民として歓迎できることなのではないかと思います。ただし、福山氏の主張がところどころで「矛盾」(例えば、「最悪のケースを提示すると混乱を招くので提示しなかった」としながらも、「最悪のケースをつかめていなかった」ということが書かれている)しており読む際には読者側の十分な注意力が必要になってくると思います(もちろん、右「矛盾」があるからといって本書に価値がないと決めつけられるものでもないと思います)。
突発的な事態を受けての情報管理や連絡の在り方などは、危機管理を考えていく上で大変具体的な参考になると思います。また、通説的に出回っている原発事故対応に関する認識の誤りもしっかりと裏付けとともに指摘されている点も評価できます。一概にどう、という評価はなかなか一人ひとりでは下せない本だと思いますので、ぜひ広く読まれてその反応を伺ってみたい一冊です。
〜私は何でもかんでも政治の介入を正当化するつもりはない。政治が介入することの問題点も理解できる。しかし、危機管理の最終的な意思決定は政治が担う以外ないと考える。〜
危機管理は個人的にもテーマなので☆5つ
Posted by ブクログ
原発危機の際に官邸には何が見えてきたのかがわかる貴重な本。主張の正しさを評価するにはこの本だけでは不足だが、危機の中で情報が錯綜し、極限状態で判断を求められることについて生き生き描いていて勉強になった。
Posted by ブクログ
何度も繰り返すが、当事者の話には重みがある。批判を覚悟で、このような記録を残すことには大きな価値があると思う。外野からは何とでもいえる。批判をする者は、自分が同じ立場だったらどのように行動できたかをリアルに想像して物を語るべきだ。
それにしても、本書を読む限りにおいて、(少なくとも当時は)某電力会社と某省庁には原発を任せてはおけないというのが率直な感想だ。
また、くだらない足の引っ張り合いが多い中、最後のエピローグで氏は以下のように語っている。
「震災後、自民党の石破茂政調会長(当時)や公明党の斉藤鉄夫政調会長(当時)をはじめ、与野党を超えて、官邸で復興予算や原発対応について何度もご要望いただいた。筆者も真摯に受け止めたつもりだが、野党の協力がなければ復興はもっと遅れたように思う。…公明党の遠山清彦先生には、原発に注水する生コン圧送ポンプ車、いわゆる『キリン』の存在を3月17日の深夜に電話で知らせていただいた。…社民党の福島瑞穂先生には原発対応で有益な情報をたくさんいただいた。」
今やどちらの政党に託すかということには誰も関心がないのではないか。それより、このような政党を超えての個人の功績に期待してしまいたくなる。
建設的な議論が交わされるようにならないものかと願うばかりである。
Posted by ブクログ
太陽の蓋を見に行った際にたまたま舞台挨拶で福山さんがお越しになり、購入してみました。
情報を共有すること、また真実を知ることってなかなか難しいですね。
Posted by ブクログ
フェイスブックでおすすめしている人がいたから読んでみた。テレビや新聞では伝わらない官邸内の緊張感や関係者の苦悩が伝わってくる。あの事故が大変な出来事だったんだと改めて実感。
当時の政権にいた人が書いた本だから、多少バイアスはかかっていると思う。しかし、東電の対応というのは本当にひどい。大口の顧客(企業など)への節電要請の提案に対して「大口の顧客はお客さまですから、電力使用量を減らしてくれなどとは、我々からは言えません」と言ったという。読んでいて目を疑ってしまった。
あの事故の対応にあたった政治家や官僚も批判されたけど、あの状況でのあの判断は彼らが熟考し、苦悩した結果だったのだと分かった。決してベストではないけれど、東電に比べると、はるかに責任感と誠意があると思う。
Posted by ブクログ
東日本大震災・福島第一原発事故当時の官房副長官だった筆者のノートにもとづく、〈官邸から見えていた風景〉の記録。避難区域設定、被曝上限値の設定など強く批判されるべき点は多々あるが、少なくとも、当時の官邸に必要な情報が十全に入らず、頼りとされた専門家が役に立たない中で決断を迫られていたことは、ひしひしと伝わってきた。
本書には、二つの大事なポイントがあると思う。
?東電や保安院、経産省の対応を見ると、官僚機構は、自分の持っている情報にフィルタリングをかけることで利益共同体を維持していることが火を見るより明らか。それは逆にも使えるので、フィルターとしての官僚機構が、命令・発信の主体を曖昧化する(政府が・官邸が・総理が)ことで、現場の権限を奪ったり、現場に対する権力の行使を正当化する資源としている。
?日本政府にとっての「アメリカ」の存在。筆者は書き流しているが、アメリカ政府の派遣した専門家が官邸の対策室のすぐそばに常駐していた。つまり、アメリカだけは、日本政府の情報をすべて把握出来る仕組みになっていたわけだ。少し考えれば、このことがいかに異様かは自明である。まるで冷戦時代のソ連と東欧諸国のような関係が、21世紀にもなお継続し、空気のように自明化されている、ということだ。
逆を考えてみれば、アメリカで核事故が起こった際、ホワイトハウスに日本人が常駐するなどということはまったく考えられない。韓国の青瓦台に日本人が常駐することもないだろう(逆もそうだ)。危機の瞬間にこそ存在の本質がかいま見えるとすれば、「戦後日本」を象徴するような事態だったと言えるだろう。
Posted by ブクログ
当時の福山官房副長官による3.11後の官邸の動きの記録。東電と官邸の意思疎通の悪さに読んでいる側がイライラすることも。証言記録としてぜひ読んでおきたい一冊。星3つ
Posted by ブクログ
東日本大震災の福島第一原発事故に対する政府の対応を官房副長官だった著者の目で記されている。混乱と緊迫感の中で対応してきたことがよくわかる。これだけ大きな事故になると日本の様々な所で様々な現象、事象が起こっており、それらのすべてを把握することは不可能だし、どこまで集めても終わりはないと思う。大事なことは、その時に得た、または与えられた情報で、より合理的な判断を行えるか?だと思う。そういう意味では事故に対する政府の対応、総理大臣の判断は大きく間違っていなかったと思う。
ただ、本書に関して言えば、事故の対応が途中までしか書かれておらず、話が”脱原発”に移ってしまったのはちょっと残念。菅元総理大臣が著した同様の新書のほうがより緊迫感は伝わるかな。
Posted by ブクログ
官邸にいた福山副官房長官の福一原発事故の回顧録。第一章は当事者目線からの参考になる話が多かったが、後半はエクスキューズのような話が多くなってきた。基本的に回顧録というのはそういうものではあるが。
Posted by ブクログ
3.11の時、実際に官邸で対応にあたった政治家の証言録。当時を知るための資料であり、非常に貴重な証言録になると思う。
この本を読んで思ったのは、緊急事態における情報伝達の難しさ、合意形成の困難さ、既存の制度での対応の難しさである。これらについてどのようにすべきか真剣に考えなければならない。
この本に注文をつけるとすると、その構成にある。第一二章は証言録になっており、第三章は脱原発にむけて何をすべきかと言う内容になっているが、第三章は危機管理に関する記述にすべきだと思う。なぜなら第一二章と三章に一貫性が見られず、第三章が浮いている印象を受けるからだ。
加えて、自分の実感と異なるために?と思うところもいくつかあったが、証言録という性質上、仕方ないだろう。