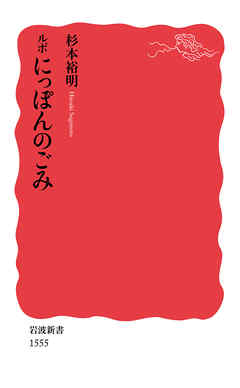あらすじ
日本のごみは年間約4億2000万トン。分別収集やリサイクルが奨励され、最新型の焼却炉は環境に配慮されている。しかし日々の「ごみの行方」はどうなっているのか。最先端のリサイクル施設、不法投棄の現場、海を渡った中古品、関連法施行の背景、拡大するリユース事情などを、20年以上取材を重ねてきた著者が活写する。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
「ハイ 今日カラレジ袋ハ アリマセン」
ある写真家さんがライフワークとしてバリ島へ行かれた
昨年('99年)のお話だそうです。
いつものように いつものホテルに宿をとり
いつものように いつものお店で買い物を終えて
支払いを済ませたところ
上記のような言葉を笑顔と共に投げかけられた
そんな記事を目にしました
バリ島では、そのようなことは日常茶飯事であるらしく
大いに考えさせられたという記事でした
さて 本書です
一枚のレジ袋、一本のペットボトルが
廃棄された瞬間から
3/11の災害が始まった瞬間からの
「にっぽんのごみ」を
徹底して追いかけていった
貴重なルポルタージュです
どれもこれも
わたしたちの身近な問題であり
わたしたちの政治へのかかわりである
そんなことが
見事にルポルタージュされていく
これは他人事ではないなぁ
と見に沁みて考えさせてもらえる
一冊です
さて
もし、今の日本で
いきなり
「今日から ○○はありません」
と 投げかけられたら
この日本では…
と 考えさせられました
Posted by ブクログ
ゴミの今がわかる大変重要な本だった
法作成の裏側も記載されており今までの考え方の流れがよくわかったゴミの今がわかる大変重要な本だった
最新の考えは3Rより2R。
リサイクルはお金がかかりすぎる
Posted by ブクログ
日本のゴミ行政の持続可能性を当時最新のデータで概観した本。
2015年の本だけど、ごみ行政を俯瞰してみられて、今のタイミングだから内容を理解しながら読み進められた(ただしすげえ時間がかかった)
Posted by ブクログ
「ゴミの行方」をテーマにしたルポをもとにまとめられた1冊。不法投棄問題やリユース会社の成長、輸出された中古品の扱い、核のゴミと言われる放射性物質、また国と自治体と関連企業とのかみ合わない三角関係の図式、中国との再生資源の奪い合い、不可解な経緯をたどってきた法制度の問題点など、ゴミにまつわる様々が分かりやすく浮き彫りにされている。身近なテーマであるだけに、興味を持って読んでもらえれば思う。
Posted by ブクログ
「ごみ」にもいろいろ種類があって、家庭から出る生ごみもあれば、原発から出る放射性廃棄物もあります。
そういった様々な「ごみ」についての現状、おもに「リサイクル」「リユース」「リデュース」のいわゆる3Rの視点から書かれた本です。
この本によれば、「ごみ問題の解決には、意識の改善が必要」だが、「意識の改善は難しい」だから「ごみ問題の解決は難しい」とのことですが、適切なインセンティブを用意すれば、劇的に改善する可能性はあるように思います。
ただ、そのインセンティブが思いつかないんですけどね…。
Posted by ブクログ
縦割り行政 p52
東京都はプラスチックを燃やさず埋め立てていたのは知らなかった。
不燃ごみ→可燃ごみ→請願、陳情で再資源化→コスト高
p54
製品プラスチックと容器包装プラスチック、製品プラの収集はコスト高で自治体に負担
環境省から容リ協が認めるならどうぞと言われ容リ協は環境省が認めていないものはできない
収集しない、焼却発電
p73
リサイクル貧乏
p90
バイオガス化
食品廃棄物は事業系ごみとして焼却、低価格で受け入れ
1キロ当たり大阪9円、神戸8円、京都10円、横浜13円、東京23区15.5円、飼料化施設は平均21.4円
事業系と家庭系と焼却施設分けては?→ごみが少ないと焼却コスト割高
p159リサイクル率
リサイクル率ワースト大阪市、事業系ごみ約6割
横浜市分別の数が増えても収集回数が増えない収集の仕方になるように合理化
1台3人→2人収集
p163建設、管理、運営 20年の運営で建設費の2倍儲けよう、がプラントメーカーの合言葉
P238
拡大生産者責任をかつて環境省は目指し廃棄物処理法を改正しようとしたが、経済産業省が裏で経団連に働きかけ、ひっくり返した
Posted by ブクログ
2015.7刊 著者は2014年まで朝日新聞の記者。
日本のごみ、家庭からのごみ、産業廃棄物、リサイクルの現場、バイマス発電、などの現場をルポ。
環境省は2001年に環境庁(1971年創設)から昇格。それに伴い廃棄物行政は厚生労働省から環境省へ。
ごみ法案は、産業界とリサイクル業界の圧力というか調整があり、環境省発案の法令も経済産業省との調整で微妙に変化してゆく、のがわかった。
Posted by ブクログ
ゴミが右肩上がりで増え続けた頃、自治体は焼却施設と埋め立て処分場の整備に力を入れた。しかし、バブルがはじけ、経済活動の停滞でゴミが減り、リサイクルが進展し、実はゴミの排出量は減少している。ゴミの排出量は2002年度の5,161万トンから2013年度は4,487万トンに減ったが、焼却能力は1割しか減っておらず、2013年度の焼却能力は実際の焼却量を4割以上も上回っている。ゴミ焼却施設が過剰となる時代が到来しているという事実は、かなりの勢いで驚きである。また、昨今では、リサイクルのためペットボトルを求めて激しい入札競争が繰り広げられている。隔世の感。ちょっと目を離している間に世の中が大きく変わっている。時代の移り変わりのスピードに驚かされた。日進月歩、技術の進展。清掃工場は、今、それを維持するためのゴミがないという状況に立ち至っている。ゴミ事情の最先端を知ることができる。