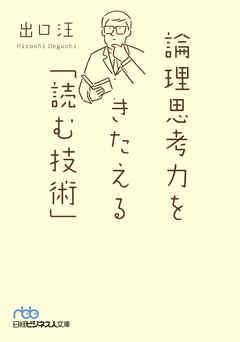あらすじ
本の読み方を変えるだけで、論理思考力がどんどん高まる! ただ漠然と字をたどる読み方から、論理の筋道を追っていく読み方へ転換することによって、あなたの頭の使い方はまったく違うものになる。本や新聞の内容を早く正確に把握できるだけでなく、相手を納得させる話し方も身に付く。受験現代文のカリスマ講師が教えるロジカルな読書法。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
結論から言うとかなり参考になった。試しに別の本を読みながら、この本で習ったことを参照しているが、以前よりかなり整理ができ格段に理解を深めながら読めている。
この本を読んで、まず驚いたのが「意味がよく分からん」とか「読み辛い文章だなー」とか、そういったストレスが微塵もないこと。著者の主張は過不足なくミニマルな味付けのみされており、文章は整然と連なっている。本書は、論理思考力とは何か、また身につけるために何をすべきかを本の読み方を通してレクチャーする本だが、著者の文章がそもそも理解しやすいため、信頼してぐんぐん読み進めることができるだろう。
また、比喩表現もとても的確でイメージしやすい。言語OSの更新、雪だるま式勉強法、要点とは骨であり論理はそのつながりで背骨である。こういった比喩は突き詰めると意味が通じなかったり、そもそも比喩を出す意味がない所で出てきたりというのが悪文にはつきものだが、この書籍ではそれがない。文章を扱うレベルの高さがひしひしと伝わる。さすが現代文の塾講師といったところで、読むほどに感心しながら文字を追えた。
反面、書籍の半分はどこか大学受験の現代文講義っぽさもあり、少し気にはなるところではあったが、個人的にとても良い刺激をいただいたので、目を瞑れる。幅広い年齢を対象に読む意義のある本だと思う。
Posted by ブクログ
論理力は、あらゆる場面で役に立つ、生涯の強力な武器、ロジカル・リーディング、読書を通じて、論理力を養成することこそが、本書の真の目的である。
大切なことは、毎日本を読み読書の習慣を身に付けることである。
本書が提示するのは、
① 言葉の規則を理解すること
② 論理の法則を理解すること
が目的である。
気になることは以下です。
<ロジカル・リーディングとは>
・他社意識が希薄なほど、言葉は省略に向かう 論理の言葉と対極にある
・感情語が氾濫し、言葉が次々に省略されていく。その裏で、論理語が死滅しかけているのが、今の日本の現実そのものである。
・米国の国民たちは、民族も宗教も文化も、そして言語も異なる人間たちと、共同社会を作る必要に迫られた。それゆえ、言葉は当然、論理的なものになる。
・英語の言語形態は、相手に対する不信に根ざしたものだ。対して、日本語は、相手の信頼を前提として会話をしている。
・論理とは、いうなれば言葉の最小限度の規則に従った使い方である。
①イコールの関係、②対立関係、③因果関係
この3つの言葉の規則を獲得すればいい
・論理的な頭脳を養成するには、習熟することが必要である。
・一文は要点と、飾りがあり、主語と述語さえつかめれば、どんな複雑な文であっても、簡単に意味を理解することができる。
・まとまった文章には、筆者の主張が、かならずある。その主張をわかってもらおうと、筋道を立てて説明する。その筋道が、論理である。
① イコールの関係 具体例、体験、引用、比喩
② 対立関係 対立、比較
③ 因果関係 A ならば B 理由・原因 ⇒ 結論・結果
・巷の速読法は、ななめよみ、飛ばし読みである。が、ザルですくう限り、労多くして功少なし である。
・速く読むためには、筆者の立てた筋道を早く、正確に読み取らなければならない。それ以外は、本来ないはずである。
・どんなに長い文章でも、かならず、「要点」と「飾り」でできている。
・精読とは、素早く、しかも正確に文章を読み取り、それをゆっくりを鑑賞するこである。
<速く読む為のヒント>
・目次、小見出しを利用する 全体を俯瞰できる点で大切な役割を担っている 小見出し段落もよむ
・筆者がもっとも言いたいことが 趣旨・要旨である。 ⇒ それを語句にしたものが 標題・主題
・小見出しの内容を理解した上で本文を読む。 ⇒ 論証過程をとらえる
・具体と一般を意識しながら、読む。⇒ 抽象の能力を身に付ける。
・筆者の主張を「命題」という。命題には2つの条件がある ①一般的であること ②論証責任を果たすこと
・文章は汚して読む 線を引きながら読む 手を動かしながら読む それだけで文章に集中することができる
・線を引くのは ①文章の要点となる箇所 ②自分が必要とする情報 の2つ
・要点となる箇所を拾い読みすると、小見出し段落全体を俯瞰することができる ⇒ 図式化したら、要約文を書く
・他人と違う発想そこが必要で、その意味では隠れた名著を発見することのほうが、ずっと役にたつ
・タイトルにだまされない
・筆者のプロファイルを読む
・目次に眼を通す
・はじめに、おわりに、をじっくりと読む
・小見出し段落を眺めてみる
・1冊全部読むこともなく、また、最初から読む必要もない
<ロジカル・リーディングの実践>
・その文章の話題がなにかを着目する 次に その話題に対して、筆者の主張を捉まえる
・①文章の図式化、②要約を行う 文章を論理的に読むとは、衣装を剝がし、肉を削ぎ落して、その骨だけをつかむこと
・ストックノートを作る ①まず理解する、②次にそれを保存する、③絶えず活用できるようにしておく
・左側は、筆者のことば、右側に自分考えたこと、自分の言葉のメモをする
・ノートは汚く書け
・要点だけを、大きな字でかく
・余分なことはかかない、これだけは絶対に覚えようという誓いの印をかく
・もの事には、どうしても理解しなければならない、核がある。論理的関係の中でそれを記録して、雪だるま式に増やしていく
・長期記憶にするためには、①論理的に理解し、整理する ②繰り返す 最低でも5回繰り返す
・伝わる文章を書くための文章力 加えて、正確な日本語の使い方を問われることはいうまでもない
・過去から現在、将来を見据える俯瞰力
<結論>
・頭は使い続けることで、ある程度の老化を防止できる
・本書を手にしたあなたも、論理力を獲得したなら、必ず自分の夢が叶うはず
目次
はじめに 読書法改革のすすめ
本書の利用の仕方
第1章 あなたの論理力はどのレベル?
第2章 論理とは何だろう
第3章 まずは、言葉の使い方を変えてみよう
第4章 論理の基礎を学ぼう Ⅰ
第5章 論理の基礎を学ぼう Ⅱ
第6章 読書テクニックを身に付けよう
第7章 ロジカル・リーディングを実践してみよう
第8章 1冊のストックノートにまとめてみよう
第9章 論理力を普段の生活に生かそう
おわりに
Posted by ブクログ
論理的な思考を文書を読むことで身につけられることを、論理的に証明している本。著者の解説があり、ふと枠で注目するべきポイントを明確にしてくれている。道標がはっきりと明示された地図をもとに、道を進むが如く読み進められるので、論理的思考を簡単に身につけられたという錯覚をもたらすほど、わかりやすい。
出口さんの書籍は、とてもわかりやすいので、他にもいくつかの書籍を読んでいる。本書も期待を裏切らない一冊でした。
Posted by ブクログ
言葉のつながりを意識して読書をすることで、自然と論理的に物事を考えられるようになる。
また、人と会話する時に、主張+理由を意識するだけでも、これまでと違った世界が見えるらしい。なぜならほとんどな人が、思いつきで話していることが多く、論理が飛躍しているから。
・文のつながりを意識
・主張+理由を常に意識
Posted by ブクログ
氏が言う論理思考力とは、まず相手の意見を「正確」に捉えることが基礎となっている。
その「正確性」は、正確な読解力を培うことが先決です。
何が、相手の主張なのか。
それを理解するために、逆説、比喩、順接、対比等の、
接続詞の役割を理解しないといけません。
この理解が、論理的思考力を伸ばすことにつながります。
そして、もっとも、論理的思考力を伸ばすには、
第三者に向けて、書くことである。
この書く能力が、今、現代で求められているものです。
必須の能力と言ってもよいかもしれない。
仕事でのメールやSNSと、現代で、書く行為から、
逃避することはできません。これからも、ますます、
論理的に書くこと、つまり第三者に自分の意見や考えを伝える能力が求められます。
そういういった状況の中で、
出口氏の著作は、わかりやすく、また本質にせまっていると思います。
Posted by ブクログ
東進衛星予備校、現代文の出口先生の「論理的に文章を読む」ための本。
論理構造をイコールの関係、対立関係、因果関係と3つに分類し、例題とともに紹介している。簡潔でわかりやすい。
レバレッジメモ
1.一般か具体かは、相対的なもの。例えば、受験生は人に比べて具体的だが、A君に比べると一般的。
2.ストックノートを作る。著者の言葉(書名、要約文、話題、図式など)をまとめておき、自分の考えを随時加えていく→次から次へと考えが浮かんでくるようになる→論理性が身に付く。
3.相手が、自分のどの部分を突いてくるか、あらかじめ想定できる=対立関係(反論)を使える=論理力がある。説得力が得られる。
Posted by ブクログ
『出口式ロジカル・リーディング』の改題、文庫化。
イコール、対立、因果関係の構造を踏まえて、文章の要点をつかむロジカル・リーディング。分かり合えないからこそ論理的に伝えようとする他者感覚の重要性には納得する。
読んで理解したことを整理し定着させるストックノートまでは実行できそうにないかな。
15-156