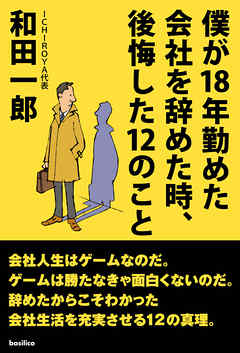あらすじ
「考えてみれば、人生は長いようで短い。そして、そのかけがえのない人生の相当部分にあたる時間を、ほとんどの人々が会社(組織)での生活に費やしている。であるならば、会社生活を嫌々ながら過ごすより心底から楽しんで過ごした方がいいに決まっている。」と、著者が自ら「なぜ勝てなかったのか?」を分析・解説。会社人生の指南書といえる1冊!
...続きを読む感情タグBEST3
このページにはネタバレを含むレビューが表示されています
Posted by ブクログ
自己啓発本は世の中に数多くあるが成功者による事例ばかり。成功者の話はその人の成功事例であって反復可能なものでは必ずしもなく、また共感を得にくいものも多い。
この本は失敗した(と自認している優秀な方)側からこうすればよかったという反省点を在職時のエピソードを交えリアルに描写していて、共感と危機感をリアルに感じさせる。
なんだか自分のことを書いているように思えてくる本。アイディアマンと呼ばれることに誇りを感じる貴方、と書いてあってドキリとしたり。。
以下、章別にメモを記載。
目次
01 入社初日から社長を目指して全力疾走すればよかった
●高々数千円の給料の違いでも時間を味方に頑張れという話。会社の投資と効果のグラフ:リストラする際、損益分岐点が上がり並のBさんもリストラ対象になってしまう。少しの差の中で選ばれた役職を経験するとしないとではその後の成長に大きな差がうまれる。
02 会社のカラーに染まりたくないなんて思わなければよかった
●職場の運営や、飲み会出席等会社のカラーに強い違和感を抱いていたが、マネージャー経験で打ちのめされながら学ぶうち、気づけば違和感が無くなっていた。歴史によって社風(カラー)が作られている。否定せず馴染もうとすることで会社の実像と自分の立ち位置が見えてくる。
03 あんな風になりたいと思う上司をもっと早く見つければよかった
●モデルとすべき上司を早く見つけその仕事の進め方会社における身の処し方を学ぶことができれば早くスキルアップできる。いないのではなく視えていない。仕事に没頭し楽しさ難しさを知り、その難しさを別次元でやっているような人を見てはじめて見つけられる
04 社内の人間関係にもっと関心を持てばよかった
●組織の中で様々な仕事をうまくやるためには、部下にうまく動いてもらうためには論理ではなく感情こそが大事なのだ。酒:普段あまり接点のない人バリバリ仕事して忙しそうな人他部署の人に誘ってもらったらチャンス。どんぐりの背比べ状態を抜け出すレバレッジ。上司が引っ張り上げる信頼できる下駄。社内の人間に知られる努力。近道は自分から社内の人を知る。
05 思い上がらなければよかった
●組織人には4種類の人間がいる話。①出来るが使いにくい②できる上に使いやすい③出来ない上に使いにくい④出来ないが使いやすい。①高転び
会社人は次のステップの為に他の部署への異動が用意される。万能感尊大さをまとってしまうと新しい仕事に対してイチから謙虚に学ぶことが難しい。催事からプロパー企画に移った話。納得できるレベルの仕事が出来なかった。おしゃれでもない自分がファッションのディレクションをする資格があるのか、できるのかと悩み。苦労した要因:ファッション苦手、現場を知らぬままポストについたことに加え「ファッションはわからないけどという開き直り、飄々とポストをやり抜く柔軟性」がなかった = 目に見える大きな成果・即効性を目指さない。ほどほどで何を言われても笑い流して牙を研ぐこと。マラソンレース。区間賞得ても忘れて淡々と走ろう。
06 できない上司や嫌いな上司に優しくすればよかった
●ゲームを有利に戦うには嫌われないほうが得策。好きになる必要はなく割り切る。最速でフィードバック。
2:損得勘定でもゲームに有利かどうかという話ではなく、かけがえのない人間関係を失う、二度と取り戻せない。人を愛する。ジョージサンダースの卒業生へのスピーチ。何も達成していないと思われる自分の両親があなたを愛することであれほど幸せになっていることを見ればわかるだろう。成功を求めて走れば良いが一番大事なことは他者を愛する心が高まることのスピードを上げること。
07 もっと勉強すればよかった
●流行りではなく教科書で幹を学ぶ。スピーキング。サイドスキル(英語、プラグラミング、デザイン)。
08 ゴルフを始めワインをたしなめばよかった
09 信念なんてゴミ箱に捨てればよかった
10 クリエイティブであるよりも堅実であればよかった
ん
11 周りからの評価を得るために長時間働かなければよかった
12 同期が先に昇進したことを笑ってやり過ごせばよかった
Posted by ブクログ
僕が18年勤めた会社を辞めた時、後悔した12のこと
5つ星のうち5.0 組織人として持つべきマインドセット(気持ちの持ち方)
2019年11月8日記述
和田一郎氏による著作。
2015年2月10日初版第1刷発行
著者は1959年3月8日生まれ。
大阪府豊中市出身。京都大学農学部水産学科卒業。
大手百貨店(現大丸松坂屋)に18年勤務。
42歳で退職し、まだ珍しかった海外向けの
アンティーク・リサイクル着物の販売を始める。
2003年有限会社ICHIROYA設立。
リーマン・ショックを経て、現在は日本向けの
販売に力を入れている。
著者の勤務先在籍時期は
大学を卒業した24歳の時1983年(昭和58年)から
42歳の時2001年(平成13年)
著者が半生を振り返り、大手企業に勤める
ビジネスパーソンとしての反省、後悔、今だからわかることを述べた本。
本となるとネットでの発信に比べ敷居がやや高いこともありいわゆる成功者、出世した人の物ばかりになりがちだ。
その中、本書はある意味大多数の敗れた者の弁となる。
極端なブラック企業を除いて、ある程度の規模の組織でどういった心構えで仕事をするべきなのか、
暗黙知であり、研修などでは教えることも無い内容だ。
会社人生というマラソン、ゲームで勝ち抜く為の
ビジネスパーソンとして正しい態度とはどういうものか理解する為に役に立つ。
吉越浩一郎氏の著作だと既に社長としてスタートした話ばかりでいかに出世していくかという大組織の中での苦闘はあまり見えてこなかっただけに本書は貴重だと思う。
印象に残った部分を示していくと
大半の人々は「会社人生」というゲームに参加させられることから逃れることはできない。
だとすれば、そのルールを否定して上の空でゲーム参加するのではなく、本気で参加してみればいいと僕は思うのだ。
会社での人生は「モノポリー」に似たところがある。
1.01×365=37.8
0.99×365=0.026
最初から全力疾走しないと、20年後、30年後にはその差は驚くべきものとなるのだ。
ほんの少しの差は上の役職に選ばれることで大きな差にある。
なぜなら、その役職をこなすことで学べるが多いからである。
よく言われるように「地位が人をつくる」のだ。
そして、そこでもまた小さな差が、次の役職の決め手となって
さらに上位の能力を身につけていく。
そうやって、長い年月の間に、わずかの差が決定的な差へと変わってしまうのである。
能力アップのための時間をきちんと割いてそれを継続すれば、20年、30年という長い間に大きな能力の差となって、ゲームを有利に導いてくれる。
自分から与えられたことに100%コミットすることで、会社からそういうものを引き出すぐらいのつもりでないと、いつまで経っても仕事の面白さは味わえないのではないかと思う。
オブラートに包まれたような状態で提示される「会社人生」という名のゲームの正体を直視してみよう。
それはやはり「社長」になることなのである。
部長や、単なる取締役がゴールだということはあり得ない。
社長を目指して頑張ったからこそ、取締役にもなれる。
競争で、はじめから二等賞を目標とするなどということはあり得ないのと同じである。
会社という長いゲームで勝つためには、早く走り始めて、長く走り続けることが、最も大切なことのひとつである。
職場に対して強い違和感を覚えていたとしても、それはキャリアの浅い多くのサラリーマンが等しく感じるものであり、深刻になる必要はないのだと。
あなたが抱いている違和感は、マネージャーになったり、専門職として認められたりしていくうちに、やがて消えてしまうものだと。
あなたが会社人生という名のゲームを本当に楽しみたいのなら、自分のいる会社の社風を頭から否定するのではなく、まず馴染もうとするべきだろう。
そうすることによって、その会社の実像と自分の
立ち位置が見えてくるのではないだろうか。
隅から隅まで善意で満たされた会社は存在しないように、すべてが嫌悪の対象となるような会社も存在しない。
学生から社会人となり、そういうことを理解し、会社の本当の良さが見えてくるまでには、それなりの時間がかかるものだと思うのである。
自分がモデルとすべきような上司を見つけるには、まずそういう人が傍にいる必要があるけれど、それだけではダメだ。
実際に、その人の内実を視る力が自分になければならないのだ。
そのためには、自ら仕事に没頭して、仕事の楽しさや難しさを知り、
その難しいことを別次元でやっているような人を見てはじめて
「その人のようになりたい」と切に思うようになる。
社内での噂話は大いに楽しめばいいのだ。
複雑な人間関係が見えてくると「会社人生」という名のゲーム盤の上で行われていることも別の角度から見ることができて、とても面白いではないか。
それは無駄なことでも、恥ずべきことでもない。
それぞれの個人が組織の中でどんな風に生きているのか、それをつぶさに観察することは人間学の王道ではないか。
組織人ではなくなった今の僕には、そんな風に思えるのである。
望み得る最高の状態とは、ずば抜けた実績を継続的に上げて、社内の誰からも知られている状態になることである。
それができないとすれば、なるべく社内の人間に知られる努力をしなければならない。
そして、そのための最も近い道は、自分から社内の人のことを知ることなのである。
組織とは、つまるところ人間の集合体であり、人間には感情があるということを考慮に入れないビジネス論には、リアリティがないのだ。
できるといわれていた人たちのほとんどは「事情通」であって、そういうことをよく理解していた。あるいは、理解しようとして様々な情報を集めていた。
会社には、神の目のようなものが存在して、必ず正しい判断が下されるものと想像したものだが、やがて神の目なんか存在せず、
それぞれの決定は微妙なパワーバランスの下に社内の特定の誰かが行っていることがわかってくる。
それはあくまで、職位者が決定したというかたちをとって行われるのだが。
会社人が忘れてはならない事のひとつに、会社人生はマラソンのような長いレースであって、決して短距離レースを走っているのではないということがある。
僕のように面と向かって反論したり、ウルトラCの解決策を期待したりしない。
自分が何をやりたいかということよりも、上司が何を求めているかということに敏感で、いつも上司の誰かのために仕事をしている感じだった。
過激なことや威勢のいいことを言ったりしているようでも、攻撃してはならない相手を冷静に見極めていて、直属の上司や将来自分に対して影響力を持ちそうな相手に対しては、決して失礼なセリフなど吐かない。
組織人には、4種類の人間がいるという。
1できるが使いにくい人間
2できる上に使いやすい人間
3できない上に使いにくい人間
4できないが使いやすい人間
ゲームに勝ち抜き、組織の中で将来重きをなそうとするのであれば、
はっきりと意識して2の「できる上に使いやすい人間」を目指すべきだった。
「できるが使いにくい人間」は、自分で将来の昇進のチャンスを潰しながら
上に進もうとしているようなもので、いつか必ず天井にぶち当たる。
このことは会社組織におけるシンプルな真実であり、組織人なら皆わきまえていると思うのは大きな勘違いだ。
1の「できるが使いにくい人間」がかなりいる。
組織人とは、オーナー企業でもない限り、どこまで偉くなろうと上と下に繋がれたチェーンのひとつに過ぎない。
部長の上には取締役がいて、取締役の上には専務がいて、専務の上には社長がいて、社長の上には株主がいる。
「使いやすい人間」は、決してそのことを忘れない。
しかし、多くのできる人間は実績を積むと尊大になり、自分が上司をも動かしていると錯覚してしまう。
その結果、自分の哲学や主義と上司の望むことがぶつかってしまった場合ギリギリまで抵抗し、結局「転んでしまう」ことになる。
(利己的な)上司を好きになる必要はなかったのだ。
そういう人だと割り切って、嫌われることのないよう、望まれる仕事をちゃんとこなせばよかったのだ。
上司と意見が対立した時の最も適切な対応とは、
「意見は言うが指示を受け入れる。そしてチーム一丸となり全力で指示された仕事にあたる。その結果、失敗したならその内容を速やかに報告しフィードバックする」ということだ。
どんな上司であれ、どれほど利己的な、人間的に好きになれない上司であれ、自分が仕える時々の上司すべてにできることなら好意を少なくとも嫌われないようにすることは、ゲームにおける必勝法のひとつであった。
ゲームを有利に進める為の武器となるのは、文章力よりもまず口頭表現力である。
会社というゲームを全力で戦い、勝ち抜く覚悟でいるのなら、僕のように「信念」に凝り固まり「頑固である」と言われないように振る舞わななければならない。
もし、あなたが誰かに「信念のある人だ」と言われたら、
それが本当に褒め言葉なのか、暗に「頑固者」と言われているだけのことなのか、ちょっと立ち止まって考えてみても損はない。
自分の信念やこうあるべきという理想から、僕はもう少し柔軟であってもよかったのではないか。
ゲームはマラソンで、逆転は可能なのだから、チャンスはまだまだあると思い、淡々と自分の役割をこなし続ける。
たまたま、同一部署の上司部下となったとしても、部下の役割を完璧に演じる。
会社が求めているのはそういう態度であって、
一度の負けで諦めて走ることを止めてしまうことではない。
そんなゲームの結果に興味などないという風に装って、先行する同期を笑って祝福し、自らは変わることなく前を向いて走る。
自制心でそれを見事に演じきることができれば、組織人としての評価も上がるはずだ。
Posted by ブクログ
痛々しかったけれど、たしかに大学生に読んでもらうことには非常に意味があるだろう。推薦本にキープできる。安いやつをプレゼント用に一冊買っておこうかな。
SNSで見かけた良さそうな啓発本。うん、仏教で解決だね。変なこだわりが自分をおかしくするんだね。
この人は変に達観した感じを入社当時から持っていた。それが失敗だったみたいだ。若者の変な達観というのは、ただの背伸びをした上から目線でしかないんだよな。それもやはり、自分は優れているという自負に執着しているから。仏教を勉強して執着から解放されればよかったんだ。
と、批判的に書いたけれど、どれも読んでいて心が痛くなった。自分だってやってしまっていそうなことばかり。非常に身につまされるいい啓発本だった。
なぜいい啓発本になるのか。失敗をきちんとフィードバックしているからである。ここは筆者が小説家を目指していたからなのかも。文章力。論理力。
目次
①入社初日から社長を目指して全力疾走すればよかった
②会社のカラーに染まりたくないなんて思わなければよかった
③あんな風になりたいと思う上司をもっと早く見つければよかった
④社内の人間関係にもっと関心を持てばよかった
⑤思い上がらなければよかった
⑥できない上司や嫌いな上司に優しくすればよかった
⑦もっと勉強すればよかった
⑧ゴルフを始めワインをたしなめばよかった
⑨信念なんてごみ箱に捨てればよかった
⑩クリエイティヴであるよりも堅実であればよかった
⑪周りからの評価を得るために長時間働かなければよかった
⑫同期が先に昇進したことを笑ってやり過ごせばよかった
もっと勉強すればよかったというのは、いつでもだよね。1.01*365=37.8に対して0.99*365=0.026という有名な努力の継続の必要性の数式。