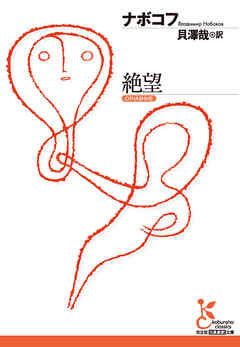あらすじ
ベルリン在住のビジネスマンのゲルマンは、プラハ出張の際、自分と“瓜二つ”の浮浪者を偶然発見する。そしてこの男を身代わりにした保険金殺人を企てるのだが……。“完全犯罪”を狙った主人公がみずからの行動を小説にまとめ上げるという形で書かれたナボコフ初期の傑作!
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
解説を読むとめちゃめちゃ面白かった。
翻訳の文体が分かりにくいのかと思ったけど、完全犯罪が破れて追い詰められたゲルマンが、芸術作品として創造した手記という額縁小説のような形になっているから分かりにくい。一回通読してから読み返すと、あああの話ね、とつながる。
読み返してみれば、たしかにフェリックスと似ていると言っているのは語り手のゲルマンだけで、フェリックスだって2人が似ていると自分から言ってはいない。一人称小説だからゲルマンの主観で書かれており、アルダリオンもかなりヘボな人物に描かれているけど、ゲルマンに描かれたアルダリオン像と、引用されたアルダリオンの手紙=ゲルマンの主観ではなく、本人の言葉を通して見るアルダリオン像には隔たりがある。小説に描かれたことは小説の中では真実のはずなのに、その前提を揺さぶってくる。小説は真実ではない。小説は想像の産物、虚構でしかなく、言葉による表現は受け手によって再創造されることによって受け取られるが、客観的に目に見せることも音を聞かせることもできない以上、すべては思い込みとも言える。そもそもの語り手の言葉も本当かは分からないし、読者である自分の受け取りはミスリードされたものかもしれない。面白い。
分身なんて嘘だ。鏡だって本当の姿を映しているのではなく、「無数の鏡像からできているこの信用ならない世界」。正しく見えていると信じていたものが、本当は見えていなかったのかもしれない。
Posted by ブクログ
この話は鼻持ちならない自意識過剰な男の「芸術」なのかもしれない。ぼんくらな芸術家がいかに惨めで哀れで滑稽かと描かれているのかも。ミステリとしてのある部分をネタバレしているので解説は最後に読まれた方がいいと思う。ネタバレあってももちろん面白がソコに作者の意図があるので自ら読んで驚いた方がいい。随所に仕掛けありきらりと美しい描写あり皮肉で辛辣でナボコフ初期の作品でとても楽しめた。
Posted by ブクログ
ねっとりとした意地悪な文体。解説にて初期ロシア語による翻訳で、それがウリだそう。その解説にて一生懸命、小説の仕掛けを力説されてる訳だが、まず作者を好きで尊敬し、作品に興味を持つ、そこからが開始点であり。
淡々と読んでいるだけでは、そうなのいやそうじゃない、もったりくったりとした、自分の犯罪を計画して楽しみイラつく男の1人語り。
場面場面は昔の宝田明が出てるドラマっぽいと思った。
Posted by ブクログ
1936年刊、ナボコフ初期の小説だ。今回は犯罪者の手記といった形をとり、どうやら、ナボコフが嫌いなドストエフスキーをパロディ化しているようだ。どうにもとりとめのない、主観的な饒舌がドストエフスキーの文体を真似ているのだろうが、本家の作品のようななまなましい迫力は全然ない。
「鏡像」という「虚構」が最後に音を立てて瓦解していくところが、この作品の白眉だろう。主人公の思い込み・勘違いがさっと振り払われ、主体が一瞬消失するような感じは、ナボコフならではかもしれない。
ドストエフスキーの真似なんて、やめとけば良かったのにな。
Posted by ブクログ
ふぅ! やれやれ…。印象をとしては、「ヘッポコ主人公のながい知的遊戯に付き合いました」かな(失礼)。タネ明かしはほぼ解説にて。探偵小説を下書きにしたメタフィクション、だそう。なのですが。正直なところ、読んでいる間は、「これが、文学、芸術、なのですね?」ふふふ...コントとしてなら楽しめそうかしらん、といった感じ。
度々読者を引き止め、「読者よ...」と呼びかけては、コレにはこれこれこういう理由があるんだからね、『なんだからね!』の過剰なエクスキューズに、あ、そう。へーそう。(毛先を弄りながら)そっかそうだねあはは、と上の空で相づちをうっているイメージが続く。
好きな場面は、風がオリーブの木の葉をいっせいに裏返す様子を、飽きることなく窓から眺める場面で、お?思ったのは、妻に向かっての「脳タリンな女」発言。
ただ、示唆にとんだ文節が無かったかと言えばそんなことはないし、解説を読んで皮肉たっぷりな小説だったんだと気づいた(解説がいい)。鈍いな自分。
読書って解釈の自由さがあるから面白いし、それが醍醐味だと改めて気づかされた。
ドストエフスキーが読んだら何て言ったか、想像すると楽しい。