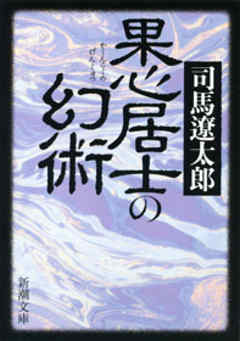あらすじ
超人的な力の持主であるがゆえに、戦国時代の武将たちの運命を左右しながらも、やがては恐れられ殺されていった忍者たちの不可思議な生き様を描いた「果心居士の幻術」「飛び加藤」。そのほか、日本建国の神話に題材を取った「八咫烏」から、幕末・新選組の裏面史を扱った「壬生狂言の夜」まで、歴史の中に埋もれた興味深い人物・事件の数々を掘りおこした作品集。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
忍者、新選組、古代史とおいしいモノがつまった、巨匠・司馬遼太郎氏による「呪術もの」「奇譚もの」的短編集です。
本書の「壬生狂言の夜」が、司馬御大が初めて手がけた新選組もの、らしいです。ここから「燃えよ剣」などにつながって行ったんですねー。
表題作の「果心居士の幻術」は、室町~安土桃山時代の怪人兼幻術師兼忍者と言われている、果心居士の話です。
好きなんですよ、この手の人物。
役小角や道鏡や、そしてこの果心居士。
怪しいけど、なんか惹かれてしまう。
中でも「八咫烏」は、司馬御大の作品としては異色な印象を受けました。
古代、神武東征の時代が舞台。出雲神話を軸に展開されています。
八咫烏は神武を大和に導いた伝説上の生物ですが(3本足の大烏。日本サッカー協会のシンボルですね)、この話では人間です。
古文書をリアルに、人間ドラマとして噛み砕いた話になっていますね。猿田彦も登場しますよ。
こう言った短編は大作に埋もれてしまいがちですが、私にとっては印象深い作品です。
「飛び加藤」は戦国時代の不思議忍者もの、「牛黄加持」は日本霊異記を思わせるような幻想的で怪しくも官能的な話、「朱盗」は藤原広嗣の乱の際、広嗣と謎の異人の数奇な交流を描いた話。
濃いですよ。ぜひオススメな一冊です。
Posted by ブクログ
著者の別作品[(空海の風景)を読んだ後だったので、さくさく読めた。それでも、一文の情報量が多いので、読み応えは十分。
歴史の大河の亜流を集めた、短編集。アヤしい話なので文献が豊富なわけでもないため、司馬史感で補強されている。しかし、記録が残っているということは、それだけ人々が信じ、言い伝えられてきたという証。今考えれば非科学的で嘘とわかることも、当時はそれが嘘だと立証するものがないし、それが事実と信じられていたし、そういう意味では真実だったのだろう。真実とは人が勝手に定義した出来事の一連の流れであり、つまりは時代によって変化する。何が真実なのか。そう思わざるを得ない。
最後の短編、牛黄加持は嘘かほんとかはわからないが、密教における生々しい性描写が軒を連ね、笑いを堪えられなかった。宗教はどこか崇高な印象を与えるが、所詮は欲を持った、われわれと同じ人間が考えたことに過ぎない。
Posted by ブクログ
前にも読んだことはあるが、最近、司馬遼太郎記念館へ行った際に、ちょうど忍者や異能の者を特集展示していて、この『果心居士』も取り上げられていた。再読したくなったもの。
『一夜官女』のあとがきにもあったとおり、司馬はさまざまな歴史の精霊たちとつきあっていたが、そのうち、妖かしに類するものの特集だ。
Posted by ブクログ
国盗と言う位置ゲームに現れた果心居士と言う歴史上の人物に関心を持ち、確か司馬遼太郎さんが書いていたと思い出し本屋で探しました。異色作を集めた短編集です。
果心居士の幻術、飛び加藤は、何も超能力を持つ忍者、または婆羅門の幻術士。前者は秀吉(和州大峰山の修験者 玄嵬)に、後者は武田信玄に殺される。
壬生狂言の夜は、新選組隊士、柔術師範頭松原忠司の心中の物語。惚れた女の亭主を暗殺し、助ける風情でその女を我が物とする。女もそれを察しながらその外道の愛を入れる。凡そ人の道の外にその心中が成る。
八咫烏は人の名前である。大和朝廷成立前、海族(わだつみ)と出雲族の混血児が、その二つの種族(歴史の流れ)の葛藤と統一に立ち会う瞬間を描いている。初めての混血故に、どちらの社会にも属せず、その埒外から人間を俯瞰する。
朱盗は藤原広嗣の太宰府におけるクーデター未遂と、異形の人間、穴蛙の出会い。百済の移民の子孫で太宰府郊外に住み、親子三代の事業として貴人墳墓の朱の盗掘の為に生きている。個人は消滅し種族の生命を生き、結果、穴蛙は人の歴史の埒外に呼吸している。
牛黄加持は若き法師義朗を主人公とする。醍醐理性院の賢覚僧都のもと真言密教の法義を学ぶ。俗世の外に生きる努力と、その為故の人の俗性の強調をそこに見る。
山崎正和氏の君子が怪力乱神を語るときー と言う解説に全作品をつなげて腑に落ちる見方を学ぶ。(それ程うがってつなげる必要もないが。)
全て人としての歴史の時間の、外に生きるしか無かったもの、その業により出てしまったもの、出自により出されてしまったもの、その中を知らないもの、出る為にあがいているもの。
司馬遼太郎氏自身が歴史、完結している人生を俯瞰する所行を続けるが故に、時に自身を歴史の部外者と感じぜずにいられなくなる、その辛さが耐え難く嵩じた時に、歴史の支配する世界の外へと失踪する。失踪せざるを得なく成る。その隠れ家としての歴史の外に生きた異形異能の人々の修羅場。
以前から常々思うこと。司馬遼太郎さんはスケベであると。人間のその本能と業はとても深いものであるという事?それを認めているということ?不思議な横の感想です。
Posted by ブクログ
☆☆☆2011年4月レビュー☆☆☆
司馬遼太郎の初期の短編集。
なかでも、戦国時代の幻術使いを描いた『果心居士』の幻術が面白かった。司馬の考えでは、人の迷信にすみつく幻術使いは、戦国時代までは存在し、記録にも残っているらしい。筆者の手で、その不気味な姿がありありと浮かんでくる。司馬氏は『妖怪』という小説でも幻術使いを扱っているが、次第に人々が合理的精神をもつようになると、こおような幻術使いは生きられなくなったようだ。
松永久秀や、筒井順慶といった戦国大名も、「さすが!」という豪胆さを見せ、非常に読み応えがある作品。
☆☆☆2018年7月レビュー☆☆☆
前回読んだときから7年も経つのかと思うと愕然とする。
「壬生狂言の夜」という作品は悲しい。
目明し与六の
(武士なんぞにならずに、八百屋で一生を送っていたら、こんなばかな死にざまをせずに済んだのに)
↑新選組・松原忠司の死を発見して
という心の声がこの物語の全てだと思う。
歴史上には、一市民で生きていればという人物がたくさんい居る。水木しげる氏は「近藤勇」もその一人だという。
Posted by ブクログ
2ヶ月くらい前に読んだ本に「果心居士」が出てきて、てっきりその本の創作人物だと思ってたら実在(かは謎だけど)の人物だったのね。
戦国時代の幻術師らしく、でもあんまり史料は残ってないのかなあ?
とは言えあり得ないような術を使うし、昔の人の創作人物なのか?
果心居士以外にも全6篇の短編集。
壬生狂言の夜が面白かった!
最初の2篇は似てたけど、あとは全部毛色の違う話で結構面白く読んだ。
前回読んだのも今回のも司馬遼太郎の初期作品だから、もうちょっと後の作品も読んでみたいな。
Posted by ブクログ
2020.2.11完了
司馬氏の話がはずすわけがない
最後の話はおぞましかった
子を成さなければ坊主の手も借りるというのが、文字通りで気味悪い
実際もそうだったのかと思わせる内容
Posted by ブクログ
・果心居士の幻術
信長の時代
松永弾正小弼久秀の使われ者「悪人の手伝いをしたい」
天竺人と倭人との混血
婆羅門教
・飛び加藤
忍者
五尺にみたぬ小男
永江四郎左衛門が連れてきたが上杉謙信は召抱えず
・壬生狂言の夜
新撰組=壬生浪
土方歳三(副長)が松原忠司を暗殺する
・八咫烏
海族×出雲族の混血
海族としての精神×出雲族の心&体&顔
比叡山麓の御生山「御影神社」(京福電鉄三宅八幡駅)
・朱盗
死者の腐敗を防ぐために棺に詰められている唐渡りの朱を盗む
大宰府ノ少弐藤原広嗣
扶余の大将軍
・牛黄加持
牛黄=牛の病塊
牛の角、肝臓、胆嚢、心臓に生ずる肉腫or癌
肝 黄=死牛からとったもの
角中黄=殺した牛の角からとったもの
生 黄=生牛から得るもの
生黄は医薬の中でももっとも高貴なもの、1匁(3.75g)あたり黄金数十倍、服用すれば死者すらよみがえる!
Posted by ブクログ
司馬遼太郎の短編集全六編からなる。
表題の「果心居士の幻術」は、戦国時代の有名な居士が起こす幻術に翻弄される戦国大名たちの姿を描く。
松永久秀、筒井順慶、豊臣秀吉など、果心居士を通したそれぞれの個性が描かれており、非常に面白かった。
また、戦国時代の有名な忍者を描いた「飛び加藤」も素晴らしい。
忍者の技試しをコミカルに描きつつ、戦乱の世を生きる人々が求め続けた「力」への憧憬と畏怖という表裏一体をコンパクトにまとめている力作。
個人的に非常に興味深かったのが、「壬生狂言の夜」。
新撰組の跋扈する京で起こった殺人事件を、名もなき目明かしが土方歳三と供に真相を糾明する話。
殺人事件を通して、新撰組が常に内包していた闇をさらけ出すラストはある種の恐怖を感じさせる。
どの作品も語り口は穏やかで、どこか滑稽ではあるものの、ラストには一転して物悲しい余韻を残させるあたりが見事!
Posted by ブクログ
「いずれへ行く」
「行くのは、おぬしじゃよ」
弾正が死んだのは、その日の翌日である。
----
その目の前にある板が、わずかにうごいた。板が、ゆっくり翻って、広嗣をみた。顔がついていた。人であった。
----
上述のような、司馬遼太郎特有の急調子の展開やユーモアたっぷりの文章が好き。
いまではとても考えられない風習や文化が伺える六編。
なかでも「牛黄加持」には、言葉を失くした。
「現代となんも変わらないじゃないか」と一笑に付すことも出来るけど、真顔であんなことしてるんだもんなぁ。
Posted by ブクログ
「八咫烏」を収録。
出雲族の植民地・ヤマトを手に入れるべく、イワレ彦率いる海族は、その植民地である牟婁に渡ってきた。八咫烏はこの地で唯一の出雲族との混血児だ。自分は海族であると思っているが、出雲族の賤民として差別を受けていた。
ヤマトへの案内役を命ぜられた八咫烏は海族軍の先頭に立って進む。途中、老イワレ彦をかついで歩くことになり、彼の立場は好転した。
吉野についた彼らは出雲族への攻撃を開始する。やがて、ヤマトで長髄彦の大軍と対峙した。八咫烏は、長髄彦の館へ忍び入り、降伏をすすめたが拒否され、同道した海族の赤目彦は長髄彦を殺す。このとき八咫烏は赤目彦の出雲族への侮蔑に怒り、赤目彦を殴り殺してしまう。
海族は勝利しヤマトは征服された。イワレ彦は八咫烏の功績を認め建津身命の名を与えた。さらに重職に迎える話もあったが、八咫烏は固辞し、未開の原野に隠棲した。
彼の暮らした住居の跡に建つという神社の古伝には、八咫烏には子があったという。当然妻もいた訳だが、海族と出雲族、どちらの出だったのだろうか…