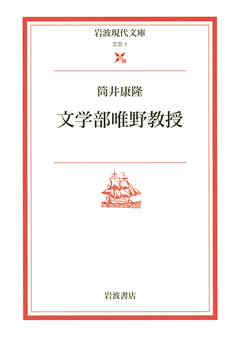あらすじ
これは究極のパロディか、抱腹絶倒のメタフィクションか! 大学に内緒で小説を発表している唯野先生は、グロテスクな日常を乗り切りながら、講義では印象批評からポスト構造主義まで壮観な文学理論を展開して行くのであったが…。「大学」と「文学」という2つの制度=権力と渡り合った、爆笑と驚愕のスーパー話題騒然小説。
...続きを読む感情タグBEST3
このページにはネタバレを含むレビューが表示されています
Posted by ブクログ
その当時のアカデミアの人事というか人間関係はこういうところなのだろうか、、、と考えざるをえなかった。。。本当かウソなのかはこの小説を貸してくれた教授に聞いてみよう。
授業形式で前半にアカデミア界隈の人間模様、後半に授業が盛り込まれ、知識も増やせた一冊であったように思う。
以下読書メモ
ーーーーー
・ひとに例外を許さない、個性を認めず独自の行動をさせない、そのかわりその人が自分のものとして負うべき苦しみや悩みや責任を忘れさせてくれるような存在を「世人」という。こういう世人と話すときの普通の会話や雑談や無駄話のことを『空談』といいます。これは『語り』の日常的な、非本来的なありかたで、語りというのは、人間それぞれが、自分は他の道具的なモノやモノ的なモノではなくて、そういうものを理解したり照らし出したりできる、そして自分も照らし出せる、この世に生きている存在だと自分でわかっているということ、それを了解し、解釈している場面なの。この場面ではじめて言語が可能になる。だから本来の語りなら、われわれは話している相手がわかっていることを聞いて相手と同じようにわかることができる筈だけど、空談はそうじゃない。直接的な出会いじゃないんだよね。話が話し手からひとり立ちして、内容は薄くなって、語り広められて真似される。マスコミの発達でそれはますますひどくなって、聞く方は了解するという面倒なことをしなくていいわけ。さらにこの語りということの中には、聞くことや焼熟することも含まれています。人間の『語り』というのは、語る存在として自分を示すこと以外にも、世界に耳を傾けるということでもあるの。
・人間の非本来性の中には、自分の死をまともに見ようとしないってのがあったね。では、まともに見るとはどういうことか。他人の死というのは経験できないし、代わってやることもできない。ところが自分の死は、それがやってくれば人間は現存在でなくなっちまう、しかも、いつやってくるかわからない。つまり死はそのたびごとの可能性で、人間はそのたびことに自分の終りにかかわっている存在だ。そのたびごとといったって、やはり死はいくら早くても一瞬先にあるわけだから。つまり本来的に死を見るというのは、自分に先んじて死とかかわり、それを本来的に了解することで、これを『先駆的了解』といいます。おおいやだいやだ。おれなんか自分の死を了解したくないね。あたしゃ自分が死ぬ時なんぞは、もう、そこにいたくありませんよ。しかしハイデガーは、常に先駆的了解のために自分に先立って、自分が先へ投げこまれるのではなく、自分を先へ投げこめと言っています。それが自分の全体性をとらえ、新たな可能性に向けさせるのだと言っているわけで、ハイデガーの場合、人間的な知は、常にこの先駆的了解から始まるの。と同時に、その中から出られないところがこれまた限界なの。ハイデガーに言わせるなら、人間の存在というのはいつでも新たな可能性の問題なのだから、つまり完成なんてことはあり得ない。どんな科学も理論も、先駆的了解を行った結果を部分的に抽象化したものに過ぎないっていうの。
11:29 田村まり ハイデガーの著作は『存在と時間』だったよね。では人間にとって時間とは何か。ハイデガーは、人間の存在している意味、それから、人間が存在することを可能にしているもの、それが時間性だと言います。あのう、歴史、と言わないで、時間、と言ってることにご注目ください。人間が全体的に、本来的にこの世界に存在するには、死という可能性をめざしながら自分を見る、つまり未来を見ると同時に、過去を見て自分の非力なことを知り、同時に現在を見て自分を解放する。つまり『過去を見つつ現在にある未来』というのが人間存在の意味、つまり時間性だっていうの。
・文学作品の意図というのは、ただ作者の意図というだけでは説明できないものがあって、その時代、その文化が、われわれの時代、われわれの文化へやってくる時、そこには作者が意図することのできなかった新しい意味が生まれてくる筈だ。この不安定性こそ文学作品の特質だとガダマーは言うの。たしかに不安定だよなあ。作品から問いかけられるわれわれ現代の読者の方は、何百人も、何千人もいるわけでしょ。そしたらその答えは同じじゃない筈だよね。で、これをガダマーに言わせると、作品を了解するのは常に、別のかたちの了解なのだ、その意味をずらせることだ。だからこそ、現代でほんとの了解をするのは、現代だけにしかない意味で作品を了解することだ。つまり新しい現代的な意味をひっさげて故郷へ帰るみたいなもんだって言うの。
・フッサールってのはほら、意味というのは意図された事象だ、その中から絶対不変のものを発見すればそれが本賞だ、イデアだって言いましたね。だからハーシュがそう言うのも当然といえば当然。意味というのは言葉以前にあるものだ。意味が言葉によって固定されるのはそのあとのことだっていうんだけどさ。じゃあ君たち、ちょっと、言葉を使わないで、頭の中で何か意味することを考えてくれるかい。できましたか。そりゃまあ、あんな感じ、こんな感覚、言葉で言いにくいものはあるだろうけど、それはまだ意味ができていないからだよ。では一方ハイデガーはどうかというと、『存在と時間』の中で彼は、言語が可能になる『語り』というのは、世界に耳を傾けることでもあると言ってたよね。そもそも人間は、時間によって構成されているのと同じで、言語によっても構成されているのだってわけ、つまり言語はコミュニケーションの手段でもないし、意味を表現する手段でもない、それ以前に世界を生み出し、人間を生み出したのが言語だっていうの。言語によってはじめで人間は人間になれる、言爵は、人間が自分の全体性をそっくりそのまま提示するたの場所として、ひとりひとりの人間よりも先に存在していて、それによって人間は成長するにつれ人間らしくなっていく。
Posted by ブクログ
大橋洋一著『新文学入門』に登場していたから読んでみた。文学理論の本でもあり、物語でもある。難解な文学理論を唯野教授が軽妙な語り口でもって説明してくれるので、雰囲気はつかめた。けれど、自分の言葉で説明できるくらいの理解は私の力不足でできなかった。大学での文学の講義と、『新文学入門』を照らし合わせて、補完的に読むのが一番いいんだろうなあ。時間をおいて、もう一回読みたい。