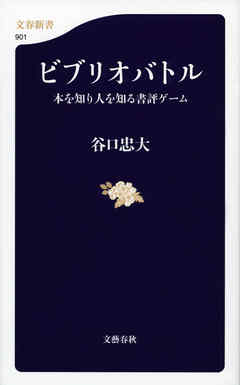あらすじ
おすすめの一冊を持ち合い、本の魅力を紹介しあう。ゲーム感覚を取り入れた新しい“書評”のかたちが、今、注目を集めています。「人を通して本を知る。本を通して人を知る」ことができる、それがビブリオバトルです。京都大学の研究室で生まれ、今や全国大会が催されるまでになったビブリオバトルの誕生秘話から遊び方まで、その全貌を発案者自らが書いた入門的一冊。書評は読むだけのものではなく、参加するもの。読書嫌いも本好きになること請け合いです。情報が多いネット時代だからこその、新しい本との出会いを提案します。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
ビブリオバトルという書評ゲームの奥深さを知れた本です。
これまでビブリオバトルのルールなどは、他の物語形式の本を読んでわかっていたけれど、ビブリオバトルができた経緯、存在意義などについて知ったのは初めてで、感動しました。
私もこんな風に何かを作りたいなと思います!
Posted by ブクログ
この本は深い。ビブリオバトルは深い。
単にビブリオバトルのやり方を書いてある本と思って手にしたが、いやいや、OMOの時代に大切なことや、最新のコミュニティマーケティングの肝になる部分もしっかり分析して伝えてくれる。理系の研究者の言葉の説得力は素晴らしいものがある。
Posted by ブクログ
発案者によるビブリオバトルの解説本である。その公式ルールから、発案に至った経緯、そのルール設計の工程などが詳しく説明されている。
この本を読めば、公式ルールの重要性やその意図するところはハッキリとわかる。なぜチャンプ本を決める必要があるのか、なぜ5分なのか、そうした公式ルールを破ることでビブリオバトルが意図する部分が損なわれる(可能性がある)ことが理解できるだろう。
イベントとしてのビブリオバトルが紹介されている一方で、物語仕立てで実際の実施する風景が著述されている点も、実施する上では参考になるだろう。
発案者の意図するところでは、家庭単位で行えるくらい身近な知的スポーツであるようだし、この本を読んで仲間内で始めるくらいの姿勢が望ましく思える。
某テレビ番組では「自分のお勧め本を紹介するなんて、××(下ネタ表現のため自主規制)を見せてるようなもんですよ」と、そうした考え方もあるため、ビブリオバトルそのものが万人に受け入れられるかというとまた別ものだろう。
そうした方への啓蒙としては機能しないが、より正しい形でビブリオバトルを行う上での教書としては適切な一冊である。内容に不足はなく、ここでは星五つで評価している。
Posted by ブクログ
「本を通して人を知る。人を通して本を知る。」という筆者の理論に感銘を受けました。ビブリオバトルは、読書活動だけでなく、コミュニケーション力やプレゼンテーション能力の向上にも繋がり、また、人と人との関係づくりにも繋がるなど、あらゆる可能性を感じました。
Posted by ブクログ
ビブリオバトルの考案者による、ビブリオバトルについての本です。発端は、著者が所属していた研究室で読書会を始めようとしたこと。従来の読書会では発表者以外読んでこなかったり、レジュメを読み上げるだけで退屈だったり、そもそもどの本を読むべきか判断できなかったりと、問題が多いと感じていたそうです。そこで、みんなが読むべき本をそれぞれプレゼンし、「チャンプ本」を改めて研究しようと考えた――それがビブリオバトルにつながったと知って驚きました。
研究室というコミュニティで始まったため、コミュニティ構成員によるビブリオバトルでは、回を重ねるごとに互いを深く知ることができます。コミュニケーションを深めることは目指していなかったにせよ、人を知るツールとして役立つことになりました。最初の思いつきがそのままの形で実現しなくても、思いつくことが重要なのだと感じます。
ちょっとした短編小説も挟まれ、ビブリオバトルの様子が具体的に描かれているだけでなく、ビブリオバトルがその後の人生にどう影響を与えたかも書かれており、楽しみながら読むことができました。
Posted by ブクログ
東京都知事の猪瀬さんも『解決する力』の中で推奨されていたりと、
ここ最近、意外と耳にすることが増えてきている、「ビブリオバトル」。
ルールは至極単純で、、
・参加者が読んで面白いと思った本を持ち寄る
・順番に1人5分で本を紹介する
・それぞれの発表後に、参加者全員で2-3分のディスカッションを行う
・全ての発表終了後に、「どの本が一番読みたくなったか?」を基準に、
参加者全員1票で行い、最多票の本を「チャンプ本」とする
と、人と本が集まれば、どこでも誰でもできる内容です。
ドッジボールやフットサルのようにすそ野を広げたいとは、なるほどと。
本の魅力を伝えるにも、相手の琴線に触れないと意味が無いので、
プレゼンやコミュニケーション能力等の「伝える力」を磨くのにも、いいなぁ、、と。
また、定期的に開催することで、読書に対するモチベーションの維持にもなりますしね。
実際に企業でも取り入れているところもあり、効果も出てきているとのこと。
個人的には、ちょっと前に「西荻夕市」でやっていたのを横目で見た位なのですが、
機会を見つけて是非一度、参加してみたいところ、、選書に悩みますけども。。
ブクブク交換なんかとも相性がよいのでしょうか
ビブリオに特化した朝活なんてのも面白そうかなぁ、、とも。
そんなに大規模なものでなく、4-5名で一時間程とかでも小気味よく行けそうです。
Posted by ブクログ
152〜160ページ辺りにビブリオバトルの本質が書かれている。バトルを通して、人を知る。そうしてコミュニケーションをとることで、豊かな時間を過ごすことができると思う。
Posted by ブクログ
ビブリオバトルのルール、成り立ち、目的、効果効用、世間への浸透具合が説明された本
最近、初めてビブリオバトルに参加してみてイメージしてたより楽しかったので読んでみた
読書会にはよく参加するけど、ビブリオバトルはやったことがなかった
「チャンプ本」を決める、という行為が本に優劣をつけているように思っていた
本はあくまであるだけで、それを読んでどう感じるかは人それぞれであって、どんな本でも特定の人にとっては唯一無二の本
なのに、限られた集団の中で発表の内容も含めてチャンプ本を決めるのは乱暴な気がしてた
でも、実際に参加してみると、チャンプ本に選ばれるのはその本を面白いと感じて他の人にも伝えたいという想いが伝わってくる発表をされた本
なるほど、確かに本を知ると共に人を知る事ができるなぁと思った
ビブリオバトルの発祥は工学部の情報系研究室の輪読会の選書からとのこと
著者が所属していた研究室の輪読会
発表者以外は読んでこなかったり、自分の担当意外の部分は理解は浅かったり、そもそもどの本を選ぶかという最初の問題がある
そこで、次に読む本を皆で持ち寄ってプレゼンし合い、一番得票数の多かった本を次回まで読んでくることにしたのが始まり
その後、本について話したい人は研究室内で話すし、読みたい人は勝手に読むという事で、チャンプ本を決めるだけの形式に落ち着いたらしい
☆ビブリオバトルのルール
1.発表参加者が読んで面白いと思った本を持って集まる
2.順番に一人5分間で本を紹介する
3.それぞれの発表の後に参加者全員でその発表に関するディスカッションを2~3分行う
4.全ての発表が終了した後に「どの本が一番読みたくなったか?」を基準とした投票を参加者全員一票で行い、最多票を集めたものを『チャンプ本』とする
基本ルールはこれだけ
他には、テーマを設けても良いとか、質疑応答は4チャンプ本を決めるための参考となるような質問にするとか、審査員等を設けずに参加者の投票で決めるとか
あと、紳士協定として発表者は自分以外の本に投票するとかくらい
その他の決まりは特になく、順番の決め方やタイトルの発表方法などは適宜決めて良い
レジュメや原稿の使用を禁止していないのは、チャンプ本に選ばれるためにはそういった物を使わない発表が必要になるため、必然的になくなるとのこと
ビブリオバトルの意義としてはいくつかあって
その一つは「本とどうやって出会うか?」という事
リアル書店で買うか、ネットで買うかといった議論よりも前に、その本を買おうと思ったのは何がきっかけか?
ネットでのレコメンドなどいくつかあるものの、自分の好みと類似したものがオススメされるので意外性がない
他の人に薦められるという経験はなかなかない
そこで、ビブリオバトルでの本の出会い
あと、ビブリオバトルは
「人を通して本を知る。本を通して人を知る」
という行為
そもそもチャンプ本を決める意義としては
ささやかな心理的インセンティブとしてのチャンプ本という動機づけ
発表者はチャンプ本に選ばれるように、発表するコミュニティに沿った選書になる
そこで聴衆への理解というコミュニケーションが発生する
聴講参加の人は、チャンプ本を決める一端を担うという責任感で発表を真剣に聞くようになる
だからこそ、単なる本のプレゼンだけで終わらずにチャンプ本を決めるルールが必要
チャンプ本に選ばれるため、チャンプ本を選ぶため、参加者は本をううじてお互いを理解しあう
ビブリオバトルの効果効用としては
まずは、本と出会える
本の内容を共有できる
お互いの理解が深まる
スピーチの訓練になる
著者としては、ビブリオバトルをもっと気軽に楽しめるようなもとして普及させたいとのこと
固有名詞ではなく一般名詞になるくらいになってほしいらしい
今はビブリオバトルがイベントとして行われていたりするが
フットサルやドッヂボールのように、気軽に人が集まって行われるようなもの
例えば、家族内でもいいし、最少人数3人でも開催できる
私は冒頭でも書いた通り、読書会にはよく参加するけどビブリオバトルの経験はまだ少ない
でも、小説や「BISビブリオバトル」、藤野恵美「ふたりの文化祭」でのビブリオバトルのシーンなど、何かと影響を受けて本を読んでいるわけで
普通の読書会だけじゃなくて、もっとビブリオバトルにも参加してもいいかもしれないと思った
Posted by ブクログ
ビブリオバトルの目的、よさについて理解できた。
・書籍情報共有機能
・スピーチ能力向上機能
・良書探索機能
数え切れない本の中から、良い本を選定するためのフィルター的機能がある。
・コミュニティ開発期間
紹介する本を通してその人を知ることができる。コミュニケーションの場づくりがビブリオバトルの本質である。
☆チャンプ本を決めることの意味
本を紹介するコミュニティに対して良書を選ぼうという動機付けのため、一方的でなく聞き手に一生懸命伝える努力をうながすために、チャンプ本を選ぶという仕組みか必要である。チャンプ本を決めるために投票する側もしっかり聞くようになる。
Posted by ブクログ
ビブリオバトル、面白そう!ってのがとりあえず一読の感想。プレゼン下手の治療にはもってこいだろうし、どうしても独りよがりに陥りがちな読書っていう営為に、思いも寄らない自己的ブレイクスルーをもたらしてくれそう。職場とか家庭で取り入れてみたい!っていう欲望が沸々。という意味では、本書の目論見は見事に果たされているってことですね。というか、本書そのものをビブバトしてみたい、って感じ。既にどこかではやられているんだろうけど。ただ、最初と最後の小説風パートは完全に蛇足。最終的には読み飛ばしたけど、何でこんなもの混ぜたんだろ?頁数(=収容スペース)の無駄です。
Posted by ブクログ
ビブリオバトルの起こってきた背景、本来目指しているものについて丁寧に書かれており、単なるビブリオのノウハウ的なものではなく、一読に値する内容。
情報検索という視点からのビブリオの有用性について述べている部分や、研究室での勉強会を活性化させるところに端を発しているところなど、とても納得がいく。確かに読書会でみんなが本を読んでくる状況を作るのは難しい。ただ、学校でビブリオをやってみようとすると、どうしても「本を知る」方に力点が行っしまい、本来のコミュニーケーションの視点が抜けてしまうのが残念・・・。
Posted by ブクログ
著者は、好きな本を1人1冊5分間で紹介しあい、どの本を読みたくなったかを投票で選ぶゲーム「ビブリオバトル」の創始者で、ルールや歴史が紹介されている。キャッチコピーは「人を通して本を知る。本を通して人を知る」。本との出会いの場となるだけではなく、参加者のコミュニケーション能力が高まり、学校、職場、地域などで行えばよいコミュニティを形成するのに役立つという。とても面白そうだ。
Posted by ブクログ
ビブリオバトルというゲームのルールは今の時代にあっていて、発明だと思う。
知識は人に結びついていうこと。文章は人(その人のバックグラウンド)により読まれ方が違う。
人格を持った一個人に知識が結びついてるからこそ、ダイナミックな活動の中でしか、人が人を理解したり、人が人を通して知識を得られない。
Posted by ブクログ
好きな本を持ち寄ってそれを推薦する5分のプレゼンを行い、それを競い合って一番を決めるというビブリオバトルの考案者による案内書である。世間に横溢する出版物はすでに読書歴を共有することが困難であることを示している。このゲームは自分の知らなかった本と出会うきっかけを与えてくれるという点で興味深い。
本書のサブタイトルが「本を知り人を知る書評ゲーム」であることが端的に示すように、筆者はこのゲームを通して人と人との深いコミュニケーションを図ってもいる。学術的な評論ではなく、アドリブを含めた5分間のパフォーマンスを軸としたのも、より人間的な要素を引き出す工夫になっている。
実は私は読書活動推進策の一つとして中学生にビブリオバトルを紹介することを考えている。これを完成させるためには、まずは自由に自分の意見を表現できる雰囲気をつくらなくてはならない。本書は京都大学などの大学生や院生といった「大人」の例が大半であるが、中等教育に導入するためにはそれなりの下地づくりも欠かせないと思った。
Posted by ブクログ
巷で話題のビブリオバトルの概要を一冊にまとめたもの。
そもそも、ビブリオバトルとはなにか。一言で言えば、「本を紹介するプレゼン大会」といえる。
何より、ビブリオバトルのルールは非常にシンプル。
・お気に入りの本を持参する
・順番に一人5分で紹介する!(+2~3分のディスカッション)
・「どの本を一番読みたくなったか?」で投票を行い チャンプ本を決める
プレゼン力も上がるし、みんなでワイワイ話して楽しめるなと思った。個人的にはこれを機会にやってみたいと思う。
Posted by ブクログ
これ、見るからに楽しそうです。
仕事で使えないか、検討中。
まぁ、あとは上司の頭がどれだけ柔らかくて、いろくなところにアンテナを伸ばせるかどうかですよねぇ。
今日、ちょっと話したらルール崩せ的なことを言ってました。
うーん、それではあんまり意味がない……というか、楽しくないなぁ。
まぁ、最終的には、上司関係なく、環境を無理矢理作って、やりたいことをやるというのが、わたしのスタイルではあるのですが。
まぁ、できることなら、楽しくやりたいですねぇ。
あと、前後の小説部分は、ちょっと蛇足かなあと思った。
この部分があるから、この本を手に取らない層もいるのではないかと思った。
Posted by ブクログ
ビブリオバトルとは、集まった人でオススメの本を紹介し合い、その中から一番読みたくなった本を決めるゲームです。この本は、そのビブリオバトルのルールや歴史から、なぜこのようなルール設計にしたかなどについてビブリオバトルの考案者が解説されているものです。
ビブリオバトルを通して新しい本に出会えるだけでなく、本の紹介を聞くことで相手の考えや背景を知ることができる、「本を通して人を知る」側面を考えてルール設計されている点が驚きだった。まだビブリオバトルは観たことしかないので、「本を通して人を知る」側面に触れるためにも発表者に挑戦してみたいと思いました。
Posted by ブクログ
Kさんのお勧め。
巷ではビブリオバトルという、
好きな本をプレゼンしあって賛同の数を競いあうのが
流行りつつあるらしいので、
読んでみた。
読書会というものにも参加したいことがないので、
何とも言えないが、
人が勧める本には興味があるので
とりあえず聴きに行ってみたい。
バトルの開催レポートに出てきた書籍を
思わずメモってしまいました。
Posted by ブクログ
とても簡単で、本と人となりを知れる強力なツールだ。実例も載っているが、チャンプ本は読みたくなる。
【公式ルール】
1 発表参加者が読んで面白いと思った本を持って集まる。
(テーマ設定しても可。コミュニティ内なら自然と絞られることも。)
2 順番に一人5分間で本を紹介する。
(5分ちょうどでタイムアップ。早く発表が終わってしまっても何かしゃべること。メモ程度なら良いが、原稿を読むととてもつまらなくなる。)
3 それぞれの発表の後に参加者全員でその発表に関するディスカッションを2~3分行う(質疑応答)。
(批評では無く、4の投票の為の追加質問の時間。)
4 全ての発表が終了した後に「どの本が一番読みたくなったか?」を基準とした投票を参加者全員一票で行い、最多票を集めたものを『チャンプ本』とする。
(紹介者は他の発表者の本に投票する。審査員を設定せず全員投票とすること。)
・大学には面白い学問があります。面白い研究もあります。ですが、キャンパス内をふらふら歩いていてもなかなか出会うことができません。そうした中でビブリオバトルは能動的に「面白い学問や面白い人に出会える場」を作っていけると思います。
・ビブリオバトルはルールが簡単で、他のイベントとの融合も可能なので、〇〇かけるビブリオバトルという掛け算がやりやすい。例えば、船で水辺探索×ビブリオバトル、お寺で朝のお勤め×ビブリオバトル、浴衣でバーベキュー×ビブリオバトル。
Posted by ブクログ
≪目次≫
はじめに ビブリオバトルって何?
プロローグ そんな日常の「ビブリオバトル」
第1章 ビブリオバトルの遊び方
第2章 ビブリオバトルはどうして生まれたのか?
第3章 本と出会い人を知るためのテクノロジー
第4章 広がるビブリオバトル
エピローグ いつか会えたら「ビブリオバトル」の話をしよう
≪内容≫
4つのシンプルなルールの基に、書評合戦をするゲーム「ビブリオバトル」。その発案者の著書。第2章はやや専門的な部分も見られるが、始める勇気があれば、だれでも始められるこの遊び(ゲーム)。第1章や第4章のゲームのやり方や実例を読みながら、実践してみたいと思った。
また、プロローグやエピローグの「ライトノベル」が実にいい味を出している。わかりやすさをより深めているのではないか?
Posted by ブクログ
ビブリオバトルの紹介・解説本.平易な文体で読みやすい.簡単なルールで効果が多様で大きそうで「開催してみたい」と思わせる.ゲーム自体も興味深いが,黎明期の試行錯誤や情報技術との関連性といった分析が更に面白い.あと,趣味丸出しのラノベパートもね.
Posted by ブクログ
人に本を薦める、薦められた本を読むというのは、一つのコミュニケーションとして重要であるし、そういうことを通じて、お互いを知り合う機会にもなる。ビブリオは書籍を表すラテン語由来の接頭辞であり、バトルは戦いを意味する、つまり、「本を使った戦い」というのが直訳だ。ビブリオバトルは、簡単に言ってしまえば「本の紹介ゲーム」だ、もう少しカッコ良く言えば、「書評を媒介としたコミュニケーションの場づくり手法」である。発表者は自分で面白いと思った本、みんなに紹介したいと思った本を持ってきて集まる、基本的に本のジャンルは問わない、小説でも専門書でも、漫画でも詩集でも、写真集でも円周率百万桁表でも構わない。ちなみに決めるのは『チャンプ』ではなく『チャンプ本』である、偉いのは本の方だ、「どの本が一番読みたくなったか?」という基準での投票を行い多数決でチャンプ本を決定する。
Posted by ブクログ
ビブリオバトル、面白いですよ!
やり方を知りたい人は、
本を読むよりHPを覗いた方がいいですね。
本書は、ビブリオバトルの歴史が綴られ、
それを味わうための本。
Posted by ブクログ
ビブリオバトルというものがあるというのは聞いたことがあったけど、起源が明確なものとは思わなかった。京都大学の輪読会が発祥というのはなんか納得できた。
書籍情報共有、スピーチ能力向上、良書探索、コミュニティ開発、いろんな効果があるんですね。
Posted by ブクログ
書評紹介なら、勝ち負けはいらないと抵抗感があったが、観客を意識して本を選び、プレゼンの仕方を工夫するというところで、闘争心をあおるきっかけとしての勝ち負け。そのうちに技術論、ビブリオバトルの勝ち方なんて言う事にならないだろうか。
Posted by ブクログ
ビブリオバトルの創設者による、ビブリオバトルについての本です。
ビブリオバトルが大学の研究室で生まれた経緯などが書かれています。
一つ一つのルールの意味を知れるので、なるほど、そこは参考になりました。
とにかく、本を紹介すれば、その紹介者の人柄がわかる、ということ。
私も生徒にやらせてみたけれど、本の紹介そのものは楽しんでいたように思います。
ビブリオバトルの小説チックな内容は読むのが辛かったかな…。
Posted by ブクログ
やってみたいなぁ。
この本をよんで、思っていたよりもハードルは高くないと思えた。
更に、思っていたよりも色んなメリットがありそうだと。
いいな。多くの人に本で楽しんでもらう仕掛け。
Posted by ブクログ
いろんな読み方で一生かけたって、日本で1年に出版される本の3年分しか読めない。こんな事実を突き付けられた。
ではどうやって読むべき本と出会うか、そのためのひとつがビブリオバトルということだ。
本書は、冒頭の「3年分」の事実を僕に突きつけながらも、ビブリオバトルの説明ばかり(当たり前だ、その本なのだから)。第三章の「本と出会い人を知るためのテクノロジー」が、僕にはとても面白かった。コミュニティはフィルタリング装置であり、ビブリオバトルもその一つ。やっぱりそこへ行くか。
イベントとしては面白いし手軽だけど、単に本と出会うコスト、としては高すぎる気がするのだけどなあ、どうなんでしょうか。副題にもあるように「人を知る」の方に重みがあるのかな。まあ、僕は一人でヒソヒソやりますよ…。う、うらやましくなんかないんだからね!