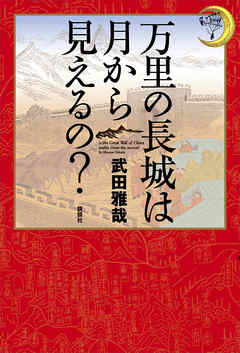あらすじ
宇宙飛行士もそう言った! ずっと教科書にも書いている! ヨーロッパ人も数百年間絶賛! ――で、本当のところはどうなの? 必要以上に巨大な「中国人の想像力」に肉薄する、長城伝説の図像学! 中国人宇宙飛行士が「見えません」と会見で答えたら、中国全土が大騒ぎ! 教科書問題が勃発し、なぜか歴史的事件になってしまった「長城騒動」の顛末を追いつつ、日本人もヨーロッパ人もダマされていた「長城伝説」を縦横に検証。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
中国の文化についていつも面白おかしくそして深く考察し、読者を中国文化の深層に誘ってくれる北海道大学教授武田雅哉先生の新刊です。タイトルに「万里の長城は月から見えるの?」と言っておきながら冒頭から「見えません」と即答しています。「万里の長城は地球から見える唯一(もしくはオランダの大堤防と2つだけ)の人工建造物」というフレーズは私も何度も聞いたことがあり、それに対してとくに疑問の何も持ちませんでした。まあ授業でこのことに触れたこともないので要するにとくに関心がなかったというだけですが、この本はのっけから「見えない」と断言していることからも分かるとおり、万里の長城が月(ないしは宇宙)から見える・見えないを科学的に考察した本ではありません。「月から見える」神話がどのように形成され、それに対して中国人がどのような態度をとってきたかを探り、ここから中国人の心性にアプローチする内容となっています。
もともと、「月(宇宙)から長城が見える」という神話は中国を見聞した西洋人によってまことしやかに囁かれていた中国文明が生んだ巨大建築を誇張的に形容する言葉でした。最初は「月の人」が長城を見ているとされ、それが19~20世紀前半になると月に住む知的生命体に、そして「天文学者の意見」と宇宙時代にふさわしい権威付けがなされました。そして1969年アームスロトングが月に降り立つと「彼が実際に見た」と(本人は言っていないにもかかわらず!)され、中国人に自分たちの文明への誇りと愛国心をもって受け入れられ、さまざまなメディアや教科書に取り上げられ、それは自明のものとなりました。そしてここから面白くなります。2003年、中国人初の宇宙飛行士となった楊利偉氏が地球帰還後のインタビューで「見えなかった」と言ったものだから中国では大騒動となります。客観的に考えれば、見えるはずはない(視力1.0の人だと幅約10メートルの長城は約35キロ上空で見えなくなるが、宇宙船は地球の軌道上を高度350キロで周回する。ちなみに月と地球の距離は38万キロ)のですが、これを素直に受け入れられない中国人は2つの態度をとります。一つは、「アメリカ人のでたらめな言葉を、正直な中国人が勇気を持って科学的態度でただした」という態度で、これだと中国人のプライドは傷つけられません。またもう一つの態度は、日本式に言うと「鳴かぬなら鳴かせてみしょうホトトギス」、つまりどうにかして宇宙から(月からはさすがに無茶だと分かっていたようで)見えるようにしようと、長城をサーチライトで照らしたり、肉眼で・・・のはずが望遠鏡などを使ってまで見よう(見せよう)としました。何か昔テレビタックルでやってたたま出版の韮沢さんと科学者の大槻教授のギャグみたいな論争を国家規模で大まじめにするものだから面白くて仕方がありません。
このような中国人(中国文化)を日本人と相容れないといって切り捨てるのは簡単です。しかし、武田先生のようにこれらを楽しく見守る態度も大事だと思います。そして、何よりそちらの方が絶対に面白い!
Posted by ブクログ
「月から(あるいは宇宙から)万里の長城が(肉眼で)見える」という都市伝説を検証した本。結局はうそっぱちなのだが,多くの文献を渉猟して,なぜそんな話が生れたのかまで考察する。
中国の宇宙開発で2003年に初の有人飛行をやったとき,帰還した飛行士が「長城見えなかったよ」と言って騒動になったらしい。日本ではあまり知られていないが,中国では国民的議論になったという。なんせ,教科書にも「万里の長城宇宙から見える」旨の記述があって,それを削除すべきかで侃々諤々。
たまたまその宇宙飛行士が運悪く見えなかったのではなくて,幅10メートルの長城が高度300kmの上空から見えないであろうことは,過去に何度も指摘されてきた。3km先から10cmの物を見るのと同じだから,双眼鏡でもない限りちょっと無理だろう。38万km遠くの月からなんて絶対無理だ。
ではなぜそんなガセネタが広まったのか?結局18世紀西洋のオリエンタル趣味から,万里の長城のすごさに尾鰭がついて,当初は修辞的形容だった「月の人にも見える」がどんどん変容していった。宇宙時代が来て,アポロ以降には「アームストロングが見えたと言ってた」までエスカレート。
もう百年も前から,科学者等によって否定がなされてきたが,なかなか普及せずこの都市伝説は生き残ってきた。2006年のNHK番組「探検ロマン世界遺産」でも放映されたとの由。結局,突飛でオモシロイ言説が根拠なしに信じられ,それに水を差す科学的意見は無視されるという,まあ都市伝説の都市伝説たるゆえんの作用が生み出したお話ということ。ちょっと前にQWERTY配列についてもそんな話を読んだな。
中国のすごいとこは,「アメリカ人が言い出したうそっぱち長城伝説に,我が国の宇宙飛行士が終止符を打った」と得意気なとこ。国威発揚に散々使っておきながら…。月へ行ったアメリカの宇宙飛行士たちは,一貫して明確に否定してたのに,いい面の皮だよな。
Posted by ブクログ
見えるのかと言えば、見えない。
当然なのだが、ではなぜ何時からそんな言葉が流布され、且つ彼の国ではどんな意味を持ってきて、これからどうなるのか。
とっても面白い。物理の本ではありません。
Posted by ブクログ
まず大前提として、タイトルの問は否、である。長細すぎて見えないそうな。
じゃあこの本は何?というと、この説が産まれた背景や、初の中国人宇宙飛行士の見えなかった証言から始まる一連の騒動を追いながら、中国をめぐる諸外国と、中国自身の想像力を覗こうという、著者曰く「長編エッセイ」。
で、この神話の始まりはどうも17世紀頃のヨーロッパ人が中国に来て、その大きさを表現するために、これは宇宙からも見えるに違いない!と書いたあたりから始まったっぽい。
で、天文学者をはじめ、色んな人がしばしば否定したものの、何時の間にか、20世紀に入るころには定着した模様。で、アームストロング船長の発言(のちに自ら訂正したけれども)で月から見えることになってしまう。
で、どうも見えない、となったときの中国での話が本書のミソ。教科書の話をどうする?アメリカがウソついたのを我らが中国の宇宙飛行士はホントのことを言ったetc…
ひとくくりに中国人、とするのは難しいですが、彼らの考え方や思考回路みたいなのをちょっと垣間見るような一冊。