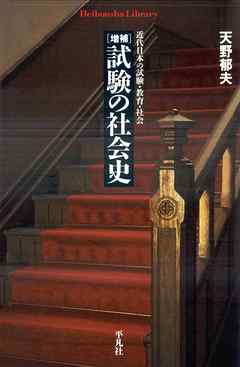あらすじ
※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。
学校生活のなかで繰り返されるテストや、入学試験・資格試験など、現代日本はまさに試験の社会といえる。明治維新期の日本は、近代化・産業化を図る手段として、中国の科挙を淵源とし、西欧の近代産業社会で発展した試験制度をきわめて積極的に取り入れ、活用していった。日本の学校教育と選抜のシステムはどのようにして作られたのか、そして試験社会はどのような功罪をもたらしたのか。豊富な事例をあげつつ検証する。
感情タグBEST3
Posted by ブクログ
結構読み切るのがしんどかった本。
(固有名詞&人物名の多い)史実の詳述に中ごろのページが割かれていて、
そういう本を読むことから遠ざかっていた身には、
要素要素を全体文脈の中で位置づけつつ読むような腕力が足りず・・・睡魔に誘われることがしばしば、だった。
本の構成としては、考察(大文脈)を明示しているのは、
1章 近代化と試験の時代 -2 一九世紀ヨーロッパの試験
~2章 試験と選抜の伝統 -2 私塾・試験・競争
まで。
ここで引用されるのが、
デュルケームの『フランス教育思想史』だったりする。
(苅谷先生の冬休みの集中ゼミで読んだ・・・多分大学在学中に読んだ中で一番分厚い&手に入りにくい本・・・あのゼミは楽しかったのですごい懐かしい・・・もっとも引用部分とか全然記憶なかったけどなっ)
デュルケームを引用して紹介されているのが、イエズス会のコレージュにおける試験の導入の状況と、その背景としての個人「個我の意識」の目覚めという「近代の接近を告げるもの」としての競争の意味。
コレージュは、何よりもまず「現世的な利益とはかかわりのない、名誉をかけた学習と競争の場」として設計された。
これにより「生徒の自尊心はためにたえず過敏状態に」おかれ、
「生徒がその中で生活していた不断の競争状態は、生徒をしてその知力、意欲の全活動力を緊張せしめ、しかもそれを必然のことたらしめていた」。(p68)
自我の観念に目覚めた人間において、初めて競争に勝つという名誉が、学習への動機づけとして意味をなす。
コレージュでの教育が(ある種の)成功を収めた背景には、近代的個人としての自我の目覚めがあったという考察。
但し、デュルケームは、コレージュは(競争)試験の導入という教育システム上は「近代」の先駆けだったが、内容的には空虚であったとしている。
「生徒をはげしい、形式的な、しかし内容のない勉強に導くためには、姓との周囲を監視的配慮でとりまき、それを強化するだけでは足りないのである。
つまり・・さらに生徒に刺激を与えることが必要であった。
このためジェスイットが用いた刺激は、もっぱら競争心であった。」(p30)
(学習内容に関係なく)学習への意欲を刺激する方便、というのが、この著作の前提としての試験観になる。
*
2章 試験と選抜の伝統 - 2 私塾・試験・競争
で示されるのは、江戸時代の私塾(咸宜園、適塾)において、
競争(試験)が時代に先行して取り入れられていたか。
江戸時代末期の私塾内部においては、塾生は一定のレベルで
家やその後の出世栄達へのルートと切り離された、つまり「個人として」の学力レベルや入学年次により位置づけられていた。
明治政府設立時メンバーの多くが、こうした私塾において「競争の中での個人」という自我形成を経験していたからこそ、
明治政府に対し、東大設立時のお雇い外国人ダビット・モルレーが具体的に提言した、近代学校制度における試験の導入がすんなりと受け入れられたのではないか(と、2章⇒1章に振り返るかたちで「試験ことはじめ」が語られる)
*
3章以降は、明治政府において試験制度がどのように導入されていったかを学制の変遷とともに詳述される。
(いまも残る有名大学の設立経緯なんかが記述されているのでその意味では面白い。
官立大学の受験予備校として発足した私立大学とか・・・)
長い長い記述を経て語られるのは、
なぜ日本が欧米のような「卒業試験の国」ではなく、「入学試験の国」になったのかという事情。
ものすごくざっくり要約すると、高等教育機関としての大学と、初等教育機関としての小学校とが別々に、しかし同時期に作られた日本では、
小学校卒業=大学入学に足りるだけの学力を身に着けた者、とはならなかったということ。
特にネックになったのが語学力。
大学で行われる英語での授業を理解し得るだけの語学力を身に着けさせるような教育施しうるような、体系だった初等/中等教育機関を公的に作り出すことが難しかった。
この為、卒業試験とは別に、入学時にフィルタリングを行う必要があった、という。ような、話。
だった、気がする。