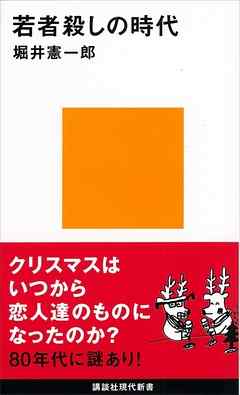あらすじ
ずんずん調査のホリイ博士が80年代と対峙。クリスマス・ファシズムの勃興、回転ベッドの衰退、浮遊する月9ドラマ、宮崎勤事件、バブル絶頂期の「一杯のかけそば」騒動……あの時なにが葬られたのか? (講談社現代新書)
...続きを読む感情タグBEST3
このページにはネタバレを含むレビューが表示されています
Posted by ブクログ
新書としてはべらぼうに軽くて読みやすい。
恋人と過ごすクリスマスをはじめ、バレンタインデーのチョコレート、デートスポットとしてのディズニーランド、携帯電話、マンガ、月9ドラマ、単位が「来る」という表現などといった、今の若者を取り巻く仕組みが、いつから、どのようにして生まれてきたのかについて、当時のドラマや漫研の資料、雑誌などを用いて解説している。
ただ、もっと突っ込んで欲しかった部分も多い。例えば、「内にこもるな。外へ出でよ。仲間と遊べ」というスローガンはどこから出てきたのかとか。
「こういう時代があった」という事実関係を楽しむ本としての性格が強い。
Posted by ブクログ
もはやインパクトのあるタイトルで勝負!ってのは新書界での常識なのでしょうか。
非常に社会学的で、各年代の若者たちを追った内容は単純に興味深かった。雑誌アンアンの1983歴史的宣言が、クリスマスを「パーティー」から「恋人たちの夜」とするクリスマス・ファシズムの走りだとか。ホームドラマが衰退し、トレンディドラマが台頭してきたあたりに若者はアウトドア派(サーフィン、スノボ)とインドア派(オタク)に二分されたとか。1997年、若者が携帯電話で覆い尽くされてしまったとか。例を挙げたらキリが無いのだが。
自分のお誕生日に、いったいいくつメールが来たか。そのメールの数で「いま存在する世界の中で、あなたの誕生日を覚えていて、祝ってくれる気持ちのあったすべてのひとの数」が示されるのだ。逃げようがない。来てない人は、誕生日を知らないか忘れたかどうでもいいと思った人なのだ。それがきちんと数字になって示される。
こういう考え方をすると本当に生きにくい感じがする世の中。携帯電話を破壊して、ようやく世界と繋がったってうたってたのは誰だっけ。
最後までしっかり読めば、何故「若者殺しの時代」なのかわかる。平易な文体なので読みやすい。首尾一貫しているとは言えないがそこはご愛嬌。最後に「戦う」か「逃げる」かという選択肢が提示されているが、「ニート」とは逃げようとして現代に捕まってしまった若者たちの総称らしい。この本によると。
Posted by ブクログ
2006年。80年代あたりの、若者たちが消費の奴隷化されてクリスマスやバレンタイン、いわゆるトレンディドラマに踊らされていく感じを書いている。曖昧模糊といえばまあそんな感じもするのだが、時代の雰囲気を語るとはこういうことではないのか。
後半の予測みたいなものも、2021年の俺から見ると結構当たってると思う。最後のアドバイスについても、かなり正しいと思う。
Posted by ブクログ
若者は、「若者」というくくりをつけられた上で、ある一定の方向性に誘導させられ、搾取させられてきた。例えば、「クリスマスは彼女とリッチに過ごす(1983)」だったり、「バレンタインにチョコレートをあげる(1977)」などである。
これらは、1980年代に女性主導で起こった。ディズニーランドも1987年あたりで聖地化した。これらは、女性主導で行われた。ラブホテルから回転ベッドなどの面妖さが抜け、女性好みのシンプルさになっていったのも、その一環だと思われる。女性の要求は、洗練され細分化された形で事前に用意された。
1980年代後半にはコンビニが普及し、人々が「無駄な消費」を覚えた。水や茶の販売も始まった(それまでは自販機でもジュースしか売っていなかった)。
1959年には漫画の認知度は低く、始めてサンデーとマガジンが連載開始した。1960年代から徐々に人口に膾炙し始め、サブカルチャーの普及とともに1970年代には大学生でも一般化した(ただ、1960年末は学生運動が本格化していたため、それどころではなかった。)。80年代には「ネクラ」と「ネアカ」の二分化が始まり、漫画執筆はネクラにカテゴライズされた。ここまではカルチャーとしての漫画だったが、想像上の擬似世界としての漫画を消費する傾向が高まり、それが「おたく」だった。ネアカになりきれない連中が、おたくとして存在した。そして、89年の宮崎勤事件(おたくが性犯罪者と結び付けられた事件)を機に、おたくは忌避すべき存在となった。
1990年以前はホームドラマが中心だったが、それ以降はトレンディドラマ(トレンドを中心にした恋愛)が中心になった。91年の「東京ラブストーリー」が契機になり、月9が形成された。女性は「折れない」生き方が理想になった。女性は処女性を捨て、91年からはきれいな女性がアダルトビデオに出演するようになった。一瞬ポケベルの時代があったが、97年からは携帯が安価になり、普及し始めた。その結果、常にあらゆるところとつながることになった。
何にせよ、あらゆるものが商品化され、金に買えられていった。