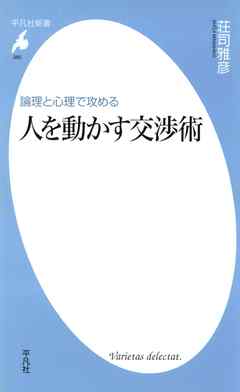あらすじ
※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。
交渉には「確かな方法」がある。それは、単なる経験として語られるものではなく、理論の裏づけがなければならない。数多くの案件を、誰よりも早く、そして円満に解決し続けてきた弁護士が、交渉に必須の「論理」と「心理」をわかりやすく伝授。確実に身につき、役立つ、実戦で負けない交渉術。
感情タグBEST3
Posted by ブクログ
交渉術といえば交渉術なのだが、ゲーム理論やクリティカルシンキング、ストーリー理論などを簡易に説明し、また人が行動する時の心理的要因の分析などもまとめている。
心理学やマーケティング、経営論などを学んでいる時に、おさらいを兼ねて軽く読むことがいい方法かも。
Posted by ブクログ
交渉は相手が誰であれ対等。
まず話を聴く。聴くことがコミュニケーションのもっとも根本的な要素。
相手に話をさせることで相手の主張を全て出させる。その後、こちらが話をする。
交渉の参加者には事前の相談、事前の一言を忘れない。
小さな貸しから譲歩を引き出す(door in the faceテクニック)
YESを重ねて条件を引き出す(foot in the doorテクニック)
権威ある材料が多くあると交渉のイニシアティブを取り易い。
情報伝達の手段としてストーリーが効果的。それは相手の頭脳だけでなく心情に訴える。
交渉の場で心情に訴えるには身近な具体例がよい。ストーリーの構成は誘引、期待、満足。
ゲーム理論は相手の行動を想定して戦略を立てる際に有効である。
交渉力を強化するにはコミットメントが効く。背水の陣で望むことも必要である。またシグナリングを使い自分の立場を戦略的に良くすることも出来る。つまり相手に自分の情報を送り相手を牽制する戦略も有効である。
主張を論理的に展開するツールがクリティカルシンキング。そのツールには演繹法と帰納法がある。これはあくまで仮説を立てる為のツールである。交渉にあたっては事前に幾つかの仮説を立てて臨むことが大切である。また相手を説得する為には当方の主張をピラミッド構造に組み立ててしっかりとした理由づけが不可欠。かつ相手のピラミッド構造を把握することで的確な反論も可能になる。
ピラミッド構造とは主張、結論を設定してその下に理由や根拠を記し、さらにその下にその理由や根拠が出てきた事実を記す。
大切な交渉の時は服装にも気を配る。話し方も重要である。時間を限定して相手の決断を促す。交渉場所はホームが必ずしも有利ではないが、近場の方がよい。内部に強硬派、悪者を作り言いにくい回答を言う。いわゆるなだめたり、すかしたりすることが有効である。別れ際の雑談にも注意する。情報は色々な所から漏れる。
新書で読み易い。自分にも気を付けて取り入れる。
Posted by ブクログ
交渉術を非常に読みやすくまとめた本
深く突っ込んで書いていないので、実践的とも思える。
少し気になるのが著者の過去実例が「自慢」とも取れる
書き方となっておいる点。また実例をあげるときに
「私の記憶では●●だったので、実際には違うかも
しれませんが」といった表現。(確かに重要な要素
ではないが、それならば調べるか、書かなければよいのに)
交渉術を色々と勉強している人には全く役に立たないが
興味をもって勉強をしてみようか、という人には最適な
本ではなかろうか
●メモ
・交渉相手はどのような人物であれ「常識を備えた対等な
人間」と考える
・常に丁寧な話し方を続ければ、相手も感化される
・相手の主張を理解するところから始める
・相手とのつながりを見つけて、空気を和ませる
(和解の方向をつくる)
・人は決定に不満がなくても、プロセスに不満があれば
不満をもつ
・権威の材料を沢山持つと説得性が増す
・プレゼンテーションではストーリーを作る
誘因→期待→満足
・Aさんは550万円以内で買いたい
Bさんは500万円以上で売りたい
この50万円のパイをどう分けるかが交渉
・裁判では敗訴することもある。
敗訴の論理が間違っているわけではない。
ロジックがすべてではない
・言葉よりも相手が受け取る情報は「声の威力」が大きい
Posted by ブクログ
荘司雅彦著「人を動かす交渉術」平凡社出版(2007)
この本は従来の交渉を対立と考えるハードな交渉述も、交渉社同士の関係を重視するソフトな交渉術超えた、共通の利益を出来るだけ見いだすというウィンウィンの関係の実践本としての考え方を強くだしてる。交渉というと以前までは経験者の経験を綴った本など、概念がしっかりしていなかったが、ハーバード大学によって交渉が学問として発達してきた頃から、このウィンウィンの関係を軸とした交渉学というのもが研究の結果知られるようになってきた。アメリカでは、1980年代から盛んに交渉術が実践的な学問として重視されてきたのですが、日本はというと、「阿吽の呼吸」や「場の空気」で物事が決まって行く事が多くあり交渉としうて他人行儀的なことはあまり好まれていなかった。ところが2000年以降、グローバリゼーションという波が日本にも押し寄せ、海外とのビジネスに交渉が必要な場が多く出てくることとなる。この交渉を円滑に進めるためのツールが交渉学、交渉術、という学問という位置づけがされている。
*交渉は相手が誰であれ対等である。常識を備えた対等な人間であることを前提とすべきです。そして対等な交渉相手としての敬意を払う事を忘れては行けません。
*相手の「主張の価値」を身と得る。相手の主張には意味があることを認識して、しっかり聞く事が大切。決して相手の主張を認めたり肯定したりすることではなく、とうていのめないような主張であっても常識ある人間と交渉している以上、相手のいい分にはそれなりの意味を認め、拒絶しないことが重要
*相手の主張を全部聞いた後で、以上ですべてでしょうか?と念押しをすることが大切。これですべてだ!ということになったら、この段階で相手の主張が全部でたという既成事実を創り上げる事ができる。主張をすべて出させるという事は、隠し球や後だしを封じてしまえ、重要な要素となる。
*相手とのつながりをとっかりに話を進めるのは意義がある。相手とのつながりをさぐるというのは、交渉相手との共通点を見つけてそれを示す事です。これにより最初のアイスブレイクができリラックスした雰囲気を創り出せる。
*人間あその決定そのものに不満があんくても、その決定プロセスに全く参加させられなかったような場合は多いに不満を抱く事がある。そのため、交渉においても場所の設定、参加メンバー、予定時間などは打ち合わせ、その決定プロセスに相手を参加させることが重要である。
Posted by ブクログ
[ 内容 ]
交渉には「確かな方法」がある。
それは、単なる経験として語られるものではなく、理論の裏づけがなければならない。
数多くの案件を、誰よりも早く、そして円満に解決し続けてきた弁護士が、交渉に必須の「論理」と「心理」をわかりやすく伝授。
確実に身につき、役立つ、実戦で負けない交渉術。
[ 目次 ]
第1章 相手の心をつかむ-交渉の心理学(アメリカでは交渉心理を学ぶ時代 グローバリゼーション時代の交渉 ほか)
第2章 心を揺さぶる、感性の交渉-ストーリー理論(人は理屈で動かない なぜ塚田氏のプレゼンが受けなかったのか? ほか)
第3章 落としどころを見極める-ゲーム理論(なぜ交渉で「ゲーム理論」が必要になるのか ゲーム理論とは? ほか)
第4章 確実に攻めるためのツール-クリティカル・シンキング(なぜクリティカル・シンキングが重要なのか クリティカル・シンキングとは? ほか)
第5章 機先を制する交渉のスタイル(ちょっとしたことで、後手に回ることも 交渉のときの服装 ほか)
[ POP ]
[ おすすめ度 ]
☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度
☆☆☆☆☆☆☆ 文章
☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー
☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性
☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性
☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度
共感度(空振り三振・一部・参った!)
読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ)
[ 関連図書 ]
[ 参考となる書評 ]
Posted by ブクログ
【読者】 ビジネスから日常生活まで大小問わず交渉に関わる人
【目的】 理論と経験知を融合させた普遍的かつ実践的な交渉スキルの提供
【一押】 著者の実体験に裏打ちされた具体的な対処例。コンパクトにまとめられた交渉におけるツールの紹介
【概要】 交渉術とは、究極的に社会全体の利益を高めることを目的としたスキルで、理論と実際の経験知の融合によって生み出されるスキルである。そこでは、心理学やストーリー理論、ゲーム理論にクリティカルシンキング、そして機先を制する交渉スタイルが求められてくる。心理学では、人間の返報性や一貫性、権威への従属性を利用する。ただし、相手を対等な交渉相手として敬意を持って接することを忘れない。ストーリー理論は、①誘因、②期待、③満足というストーリーを展開することで相手の心情を揺さぶるものである。データだけでは動かない相手に有効。ゲーム理論は、相手の戦略をもとに落としどころを探る上で有用。交渉における武器は「代替的選択肢」、「オプション」、「時間的コスト」、「情報」の4つがある。また、時間を決めるなどの「コミットメント」も活用できる。クリティカル・シンキングは、論理的に批判検証するための思考ツール。演繹法と帰納法で交渉前に仮説を立てておく。その際、ピラミッド構造、ゼロベース思考を意識することも重要。
【感想】 自分は今まで交渉において人間関係を崩したくないあまり、なあなあでやろうとすることが多かった。だが、今後ビジネスではそういう姿勢は通じないため、本書に書かれているようなポイントを最低限押さえて、交渉に当たるようにしたい。特に仮説思考とストーリー理論は、小手先ではなく本質的に自分のなかに落とし込んでいく必要があると感じた。
Posted by ブクログ
新書の帯の著者の顔をみると、難しい本なのかな?と思いますが、読んでみると軽い語り口で読みやすいです。弁護士である著者が長年の経験から得た交渉のコツがまとまられています。ゲーム理論、クリティカルシンキングなどの考え方がわかりやすく説明されていたところが良かったです。
Posted by ブクログ
実践できそうな目新しいアイデアが多少含まれている。
※ドア・イン・ザ・フェース・テクニック
最初に大きな要求をして譲歩するという「貸し」をつくってから目的を果たす。
※フット・イン・ザ・ドア・テクニック
一貫性を保ちたいという人間の心理があるため自己判断を擁護する煩悩を利用。
小さなコミットメントから始めて大きな要求をしていく。
まず最初に小さなイエスを言わせる。
※将来の目的を手帖に書きこむと実現しやすくなる。
行為に一貫性が保てるよう自己制約するようになるから。
Posted by ブクログ
理屈だけで人は動かないということは、ある低程度のビジネス経験のある人であれば経験的に理解していると思われることから、本書の主張する心理学的アプローチは、それほど新しい概念という訳ではない。但し、本書は事例や参考文献等により、主張するアプローチを非常に判りやすく説明しており、交渉経験の乏しい人でも実践に使えるような内容になっていることから、有用であると思う。
Posted by ブクログ
瀧本さんの武器としての交渉思考
読んだあとに読みました。
良書で共に大事と言われている点は、
おおかたかぶっていて、やはりそこが
大事なのだな。
この本を読んだことで、「交渉」についての考え方と
取り組み方の方法がより定まりました。