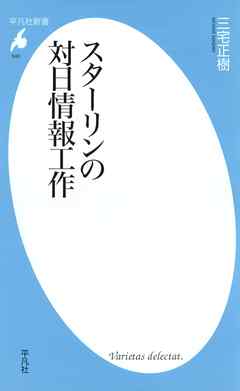あらすじ
※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。
日独防共協定の内容を締結前から完全に把握していたクリヴィツキー、東京を基点に強大な情報網を築き上げたゾルゲ、そして、一九四一年六月に始まった独ソ戦以後の日本の動きについて、核心に迫る情報をモスクワに流していた日本人スパイ「エコノミスト」。スターリン体制下におけるソ連の対日情報工作の多面的な実相を描く。
感情タグBEST3
Posted by ブクログ
◆その1 (11月11日記述)◆
「クリヴィツキー」という名前を見たらほおっておけないのが、逢坂剛症候群というか、逢坂剛ファンというか、そう、彼はその名もずばり『クリヴィツキー症候群』(1990年)という小説で、私たちの脳裏に旧ソ連のスパイのウオルター・ゲルマノヴィッチ・クリヴィツキーこと本名サミュエル・ギンスブルクのことを深く刻み込んだのですが、こうして律義に読んでいる本の引用本とか参考文献や出典やなんかまでさかのぼっての読書を実行して来て早や幾年月。
狭く深くもいいけれど、広く浅くじゃないこういう広く深くへの志向が、はたしてどこまで凡人の力量で出来るものやら心細いかぎりですが、すでに帆は張られ風に乗って走り始めたのだから、もうあとは地の果てまで行くしかないでしょう。
スパイといえば、遅れて来た映画・ドラマ愛好家として007ジェームズ・ボンドか0011ナポレオン・ソロしか知らない私ですが、いくらなんでもリヒャルト・ゾルゲの名前は思い浮かばないはずはなく、それもそのはずで篠田正浩監督の映画『スパイ・ゾルゲ』(2003年)は、なんとわが愛する上川隆也が仰天の特高役で出演しているものですから、もう何度見たかわかりません。
それに、関与というか共謀して死刑になった尾崎秀実の異母弟である尾崎秀樹は、私が敬愛してほとんどの著作を読んでいる作家・評論家ですが、『ゾルゲ事件 尾崎秀実の理想と挫折』(中公文庫)、『生きているユダ ゾルゲ事件 その戦後への証言』(角川文庫)、『上海 1930年』(岩波新書)など、この事件についてはやはりひとかたならない力の入れようです。
◆その2 (11月15日記述)◆
本書は、その著書『日独伊三国同盟の研究』(1975年)や、編著の『昭和史の軍部と政治』全5巻(1983年)などで著名な、わが国におけるこの方面の先駆的研究者にして重鎮の三宅正樹教授が、一般向けに書かれた『スターリン、ヒットラーと日ソ独伊連合構想』(2007年、朝日選書)の後さらによりコンパクトなかたちで、でも、いささかもインパクトを失わない精密さで、第二次世界大戦時のソ連による日本への情報介入のパノラマを鮮明に描かれたもので、けっして新書といっても侮れない読み応えがある本です。
ゾルゲもクリヴィツキーも鮮やかに登場しますが、もうひとり謎の日本人スパイ=エコノミストと呼ばれる人物のほうが大いに気になるところで興味津々ですが、考えてみればスパイという存在、まだまだ影が薄くなったということはなく、そういえばつい先日もアンナ・チャップマンというアメリカでソ連の美人スパイが逮捕されて国外追放になったというお話がありましたっけ。
Posted by ブクログ
●:引用
●スターリンの対日工作をめぐっては、ゾルゲの諜報活動がもっともよく知られていて、厖大な研究が積み重ねられている。しかし、スターリンの側では、特に1941年6月の独ソ開戦直後に、日本がソ連への武力攻撃に踏み切るかどうかを判断するに際して、ゾルゲの情報だけに全面的に依存していたとは考えられない。(略)おそらくスターリンは、ゾルゲや「エコノミスト」などの複数の情報を慎重に比較検討した上で、極東ソ連軍の西方への移動を決断したのであろう。
●それにしても、当時の日本の国家機密が、日独防共協定をめぐるベルリン駐在武官大島浩とナチ党の外交担当者であったリッペントロップとの秘密交渉の一切から始まって、対ソ戦争開始をさしあたり見送った1941年7月2日と9月6日の御前会議の議事にいたるまで、すべてソ連に、最終的にはスターリンに筒抜けであったことに、あらためて驚かされる。
●当時の日本の情報管理が拙劣であったことも、同じように特筆大書されるべきであろう。当時、「防諜」ということが叫ばれ、街角のいたるところに、スパイは貴方のすぐそばにいるというようなことを書いたポスターが貼ってあったと記憶しているが、この「防諜」、すなわち国家の機密情報の管理をめぐって、当時の日本はいたるところ穴だらけであった。