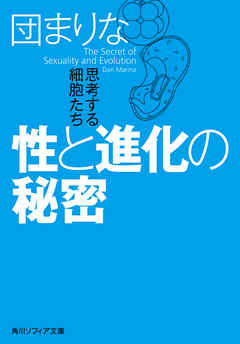あらすじ
三八億年前、とてつもない偶然が重なり、たった一つの細胞が誕生する。この細胞が人間のような複雑な生物へ進化したのは何故か。「細胞は考える」という観点から、生命と性の秘密を易しく解きあかす生物学入門。
...続きを読む感情タグBEST3
このページにはネタバレを含むレビューが表示されています
Posted by ブクログ
読み応えのある本である。
題名だけ見たときは、なぜオスはメスに惹かれるかなんてことを遺伝子と引っかけて書いてる本かと思っていたのだが、さにあらずである。養老孟司が「読み応えのある本ですから、懸命に読んでくださいね」と書くぐらいである。
本の主題は、生物の階層性(自然界にある物質の性格であり、上位の階層は下位の階層にない機能を持つ)と言う事である。原核細胞があるとき真核細胞にステップアップしたのであるが、真核細胞は飢餓状態になると合体して飢餓状態を乗り越えることをシステムとして行うことができるようになったのであります。
一単位の真核細胞はハプロイド細胞、合体したのがディプロイド細胞とよぶのだが、ディプロイド細胞は染色体を二組持つ。ハプロイド細胞もディプロイド細胞も構造はほとんど同じなのに、ディプロイドになると細胞間で仕事の役割分担ができるようになる。私たちが普段目にする生物は自分自身を含め大抵はディプロイド細胞でできている。コケ類や藻類の中にはハプロイド細胞が集まっただけの生物もいるらしい。
ところが、ハプロイド細胞が際限なく細胞分裂を繰り返すことができるのに対しディプロイド細胞は細胞分裂に制限回数があって制限回数に達すると死んでしまうのである。なぜかは不明。人間の細胞の場合52回ほど分裂すると死んでしまうらしい。
これを克服するために生まれたのが減数分裂によってハプロイド状態にもどってから再度合体する方法。このことは、生物が自分のアイデンティティを変えずに(人間なら人間、変えるならカエルという種で有り続けながら)複雑さの違う単位、階層の間を行き来するということである。同じものであり続けながら自分の複雑さを変えるというような事は自然界では外には見られないことである。
教科書では「遺伝子の組み換えが、有性生殖の本質である(目的である)」と書かれているが「有性生殖とは、生物が自分の『種』としてのアイデンティティを保ったまあm、ディプロイドとハプロイドという二つの階層を行き来して、ディプロイド細胞が運命づけられている、分裂の限界を克服するためのしくみ」というのが正しいという事だそうだ。その仕組みの中に次第にDNAを繕ったり組み替えたりする仕組みを重ねてきたという事である。
次の主題は、「DNAが決めていることは種よりもずっと階層的に下のレベルのことで、そこがいくら変わっても、上のレベルの種までは影響がおよばない」という事。
大腸菌に人間のインシュリンの遺伝子を入れるとインシュリンを生成する大腸菌ができるが大腸菌が大腸菌で無くなるわけではない。
種とはもっと複雑なもので、遺伝子から種の謎に迫ることはできない。
さらに「私たちはDNAだけでなく、配偶子という二匹の細胞の合体によって、ヒトとしての基本的内容のすべてを遺伝している」遺伝的プログラムが意味するものは、DNA上の情報などより遙かに複雑で多岐にわたる。
遺伝プログラムは、DNAではなく、細胞質、又は細胞構造そのものに書き込まれている。「ヒトとしての基本的な内容の全て」に至る鍵の多くは、受精卵の細胞質部分に潜んでいるはず。
と言う事で、遺伝というのは卵子=女性の細胞で引き継がれており、男性はそれにDNAという些末な情報を提供しているに過ぎないという事であります。