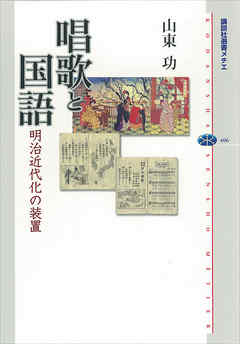あらすじ
「蛍の光」「「埴生の宿」から見える明治史。明治という近代化の時代、西洋を受容しあらたな「日本」を模索するなかで、なぜ「歌」が必要だったのか。日本語の「文法」と「唱歌」をめぐる知られざる歴史。(講談社選書メチエ)
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
明治時代に唱歌がどのように生まれ、広まっていったか、唱歌教育の歴史を「国語」や「文法」の成立と発展と関連させながら論じた本。…というよりは、唱歌を切り口にして明治期の文法研究がどのようなものか述べた、と言った方が近いかもしれない。伊沢修二に代表される音楽取調掛という文部省の機関が、「文法書を編纂していた」(p.95)という事実、つまり「唱歌歌詞に関しては、国語教育関係者が多数参加した結果、音楽取調掛員が文法書も編纂していたという事実」(同)をどう捉えるか、という話。「国語教育の中から唱歌教育は誕生した」(p.21)とも言える、ということ。
『指揮者の仕事』という本で、『指揮法教程』というバイブル的?な本の著者の父が齊藤秀三郎、というのを初めて知ったが、この本では冒頭にその事実が紹介され、指揮法の齊藤秀雄が音楽における「文法」を説いた(p.3)、という話からスタートする。
音楽科教育では、「豊かな感性」ということが謳われるのだけれど、もしかするとそれは元を辿れば明治期に唱えられた、「教育は『徳育』『智育』『体育』の三点が重要であり、特に『徳育』としての徳性を養うためには、音楽が大変有効であるとしている。音楽には人の心を正し風化を助ける働きがあるからで、このことはすでに歴史的、世界的に見ても明らかであると言うのである。これは一種の徳目主義である。」(p.22)というあたりに遡れるのではないか、と思った。
次に「国楽」創生の話が出てきて、君が代の話になるけれど、君が代のあの独特なメロディーは雅楽がモチーフになってるのか、というのはこの本で初めて知った。「現在の国歌にあたる『君が代』は宮内省式部寮雅楽課伶人長の林広守撰譜、エッケルト編曲のもので、これには雅楽の壱越律旋「君カ代」の譜も存在する。」(p.31)ということだ。「エッケルトは雅楽のメロディーである『君が代』を編曲するにあたって、最初と最後に和声を加えずユニゾン(同じ音)で通している。これは原曲が雅楽であることを考えてみれば当然のことであり、下手な和声を最初からつけてしまえば曲調は一変し、それこそ『我々日本人の特質を見事に象徴』するものにはならなかったであろう。それならば『我々の心そのもの』を体現化させたのは外国人ということになるだろう。もしかすると、国歌斉唱に際して時折耳にする不思議な音程は、西洋音階の音程に慣れきってしまった耳に対する声の抵抗だったのだろうか。一番の最初のD(レの音)が不安定で、『やちよに』のDが異常に高くなるのは、雅楽の音程からくる『我々の心そのもの』の影響なのかもしれない。」(pp.33-4)ということらしい。途中から歌いにくい、という話になっているが、「『君が代』の冒頭のDを正確に大きく出せるのは、相当音楽的な訓練を受けた者だけであろう。」(同)という、不思議な曲なんだなあと思う。
あと、「歌詞が単なる暗記要素に堕していく」(p.111)という話があったが、この時代の唱歌はとても極端で、ある意味、愉快。「堺市の人口が約六万人であるというのはまだよいとしても、なぜ水道管が十三里分延長されたことを、わざわざ声に出して歌わなければならないのであろうか。」(p.126)とか、今でも歌われる有名な鉄道唱歌も「新橋では気合が入っていた歌詞も、大阪あたりでは(略)車掌の停車駅案内のよう」(p.128)になったりする。そして暗記するための音楽は、「ヨナヌキ調、ピョンコ節、七五調の三点が、装置としての『唱歌』の基本的な文法」(p.129)ということで、音楽の創作の授業とかでこの3つを条件に唱歌風の歌を創作させる、なんて面白いのではないかと思った。
まとめると、「伊沢修二という強烈な個性のもとに編纂された『小学唱歌集』は、文法への模索と同様に『国楽』創生を模索する中で成立したものであった。国楽創生という形で求められる音楽は、日本における『雅』の創生として意識されており、この雅へのまなざしは西洋音楽の受容という過程において、それまでの日本音楽を『俗』と定置する形で形成されていった」(p.173)という話。ちなみに「伊沢修二は若い頃に進軍曲を学んでいたが、それにもかかわらずアメリカの師範学校在学中には音楽の履修に大変苦労していた。伊沢自身の回想する『終日くやし涙に泣き暮らしたることありき』という挫折経験が唱歌導入の情熱へと通じていったはずだが、それほどまでに日本人にとって西洋音楽習得は困難であったということだろう。」(p.201)というのは興味深い。
最後に、近代化の装置として使われた唱歌のあり方についての議論があるが、問題となるのは「規律化をされる側が、規律化の意識とは離れた段階で進んでいくことに対して、何ら疑問を感じないという点」(p.203)ということだそうだ。暗記そのものが楽しいので、下手をすると不適切なものも暗記しちゃうかも、という話。「規律化によるイメージと『日本』像とを重ね合わせるならば、暗記によって『日本』が構築されていくという側面が垣間見られることだろう。『忘れがたき故郷』と歌うことは、個人の中で忘れがたい故郷を表象することになる。兎もおらず小鮒もいない都会の真ん中で生まれ育ったとしても、各人の『故郷』のイメージを言葉の上だけでも統合することは可能だからです。そうした表象の集積によって『日本』像が形成されるとするならば、問題はそうしたイメージを喚起させるものの選択の方法にある。」(pp.203-4)ということで、こういう「隠れたカリキュラム」(むしろ隠れてないのかも)、みたいな話は興味を持った。
全体としては唱歌の話よりも、明治期の国語や文法の研究についての話のウェイトが多いので、唱歌を期待すると、少し期待はずれかもしれない。あとは明治期の文献がたくさん引用されるが、その元の部分を読むことには少し根気がいる。正直、原典の部分は読み飛ばしてしまった。最後のまとめの章は興味を持って読めたが、全体的にはちょっと難しい内容だった感じがする。(22/10)