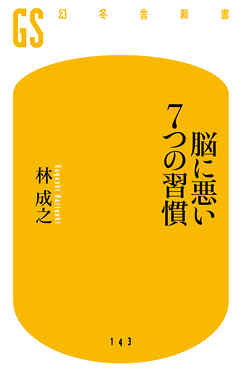あらすじ
脳は気持ちや生活習慣で、その働きがよくも悪くもなる。この事実を知らないばかりに、脳力を後退させるのはもったいない。脳に悪い習慣とは、1「興味がない」と物事を避けることが多い、2「嫌だ」「疲れた」とグチを言う、3言われたことをコツコツやる、4常に効率を考えている、5やりたくないのに、我慢して勉強する、6スポーツや絵などの趣味がない、7めったに人をほめない、の7つ。これらをやめるだけで頭の働きが倍増する理由を、脳のしくみからわかりやすく解説。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
最高にいい本。
脳科学の視点から語っているため、内容に関しての信頼度が高い。
私は常に悪い習慣をしていると感じたため、気をつけようと思った。また、私の周りにいる方で非常に脳にいい行動をしている人がいる。リスペクトだ〜
Posted by ブクログ
2020 6-7月に読んだ
脳医学から やる気を出す方法とかのアプローチを考えた本。
嫌いな人の話はうけ入れにくい、とか、 最初に嫌な感情を持つと物事でパフォーマンスが出せない。とか言う本
(7つの悪い習慣)
①「興味がない」と物事を避ける。
→人とか脳の本能として、生きたい、知りたい、仲間になりたいとかいう欲求があるので興味を持て
②「嫌だ」「疲れたとグチをいう
→相手を受け入れる。嫌いで情報をシャットアウトしない。考えが明るいと物事を考えるようになる。
③言われたことをコツコツやる
→「やってること」より、「目標」を決め、集中してやる。目標は変えない!最後まで油断せず 100%を追求
④常に効率を考えている
→いつもはこうしてる。じゃなくて常に良い方法を考えろ。くり返し考えることで独創性を高める。頑固は駄目
⑤やりなくないのに無理して勉強する
→これも興味をもつ。何でやってんだろう?って考える。買だいたい覚えた!で勉強を辞めるな。
⑥スポーツや絵の趣味がない。
→空間認知能は全体に響がる。おしゃべリをアイデアになる。独創性を高めよ
⑦めったに人をほめない。
→人の気持ちの同調、「同期発火」をおこす。話すときは喜怒哀楽を。ほめると脳がよろこぶ。 ほめるときは、相手としっかり見て、ほめるべき点をしっかり把握して褒める
また、忘れたころに見たい本でした。
やる気を出すため、人間関係のために良い本であった。
子育てにも役に立ちそうに感じた
Posted by ブクログ
知らず知らずのうちに悪い習慣が身についているなと感じた。
・4歳までは伸び伸びと、物事に興味を持たせることを第一に
・反対意見を言った人を嫌いになるは脳の癖の過剰反応→癖だということを知り、嫌いにならないようにする。
・感動しないと脳の働きは鈍る→自ら盛り上げ役に
・途中で完成した、できた、達成したは脳にとって否定語。→ここから本番だと一気にやり通す。
・言われたことをコツコツでなく、自分なりの目標を持って一気に駆け上がる。
・子供や部下に自主性を持たせるには、「君はどう思う?」と問い掛ける。
・日頃から効率だけを優先せず、繰り返し考える癖を。4日ごとに間をおいて考える。
・姿勢を正しく、いつでも真上に飛び上がれる状態を意識。
・相手の脳に同期発火を起こすには相手のリズム、アゴの動きに合わせて。
1 興味がないと物事を避ける→何にでも積極的に興味を持ち、前向きに。
2 嫌だ、疲れたと愚痴を言う
3 言われたことをコツコツやる
4 常に効率を考える
5 やりたくないのに無理して勉強する
6 スポーツや絵などの興味がない
7 めったに人を褒めない。
1から順番に止めるといいのだそうだ。
Posted by ブクログ
脳に悪い7つの習慣について、脳の仕組みから取り上げ、改善する方法を示している。
(1)「興味がない」と物事を避けることが多い
(2)「嫌だ」「疲れた」とグチを言う
(3)言われたことをコツコツやる
(4)常に効率を考えている
(5)やりたくないのに我慢して勉強する
(6)スポーツや絵などの趣味がない
(7)めったに人をほめない
特に6番目の空間認知を鍛えることが大変参考になった。
Posted by ブクログ
「なるほどな」納得の数々で面白かった。
他にも、有益な情報がいっぱいでした。
経験で理解してても、脳からかんがえるとなるほどなと説得されるものも多く、
肝に免じて実践したいなと思いました。
Posted by ブクログ
たいへん興味深く、わかりやすく書かれていた。
本書に書かれていた通り、繰り返し読んだので
さらに理解が深まりました。
太極拳に通ずる点あり、面白かった。
Posted by ブクログ
20190203
人間の脳に関してパフォーマンスを最大限に発揮するためにはどうするかといったことが書かれている本。
言われてみればなるほどうまくいっている時はここに書かれていることがきっちりできていて、うまくいってない時はいわゆる悪い習慣に陥ってしまっていることが多い。
常に意識することは難しいが参考にしたいのは悪口を言わないことや何事にも興味を持つこと、物事は「だいたい覚えた」で終わらせないこと、コツコツやるのではなく、目標と目的を定めて一気にゴールまで駆け上がることなどを注意していきたい。
20200321 追記
自分の恋人に渡そうと思って再読した。
改めて思ったのが、最後の著者の言葉、「違いを認めて共に生きる」。
この本が書かれたのは2009年のようだが、当時からダイバーシティを意識していたのかもしれない。
今回印象に残ったのは
相手に共感してもらうように喋るということ。
相手の気持ちを分かるようにし、相手に自分の気持ちを分かってもらえるように伝えるというところが今の自分にもまだ改善の余地があるなと思った。
特にOJTしたり、周りに仕事をしてもらう立場になったりすると、目的をちゃんと伝えて仕事をしてもらうことの大事さが分かる。
世界は変わり続けているし、互いに協力し合う世の中にならないと働き方改革にも少子高齢化にも対応できない。
AI,5Gなどデジタルトランスフォーメイションもめまぐるしい昨今においては何事にも興味を持ち(=外部アンテナの感度を上げ)、否定をせずにどんどん挑戦していく姿勢が必要なのだと思う。
Posted by ブクログ
脳が情報を受け取り、感じ、理解し、思考し、記憶するという順番に従って、「脳に悪い習慣」と「その習慣をやめ、脳を活かすたもの具体的な方法」を7つに分けて展開していく。著者が経験したことや実際に起こったことを交えて脳に悪い習慣を説明していて、とても分かりやすい。
また、本文中に著者が物事を説明する祭、「裏を返せば」とか「言い返せば」いう言い方が多く含まれている。物事に対して、別の角度からもアプローチしている柔軟な思考の持ち主であることが見て取れる。
今回、一気に読んだが、自分が改善すべき習慣が多く含まれていた。本の内容をまとめるに当たり、改善すべき場所を繰り返し読めるようにまとめたい。
Posted by ブクログ
何事に対しても興味を持つ
淡々とクールに話さない、感情を込めて話する
やや偏りも感じたが、実践していきたい項目もいくつかあった。基本的に、前向きに生きていくことが必要であると諭されている。男性脳には対応しやすいが、女性脳にはどうなのだろう?と言う点もあった。
Posted by ブクログ
そもそも脳は目から入った情報を①大脳皮質神経細胞が認識し、②A10神経群と呼ばれる部分に到達する。A10神経群に危機感を管理する扁桃核や好き嫌いを管理する側坐核などがある。
次に③前頭前野で情報を理解・判断する。
その情報が自分にとってプラスだと④自己報酬神経群に持ち込まれ、さらに⑤線条体—基底核—視床、⑥海馬回・リンビックに持ち込まれる。
つまり、目からの情報を感情でラベル付けし、後続の処理機構で情報を処理する。最初のラベル付けで興味が無いとラベル付けした場合、その後の処理にパフォーマンスが出ない(脳が使われない)という話。
脳神経細胞はそもそも本能を持っている。生きたい・知りたい・仲間になりたい、の三つである。
脳に悪い習慣は勇気を持ってやめる
自己報酬神経群を働かせるコツは、
・目的と目標を明確にし
・ゴールを意識せず
・主体的に、じぶんがやってやるという意思をもって
・達成のしかたにこだわる
・目標の達成に向けて一気に駆け上がる
部下に主体性を持たせるには、一から十まで教えるのではなく、「〇〇さんはどう思う?」「〇〇さんは△△と言っていたけど、✖️✖️さんはどう思う?」などの呼水で考えさせることが重要。
ゴールを意識する、または「無理かもしれない」「負けるかもしれない」と思うだけで、脳の血流が下がる
Posted by ブクログ
脳に悪い7つの習慣が取り上げられ、その対策が述べられている。中でも「言われた事をコツコツやる」、「常に効率を考えている」は、一見何故?と思えてしまう。この二人は日本人なら美徳とすらされてきただけに。
「基本からコツコツ積み上げ、効率良いアウトプットを目指す」は当然として、その上で従来の定説を疑ってみる。多面的な見方を心がける、と言う事なのだろう。理系的な考え方、でしょうか?
長い人生、そんなに簡単に楽したり、安易に流れては駄目ですよ。頑張り過ぎも駄目なのだろうが。色々な事に興味関心を持って楽しく(楽しそうに)日々を過ごす事が大切と言う事なのでしょう。無駄、回り道、大いに結構。何事も経験しておいて損は無い。「遊び心」を大切にしたい。
Posted by ブクログ
わかりやすく、納得のいく説明で読みやすかった。人は仲間がほしいということ、脳がポジティブなレッテルを貼ったことほど学習効率がいい、ということなどは今後も忘れないと思う。
Posted by ブクログ
脳に悪い習慣と聞いて、「睡眠不足」や「スマホ依存」といった行動レベルの習慣を思い浮かべたが、そうではなく脳の仕組みや人間の本能に基づいた習慣が紹介されていて勉強になった。ついつい日頃やってしまっている行動もあり、なぜそれが良くないのかということを科学的に説明されているため納得しながら読み進めることができた。
本書にも紹介されているように、繰り返し繰り返し読むことでそれらを習慣化させたい。
Posted by ブクログ
脳神経細胞がもつ本能は、「生きたい」「知りたい」「仲間になりたい」の3つ。
人間の脳には「自己保存」「統一・一貫性」のクセがある。
ゴールを意識すると脳の思考が止まってしまう。あと少しの時こそ、ここからが本番だと考えることが重要。どうしても終わりが見えると気が抜けてしまったり、残りの時間ばかり気にして集中力が切れてしまったりするので気をつけたい。
Posted by ブクログ
「嫌だ」「疲れた」「もう無理」は口にしないようにしよう。
笑顔を心がけよう。
脳のクセ「自己保存」と「統一・一貫性」の話が参考になりました。
「人を嫌って得することは何もない」
Posted by ブクログ
普段の習慣を見直してみたいと思った。日々の積み重ねは良いことも悪いことも溜まっている。悪い習慣を積み重ねれば人の脳本来の力を発揮できない。
2章の否定的な愚痴を言ってしまう習慣。疲れた、嫌だなどの発言は否定的な感情が上乗せとなっていることから脳に悪い。日々言ってしまう場面があれば、見つめ直すべき。
7章では相手との違いを理解し、自身を高めていくことは鍛えるべきこと。とても印象的だった。簡単に相手を理解するといったことでなく、普段から意識し鍛えることで相手を思うことができる。またそれが違いを認めることで本来人の脳が望んでいることだ。
普段の習慣を1から見直し、本当に脳にとって良いことを行動していきたいと思った。
Posted by ブクログ
脳に悪い習慣とは、「興味がない、と物事を避けることが多い」「嫌だ、疲れたとグチを言う」「言われたことをコツコツやる」「常に効率を考えている」「やりたくないのに、我慢して勉強する」「スポーツや絵などの趣味がない」「めったに人をほめない」でした。
これらのことを、順序立てて分かりやすく説明してあるのですっと心に入ってきます。
興味の対象が多い、というのはやっぱり良いことなのかもしれません。年を重ねても、わからないことや新たに知ることはたくさん出てくるし。
「違いを認めて、共に生きる」、このことも大事にしようと思いました。
何度も読んで、考察していきます。
Posted by ブクログ
人間の脳は「自己保存」「統一・一貫性」が原則※
①自己保存とは「生きていくために自分を守る」
②統一・一貫性とは「正誤を判断」「類似するものを区別」「バランスをとる」「話の道筋を通す」という事。
※2020.02.24再読追記
反対意見を言う人は、②により拒否し、
①により相手の意見を論破しようとする。※
▼第一章(「興味がない」と物事を避けることが多いのはNG)
「自分さえよければいい」という考えを捨てて、
多くの情報を共有すれば相手も自分も広く知ることができる
何事にも”きっとおもしろいに違いない”と思って取り組む
▼第二章(「嫌だ」「疲れた」とグチを言うのはNG)
まずは、素直に「すごいな」と感動すること
感動は判断力・理解力を高め、脳をLvUpさせる※
A10神経群は表情筋と密接な関係があり笑顔で健康になる※
▼第三章(言われたことをコツコツやるのはNG)
損得抜きで「あの人の喜ぶ顔が見たい」と思える人は力をより発揮できる
「そろそろゴールだ」と言葉をかけると、脳の血流が落ち成績はダウンする
→「ここからが勝負だ」と思え
「契約を沢山とる」→「契約を20件とる」みたいに明確な目標を定める
「主体性を持ち、言われたことには付加価値をつける」
「本番前に休息を挟むのではなく、目標の達成に向けて最後まで一気に駆け上がる」
▼第四章(常に効率を考えているのはNG)
行き詰まったときは整理してから離れ、4日後に考え直す
多くの無駄を「必要な無駄」であったと思えるように
大事なことは早いタイミングでまとめて、くり返し考え直すこと
”新しい発想をきちんとまとめ、ときには自分を疑い、立場を捨てて人の意見を取り入れ、間をおいて考え直すことができて、初めて独創的な思考が可能になるのです”
▼第五章(やりたくないのに、我慢して勉強するのはNG)
「悔しい」と感じることが、脳の力を引き出す強力なファクター
海馬回は、複数の情報が入ることで興奮し、機能が高まる
→名前だけでなく特徴を述べて情報を伝えると覚えてもらえる
30代のアレアレを防ぐには、A10神経群で感情のレッテル(自分にとって嬉しい)を貼って、前頭前野で理解し、自己報酬神経群を介して海馬回において思考し記憶させるのが一番。※
”「成功体験に縛られていないか」
「失敗の経験によって、チャレンジする勇気を損なっていないか」
--物事を考えるとき、行動に移すときは、この2点をチェック”
▼第六章(スポーツや絵などに興味がないのはNG)
姿勢が悪いと空間認知能力が低下する※
字を雑に書くと空間認知能力が低下する※
スポーツは距離、空間の間合いを測るのに最適※
絵画は対象物との距離計測、縮小率、形・角度を正確にとらえるのに最適※
おしゃべりは空間認知能力を活発にする。※
▼第七章(めったに人をほめないのはNG)
”コミュ力アップには「うれしそうに人をほめること」が有効”
”「同期発火する脳」をつくるには「人間性を磨くこと」が大事。”
▼悪い7つの習慣の目次まとめ
「興味がない」と物事を避けることが多い
「嫌だ」「疲れた」とグチを言う
言われたことをコツコツやる
常に効率を考えている
やりたくないのに、我慢して勉強する
スポーツや絵などの趣味がない
めったに人をほめない
Posted by ブクログ
内容が身に染みる。いや、脳に染みているのかも。
目次
第1章 脳に悪い習慣1―「興味がない」と物事を避けることが多い
第2章 脳に悪い習慣2―「嫌だ」「疲れた」とグチを言う
第3章 脳に悪い習慣3―言われたことをコツコツやる
第4章 脳に悪い習慣4―常に効率を考えている
第5章 脳に悪い習慣5―やりたくないのに、我慢して勉強する
第6章 脳に悪い習慣6―スポーツや絵などの趣味がない
第7章 脳に悪い習慣7―めったに人をほめない
よくある、前向きに物事を考えましょうと、精神論を問いている訳ではなく、脳科学の観点からきちっと説明してあり、好感が持てる。一時の脳科学ブームが落ち着いたとは思うけど、単なるブームで捨ててしまうのでは無く、いいものはいいと受け入れればいいと思う。
この本を読むと、脳というのは、ワクワクさせてなんぼというのが分かる。脳を興奮させて活性化することで、脳が動き、体が動く。なんとなくイメージで分かっていた感覚が、実際に脳科学の観点で証明されると、説得力がある。
やはり、キーワードは「楽しい」であろう。自分も大学受験の頃は、教科書を見るのもイヤだった古典を「楽しい、楽しい」と自分に言い聞かせて、勉強していた思い出がある。著書で学んだのは、いくらそうやってごまかしても、脳が察知すれば、瞬く間に受け付けなくなってしまう。どこかに本当の古典の楽しさを見付けて、自分が好きだった数学のように、前向きに取り組んでいたら、もう少し成績もあがったのかもしれない。
もうひとつのキーワードは「自分を捨てる」であろう。何か悪いことが起こると、脳は自己保存の方向に走って、自分を守ろうとする。ちょうど政治家が都合の悪いことがあると、必死に保身に走って、かっこわるい状況と似ている。
「自分を捨てる」というのは簡単で難しい。だれもが自分が可愛いものだ。都合の悪いことが起こり出すと、自分の身を守ろうとして殻に閉じこもって、人の話を聞かなくなる。著者いわく、人間というのは、もともと本能で「生きたい」、「知りたい」、「仲間になりたい」の3つがあるとのこと。
この「仲間になりたい」は、意外と盲点となっている。どちらかというと、この競争社会では、仲間を蹴落として上にあがるという風潮があるけど、それは本能からは逆行してるようである。
結局は、トップに立っても、指示をして動く部下や仲間がいないと、何もできない。そのためには、日頃から素直に人の話を聞いて、自分の価値観と違う意見を言われても、すぐ反論せずに、柔軟に対応できる能力が必要になる。
「仲間意識」というのは、どちらかというとネガティブなイメージもあるけど、実は本能が欲しているものだと頭を切り替えて、これからは、どんどん「仲間」を増やしていければと思う。
Posted by ブクログ
2009年刊行の本を2014年に読んでいたことも忘れて、2025年に読んだという何とも笑えない読後感となった。
記録を続けているといつの間にかこういった再会もあるものだ。
脳の特性を知ることで、記憶力を良くしたり、幸福になったりとメリットが多い。
笑うこと、話すこと、気持ちよくいるだけで脳には良いということが再度認識できた。
また忘れた頃に出会えたらいいな。
Posted by ブクログ
著者の林成之氏は、脳神経外科医。
脳のしくみにもとづいて、「脳に悪い習慣はやめよう」と書かれている。
本書で紹介されている脳に悪い習慣は7つある。それがそのまま章立てとなっている。つまり、目次は、悪い習慣の一覧である。
目次
第1章 「興味がない」と物事を避けることが多い
第2章 「嫌だ」「疲れた」とグチを言う
第3章 言われたことをコツコツやる
第4章 常に効率を考えている
第5章 やりたくないのに、我慢して勉強する
第6章 スポーツや絵などの趣味がない
第7章 めったに人をほめない
この一覧を見て、ドキッとした人は一読の価値がある。
一方で、あたりまえのことばかりだと感じた人は読まなくて良さそうだ。指南されていることだけ見ると、あえて脳のしくみを持ち出すまでもないような気もする。根拠や裏付けを知りたい人に向いている。
脳のしくみで何度も出てくるのは、脳の「A10(エーテン)神経群」という部位だ。A10神経群は情報に対して、好き・嫌いという感情のレッテルを貼る。レッテルを貼られた情報は、「前頭前野」に入り、理解する。つまり、理解する前に、「嫌いだ」とか、「自分には関係ない」というレッテルが貼られると、脳がしっかり働かない。だから、「興味がない」と物事を避けることはやめましょうという流れで説明されている。
関心のないことは、なかなか覚えられない。こういう経験は、誰でもしたことがあるだろう。経験則で知っていることを、脳のしくみと絡めて説明されるのを好むかどうか。この辺りが、本書を読む・読まないの分かれ目になりそうだ。
本書のキーワードは、脳の持つ3つの本能、「生きたい」、「知りたい」、「仲間になりたい」だ。脳の機能を最大限に活かすには、脳の本能を磨くべきだとし、本能に背くことはやめようという。
それを一言でいえば、「あとがき」にある、次の言葉になる。
人に興味をもち、好きになり、心を伝えあい、支えあって生きていく(p182)
Posted by ブクログ
「興味がない」と物事を避けない
コツコツとすることをやめる
「疲れた」「面倒くさい」と言わない
などなど。
わたしにはハードルが高く、今までやってきたことばかりでした
Posted by ブクログ
脳という視点から語る話。
自分ができそうな習慣は
絵を描く
否定語を使わない
息子とキャッチボール
喋る
絵を描くは空間認知能力を上げるために必要ということで昨今の美術の時間削減に対して1つ切り札として使えると感じた。
Posted by ブクログ
脳に関する本は何冊か読んでいるけれど、読むたびに発見がある。
脳はまだまだ研究できていない部分も多いというから、何か生活を潤すために良いことがたくさんあるだろう。
当たり前に言われていることが、脳を理解することでより、大事に思えてきて実行しようと思える。
Posted by ブクログ
■印象に残ったところ、覚えておきたいところ
・「だいたいできた」と安心してはいけない
安心して脳にストップをかけてします。もう少しで完成というときこそ、「これからが本番だ」と思うようにすること
・「無理かもしれない」と考えるのはNG
脳血流がダウン。「なぜ難しいのか?」を考え、対策に集中すること
・脳の癖
キーワード:「自己保存」と「統一・一貫性」
・空間認知脳を鍛えるため
姿勢と正しくする。
きれいに字を書くことを習慣付ける。
=>子どもに意識させたい
Posted by ブクログ
脳に悪い習慣とは、
(1)「興味がない」と物事を避けることが多い
(2)「嫌だ」「疲れた」とグチを言う
(3)言われたことをコツコツやる
(4)常に効率を考えている
(5)やりたくないのに我慢して勉強する
(6)スポーツや絵などの趣味がない
(7)めったに人をほめない
の7つ。
それぞれ理由があるが、あまり脳科学的な観点という感じはしなかった。脳科学ってエビデンスって出しにくいので、仕方ないとは思うが。
とりあえず前向きな気持ちを持つということ。
オーディオブックで聴くには手頃な本だと思います。