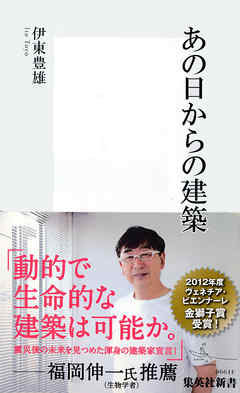あらすじ
東日本大震災後、被災地に大量に設営された仮設住宅は、共同体を排除した「個」の風景そのものである。著者は、岩手県釜石市の復興プロジェクトに携わるなかで、すべてを失った被災地にこそ、近代主義に因らない自然に溶け込む建築やまちを実現できる可能性があると考え、住民相互が心を通わせ、集う場所「みんなの家」を各地で建設している。本書では、国内外で活躍する建築家として、親自然的な減災方法や集合住宅のあり方など震災復興の具体的な提案を明示する。【目次】はじめに/第一章 あの日からの「建築」/第二章 釜石復興プロジェクト/第三章 心のよりどころとしての「みんなの家」/第四章 「伊東建築塾」について/第五章 私の歩んできた道/第六章 これからの建築を考える/おわりに
...続きを読む感情タグBEST3
このページにはネタバレを含むレビューが表示されています
Posted by ブクログ
・・・象徴物に力を求める資本主義と、建築技術の飛躍的向上により、フランクゲーリーやザハハディドの巨大彫刻のような建築が世界的ブームになっているが、
伊東やSANAAは外部空間と建築と人間の壁を無くす日本的な空間建築で風穴をあけている。
「みんなの家」
あの日から、個としてのオリジナルな表現も都会的要素も無い場を地域の人々と心をひとつにしてつくることができた。
近代主義は私と他者、内と外など物事を切り分ける思想だった。
しかし日本では、日本語や伝統建築空間、あいまいな人間関係によって豊かさが保たれていた。
機能と言う概念は人間の多彩で複雑な行動を単純に区分して抽象化したに過ぎない。
だから利用者から見れば楽しくない。
「せんだいメディアテーク」
自然の快適さをモデルにした新しい空間の秩序が快適さにつながる。
「TOD’S表参道ビル」
建物の中にいても外部的な空間に変化する、木の枝のように枝分かれしたコンクリートの構造壁。
「台中メトロポリタンオペラハウス」
二組のチューブの連続体。内部のような外部のような構造体。
自然の中にいるような自由な気持ちでいられる。
「個を超えた個へ」
現代建築での建築家は資本主義を目に見える空虚な形のアート作品にする道具になっている。
建築の原初の姿は、共同で何かを作り上げ、集団として崇め、作ることが喜びであるという共同性のあらわれ。
Posted by ブクログ
せんだいメディアテークなどに携わった建築家伊東豊雄さんの、建築に対する考え方を記した本。震災をきっかけに、建築の求められているもの、伊東さん自身が建築にとって大事なものが変わっていった、その経過を克明に書き綴っている。真摯な姿勢でわかりやすく説いてくれており、好感が持てる。
震災後2011年3月末に「帰心会」という震災について考え、行動する会を立ち上げた著者。その会で言った「批判をしないこと」という復興に対するスタンスにうなずけるものがあった。「批判は部外者だからできること。批判をしないとは(中略)自分自身が復興に関わる当事者であるという自覚を持ち続ける」ことだというのだ。すべての社会問題に当てはまる言葉に思えた。
また釜石の復興プロジェクトに携わった際に、「元の仲間と一緒に暮らしたい」という声を聞き、仮設住宅の閉鎖的な状況を打破すべく、皆が集まれる場所「みんなのいえ」を作っていく。しかもそれを、「くまもとアートポリス」という熊本県の建築やデザインによる地域向上をめざす事業に話を持ちかけ、実現していくという、縦割りの枠を超えた手法で。被災地以外の県がこういう形で被災地を援助する新しい形に光が見える。
今まで「建築が建築たる所以は自然の中に人間としての証を表現すること」だと著者は言う。建築の目的は外からの隔離で、それもグリッド(方眼)で仕切るような様式で行われてきたと。しかし、本来自然にはグリッドはない。著者は中と外との関係を考え直し、構造壁を木の枝のように枝分かれさせたり(TOD'S表参道ビル)、ゆらめくようなチューブと板とガラスで自然を表現する(せんだいメディアテーク)などの手法をとってきた。
洗練された建物、立派な建物はそれだけで広告塔で、権力や財力を誇示できる。しかし、それはやはり自と他を分ける行為にほかならない。本来外と内、自と他を分けるはずの建物の壁を限りなく曖昧にする、そういう域に近付くのも建築の形なのだと気付かせてくれた本であった。
余談であるが、この本を読む前、昨年の夏にせんだいメディアテークに行く機会があった。夫がそこで行う催し物を見に行くため偶然入ったのである。私はチケットがなく、カフェでお茶を飲んだり、ショップを見たりしていた。ホールをうろうろしたとき、チューブ状の柱を見て、何だろうと思ってはいた。惜しい、この本を読んでから見たかった。いや、きっとまた行く。伊東さん作の他の建物にもぜひ出会いたい。