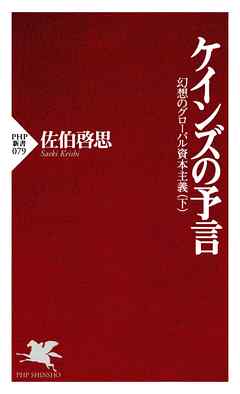あらすじ
「大きな政府」がもたらす非効率的な経済ゆえに、もはや破綻したとまでいわれるケインズ主義。しかし、ケインズが自由な市場競争主義を批判したのは、確かな基礎を持たないグローバル経済への危機感からであったと、著者はいう。また、豊かさの中の停滞と退屈が人間を衰弱させるという、今から70年近くも前の彼の「不吉な予言」は、「自立した個人」が「経済の奴隷」と化しつつあるこの世紀末の世界で、きわめてリアリティを帯びつつある。今、われわれがケインズから学べることは何だろうか? アダム・スミス、ケインズという両巨人の思想を読み直し、グローバリズムへの幻想の超克と、新たな社会秩序の可能性を論考する意欲作。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
ネオ・リベラリズムが席巻する中で凋落の憂き目を見ることになったケインズの思想の新たな可能性を取り出し、国民経済に足場を置いて市場主義の幻想を批判することを試みた本です。
ケインズは、金本位制からの脱却を支持しましたが、それはグローバルな貨幣の無制限な流動を認めることではなく、むしろ貨幣に対する人びとの信頼が国家に置かれていることによるものだったと、著者は指摘しています。そして、ケインズの経済理論のさまざまな側面に、国民経済を信用の基礎とする考え方が見られることを明らかにしてきます。
著者の理解するケインズは、アダム・スミスの経済学と対立するものではありません。上巻で論じられたように、アダム・スミスは国民経済に確固とした足場を持つことで、人びとのうちに「徳」が育つと考えており、そうした足場を掘り崩してしまう当時のグローバリズムというべき重商主義に対して厳しい批判をおこないました。
一方ケインズは、もはや土地に根ざした労働によって徳の育成を確保することのできない時代に生を受けました。ただし彼も、その時代の中でグローバリズムの潮流が、国家に対する信頼という私たちの経済と道徳の基礎を押し流してしまうことに気づいており、そうした動向を鋭く批判したのです。こうして著者は、スミスと同様にケインズも、反グローバリズムの立場を取る国民経済主義者だったと論じています。
スミスと同様、ケインズについても著者の理解がどこまで妥当なのか判断することはできないのですが、ケインズのグローバリズム批判の視点が一貫した形で論じられており、説得的に感じました。
Posted by ブクログ
当時の不気味な予言がまったくもっていまの日本に当てはまっていて、もう気持ち悪い。
著者はケインズの理論について単なる善悪の二元論ではなく、現在に有効なところとそうでないところを評価していて、好感が持てる。
経済が専門ではない私でも読み進められるほど噛み砕いて書かれていて、面白く読めた。
Posted by ブクログ
▼幻想のグローバル資本主義の下巻。上巻とともに手に取った。
▼ある程度経済成長が進むと「豊かさの中の停滞」を向える――現状を見る限り、ケインズの「予言」は正しいと言わざるを得ないだろう。先行くイギリスはもちろんのこと、日本もまた例外ではない。
▼グローバル化が進むと、資金が海外に流れ、国内市場が不活性化してしまう――とても耳が痛い指摘ではあるが、決して的外れな議論ではない。無規制も考えものではあるが、一方では、国内経済の魅力を高める自身の努力も必要だろう。
▼資本主義経済体制を選択した上で、自由民主主義と社会民主主義のバランスをどうとっていくか。「豊かさの中の『退屈』」しのぎに取り組んでみるのも面白いだろう。
Posted by ブクログ
[ 内容 ]
グローバリズムとナショナル・エコノミーの対立を警告したもう一人の経済学者、J・M・ケインズ。
その現代的意義を独自の視点で再検証。
「大きな政府」がもたらす非効率的な経済ゆえに、もはや破綻したとまでいわれるケインズ主義。
しかし、ケインズが自由な市場競争主義を批判したのは、確かな基礎を持たないグローバル経済への危機感からであったと、著者はいう。
また、豊かさの中の停滞と退屈が人間を衰弱させるという、今から70年近くも前の彼の「不吉な予言」は、「自立した個人」が「経済の奴隷」と化しつつあるこの世紀末の世界で、きわめてリアリティを帯びつつある。
今、われわれがケインズから学べることは何だろうか?
[ 目次 ]
序章 凋落したケインズ
第1章 国民経済主義者ケインズ
第2章 「確かなもの」への模索
第3章 グローバリズムの幻想
第4章 隷従への新たな道
第5章 「没落」という名の建設。
[ POP ]
[ おすすめ度 ]
☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度
☆☆☆☆☆☆☆ 文章
☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー
☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性
☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性
☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度
共感度(空振り三振・一部・参った!)
読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ)
[ 関連図書 ]
[ 参考となる書評 ]
Posted by ブクログ
「集団心理」「市場の心理」「アニマル・スピリット」「自由=責任」
投資家、経営者、労働者
変動する株価:変動する資産・負債
変動する為替:変動する材料費・燃料費
固定化された賃金
固定化された商品価格と変動する商品価格
一国では制御しきれないグローバル資本。
資本の海外への流出(投資)、海外資本の引き上げ、海外ファンドの短期投機のなかで、企業側の長期での回収を見込んだ設備や雇用増加などの投資の難しさ。
豊かさゆえにモノを持たない、または、どうしてもコレが欲しいと願うことの減少、高齢化と人口減少傾向での絶対的消費量の減少。
過剰な生産能力、貿易摩擦での輸出量の頭打ち。
豊かさゆえに消費よりも退屈しのぎ。
さて…。
自助>共助>官助
Posted by ブクログ
著者は「アダム・スミスの誤算 幻想のグローバル資本主義(上)」を発表し、その続編となるのが本書である。
アダムスミスを市場主義者とでもいう括りにいれるのならば、ケインズはアダムスミスとは対立するという見方も存在するのではあろう。だが著者の場合は、アダムスミスは一種変わった角度から論じ、グローバリズム問題という観点から考えた。そしてそのグローバリズム問題という観点から考えた場合、アダムスミスとケインズは対立するのではなく、グローバリズム問題に関してはどこか警戒的とでもいうのか、その意味ではアダムスミスとケインズは同一線上にあるのではないかと見たという事ではないかと思われる。
“ケインズ理論が七〇年代の経済、政治の現実とはそぐわなくなってきたということだ。だが、ケインズ主義の凋落の理由はそれたけではない。いわば「外的」なあるいはイデオロギー的理由というべきものがあった。それが八〇年代以降の「新自由主義」の潮流である。(16頁)”と佐伯氏は言う。
七〇年代のケインズ理論の凋落…八〇年代の新自由主義潮流…そして本書は「幻想のグローバル資本主義」というタイトルを銘打つ。
これらを含め見てみると、「(グローバリズム問題という観点からの)アダムスミスとケインズ」という要素が、時代が進むにつれて薄れてきているのではないかと私には思われてくる。また、何故にグローバリズム問題が浮上もしくは語られるのかとなれば、それは「(グローバリズム問題という観点からの)アダムスミスとケインズ」というものに対して考慮を欠いたのではないかとも私には思われてくる。
本書は、普通とは一風変わった問いかけをしている本ではないかと思う。またそして、示唆的であるのだとも思う。