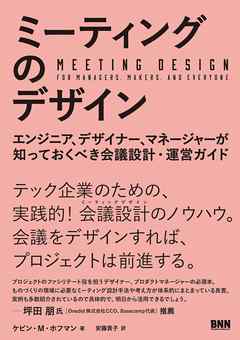あらすじ
『デザイン組織のつくりかた』『デザインリーダーシップ』に続く、テック企業のための組織づくりシリーズ第3弾!
より良いプロダクト、ソフトウェア、サービスを生み出すためには、会議/ミーティングをいかに適切に設計・運営するかが肝要となります。本書では、ミーティングにデザイン思考を導入するための具体的なノウハウやサンプルアジェンダをふんだんに紹介しつつ、各章末に重要ポイントを掲載しています。
これらを実践し、ミーティングをデザインすれば、プロジェクトの大きな成果に繋がるだけでなく、組織の文化を変えることも可能です。チームリーダーやマネージャーのみならず、共創を目指してチームを醸成したいすべての人におすすめの一冊です。
坪田 朋氏[Onedot株式会社CCO、Basecamp代表]推薦!
“プロジェクトのファシリテート役を担うデザイナー、プロダクトマネージャーの必須本。
ものづくりの現場に必要なミーティング設計手法や考え方が体系的にまとまっている良書。
実例も多数紹介されているので具体的で、明日から活用できるでしょう。”
感情タグBEST3
Posted by ブクログ
キックオフミーティング、セールスミーティング、ブレインストーミング、OKRミーティングなどの具体的なアジェンダ例が載っており、実務にそのまま活かせるのがとても良い。
今後自分がチームで果たす役割が変わるにつれて(ex. リーダー、マネージャーなど)、より参考にできる部分が増えそう。ミーティングのデザイン、プロジェクトの進め方などで迷ったら都度参考にしたい、と思える一冊だった。
すぐできることとして、まずは会議の目的・アジェンダ・参加者の選出の意図などを明らかにするよう心がけていきたい。議論をリアルタイムで視覚化するのも率先してやっていく。
【自分用メモ】
- 議論をリアルタイムで視覚化する(ホワイトボードなど)
- ミーティングではどんどん物を、手を動かす(付箋をはる、ダンボールでプロトタイプを作るなど)
- ミーティングは20〜30分単位で小分けにする(集中力維持のため)
- アイデアと人数、時間を念頭に置いてアジェンダを組み立てる
- キックオフミーティングの目標は、共通の前提を確認してプロジェクトのリスクを特定すること。
Posted by ブクログ
「ミーティングの良し悪し」=「メンバーの記憶力の良し悪し」、「どのような成果が出せるか」→「成果をどうのように測定するか」ということでミーティングを再定義。フリップボードを使うスクライブ(書記)のビジュアル・リスニングについての言及も。打ち合わせの進め方もスペース・メイキングつまり余白を空けてならべる方法やスペース・フィリングつまりどんどん広げるやり方の2つの手法は意識して使うと分かり良さそう。
Posted by ブクログ
海外のミーティングに関するデザイン例の本。前にそういった観点の定めをしていた経験があり、興味があり読んだ。
ところどころ読みにくい、入ってきにくいことが多かったが参考にはなった。
色々なミーティングアジェンダ例や豊富なコラムなどは色々と考えさせられる。
【第1部 ミーティングデザインの理論と実践】
第1章 ミーティングをデザインする
- ミーティングで解決すべき問題を見極め、開く前にリサーチ
- ミーティングに対するアプローチを複数考える
- 改善点や失敗に気づいたら、それを元に改良する
- ミーティングが役割を終えたら廃止する
第2章 ミーティングにおけるデザイン上の制約
- ミーティングでもっとも活発に働くのは作業記憶(30秒)
- 作業記憶は視覚情報と聴覚情報で処理。相補的に組み合わせる
- ミーティング後の実行に移すのに重要なのは中期記憶
- ミーティングが長すぎると中期記憶の形成が阻まれる
- 20~30分単位でプレゼンやアクティビティ、議論に小分けにすると出席者の聴く力は高まる
- 集中力維持にはいい脂質とタンパク質がよい
- ビジュアル素材は別の脳の箇所を刺激するので効果的に使う
- 付箋や小型プロトなどの触覚機能との結びつきは良い
第3章 アイデア、人、時間に合わせてアジェンダを作る
- 扱う情報の内容や数。トピックの数と時間配分
- 望ましい人数、時間の制約に合わせてアジェンダを調整
(7人以下の場合)
- コンセプトに要する時間(20分) = プレゼン10分+レビューとディスカッション10分
- 異なる15のコンセプトグループ÷5 = 3つのグループ
- 1つのコンプトグループに20分 * 3 = 60分
(大人数(15人)の場合)
- グループ分けする(1ユニット5~7人)
- 上記のコンセプトグループと同様
- 最後にサブグループごとのプレゼンを追加(5~10分)
第4章 ファシリテーションによって意見の対立を乗り切る
- 偏見のないファシリテーションをする
- 成果に意見を持つ人がファシリテーターはダメ
- ディスカッションをサポートするビジュアルフィードバックグループを作る
- 発散思考と収集思考のいずれも実行する
第5章 ファシリテーションの戦略とスタイル
- 問題把握や議論のために的確な質問を作るのは有用
- 成果のリストを元に正しいと思う方向に議論を向かわせる質問を考え、価値を高める脱線を考慮に入れた質問をする
- 質問を手直しして思い込みを排除する
- 謙虚な問いかけの4つ(感情、動機、行動、システム)
- ファシリテーションスタイルの選択
- 台本通りか臨機応変
- ことばかビジュアルか
- スペースメーキングかスペースフィリングか
第6章 よりよいミーティングがよりよい組織を作る
- 新たに会社に入った人が組織の文化ややり取りの違いを理解する一助になる
- マネージャーは文化形成の一巻で望ましい行動を促せる
- 非難や叱責はせず、失敗を分析する
- 戦略的思考は誤っていても高く評価する
- 定期ミーティングは普段接しない社員を出席させて共通目標を目指す、実践する
- 各部門間のワークフローの断片化によって生じるグループ間の知識障壁をなくせるかも
- 時には外部の視点も必要
【第2部 デザインされたミーティング 】
第7章 プロジェクトの第一歩はミーティング
- 参加メンバーの前提を明らかにし、検討
- 適切な議論パターンに従い意思決定する
- 事前の情報を活用し、主要イベントのアジェンダを改善する
- 優先順位を決める
- すでに何かできる人がそれをするのにふさわしいと思い込まない
第8章 中間地点のミーティングで道筋を示す
- 共通ビジョンの強固、信頼確立に役立つ
- 予期せぬ問題には信頼が必要
- 仕事上の人間関係を左右する前提について考えるいい機会
- 1回で終わらない長期的な人間関係を作ることが望ましい
第9章 最後のミーティングで一件落着
- ミーティングを責任追及の場にしない
- プラスの成果とマイナスの結果をバランスよく考察
- マイナスの結果はプロセスにフォーカスする
- 特定だけでなく、今後の改善アクションまで明らかに