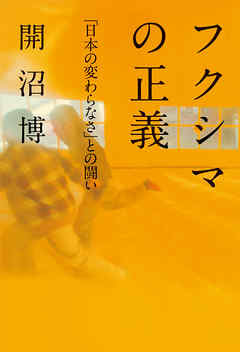あらすじ
『「フクシマ」論――原子力ムラはなぜ生まれたのか』で毎日出版文化賞を受賞し、論壇に衝撃的なデビューを果たした著者。本書は、いま最も注目される若手社会学者による待望の初評論集である。福島からの避難、瓦礫受け入れ、農産物の風評被害など、一般市民の善意が現地の人々にとっては悪意となり、正義と正義がぶつかり合う現実。そして沖縄基地問題のように、反原発運動もまた、新手の社会運動のネタとして消費されるのではないかという危惧。震災後も精力的に現地取材を続ける著者に見えてきた、「日本の変わらなさ」とは?――。3・11を経て、より深刻化した日本の病巣を浮き彫りにした、必読の論考。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
明確な善意と悪意のぶつかり合いならば目指すべき道筋は見えやすい。しかし、そうでなく、善意同士のぶつかり合いに走った分断線を上手く繋ぐ方法を私達はまだ持ち合わせていない
端的に言えば現在の善意の分断の背景にあるのは、「一つの解がない。にもかかわらず一つの解を求める志向」あるいは「科学的合理性に基づいた複数の解が並立している状況への認識不足」。これを私は近代化の進展の中で現れた、再宗教化とよべる社会現象として捉えている
私達は、その「一つの解を志向する科学」や「それによって作らられる良き社会」という前提自体が一つのフィクションに過ぎないことに気づきつつある
社会の善意の分断を再度つなぎ合わせるために今求められるのは、自らの考えが唯一最上のものではないことを自覚し、社会に複数の信心が存在する状況を認め、その前提で議論を進めることだ。自らの考えに合わぬものを、蔑み罵り責任をなすりつける宗教紛争の先には、善意の分断の中で現状の課題が忘却され、坦々と維持される未来があるだけだ
事実として「こうである」ということと、自らの信念として「こうあるべき」と思うことを混同してはならない
自分たちが声をあげられる、あるいは自分たちの知識と正しさをひけらかせる機をみつける毎に中途半端に食らいついて安直な希望を語ってみせ、興味がなくなると忘却する。まさに後出しジャンケン性そのものを基盤にしたある種の渡り歩きのデモンストレーションの中で、主要な課題が放置さらたまま今日に至ってしまった。それこそが近代そのものであった。
敗戦後論 加藤典展 ちくま文庫
現地に暮らす人々の声、リアリティを無視した形で、知識人と言われる人たちまでもが、原発推進か反対か、安全か危険かといった二項対立の中で議論している。この構造で問題が整理されていくことが、実は問題をより根深くしてしまう。単純な二項対立の議論で切り捨てられる現場の声、リアリティをきっちりみていかないと、本質に迫ることはできません。
流布している議論は概ね、専門家が他人ごととして、従属化されているひとを善意の目線で分析する枠組みにとどまっている。しかも、その善意の目線が孕む暴力性に非常に鈍感です。
福島を、あるときは都合のいいように他者表象し、またある時な自分のきれいに化粧した善意の顔を映す鏡にして気持ちよくなるのに利用する。311以前には自分自身であったはずの東電や政権を、あたかも他者であるかのように急に叩き、スケープゴートにするというねじれた構造のなかで、問題が論じられている
角田光代 空中庭園
Posted by ブクログ
フクシマ論とあわせて読むのをおすすめ。仙台になれると思って受け入れた原発。東京で言われている脱原発論からは見えてこない当事者の思いが書かれている。フクシマを理解せずして脱原発は実現出来ない。
Posted by ブクログ
「必要悪」の「必要」と「悪」は本来切り離せないものなのだが、物事を単純化したがる人びとは往々にして「必要」だから「善」、または「悪」だから「不要」と決め付けたがる。
「必要」さと「悪」さをそれぞれ直視した上でうまくバランスさせることができるのは、正に成熟した社会だけだろう。