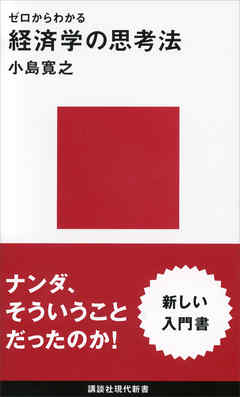あらすじ
経済学は小難しい? ちっとも現実を説明してくれない役立たず? 旧態依然とした教科書的解説を一切廃し、その本質とロジックを平易に語る。経済学の見方を塗り替える魅惑の講義、ここに開講! ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。(講談社現代新書)
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
数学科出身の経済学教授が解説した本(第2版)。
著者いわく、普通の入門書と異なるアプローチで、ミクロ経済学の基本を解説した本。「需要と供給」を中心に、貨幣や市場とは何かを解説、さらにゲーム理論の概要から、最後には再び「需要と供給」の原理に帰ってくる。
ロジカルな説明なので、「まあそうなるな」という印象で、経済学全く初学の私にとっては逆にそれほど驚きはなかった。
ただ、第2版で加筆されたという前書き、後書き著者の経済学に対する愛情(のようなもの)と、その裏返しの歯がゆさが、とても面白い(エモい)。
Posted by ブクログ
ミクロ経済学の基本、とくに需要・供給曲線の意味について、わかりやすく解説している本です。
著者は、宇沢弘文の講演をきっかけに、数学から経済学に転じた経緯を語り、それまで経済学の需要・供給曲線にどのような意味があるのかということを、はっきりとつかめていなかったと述べています。その後、塾の経営者となって現実の経済の動きに触れたことで、需要・供給曲線を効用関数としてとらえるより、選好の理論にもとづいて理解したほうがその意味を明瞭に把握できると考えるようになり、本書でもそうした観点から解説がなされています。
つづいて著者は、ゲーム理論にもとづいて、需要・供給曲線をより明瞭に理解するための見方を示しています。数学的な証明をたどっていくのに困難をおぼえましたが、直観的に理解できるような事例があげられており、おおまかな理解を得ることはそれほどむずかしくありません。じっさい著者も「もしも論理展開を面倒くさいと感じたら、次項はいったん読み飛ばして、先を読んでからもどってきても(あるいは読み飛ばしたままにしても)よいと思う」と述べているところもあり、数学が苦手な読者にとっても理解しやすいように工夫された説明がなされています。
著者とおなじように、経済学が現実の経済と対応しているように思えないと漠然と感じている読者が、経済学とはいったいなにをめざしている学問なのかということを考えるための手がかりになるような本だと思います。
Posted by ブクログ
経済学についての学説ではなく考え方をわかりやすく解説する。ゲームの理論の考え方を取り入れて解説しているところもわかりやすい。経済学の需要と供給の関係がふたつの考え方からも現れてくる。
Posted by ブクログ
経済学でどう考えるか、ではなくそのものズバリ経済学がどういう風に考えているか、という意味での思考法ってタイトル
最初から最後まで分かりやすくて基本的な部分が理解できたのでよかった。
Posted by ブクログ
オークションの例を使った需要・供給曲線の説明や合コンでのマッチングなど、イメージしやすい内容で良かった。
学生の頃、数学が好きだったので、数学的アプローチもわかりやすく興味が持てた。
Posted by ブクログ
経済学は予言的ではないなぁと改めて実感。
選好理論や効用関数が経済学の基本、らしい。
お金は「欲望の二重の一致」を探す手間を減らす。
2000円札は、自販機で使えないなどの理由から流通が阻害され、結局使われなくなってしまった。(20ドル札とか、ある国のほうが多い印象だけど、たしかに2000円札なんか最近見ないな)
Posted by ブクログ
*****
新田さんにオススメされて読んだ小島先生の一冊。確かに分かりやすいし面白い。
需給のバランスを協力ゲームという枠組みから説明するのは肌感覚としても捉えやすい視点だった。
*****
今の仕事をし始めたからこそ面白いが、それって少し特殊な要因/環境で学んでいることだなという感覚は強い。前だったらここまで興味を持たなかった。経済学がどうすれば分かりやすくなるのか、色んな人が腐心しているが、自分事になっていない人には特に分かりやすくも興味深くもないことだろうと冷めた視点で思う。いや、この本は面白いんですが。
*****
Posted by ブクログ
経済学は、大学の一般教養で選択したものの、何の興味も持てずに単位だけ取得した、という印象。
だけど、歳を重ねるにつれ、経済の仕組みをちゃんと知りたいと思うようになった。
とはいえ、何から手をつければよいものか。
わかりにくいものを、わかりやすく説してある本はないかと手にとったのが本書だった。
はじめの方はわかりづらくて、なかなか進まなかったけれど、後半は慣れてきたのか、具体例も身近だったからか、すいすい読み進めることができた。
私が大学生だった頃よりも、経済学の研究はずっとすすんで、より取っつきやすい学問になってきているようだ。
だけど、経済学がこんなに数学的だとは思わなかった。
私は学生時代、数学は苦手だったが、大人になってから、数学の大切さがわかるようになってきた。
数学なんて、社会に出ても何の役にも立たないよね、というのは間違いだと私は思う。
これは、この本を読む前から思っていたことだけど…。
中身は、タイトルからの想像とは違うものだったけれど、もっと経済学を知りたいという気にはなった。
Posted by ブクログ
電車で読めそうな本。でもちょっときっかけが無い。著者の経済学への思いは面白い。元数学科出身ということで、宇沢先生へのオマージュがあるのも面白い。
数理経済学が得意な人は、なぜ「ミクロ的根拠に乏しい」とされるケインズ体系に惹かれるんだろう。ちょっと意外に思う気がするが、「経済学はモデルとしては良くできているが、実証はイマイチ」という序文の趣旨も興味がある所なので、よくよく読んでみたいとは思う。
Posted by ブクログ
「需要・供給の原理」。経済学の入門編を勉強すると出てくる、ノの字型のグラフが交わるあれである。理屈は簡明そのものなので原理の当否について深く考えたこともないが、実際の経済においてその原理が成立しているさまを観察するのは意外に難しい。この本の大きな枠組みは、その「需要・供給の原理」がいかに成立するかをゲーム理論でもって再発見してやろうというもの。終盤戦はけっこうややこしいが、なんとか理屈を追いかけることはできた。
Posted by ブクログ
協力ゲームの代表的な解のことをシャプレー解といい、限界貢献という数値から算出される。
タクシーの相乗りにおける各人の支払額で解説していたが、リアルに支払場面を想像すると、何となく納得感がない気もしたが、私だけだろうか…
Posted by ブクログ
一見すると難しそうな算数が並びたてられているが、
しっかり読んでみるときっちり理解できる。
アダム・スミスの言葉も難しいが、
こういう意味なのかと理解できた気になれる。
これを読んで経済学の真理はわからないが、
何もわからない最初の状態で読むには最適なのではないだろうか、
と何もわからない自分は感じた。
(以下抜粋。○:完全抜粋、●:簡略抜粋)
●人々は、他人の自由を侵さない限りにおいて、
自分の内面にある欲望におもむくままに利己的に行動し、
自分が損をするような行動は強制されない。
それを価格システムを使って調和させる。
調和とは、ある種の「協力」である。
人々の直接的な接触から影響を受け、
その影響がまた他社に影響を与えている。
その相互関係が市場を作り出しているのである。(P.146-147)
Posted by ブクログ
オークションから“需要-供給曲線”を導いたり、物々交換から対価の概念を説明し、“お金“とは”信頼“をひとつの形にしたものであるなど、経済の教科書に必ず記述されているいくつかの項目を、より身近な例を使って読者に納得させる。読み物として面白い。