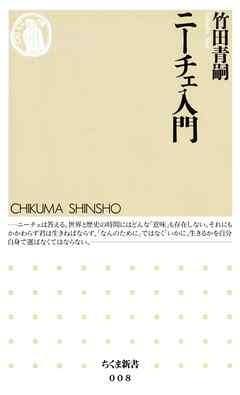あらすじ
ルサンチマンの泥沼の中で「神」や「超越的真理」へと逃避するのか、あるいは「永遠回帰」という「神聖な虚言」に賭け、自らの生を大いに肯定するのか? 二十世紀思想最大の震源地であり、今日もなお、あらゆる思想シーンに絶大な影響力を誇るニーチェの核心を果敢につかみ、さらに未来へと開かれた可能性を大胆に提示する、危険なほどの刺激的な入門書。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
めちゃよかった
ニーチェの入門書としてとても良いと思う。
一回読むだけではなくて、何回も読み直すと理解が深まる。
ニーチェ著書の本を読んだときに理解しづらくなったら、一旦この本に立ち返るとよりわかりやすい。
Posted by ブクログ
今までの読書ではないくらい精読をして挑んだ。
ニーチェは聞き覚えのあるキラーワードがたくさんあり、且つその言葉それぞれが力強く既成の概念をぶち壊してくれるような期待感は常々ありました。
徹頭徹尾人間自身の「生」にフルベットしている思想だ、そこには胡散臭いものに一切与しないかっこよさがある。よもすればルサンチマン的境地に陥りやすい世の中だけど、心の片隅にニーチェを潜めながら生きていきたいと思う。
Posted by ブクログ
ニーチェに興味を持って本書を手にとった。
著者の解釈を交えた解説がわかりやすくてよかった。いきなり原著を読んでいたら理解できずに途中で挫折していたと思う。
Posted by ブクログ
真理は醜い
事実なるものはない、ただ解釈だけがある
キリスト教はルサンチマン
認識論は弱者の論理
知や認識と権力が結びつくことの失敗。マルクス。
弱者にとって必要なのは、妬みではなく憧れ。
強者にとって必要のなのは、奢りではなく励まし。
Posted by ブクログ
なんという本だろう。衝撃を受けた。今までニーチェと言えば「神は死んだ」といったフレーズだけでろくに理解も(今も理解はしていないが)しておらず素通りしていたがそれは大間違いだと気がついた。
ニーチェの指摘したヨーロッパの病理がまさかキリスト教という宗教から生まれていたことや、真理を求めるといった普遍的に正しいと思われるような姿勢が逆に人間の弱さといった部分を、まさにルサンチマン的な態度であるということは衝撃を受けた。ルサンチマンやニヒリズムといった概念は薄く知っていたが、それが今現在の社会において特に色濃くなっているところにニーチェが指摘した病理の深さが図られる気がした。徹底したニヒリズムの先にある力への意思というものがなく、安易に何か絶対的なものや主導してくれるものに飛びつく様はトランプなどが人気になってしまう要因なんだと理解できた。しかしニーチェをこの本で学んだが、永遠回帰の部分と力への意思の部分は難解であり未だ咀嚼しきれていない。今度は道徳の系譜にチャレンジさしてみたいと思う。
Posted by ブクログ
ある企業の経営者が影響を受けた本との事で興味を持ちました。2001年宇宙の旅よく分からないままでこの歳になってしまいましたがこれでやっと分かりました。現在の混沌とした世界情勢を考えるうえでも役立ちます。
Posted by ブクログ
落合陽一が落合信彦に「ニーチェを読んでないヤツとは話ができねえな」と言われた、という話を聞き、ニーチェを読んでみようと思った。
が、いきなり「ツァラトゥストラ」なんかに手を出しても理解できないかも、と思い、この入門書を読むことにした。
一言で感想を書くならば、
「ニーチェすげぇ!」
といったところ。
著者の解釈が正しいのかどうかわからないが、自分がなんとなく考えていたことを言語化しているところがすごい。
ルサンチマン思想の批判や、絶対的理念の否定など、よくわかる。
そうだよね、と納得できるし、19世紀にこの思想を打ち出した感性が素晴らしすぎる。
理解できる人は少ないかもしれないが、みなニーチェを読むべきだな、と思った。
ということで、次は「ツァラトゥストラ」にチャレンジしようかな。
Posted by ブクログ
十牛図、ユングの錬金術にも通じて一味違う哲学。ラクダ、ライオン、子供。整体の世界でも言われている身体は何でも知っている、最後に残るのは身体だけ。今まで超人思想を誤解してました。いつの世の中を切り取っても同じような金太郎飴的な世界観が見える。一休宗純も似たような考えだったかなという感じ。ルサンチマンとは努力しない弱者の言い訳、その克服にたどり着いた答えは身体。とは言え文明は身体を弱体化する方向に進みがちにも見えるし、身体の可能性を拡大しているようにも取れる。その振り幅が大きくなっているのかもしれない。超人と弱者を分けるのは永遠の小さな違い。プロ野球選手でもその小さな差で一流と二流に分かれるのだと、かつて野村克也氏の本でも読んだ次第です。
Posted by ブクログ
ニーチェの解説書の中ではすごくわかりやすい内容だった。
抜粋×要点 という形式でまとめられていて、何ゆえにそのような解釈となるのか、その論理がわかりやすい。
しかし要点解説の中には「本当にそうか?」「いくら読んでもニーチェがそのように考えていたとは読み取れない」という個所もある。
なので、本書をとっかかりにして実際にニーチェの著作を読み込む、そして自分の頭で考え、咀嚼することが大切だと思います。
Posted by ブクログ
善きものを求める人こそニーチェを。鍛錬なき、反省なき哲学はないのだ。
時代と歴史にまみれた自分という存在をニーチェは、鍛える。
木田元の反哲学もニーチェが転回点だったが本書は、哲学だけでなく、人間が生きる上で、転回をもたらす本である。
隣人愛(宗教)、真理(学問)の反人間性を乗り越えるために。浅いニヒリズムでとどまらないために。
Posted by ブクログ
哲学やニーチェ用語を大まかに知っていたからという部分はあるものの、ニーチェ入門としてはかなり読みやすい部類に入るのではないかと思う。
ニーチェのヘーゲル以前の哲学や神学への批判的態度は今見ても鮮やかな批判で楽しめる。
第4章「力」の思想あたりからやや難しくなる印象ですが、総じて丁度良い難易度だった。
Posted by ブクログ
「力への意志」の概念は非常に良かった。世界とは客観的に存在する事実ではなく、主体によって解釈されているだけのものである。その解釈の仕方は、主体の欲望に根源を持つ(力への意志)。それは弱者にとってはルサンチマンになったりキリスト教的世界観になったりする。しかしそういった「否定」や「他者」に生の根源を求めるのではなく、強者(超人)が持つような生命感情に「力への意志」を目標として持ち、生と世界を肯定しながら生きていく、それが何のために生きるのかへのニーチェの解答であると理解した。
「私たちの知性に権力と安全の感情を最も多く与える仮説が、この知性によって最も優遇され、尊重され、したがって真と表示されるのではなかろうか?」P201
それまでの価値を顚倒させるような上記の認識とかもアツい。
一方で、永遠回帰の思想は結局よく分からずじまいであった。思考実験としては面白いが、それがニーチェの批判するキリスト教的世界観と形而上的概念として何が違うのか理解できず。永遠回帰を手段として使うというのであれば理解できる。
「「永遠回帰」が単なる「救済の物語」ではなく、一つの生への深い了解でなくてはならないということを意味する。」P178
これって結局そういうもんとして根拠なく信じることと違わないのでは?と思ってしまうが、多分理解不足。個人的には好きな解釈だけど。
ニーチェも「性欲」とか「陶酔」、「恍惚」に根源に近しいものを持ち出してきてお手上げです。2025/06現在マジで理解できません。
これがないから、純粋に生を肯定できないんだよなー、と。
最終的にニーチェの思想は、ルサンチマン等に代表されるような生の一回性を利用した否定などに傾かないで、「力への意志」に従うことで善く生きることだと理解した。
なんなら「力への意志」どころか「欲望=身体」に正直に生きることとも読み替えられるかなと。
異論に対しては
「事実なるものはない、ただ解釈だけがある」
と返します。
Posted by ブクログ
ニーチェの入門的な内容がわかった。
まず、永遠回帰という内容は理解はできるが、日本人かつ無宗教の自分にはあまり刺さらない内容だなと感じた一方で、当時の科学の発展と共にキリスト教の失墜は、インパクトがかなり大きかったんだろうなというのも容易に想像できた。
ニヒリズム的な思考は現在、増えている気はしている。特に格差が大きくなり、親ガチャという言葉が発生し、運命論に逆らえないようなこの思考はまさにニヒリズムと言ってもいいような気がする。
ルサンチマンの内包には私は常日頃から気を付けており(この本を読む前から)、さらに超人という目指すべき姿は、環境に左右されない強い理想像として私に刺さるものがあった。
まあ分かった気になっている気がするけど、正直難しかった。入門とは書いてあるけど難しい。自分なりに落とし込んで、50%でも理解できていたらなと思う。でも興味深い、特に現代人にも刺さるような内容だなと感じた。
Posted by ブクログ
ここまで切れ味鋭い問い(ルサンチマン、永劫回帰)を立てた人だとは知らなかった。一方、問いに対する答え(超人思想、力への意志)の質は決して高くないように思う。それでも哲学史上でこれだけの地位を占めているのだから、問いの質というものがいかに大事かを分からせてくれる好例。
Posted by ブクログ
第4章から急に難しくなったが、基本的に分かりやすく、ニーチェへの理解が深まった気がした。
要約すると、周りに嫉妬せず向上心を持て!みたいな感じかな?
遺伝子や環境が平均以上で、そこそこ恵まれた人には刺さりそうな哲学だとも思った。メディアやsnsで到底追いつく事の出来ない成功を見て、生まれつきの弱者は力への意志を求める事が出来るのだろうか。
向上したくても、この世のシステム的にどうにもならないことはどう対応すればいいのか。
例えばニーチェがiq80で身長150cmのブサイクに産まれてきたら、超人思想なんて考えてたのかな。とは思う。
Posted by ブクログ
「力への意志」などについての説明は分かりやすかったが、所々筆者の意見や解釈が多めに入り込んでいる気もした(ニーチェの文章の性質上ある程度は仕方の無いことかもしれない)
Posted by ブクログ
■著者が扱っているメインテーマ
いかに生きるとはどういう事か?
■筆者が最も伝えたかったメッセージ
生きようとする欲があるから苦悩はあるという世界を受け入れ
自分で世界を切り開いていこうとする意志が大事。
■学んだことは何か
苦悩が選んだ世界から生まれた結果。
人の数だけ世界は存在しているので、そこを否定する生き方は自分を否定しているようなもの。
(他人を羨んだり、苦悩を拒否したり)
Posted by ブクログ
「入門」と言いつつ、 #飲茶 さんの本を読んでいたからなんとか理解できた感じ。
それまでの「絶対的に正しいものが存在する」という「真理への意志」を否定し、この世は自然の物理科学的法則に貫かれた機械仕掛けの天体運動に過ぎず、「何をやっても一切は決定されている」と断じる。だからこそ、「いつも無限の繰り返しとしてそう欲されるべきものとなるように行為」すべきだと説く。「なんのために」ではなく「いかに」生きるかを選ばなくてはならない、世界の「価値」はただ「力への意志」による解釈からのみ生じるのだと。
Posted by ブクログ
もちろん難しかった。けど最後まで読み通すことは出来た。竹田先生の著作との相性が良いことは分かった。難しいけどすこし読みやすい。先生曰く「哲学」や「思想」が「善きこと」を求める努力で、その「善きこと」への志を持つなら、是非とも一度はニーチェ思想の深い森の中を通ってみることをすすめる。とあるのでオレはようやくその森の存在を知ることが出来たのだと思う。その森は、きっと想像以上に深くて広大で鬱蒼とした暗くてイヤなところだろうけど、途中で急に湖が出てきたり、屋敷があったり見たこともない鳥が啼いていたりしそうだ。そこにはきっと色んなまだ見ぬ未知の世界が広がっている。そこで迷って森から出られなくならない様にパンくずを落として注意しながら探検を続けたい。探検しながら自分なりの地図を、思想の地図を描けたらこれはとっても嬉しいことだなあ。きっと。
Posted by ブクログ
ニーチェさんは、実はちゃんと読んでいないんです。
読んでみようかな、とも思ったんですが、あの手の本は、どうにも訳文が不満なことが多くて、しり込み。
(村上春樹さんあたりがニーチェ翻訳してくれないかなあ…英語ではないから無理だけど)。
と、いう訳で、こういう本をひとつ読んでみようか、と。
読んでみたら、実に面白かったです。ニーチェ、けっこう好きでした。
#
●「事実などは存在しない。ただ解釈だけが存在する」
●「真実とは、もっとも強力な解釈のこと」
ニーチェさんはキリスト教が強い時代にあって、まずそれを疑った。
そして、結局、宗教というものを、疑い抜いた。
全ての「誰かが説いた価値」「誰かの語る正義」というのを疑い抜いて、
理性的にニヒリズムに堕ちていく。
ただ、それを、全然否定しない。
ニヒリズムを貫いた向こう側。そこまでいかないと、宗教も、「正義」も、全ては「つらい浮世」「なぜおれは不幸?」「なぜおれはもっと認められない?」「成功しているやつらは狡いんだ」みたいな不平不満感情(ルサンチマン)に溺れてしまう。
キリスト教も「貧しきは善」みたいな救済主張っていうのは、つまりこのルサンチマンにのっとっているだけだ。
まあつまり、ニーチェさんは「だまされるな!」と叫ぶ訳です。
ただ、その先に、どこに向かっていくのか?
この先はもう、ほとんど、芸術というか、詩というか、文学というか。
●私たちの魂がたった一回だけでも、幸福のあまりふるえて響きをたてるなら。このただ一つの幸福があるためには、全永遠が必要だった。そして全永遠は、私たちが「YES」と肯定するこのたった一つの瞬間において、許可され、救済されていたのである。
●人間の苦悩に対して、不満と鬱屈から、「勝ち組は悪い奴だ」とルサンチマンを持つか。それとも、巨大な苦悩にもかかわらず、人生を肯定して、それに「YES」というのか。
というような感じです。
この手のニヒリズムの奥に奥にだけ芽吹けるようなロマンチズム?僕はけっこう好きでした。好みですが。
#
そこから先に、更に具体的に「超人」「力への意思」というような謎めいた思想がニーチェに去来します。
ただこれは、本書の著者も書いていますが、解釈がすごくむつかしい。
ぶっちゃけ、分からん(笑)。
ただ、一部に言われるような「ナチスに繋がる選民思想」だったりはしないような気がする、というのが本書の立場。
たしかに、もう正直ぜんぜんわからない何かの「ありよう」に向かって、矛盾を抱えながら、永遠に解けない謎を、果てしなく続く壁を、それと判りながら登り続けるのが人生であって、それにYESと叫ぶのであれば、そういうワカラナイ命題を投げつける理不尽が、ニーチェさん的にはアポロン的限界を破壊するディオニュソス的表現なのかもしれませんね。と、言いながらそれが自分でも分からなくなってきましたが...。
#
以下、備忘録みたいに、メモ。
●ニーチェは、キリスト教の自己正当化の中に、後年のナチスやスターリンにつながる危機感を見つけていた。
●ニーチェの思想の柱「ルサンチマン批判」「一切の価値の転倒」「ニヒリズムの克服」。
●「自惚れや傲慢は、ルサンチマンの裏返しである」
●人間は苦悩を「哲学」「芸術」「宗教」でしか慰められない。らしい。
●ニーチェのギリシャ悲劇の研究。
●理性と整理整頓、光明と芸術のアポロン神。一方で酒の神、祝祭の狂騒や陶酔の神である、ディオニュソス。
●火を支配する、人間に火を与えたプロメテウス。
●ニーチェの語る「悲劇」。人間は欲望によって矛盾を生み出してしまう存在だが、その矛盾を引き受けつつなお生きようと欲する。それが「悲劇」。
●恋愛や芸術の体験は、苦しいけれどその苦しさがまた人間の生きる理由になる、ということを確信させる。
●自分が愛されたい、自分を認めて欲しい、という「自我」。これは「他者の承認」によってのみ可能。
●キリスト教のトリックは、「弱者=善」という図式によって、現実人生の不満=ルサンチマンを正当化して、現世がどうにもならないニヒリズムの上に載っている、という。
●「お前が苦しんでいるのはお前のせいだ」という責任のコペルニクス的転化から発生する禁欲主義。
●キリスト教の没落以降の「科学主義」も「真理への意思」を絶対善とする限り、実はキリスト教と変わらない。
●「人類の呪いは、苦悩の無意味ということであって、苦悩そのものではなかった」
●「何であれ一つの意味があるということは、何も意味がないよりはましである」
●「人間は何も欲しないよりは、むしろ虚無を欲する」
●「道徳性とは、個々人における群畜的本能」
●道徳が人間の弱さ、不安、恐怖から出ているのは事実。だがそれは別に道徳を無価値なものにはしない。
●ものごとの「起原」と「本質」はべつのもの。
●ルサンチマン人間=あいつは力がある。したがってあいつは悪い。
●真理は利益で証明される。
●性欲、陶酔、残酷、という三つの要素は、原初の芸術には強く見られる。
●「正義を言い立てる者こそ、最も警戒せよ」
Posted by ブクログ
19世紀末頃のドイツの哲学者ニーチェ。
それまでのキリスト教的モノの見方によって作られていた、
常識や思考のひな型のようなものを、
ニーチェは批判し、破壊する言説を発しました。
ヨーロッパ的にいえば、
ニーチェという点の前後で、
キリスト教的か現代的かに分けられる。
象徴的なのは、ニーチェの著作にある
「神は死んだ。」の言葉です。
入門書で助かったなあという感想ですねぇ。
多くのニーチェの文章が引用されていますが、
ほとんどその意味がわかりません。
解説を読むとわかるのですが、その解説が
どう導き出されているかも、
うまくわからないのです。
やっぱり哲学書って難しいもんです。
途中、ドゥルーズのニーチェ解釈の文章も引用されていたのですが、
そこは現代に近いからわかるかなと思いましたが、
甘かったですね、「境位」がどうたらなんて
言葉が出てきましてお手上げです。
でも、まぁ、解説のおかげで
いろいろと勉強になる部分はありました。
たとえば、超越は無い、とする態度。
僕流の喩えですが、
宝くじだとか馬券での大穴だとかで大金をゲットするのって、
ニーチェ的に言うと超越であって、
そこで超越は無い、つまり当たりっこないんだとわかった上で、
さらにそういうときにやってくる
ルサンチマン(弱者の嫉妬や恨み)にとらわれずに、
力を尽くして生きていくことが大事ってことはわかって、
頷いたところでした。
また、重要概念の「永遠回帰」についても、
こういうものも関係あるのかな、と考えました。
同じところをぐるぐる回っているようで、
少しづつ上へと上がっていっているのが
わたしの人生だと思いたいっていう人、
けっこういると思うしぼくもそうなんですが、
そんな「らせん」の人生って、
ニーチェのいう「永遠回帰」と関係があるんじゃないか、
と思って読んでました。
それと、これはどうかという思想もあって。
血統や遺伝を重んじる優生学的な主張だとか、
強者と弱者の分離を進めていくという考えだとか、
問題だと考えた方がいいところがニーチェにはある
(まぁ、ちょっとは知ってたんだけど)。
ナチスに利用された可能性うんぬんって言われるけれども、
そんな簡単に思いつくものでもないし、
やっぱり利用されたっぽいように感じます。
結びのところで、この本が出た当時の94年ころ、
ポストモダンの論者たちが、いかにニーチェを語っていながら、
そのニーチェの根本のところからかけ離れていたかという
ことが書かれています。
それでも、「超越」についてはこのあいだ送付した自分が書いた小説が
ニーチェを意識せずにそういうテーマを含んでいるし、
「永遠回帰」が人生の「らせん」的進歩になぞらえることができるならば、
ニーチェの思想や哲学って、
現代では実はすごく身近にあるものじゃないだろうか。
いまや、こんな一般人の素人の人生とともにある考えです、と感じられる。
最後に、一番気に入ったのは、
中盤でも出てきたことは出てきたんですが、
もっとも最後のページにあった一言でした。
ニーチェの文章だと、
______
――あるがままの世界に対して、差し引いたり、除外したり、
選択することなしに、ディオニュソス的に然りと断言することにまで――
______
この入門本の著者のその直前の文章だと、
______
この世界の「あるがまま」を否認し打ち消そうとし反動へと向かうより、
それを是認しそのようなものとして世界に立ち向かうことの方が
いつでも必ず「生」にとって良い結果を生むのだ
______
になります。
つまり、俺は境遇が悪い、運が悪い、弱い、だとかって思いつめて
腐っていって、俺はそんなはずはないっていう気持ちで、
誰かを呪い始めたり、社会を恨んだりするんじゃなくて、
そんな自分であっても肯定して生きていこうよ、っていう、
万能な自分、理想な自分を本当の姿としないで、
今の自分が本当であることを認めたうえで愛していこう、
みたいな考え方なんですよね。
それって、ぼくもそういう考え方を持っているところがあるので、
まったくもって、共感した次第です。
ニーチェに興味のある方は、
まず本書くらいのレベルから足ならしして、
彼の思想や哲学のアウトラインをなぞっておくと、
勉強しやすいかもしれないです。
Posted by ブクログ
[ 内容 ]
ルサンチマンの泥沼のなかで「神」や「超越的な真理」に逃避するのか、あるいは「永遠回帰」という「聖なる虚言」に賭け、自らの生を大いに肯定するのか?
二十世紀思想最大の震源地ニーチェの核心を果敢につかみ、その可能性を来世紀に向けて大胆に提示する、危険なほどに刺激的な入門書。
[ 目次 ]
第1章 はじめのニーチェ(生涯;ショーペンハウアーとワーグナー;『悲劇の誕生』について;『反時代的考察』について)
第2章 批判する獅子(キリスト教批判―『道徳の系譜』について;「道徳」とルサンチマン;「真理」について;ヨーロッパのニヒリズム)
第3章 価値の顛倒(「超人」の思想;「永遠回帰」の思想)
第4章 「力」の思想(徹底的認識論としての(認識論の破壊としての)「力への意志」 生理学としての「力への意志」 「価値」の根本理論としての「力への意志」 実存の規範としての「力への意志」)
[ POP ]
[ おすすめ度 ]
☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度
☆☆☆☆☆☆☆ 文章
☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー
☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性
☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性
☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度
共感度(空振り三振・一部・参った!)
読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ)
[ 関連図書 ]
[ 参考となる書評 ]
Posted by ブクログ
一度読んで内容が全く理解できなかった。もう一度読んで前の3分の2程度の内容は理解できないこともなかったが、最後の3分の1、特に「力への意志」や「永遠回帰」の部分は何を言っているのかさっぱりわからない。哲学初心者として粘り強く読んでいきたい。
ただ、永遠回帰というものが、抵抗のないビリヤード台の上で玉を突くと、無限に玉が跳ね返りまくってその結果、最初の玉の配置と同じ配置になることがあるから、これを物理学や宇宙の単位にまで拡大して、人生が永遠にループする(正しい理解かわからない)という例えは非常に面白かった。
Posted by ブクログ
武器になる哲学の推薦本である。最初の部分、あるいはあとがきは非常にわかりやすく書かれているが、読み進めるうちにわかりづらくなる。ニーチェがなぜ現在復活したのかということだけでも重点的にい書いてあると助かる。神という概念がない人にとってはわかりづらい。
Posted by ブクログ
ニーチェの名前をよく目にするようになったので、少しは知っておいた方がいいかと思い、本の帯にある「最も読まれている入門書です。」という言葉にひかれて買いました。
さて、著者は、恐らく大変分かりやすくニーチェの思想を解説してくださっているのだと思いますが、残念ながら、私にはほとんど理解できませんでした。もちろん、まだ1回読み終わっただけですので、再度、再々度と読み直せば、もう少し私の理解が進むのかも知れません。しかし、予備知識のない身には、理解するには厳しい内容、というのが率直なところです。
そもそも、ニーチェの時代と今の我々とではおかれている環境があまりにも違います。ですから、同じことを考えたとしても、受け止め方に相当違いがあるはずです。p.157に、こんなことが書かれていました。『ところで、現在のわたしたちにとっては、これがなぜそれほど戦慄すべきものであるか受け取りにくい面があるかもしれない。というのは、無宗教が常識になっている社会の現代人なら、誰でもうすうすは、「世界の外側」に「超越的な意味」など何も存在しないし、したがって「死んだらそれきり」であるという感覚をもっているからだ。』これは、「永遠回帰」について説明されている途中に出てくるものですが、キリスト教的な考え方が支配的な当時と、無宗教が常識になっている現代とでは、発想が違って当たり前だと思うのです。ですから、発想のベースが違うので、理解が難しいのです。多分。
とはいえ、道徳に対する考察や、永遠回帰、あるいは美や芸術における「力の意志」という発想は、新しい視点に気付かされた瞬間もありました。これであきらめるのではなく、もう少し探究してみたい気分ではあります。せっかくの10連休ですので、普段は読むことがないであろう本に挑戦できたのは、よい収穫でした。
Posted by ブクログ
竹田青嗣がニーチェの哲学について解説している本です。
おもしろく読めましたが、著者の立場にニーチェ引きつけすぎているような印象があります。たとえばニーチェは、『反時代的考察』の中で文化批判をおこない、人類の文化の目標は「より高い人間の範例」を生み出すことにあると主張しています。竹田はこのことに触れて、ニーチェの意図していたところは「人間のありかたをつねに「もっと高い、もっと人間的なもの」へと向かわせるための、いわば励まし合いの“制度”なのだ」と解説していますが、こうした解釈は、ニーチェのもっていた「毒」を微温的なものへと変えてしまっているのではないかという気がします。
そのほかでは、「永遠回帰」の思想に関して「生の一回性を利用して世界と生そのものへ復讐しようとするルサンチマンの欲望を“無効”にする」という解釈を示し、また「力への意志」を竹田欲望論の文脈に引きつけて解釈しています。とはいえ、竹田欲望論とニーチェの哲学がどのように切り結ぶのかを知ることができるという意味で、個人的にはおもしろく読むことができました。
Posted by ブクログ
『道徳の系譜』を読んだだけでは分かりにくかったニーチェの思想の全体像を概観することができた。
生と欲望を人間の本性として肯定し、それを阻害するヨーロッパ的価値観(キリスト教がその代表)を批判したニーチェ。
生の肯定と、ロマン主義と現実主義の彼岸にある思想の探求、という出発点は共感できるけど、思索の末に導かれる結論には直ちに同意することはできない。
「真理なんてない」と言ってしまえば全ての科学は存在の根拠を失うことになるし、キリスト教批判を敷衍した「道徳」批判はいかにも過剰反応という感じがする。まあそんなラディカルさがニーチェの魅力なのかもしれないけど。
著者は、「ニーチェの思想は強者の論理である」という批判を、「この世界には強者と弱者が存在する」という事実の否認と混同しているものとして退けている。が、ニーチェの思想が弱者を救ったことがあるのか、果たして? その点で言えばキリスト教の方がナンボかマシという気がしないでもない。
終わりの方で触れられている芸術論としてのニーチェの考え方はアリ。